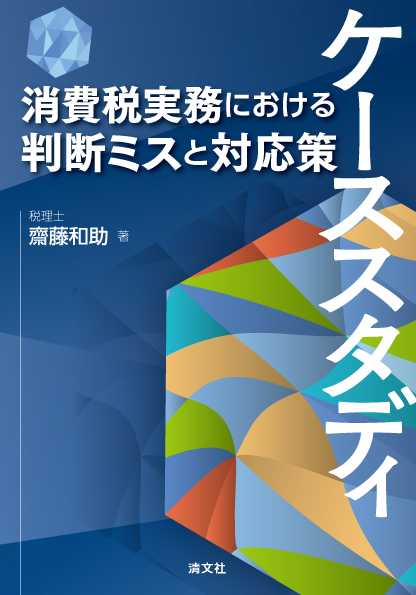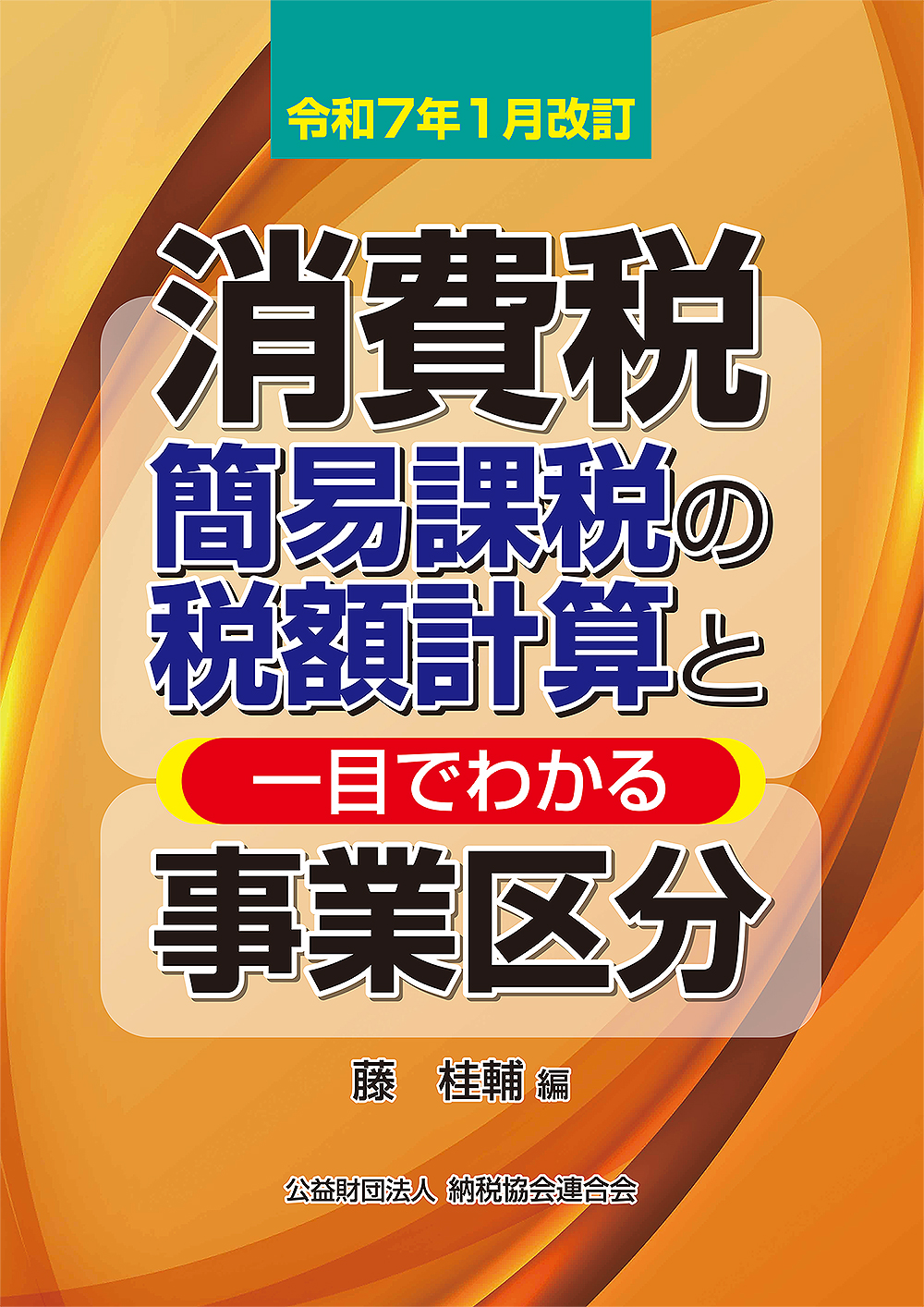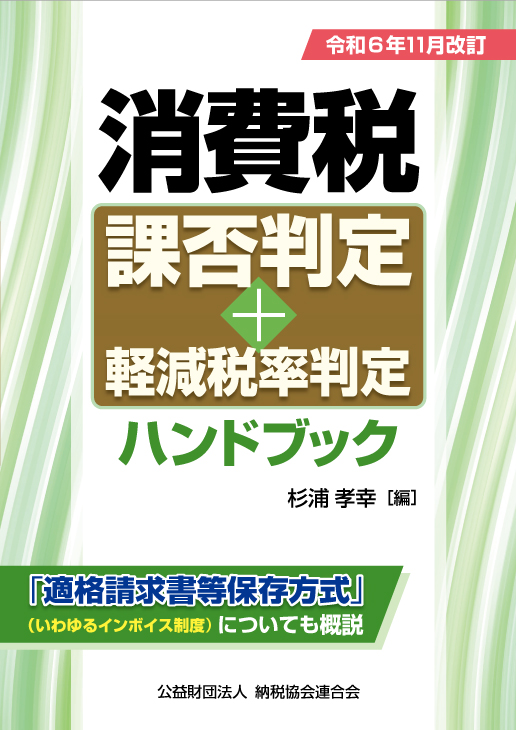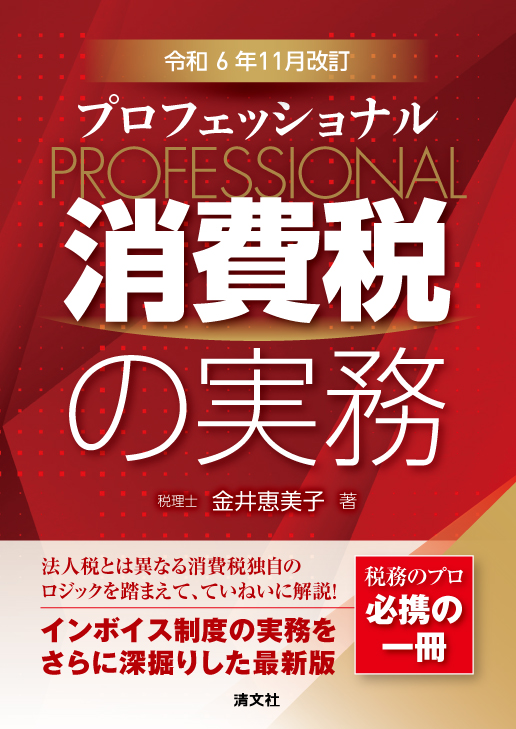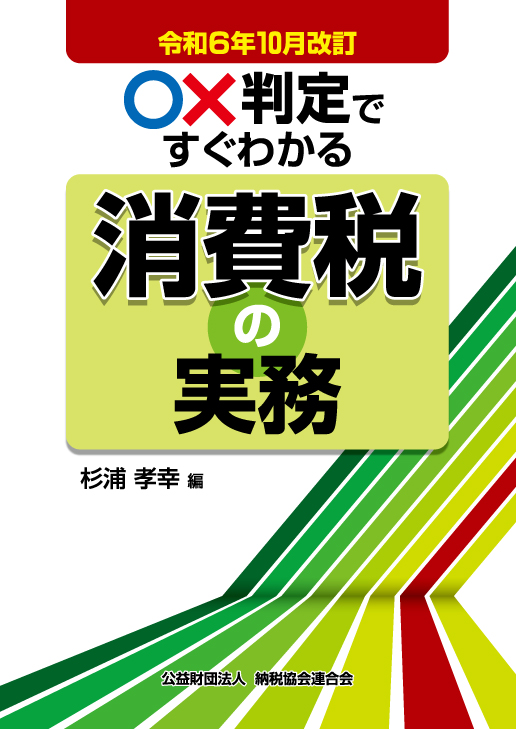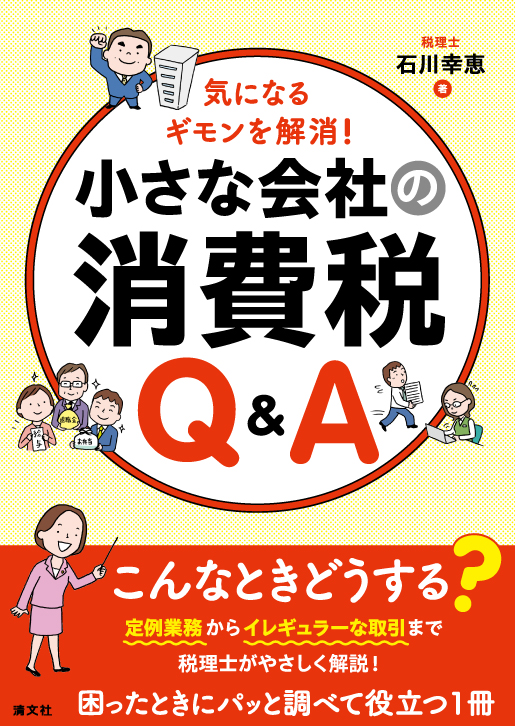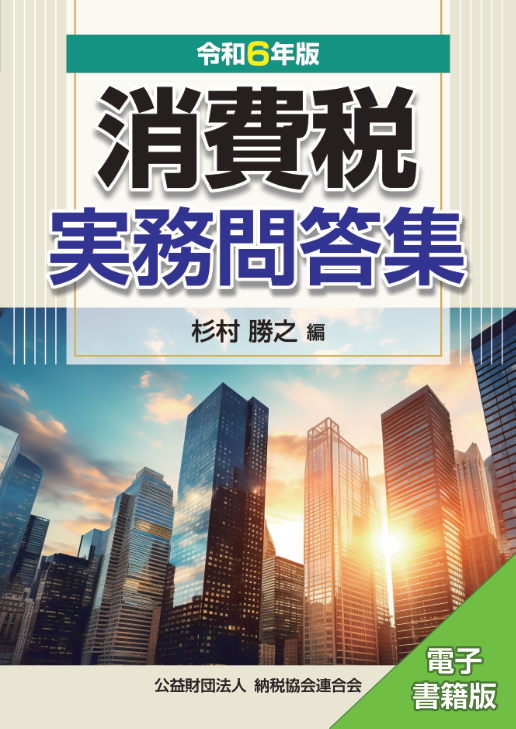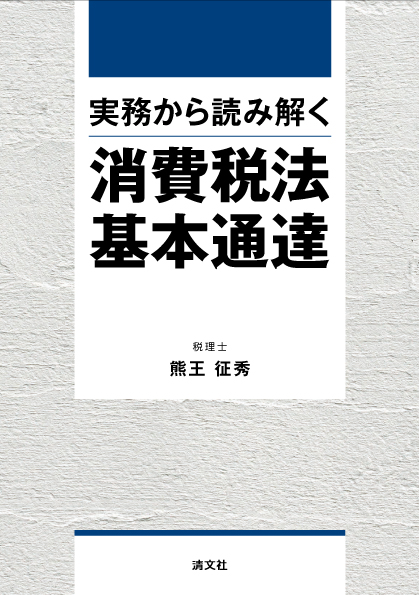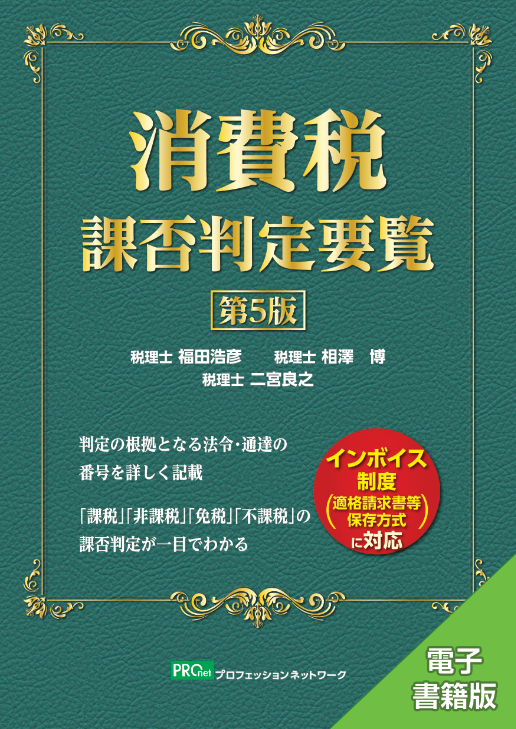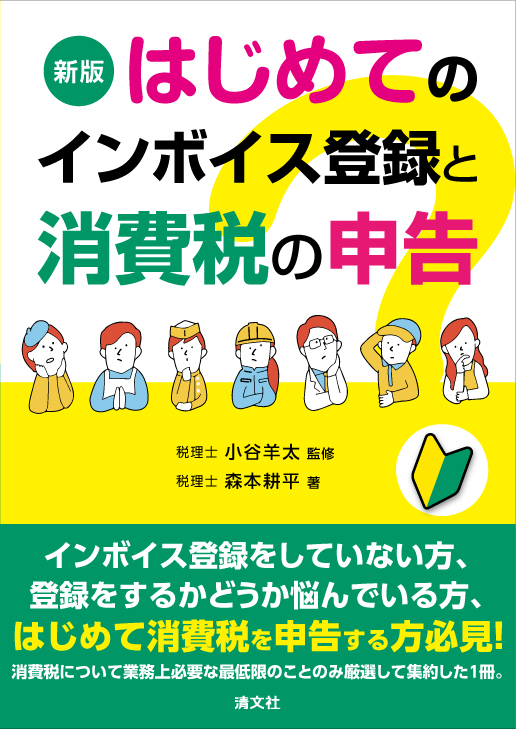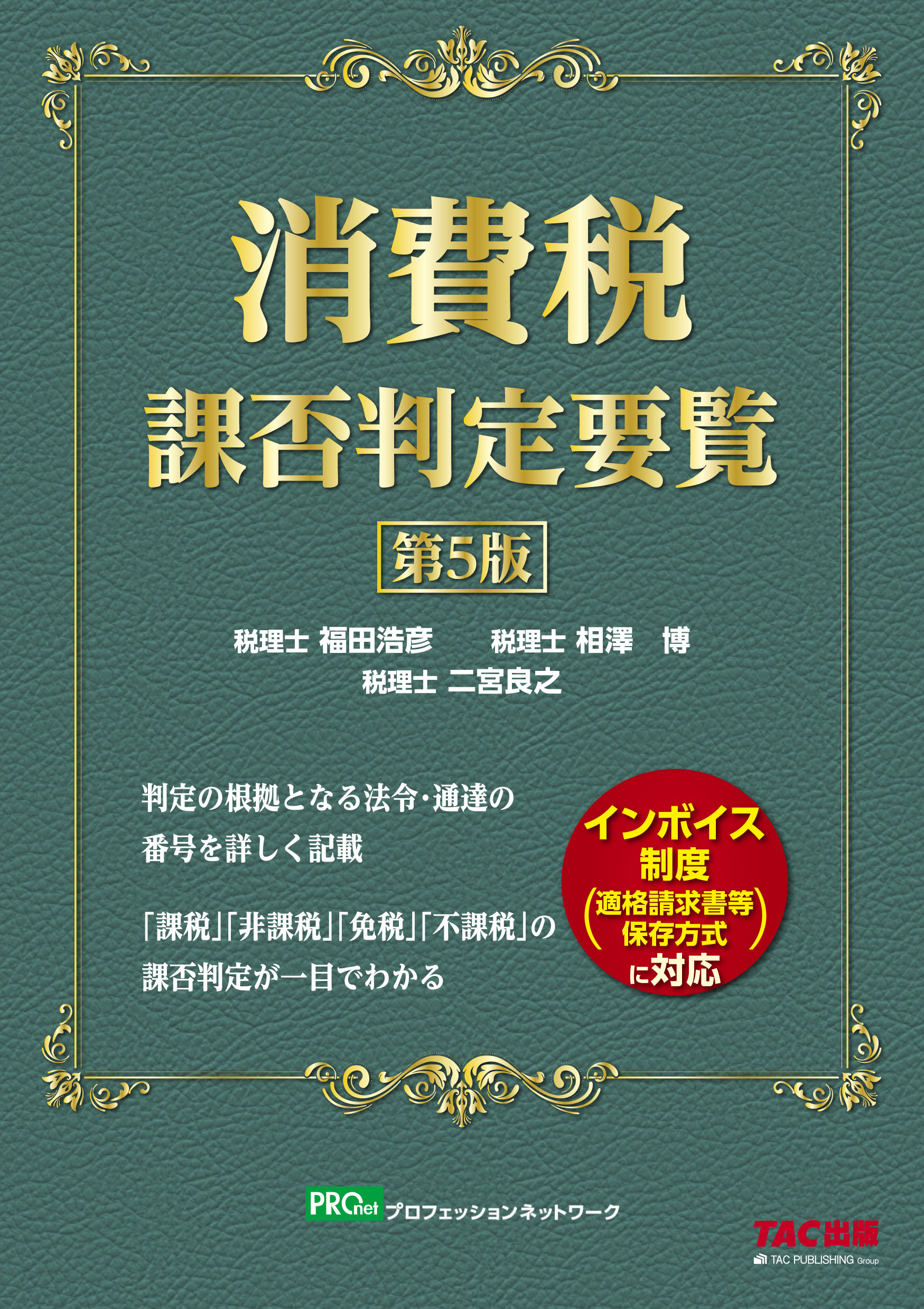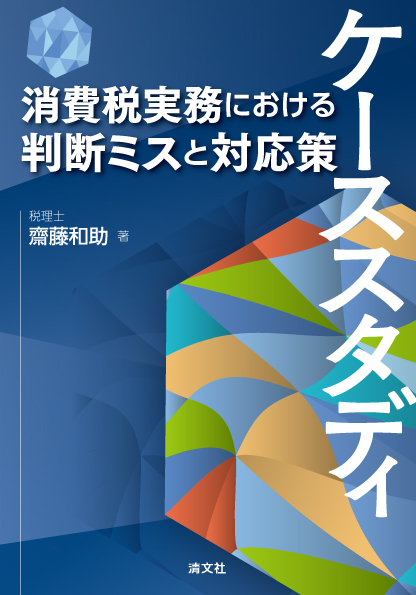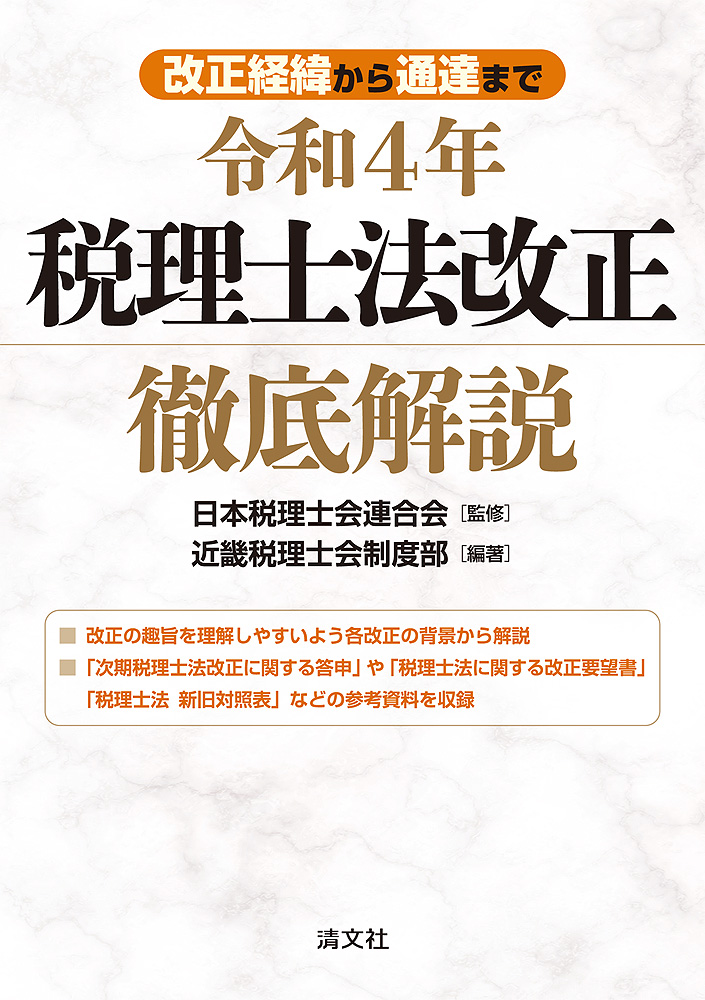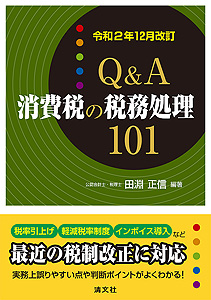「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例71(消費税)】
「課税事業者届出書」を提出すべきところ誤って「課税事業者選択届出書」を提出したため、調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の「簡易課税制度選択届出書」の提出制限(平成22年改正)により「簡易課税制度選択届出書」の提出はなかったものとみなされてしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X7年3月期から平成X9年3月期までの消費税につき、本来、提出する必要のない平成X5年3月期からの「課税事業者選択届出書」を提出し、平成X5年3月期と平成X6年3月期に調整対象固定資産を購入したため、平成X8年3月期まで原則課税の課税事業者として拘束されることとなった。
それにもかかわらず、平成X5年5月に提出できない平成X7年3月期からの「簡易課税制度選択届出書」を提出したため、届出はなかったものとみなされた。そして、これに気づくまでの3期分を簡易課税で申告してしまったため、原則課税で修正申告することとなり、修正税額につき損害賠償請求を受けた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。