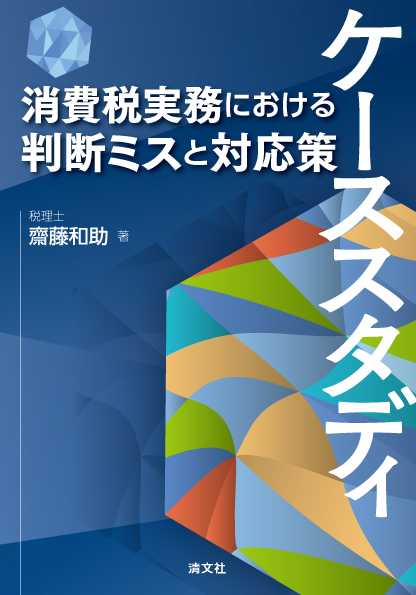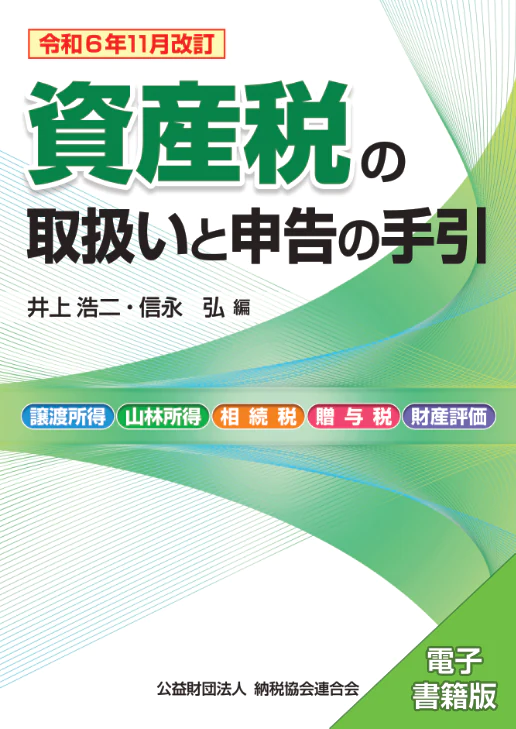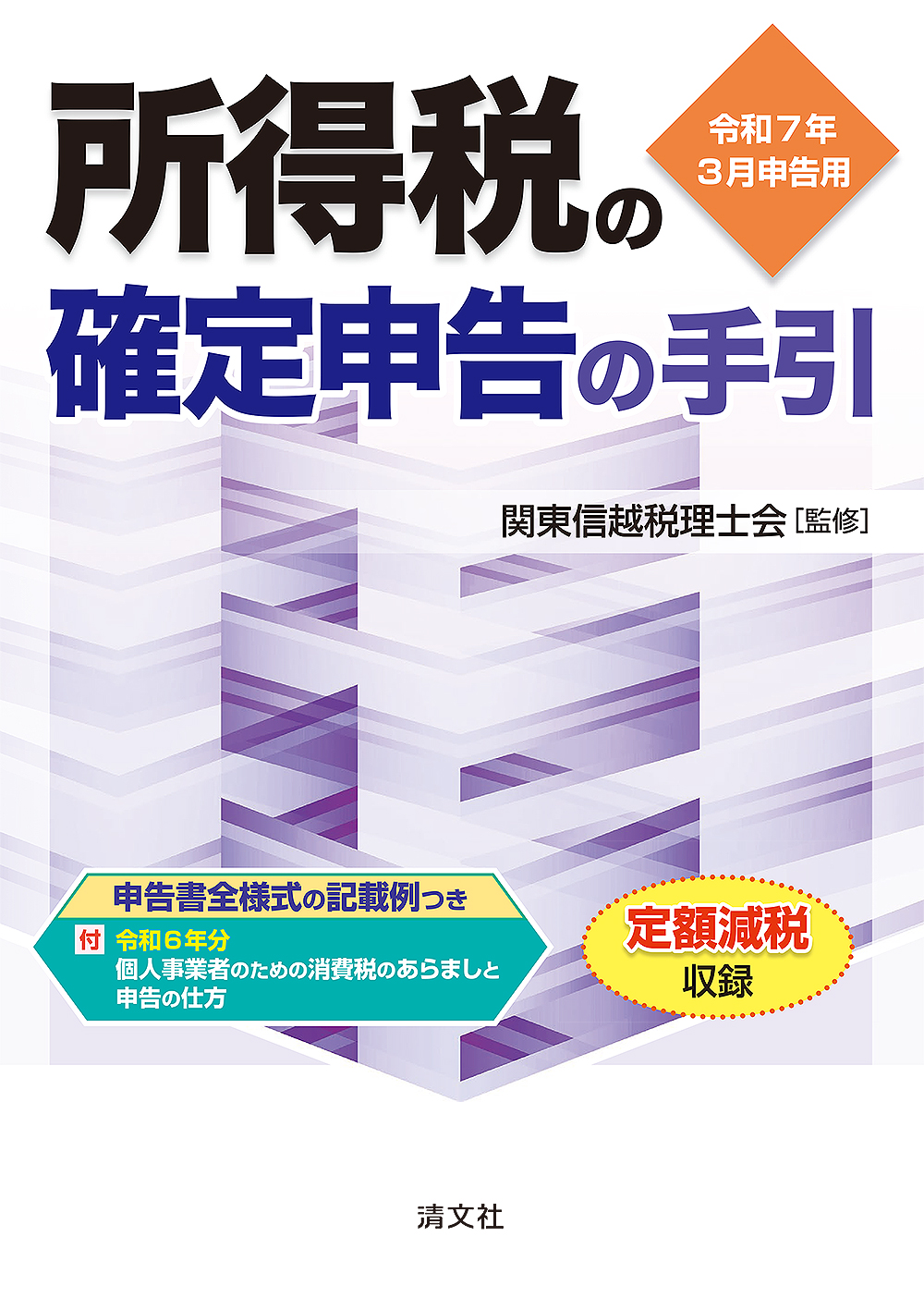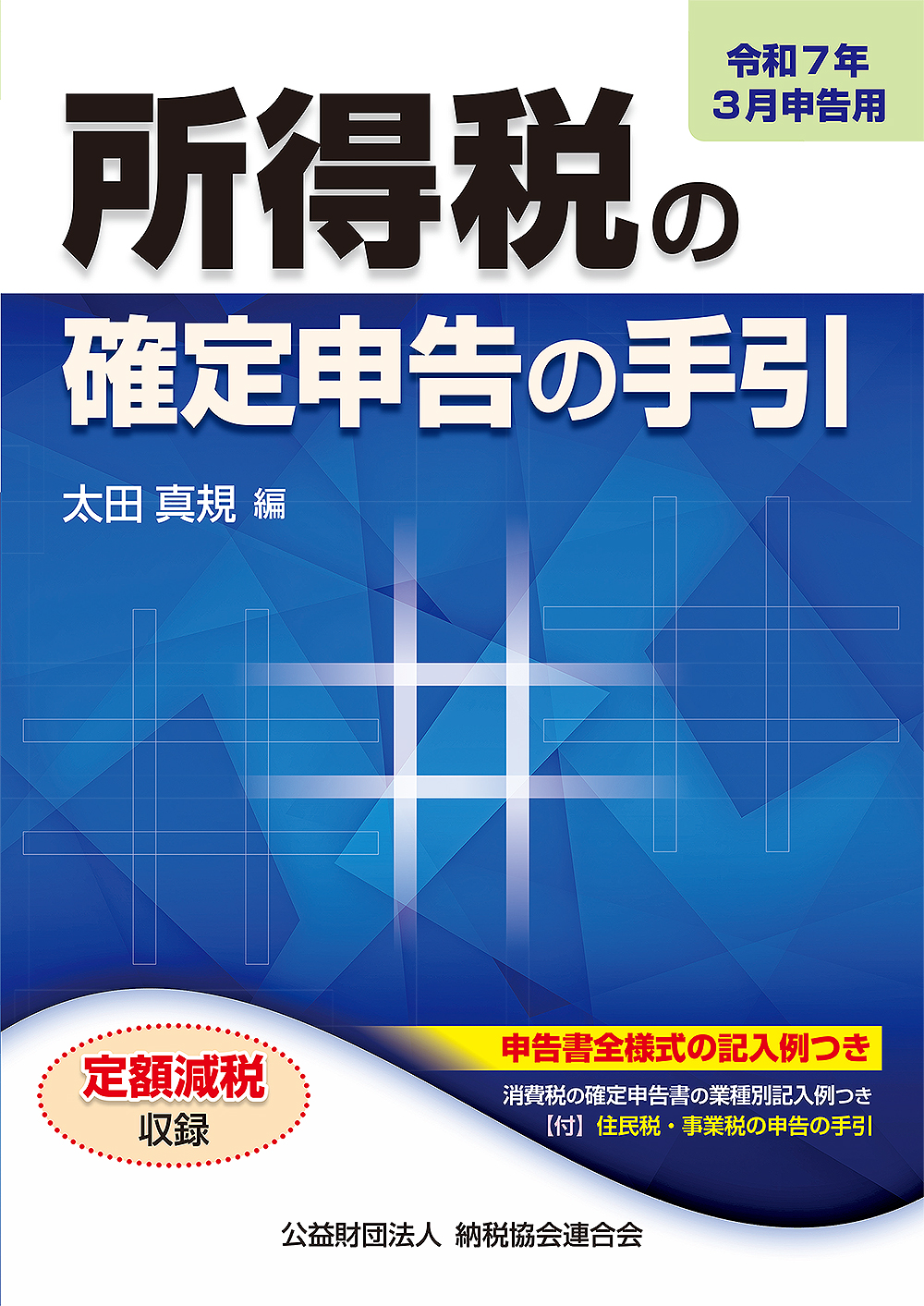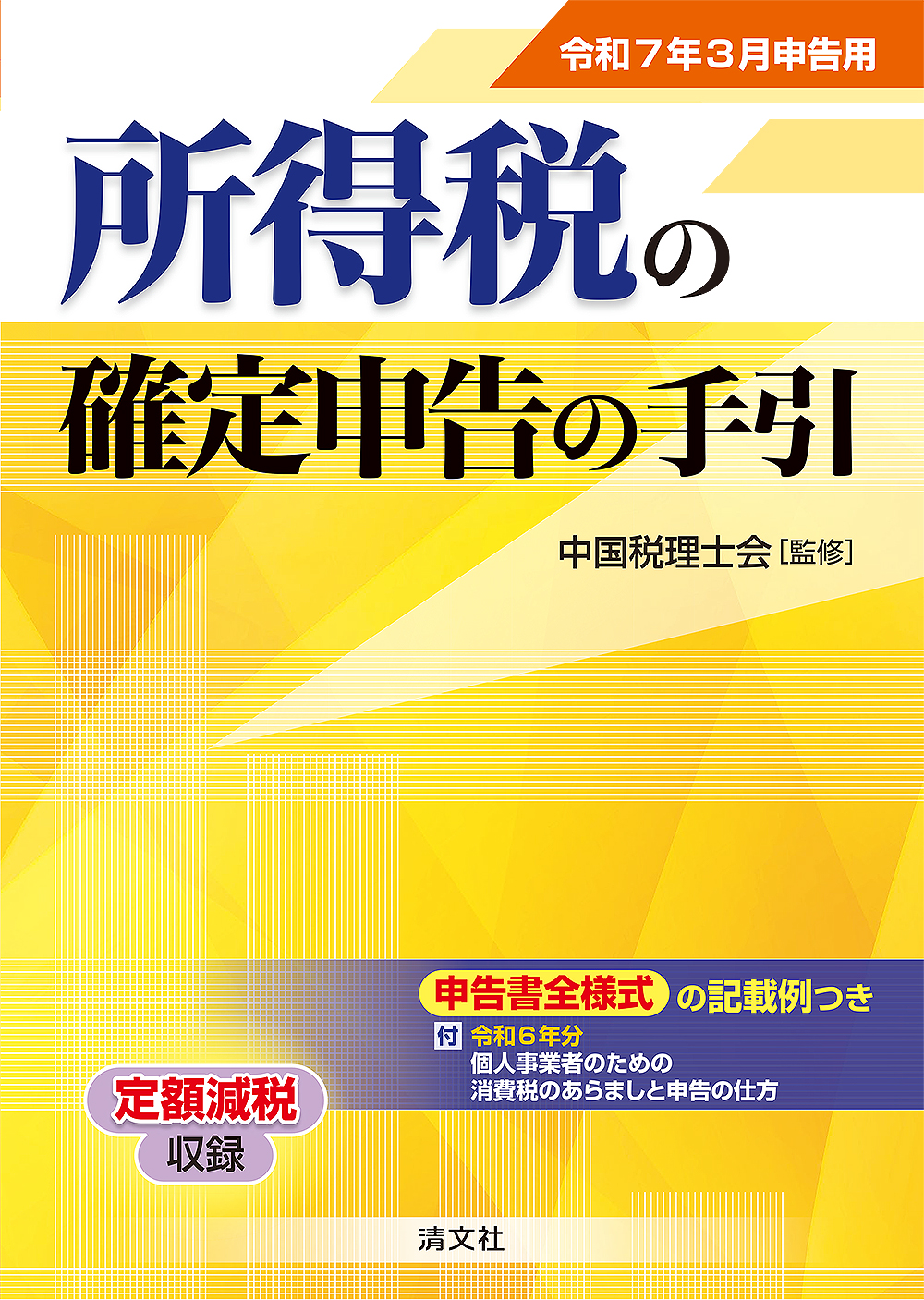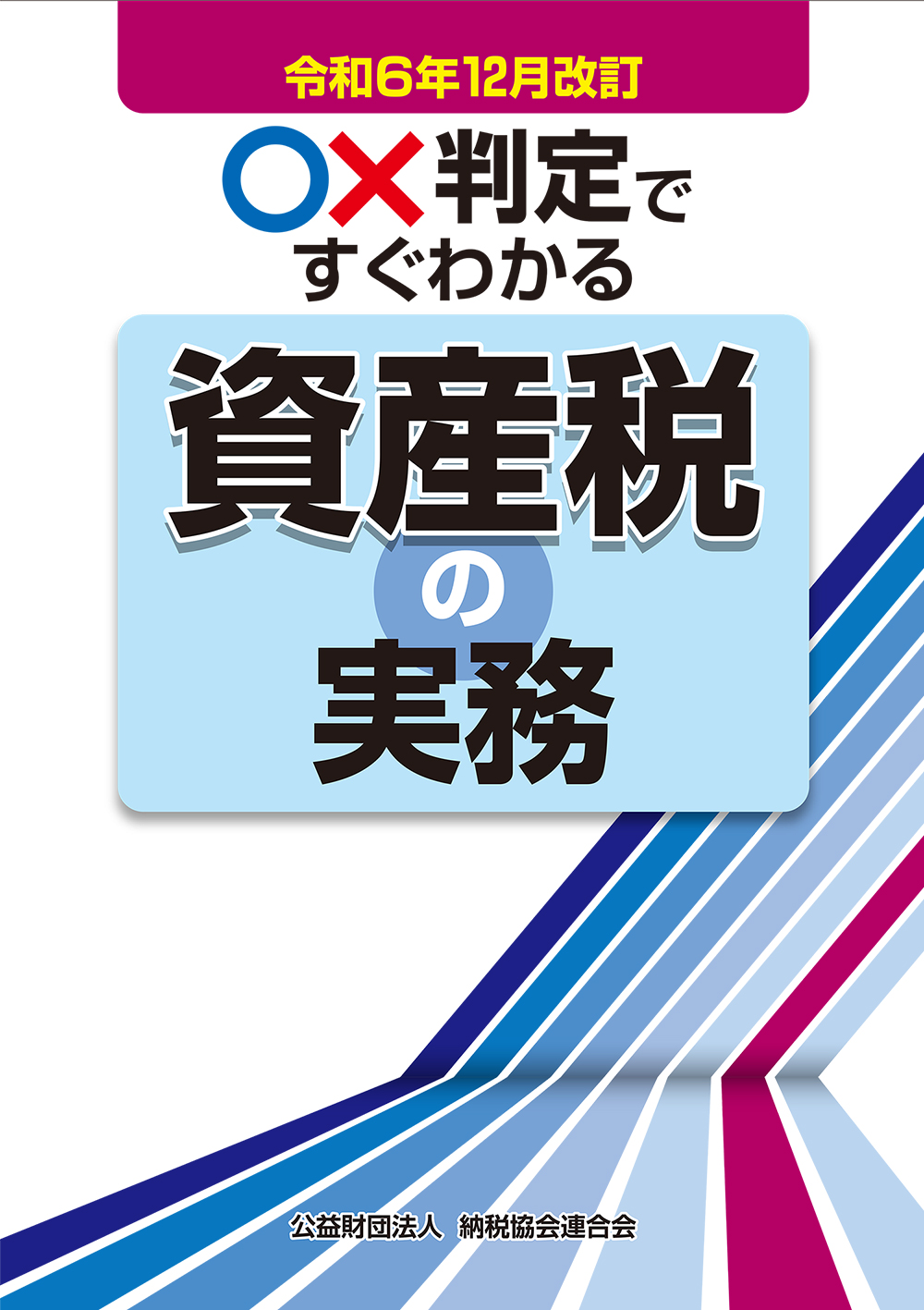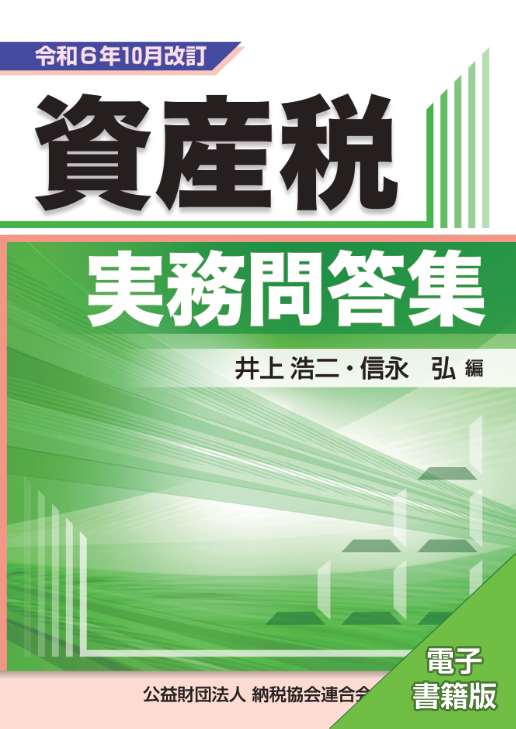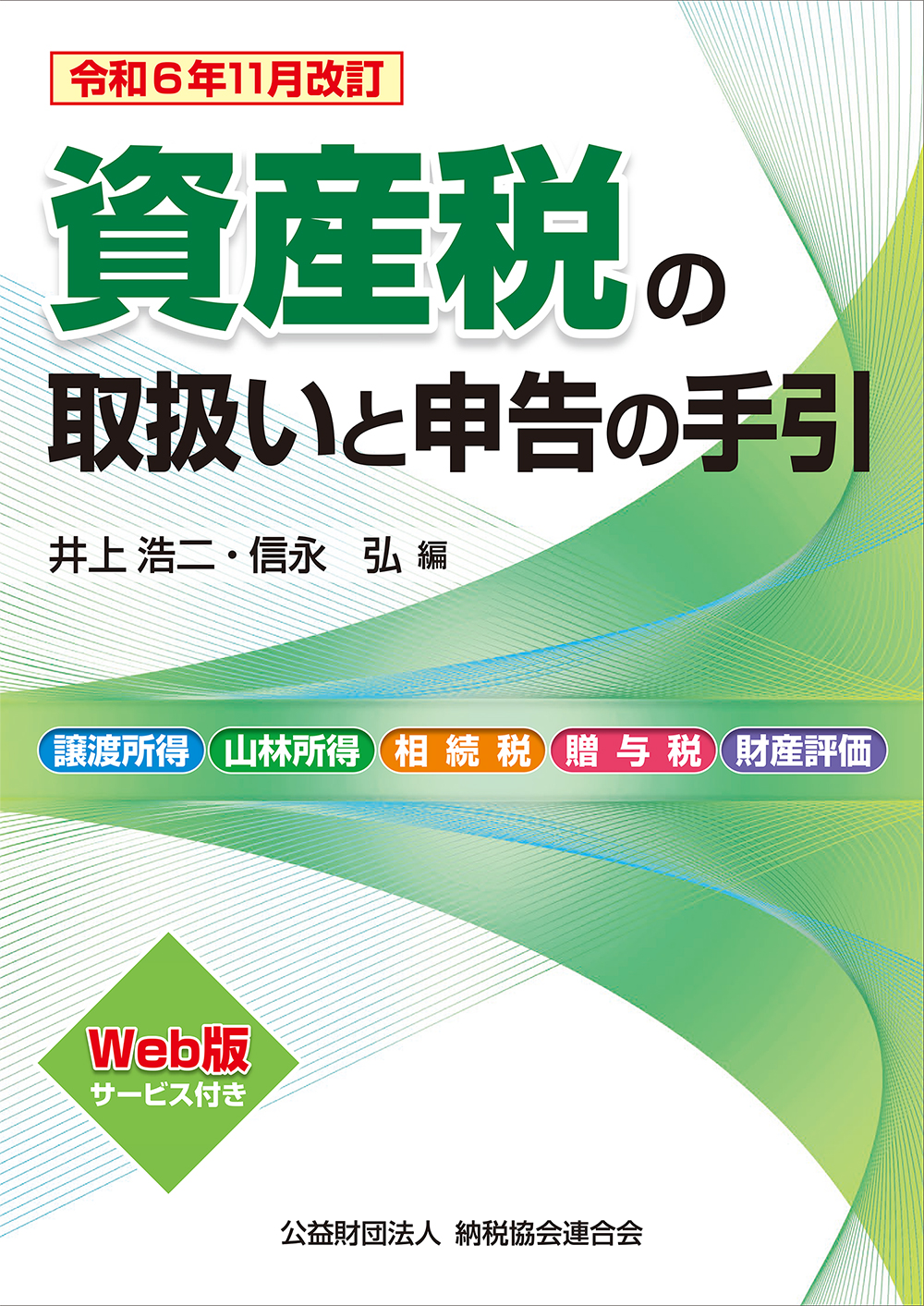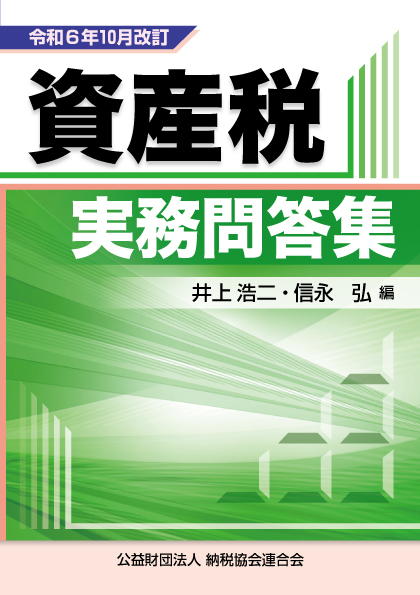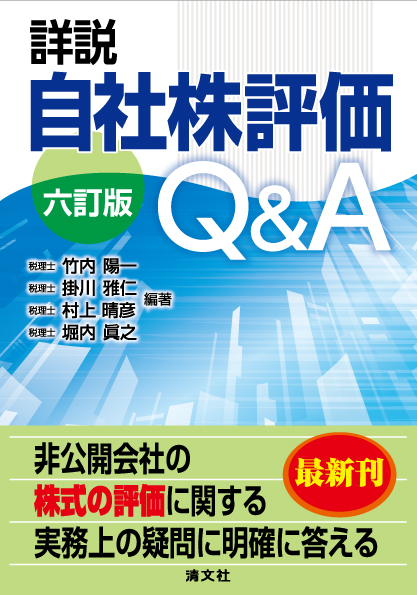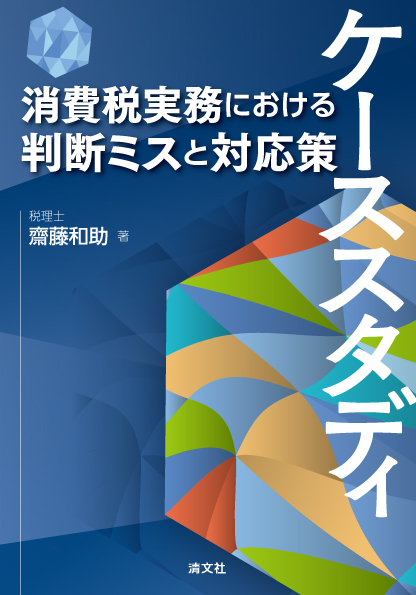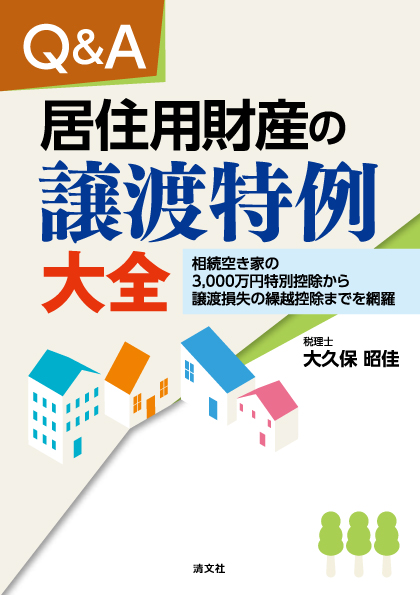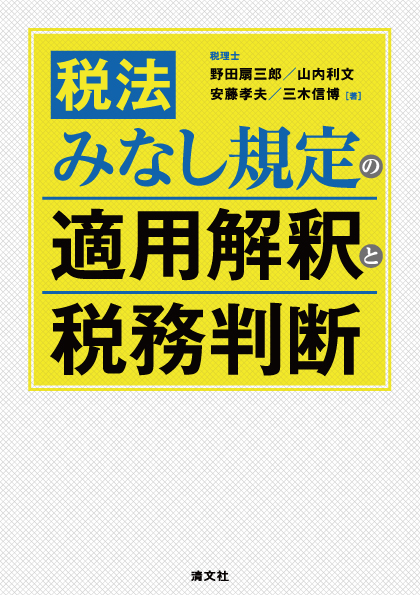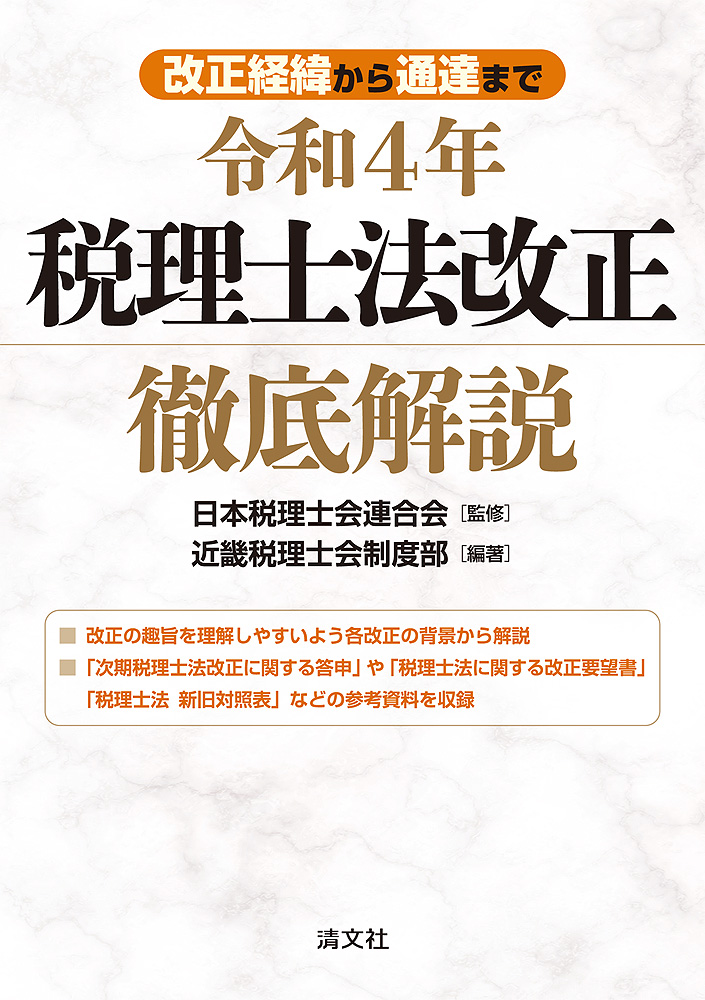「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例12(所得税)】
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
税理士は、相続税対策のため、依頼者の所有する同族法人株式を発行法人に売却することを提案した。その際、みなし配当所得の計算の基礎となる「資本金等の額」の解釈を誤り、利益剰余金をも含めたところの「株主資本」の金額に基づいて1株当たりの資本金等の額を過大に計算してしまった。
そのため、配当所得が過少で、譲渡所得が過大なシミュレーションで説明を行ってしまった。
この誤ったシミュレーションにより、依頼者は同族法人への株式売却を決断し実行した。しかし、税務調査により、上記誤りを指摘され、結果として源泉所得税の追加納付を余儀なくされ、トータルでの税負担が当初のシミュレーションの金額より過大となってしまった。
依頼者は正しい税額の説明を受けていれば売却は行わなかったとして、更正処分により増加した所得税及び住民税相当額7,000万円につき賠償を求めてきた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。