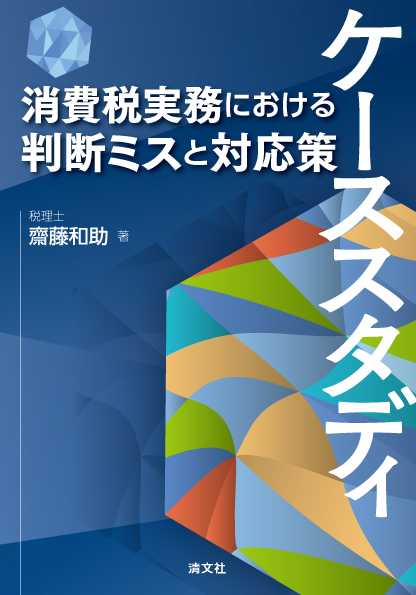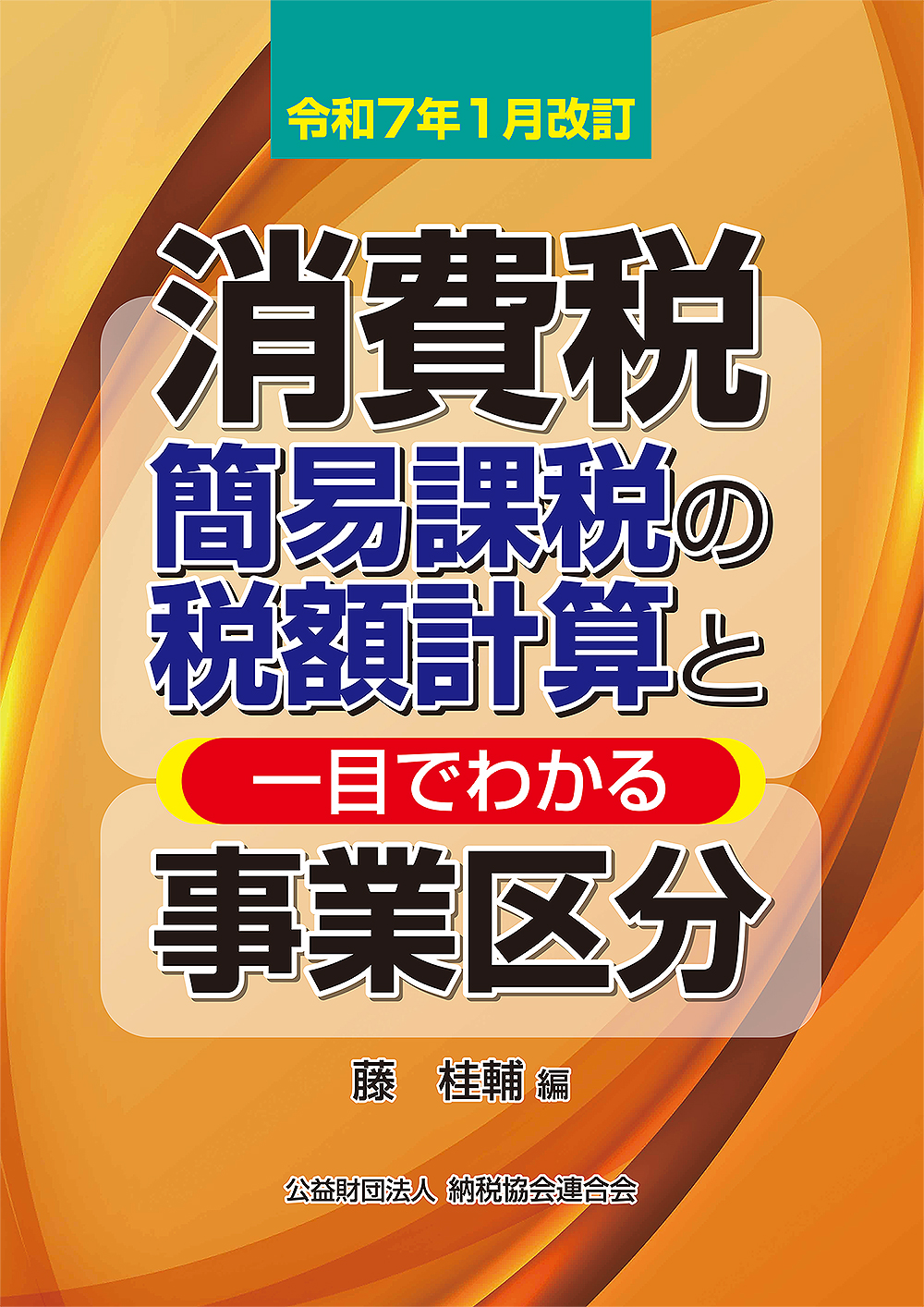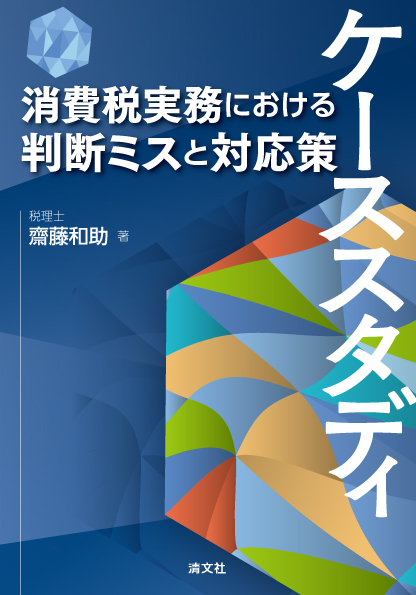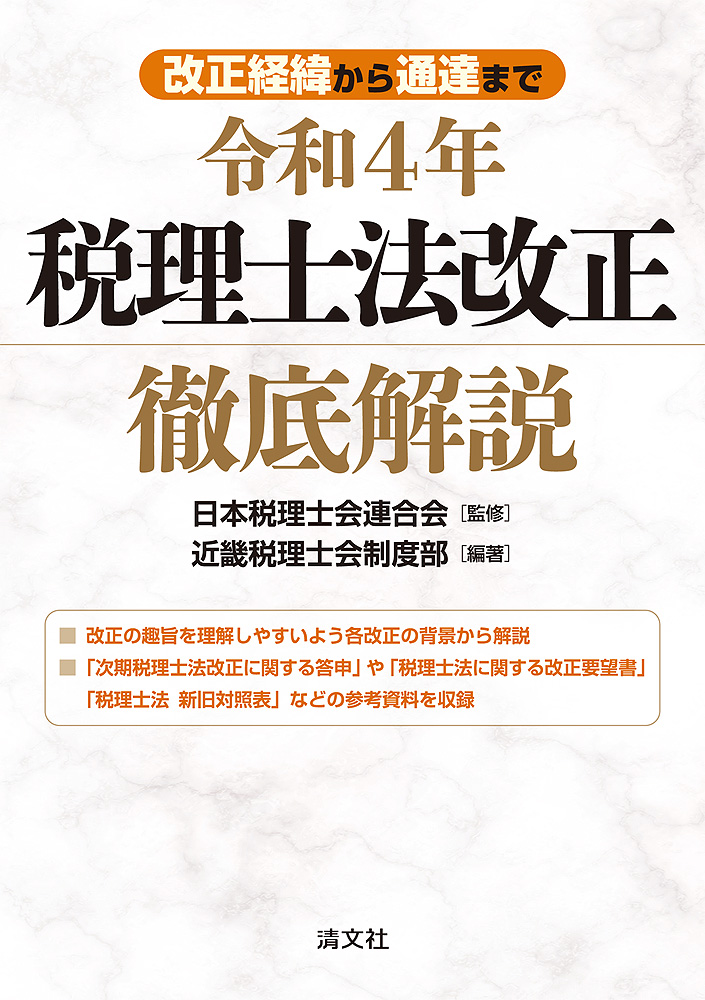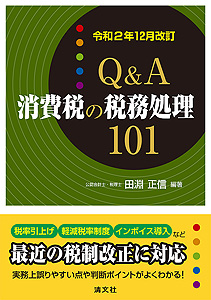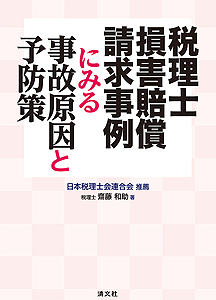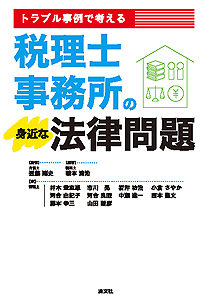「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例74(消費税)】
賃貸建物新築に係る消費税の還付を受けるため「課税事業者選択届出書」を提出したが、「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を失念したため、簡易課税での申告となり、還付を受けることができなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成29年分の消費税につき、賃貸建物新築に係る消費税の還付を受けるため「課税事業者選択届出書」を提出したが、「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を失念したため、簡易課税での申告となり、還付を受けることができなくなってしまった。これにより、消費税につき過大納付税額が発生したとして、賠償請求を受けたものである。
なお、予定通り課税事業者が選択できた場合には、「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例」により3年間、原則課税として拘束されることから、2年後の確定申告期限まで損害額が確定しないこととなる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。