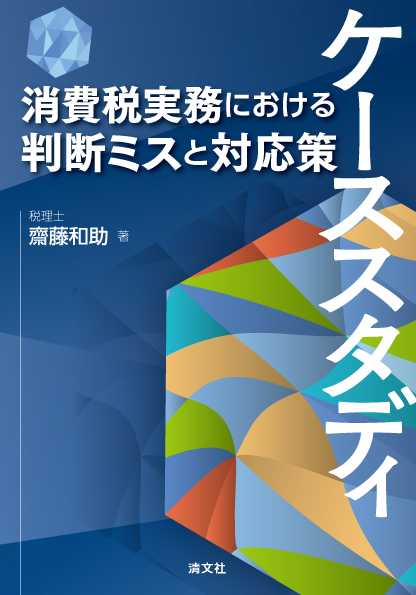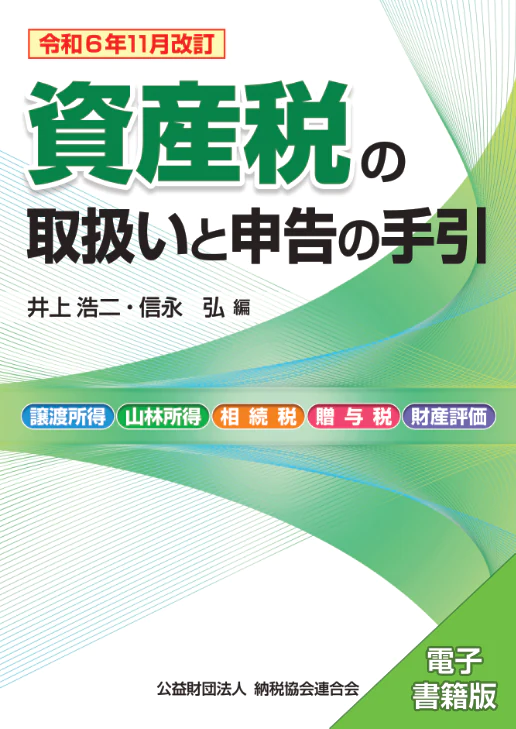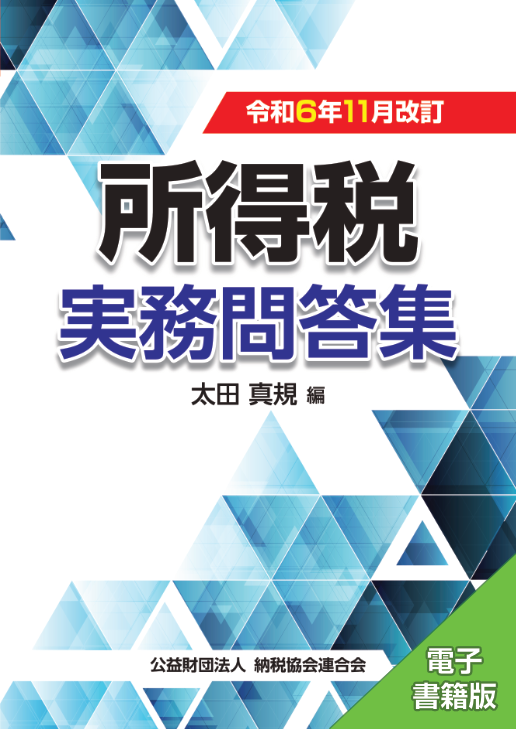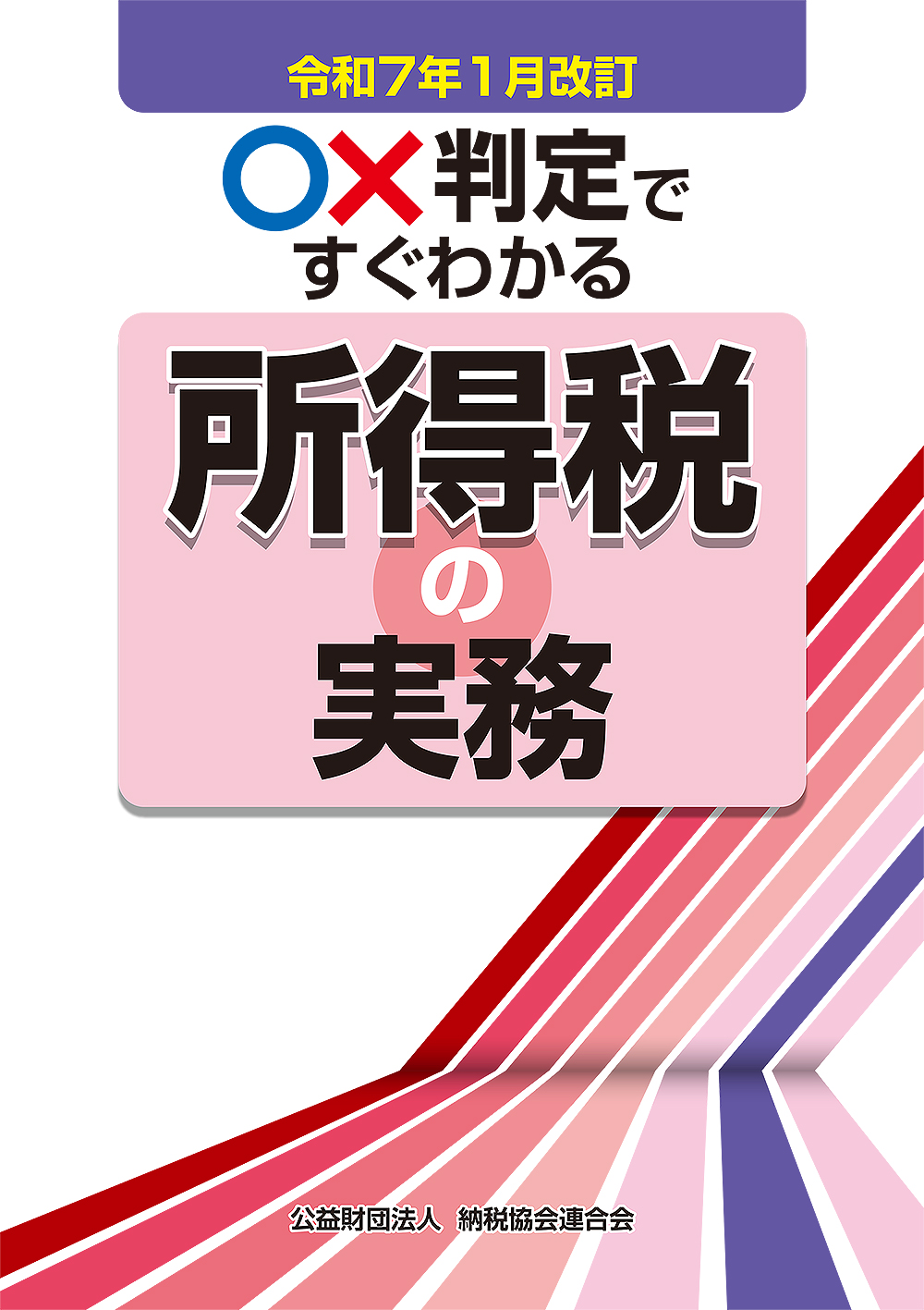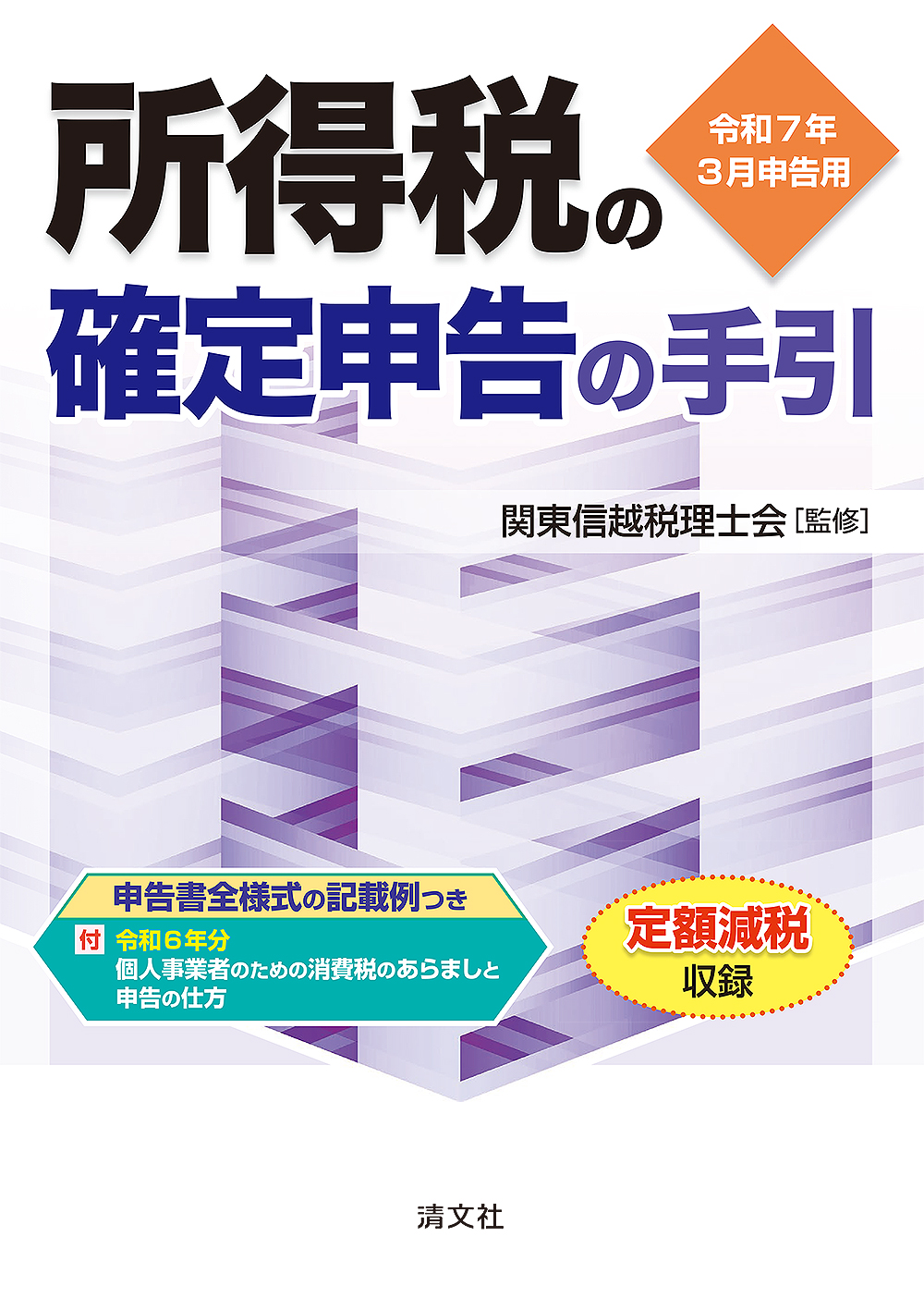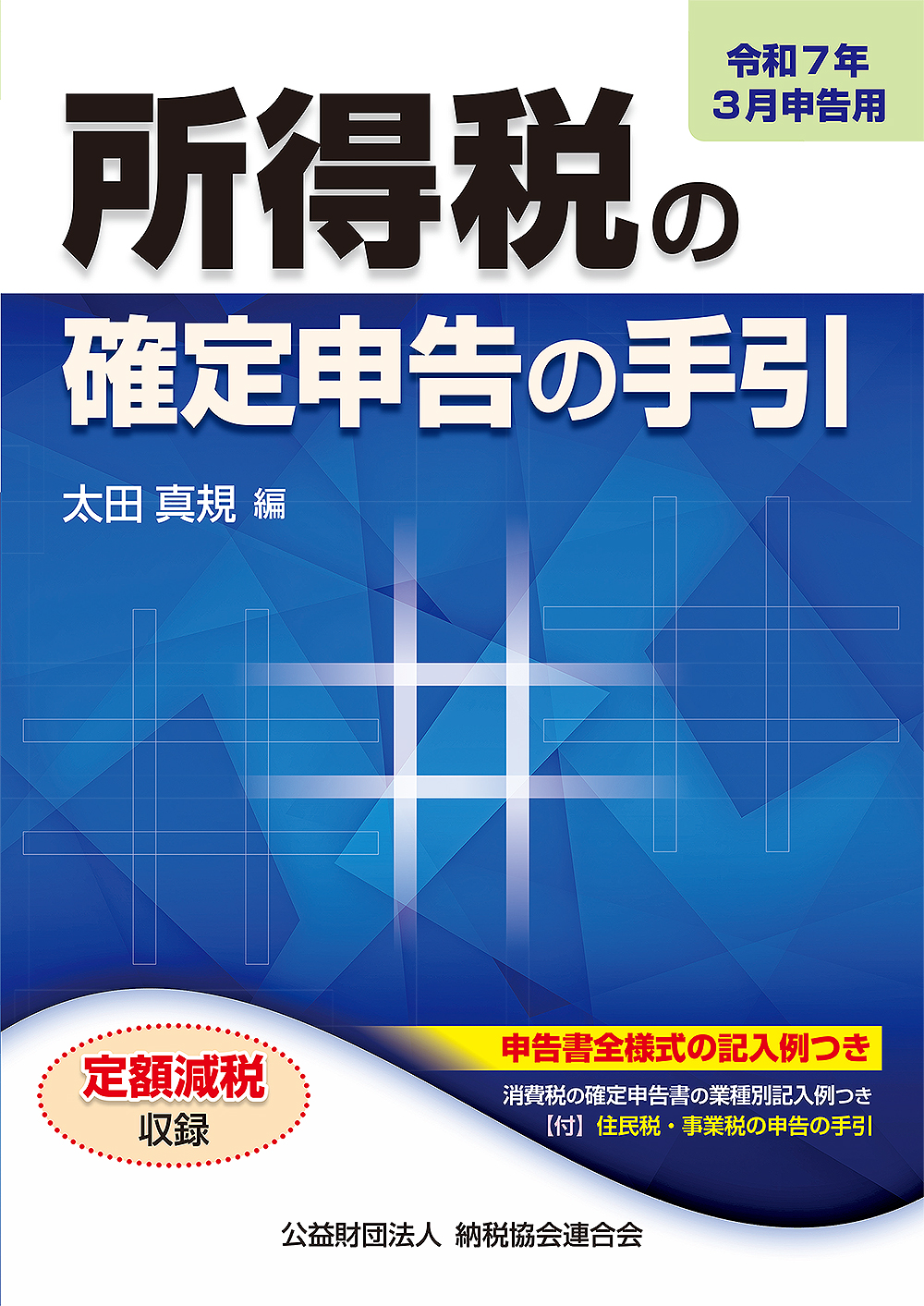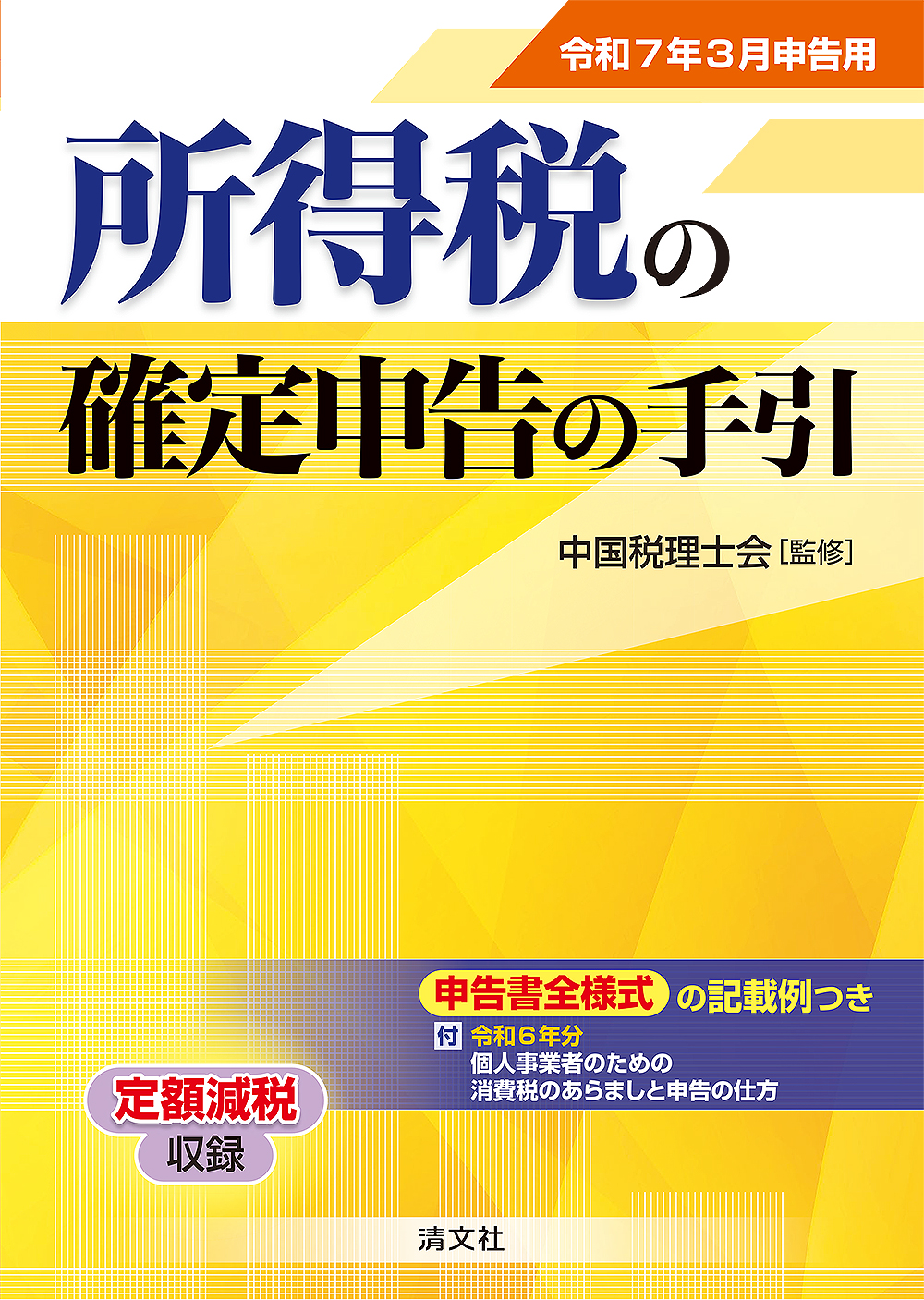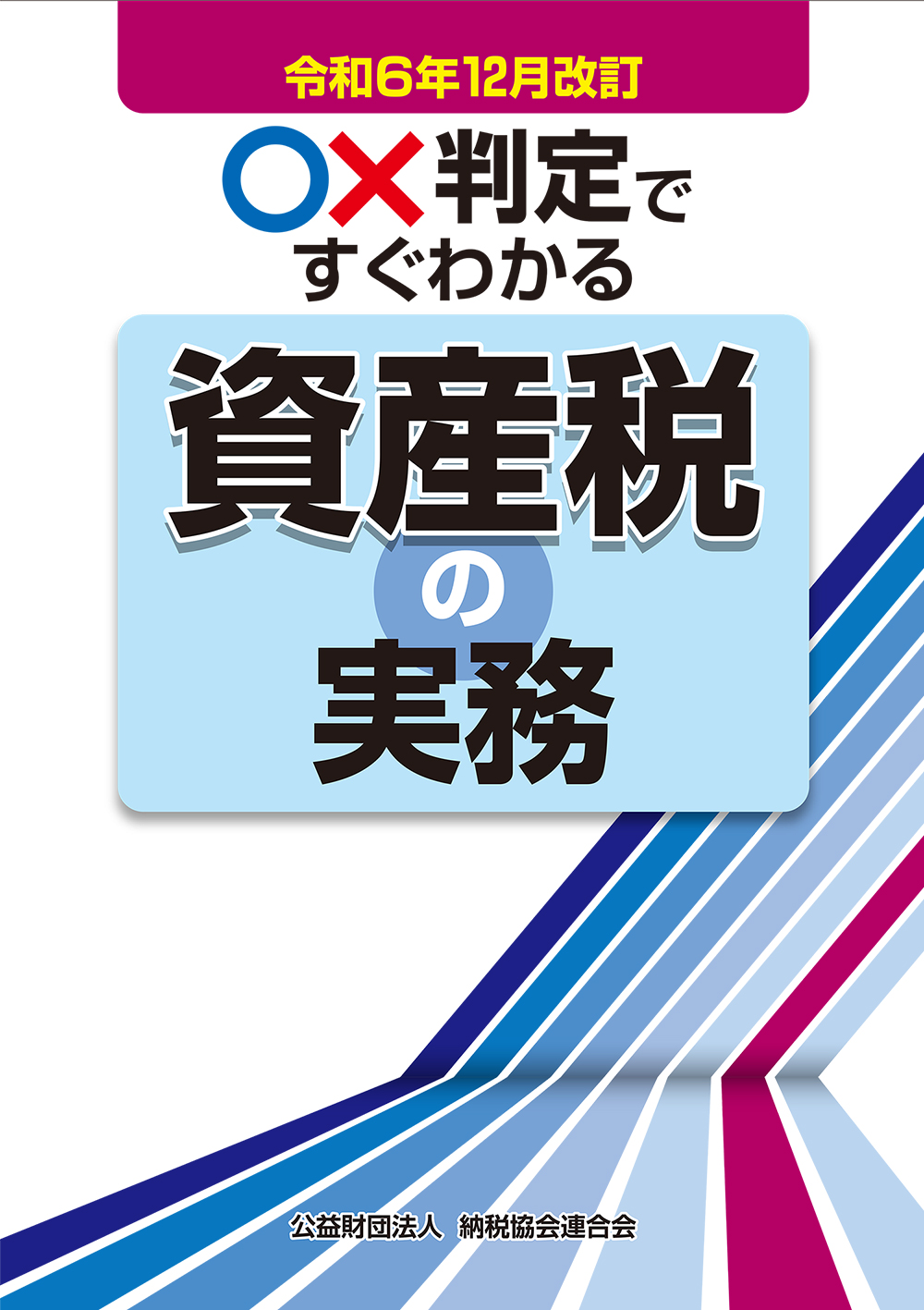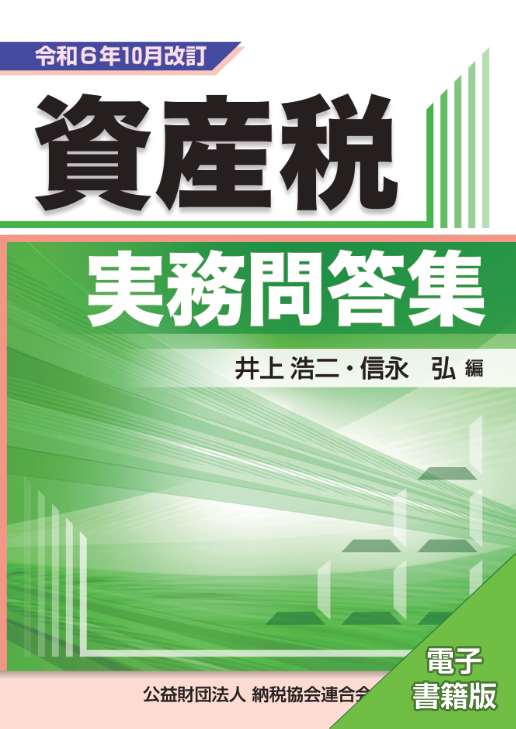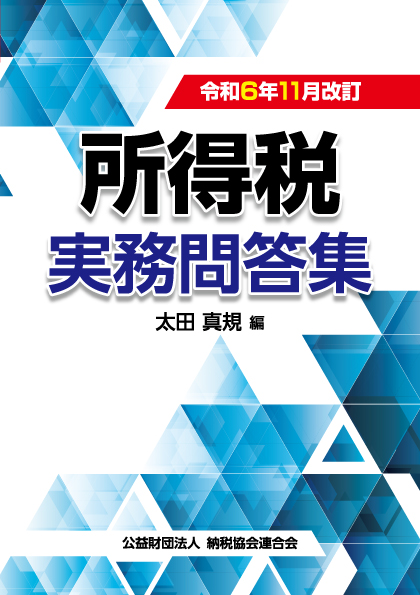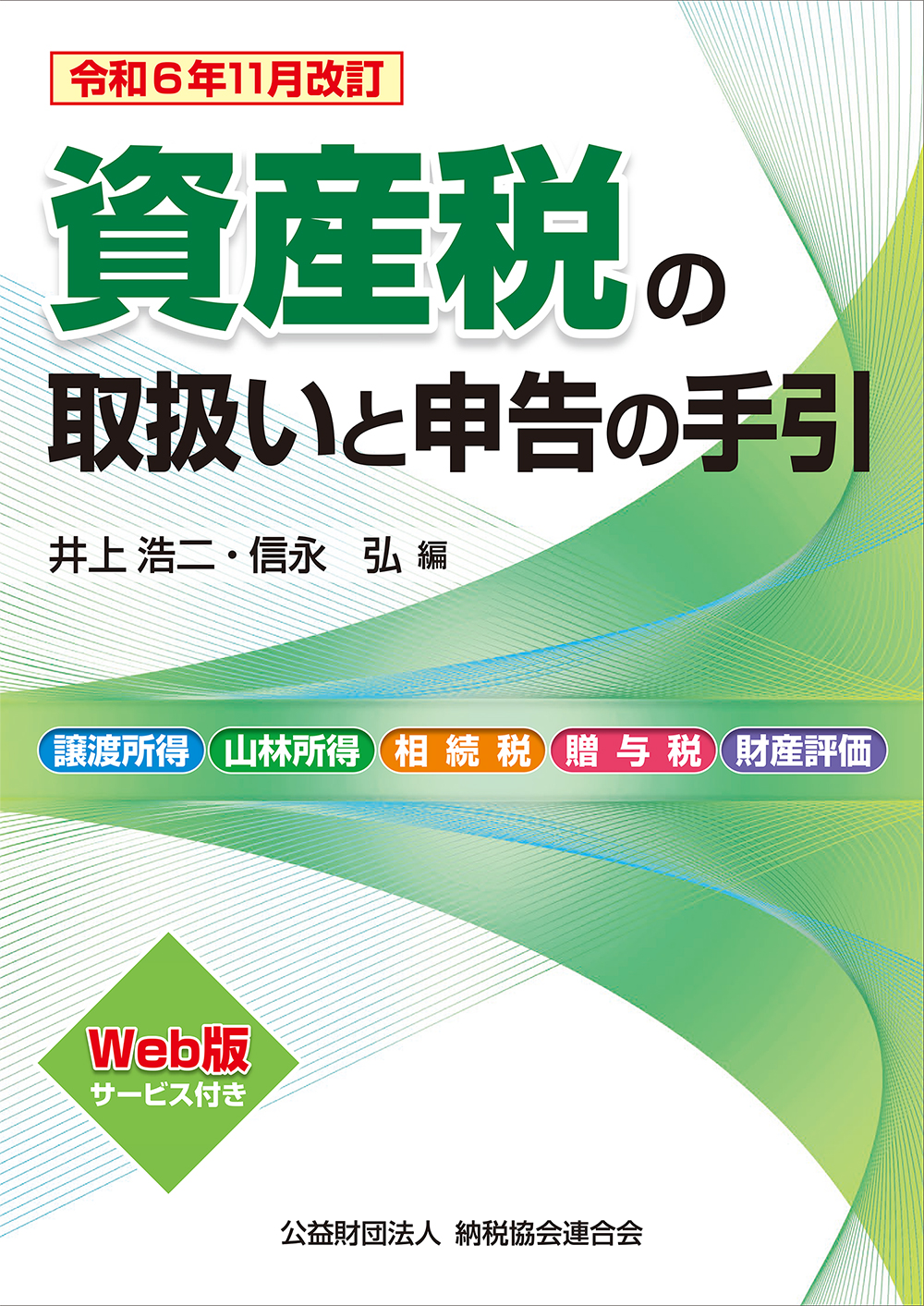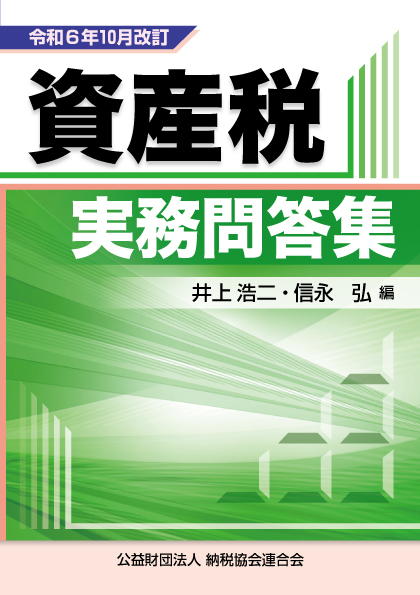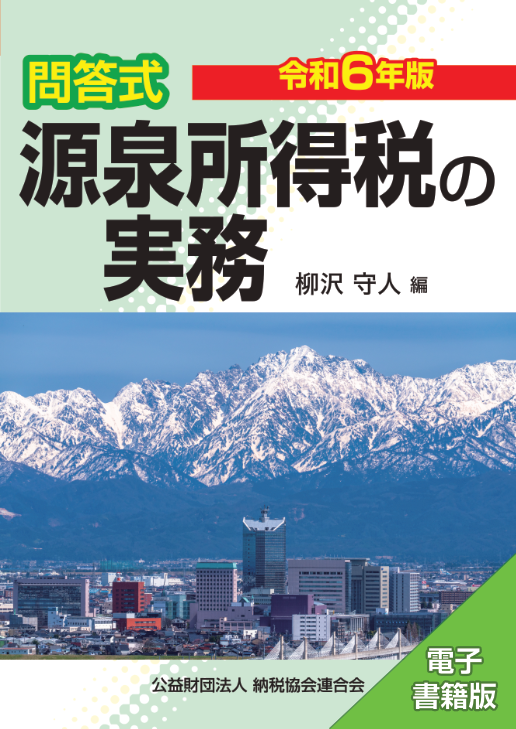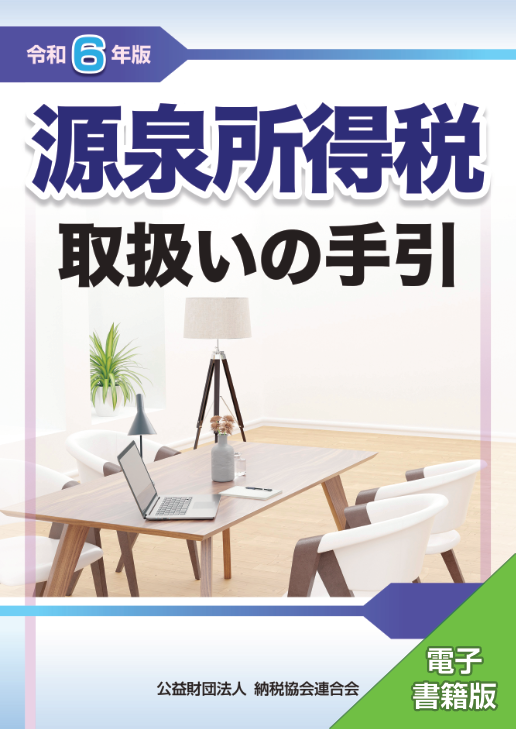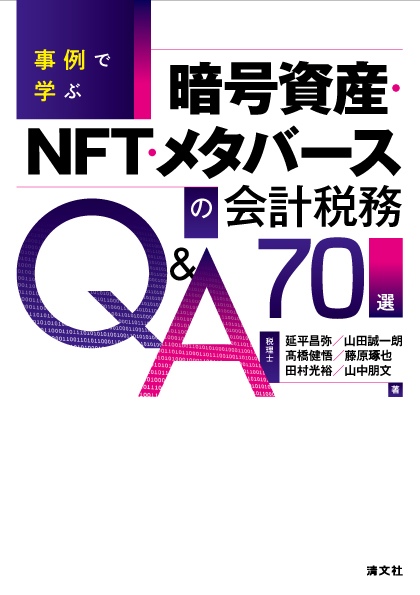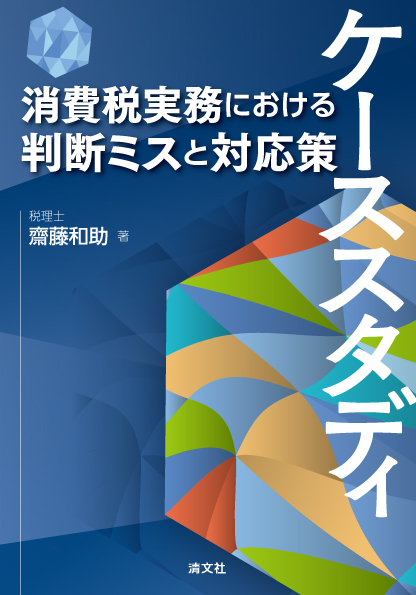「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例35(所得税)】
平成26年分の所得税につき、平成25年分の確定申告書を期限後申告しなかったため、平成24年に生じた上場株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用ができなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成26年分の所得税につき、配当控除を使用するため、平成25年分の確定申告書を期限後申告せずに総合課税で申告したため、平成24年に生じた上場株式に係る譲渡損失との損益通算ができなくなってしまった。これにより、過少となった還付所得税につき損害が発生し賠償請求を受けたものである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。