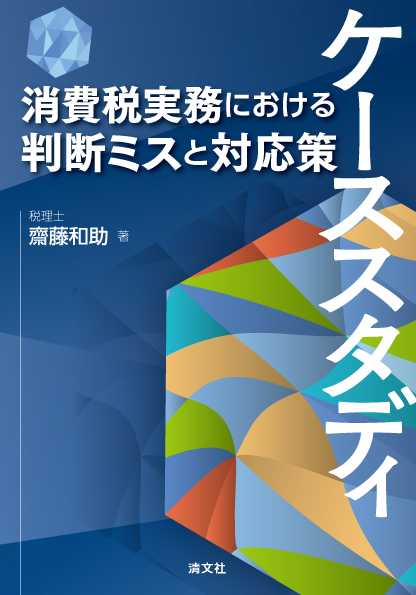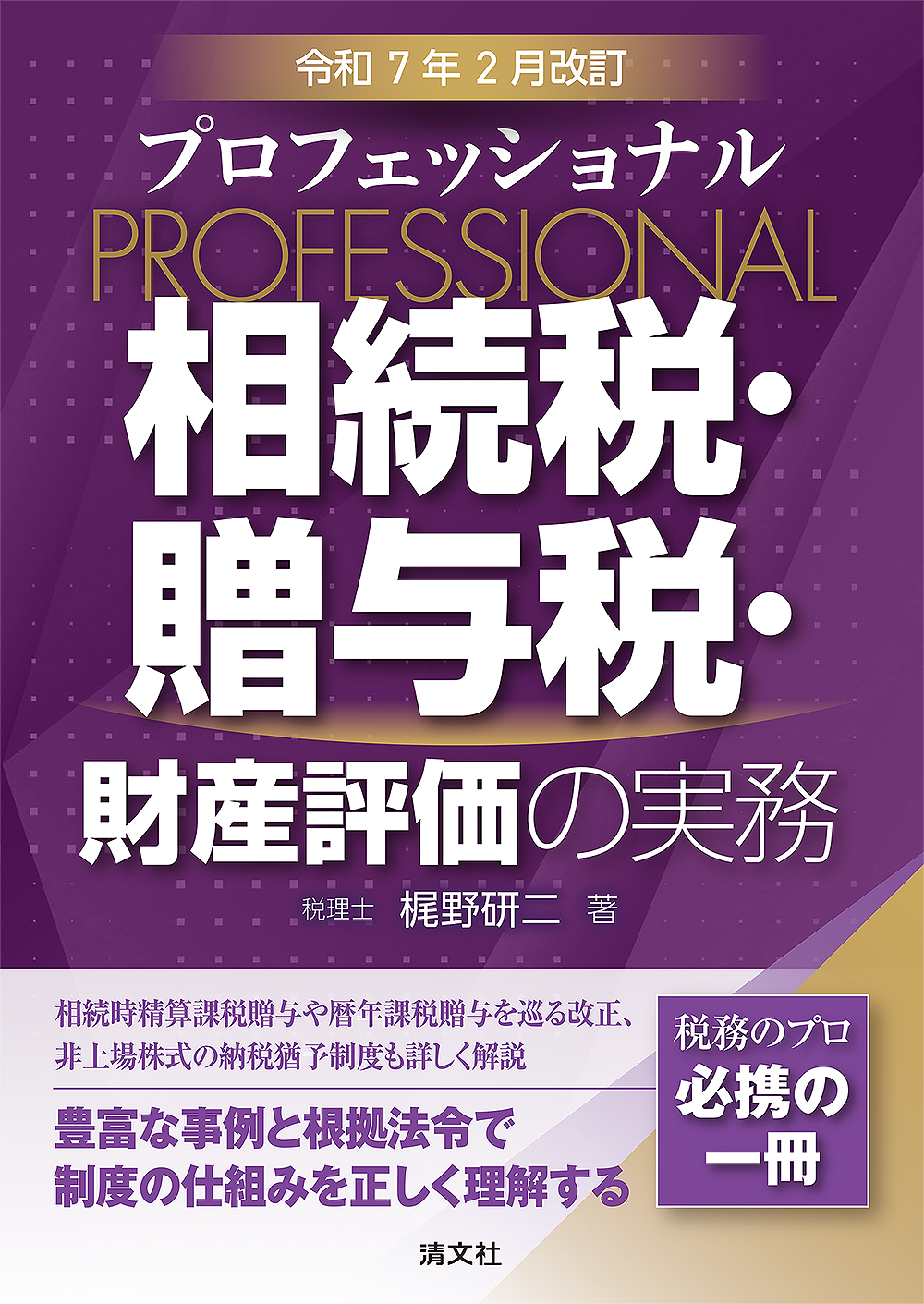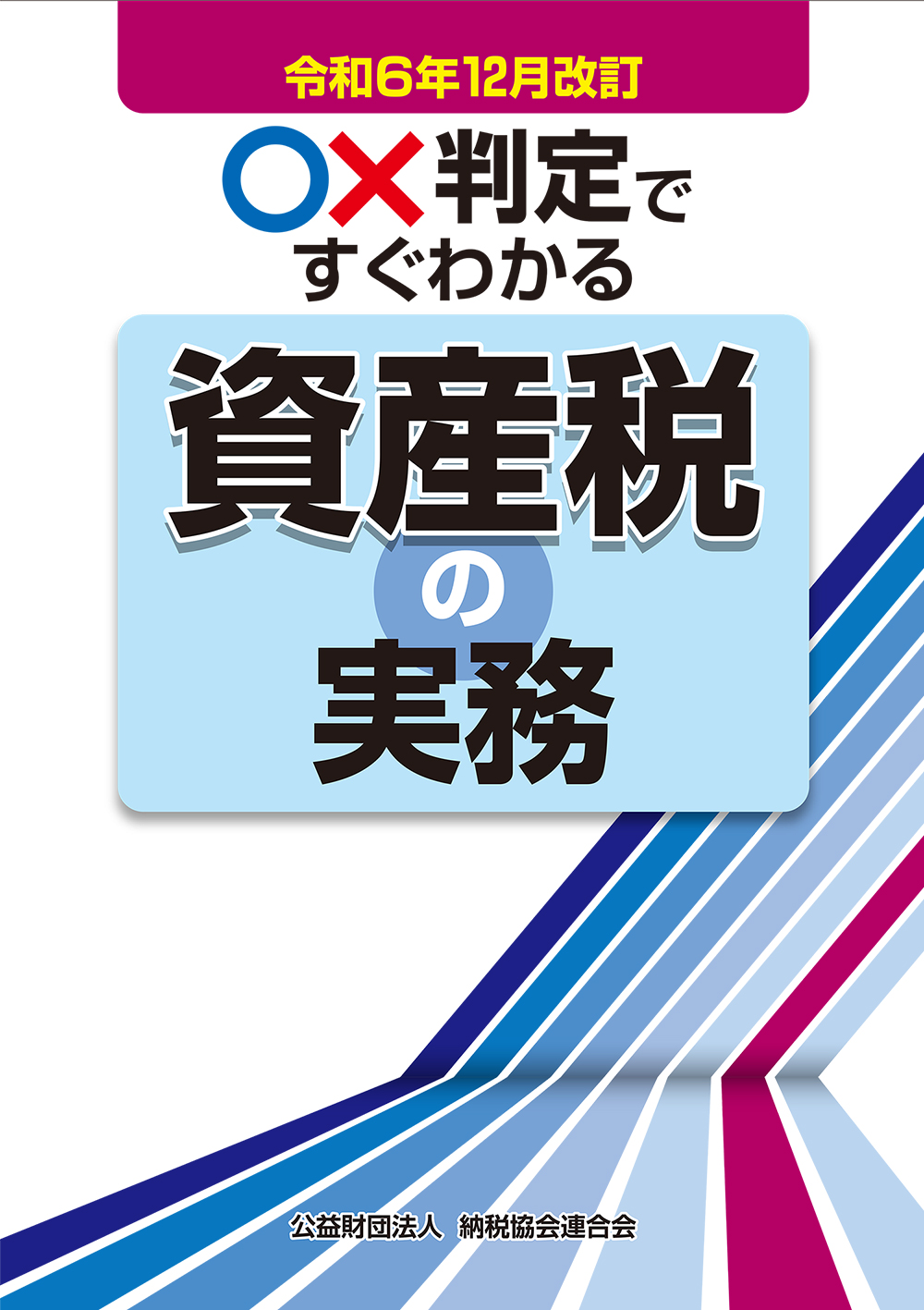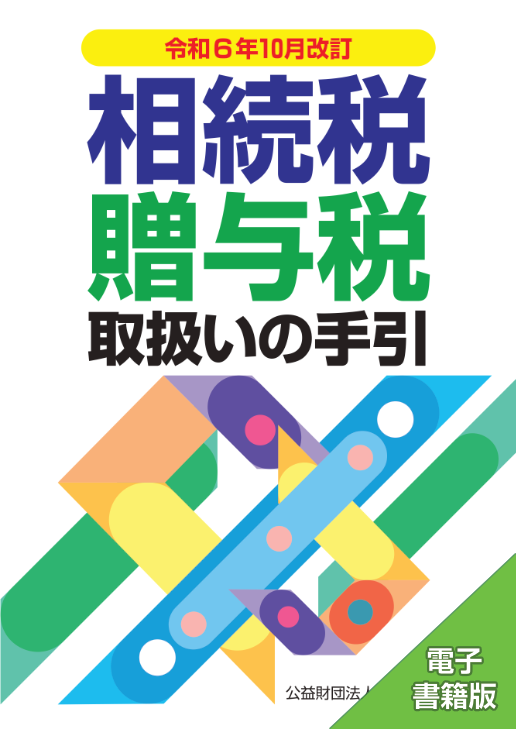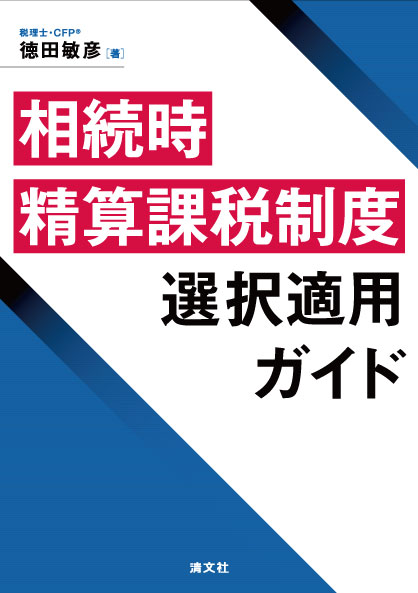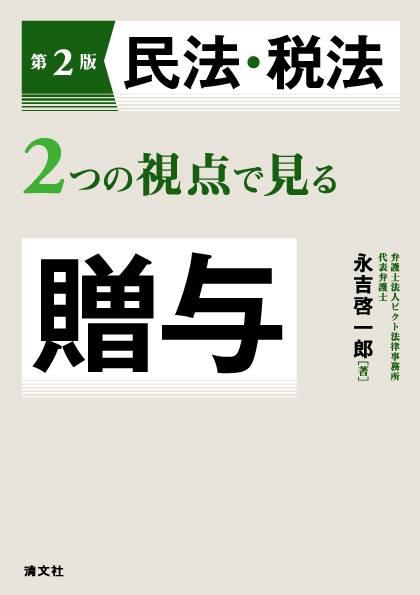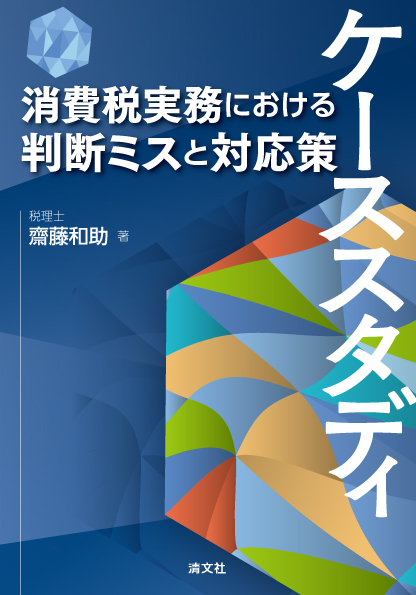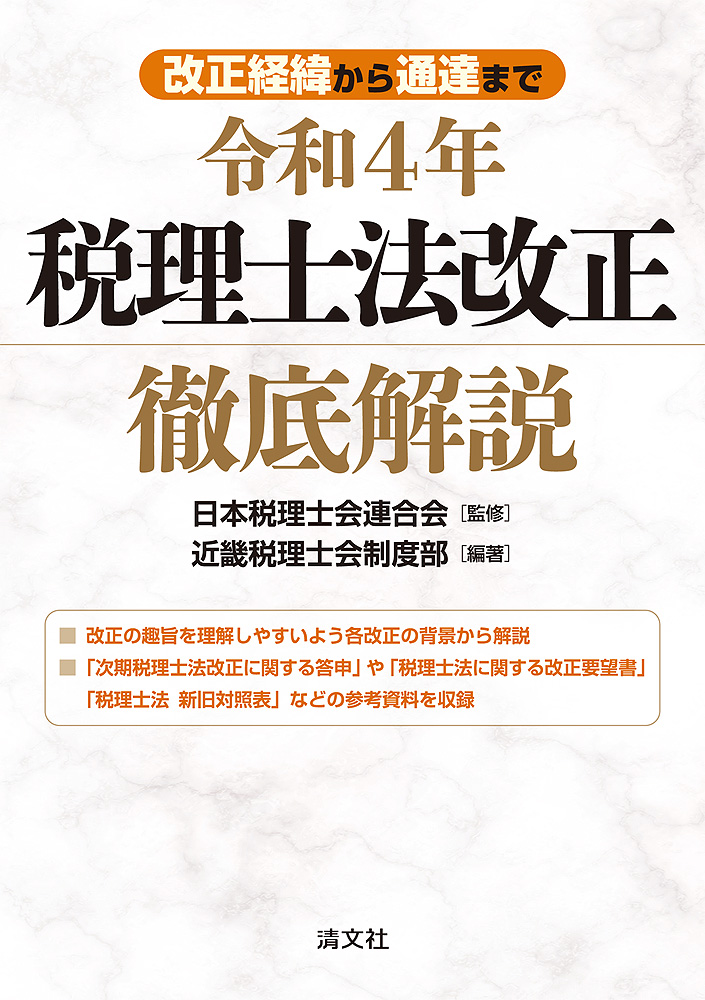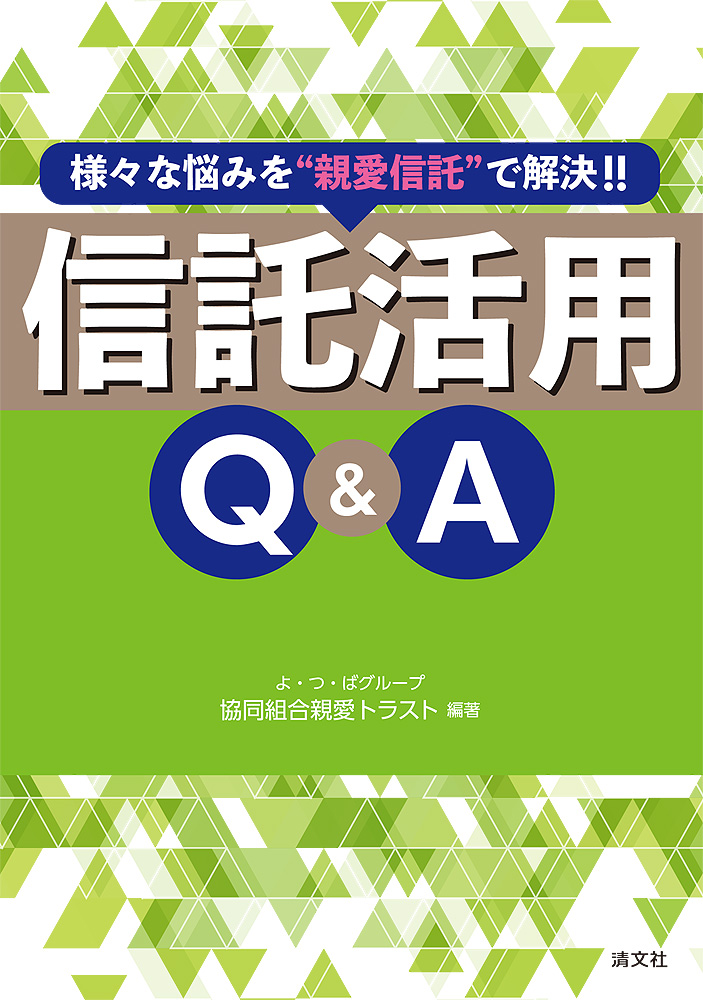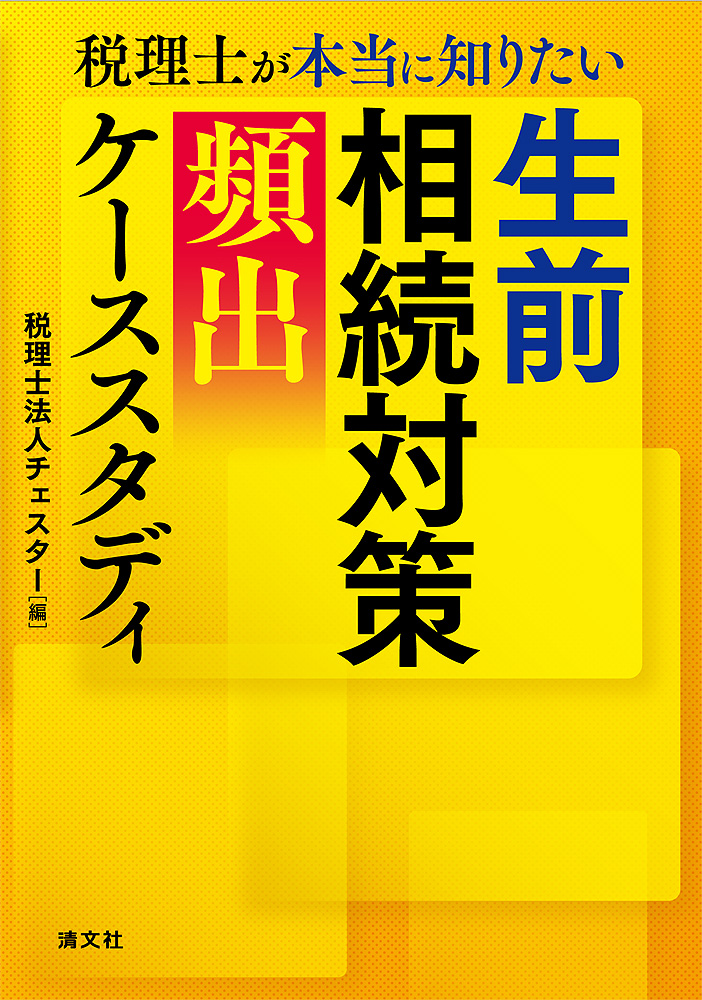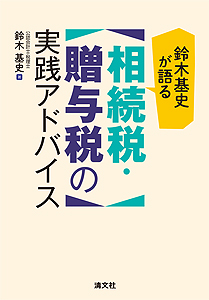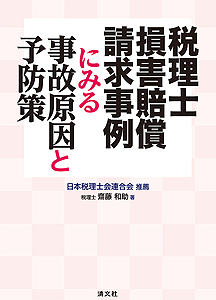「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例1(贈与税)】
税理士 齋藤 和助
〈連載に当たって〉
本連載は、長年、税理士職業賠償責任保険の調査に携わってきた筆者が、実際の事故事例を参考にして、実務において頻出しているミスや、起こりうる事故を事例として紹介し、どのようにして事故が起きたのか、事故のポイントはどこか、税理士の責任はどこにあるのか、そしてどのようにすれば事故が防げたのかを考え、その予防策を探っていこうというものである。
日常の実務において、また同じ業務を受任した際に気を付けるべき点として参考にしていただければ幸いである。
《事例の概要》
平成21年分の贈与税につき、相続時精算課税の適用を受けることができる祖母からの土地の贈与につき、暦年課税により贈与税の申告を行った。ところが贈与から3年以内の平成23年に祖母が死亡したため、贈与を受けた土地を持ち戻して相続税の申告を行おうとしたが、相続人の見積りによれば、相続財産の合計額が基礎控除以下となったため、相続税は発生しなかった。
このため、依頼者より、平成21年分の土地の贈与に相続時精算課税を適用していれば、贈与税は支払わずに済んだとして、支払った暦年贈与税額につき賠償請求を受けたものである。
《賠償請求の経緯》
相続時精算課税とは、生前の贈与について、納税者の選択により、贈与時に贈与財産に対して一定の贈与税を支払い、相続開始時にその贈与財産を相続財産にプラスして相続税を計算し、支払った贈与税を精算する制度である。ただし、特別控除額の2,500万円までは贈与税はかからず、さらに相続開始時にこれらの生前贈与財産をプラスしても相続税がかからない場合には、贈与税の負担なしで生前贈与が可能となる。
一方、暦年課税は、年間110万円を超える部分に関しては贈与税がかかるが、相続開始前3年を超える贈与に関しては、相続財産から切り離して相続税の計算をすることができる。
依頼者は、相続時精算課税の適用のある祖母から特別控除額以下の土地の贈与を受け、贈与税の申告について税理士に相談した。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。