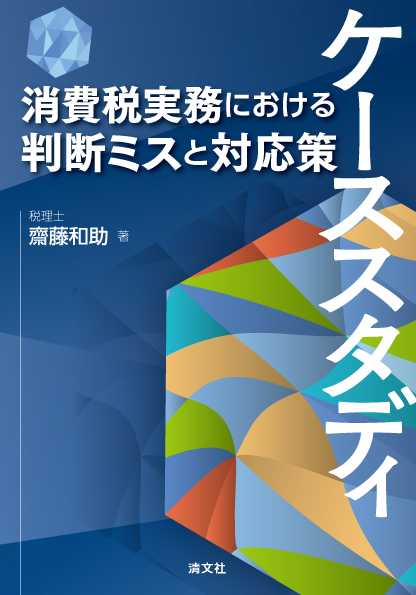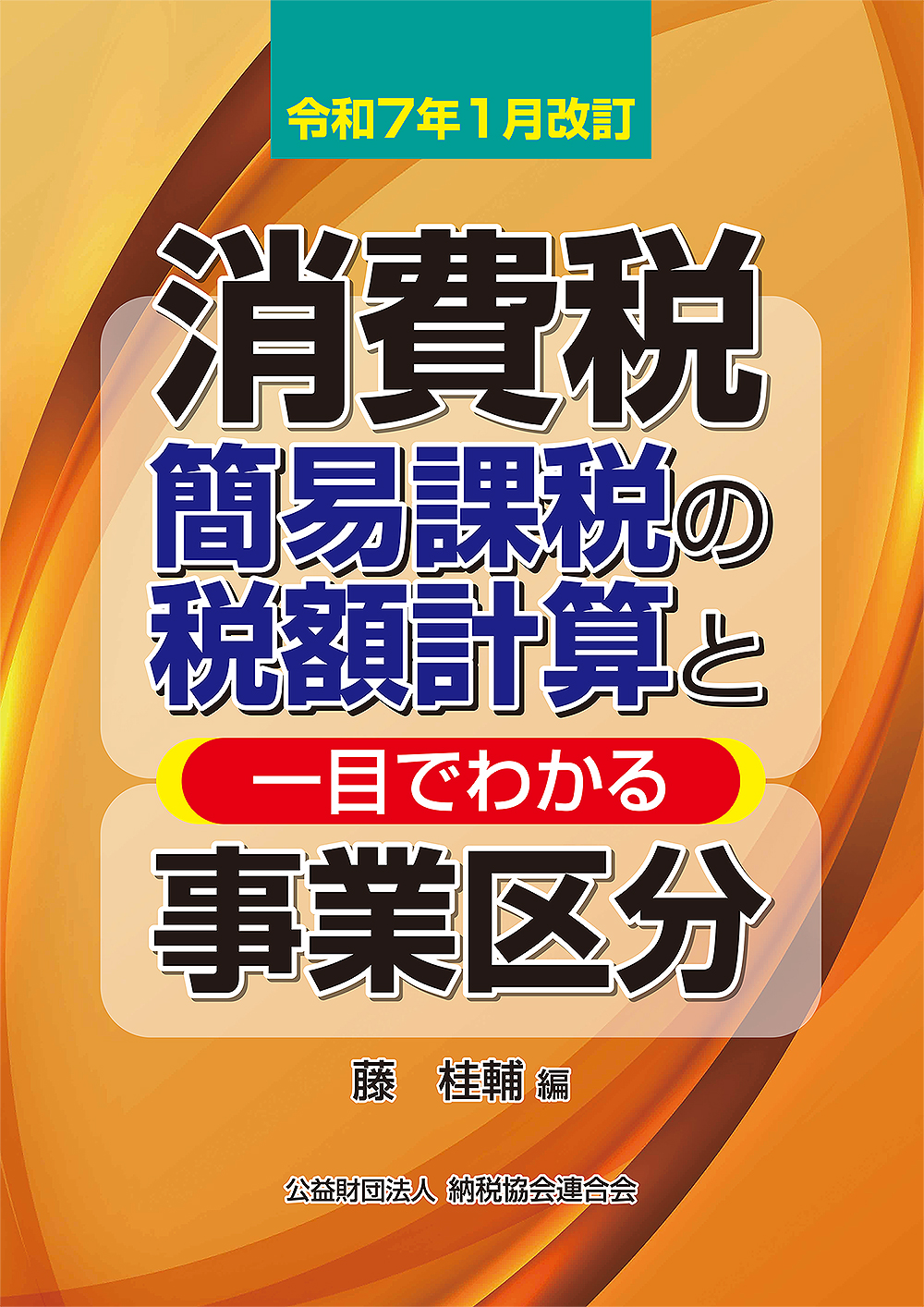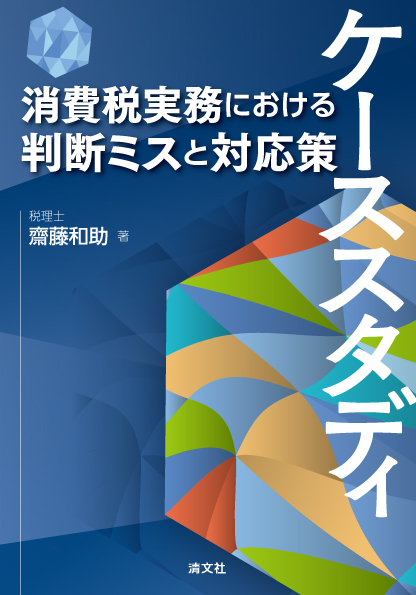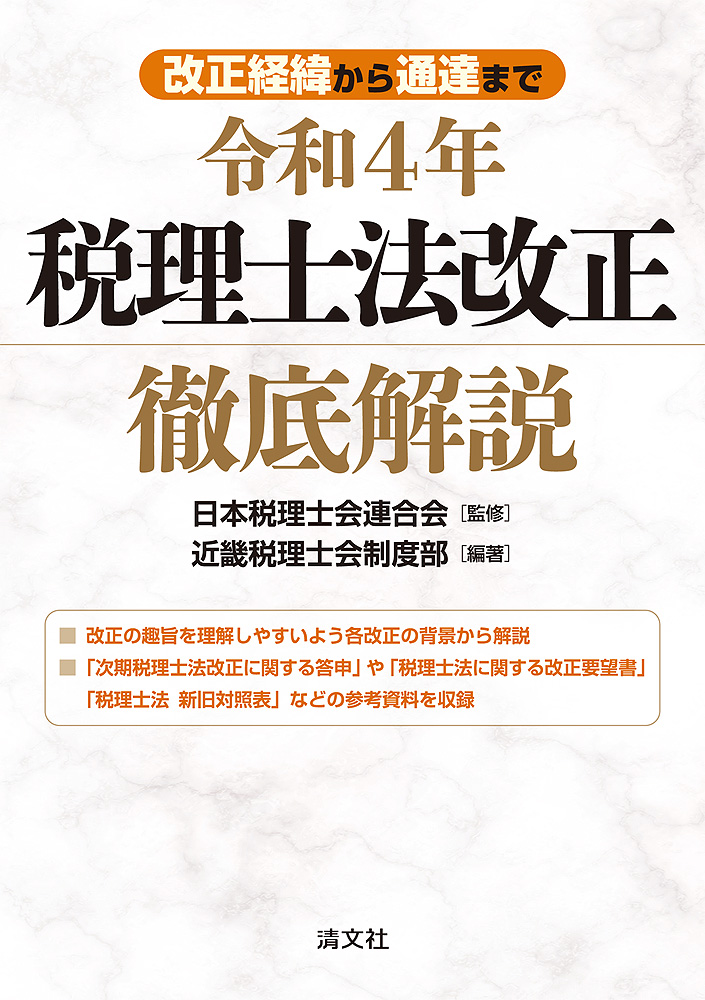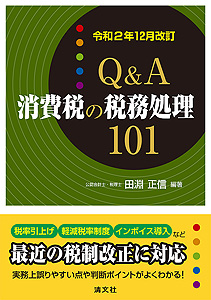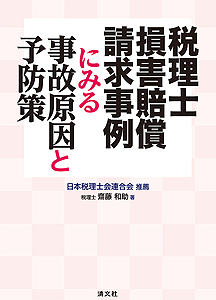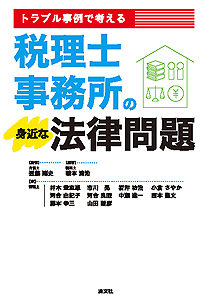「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例93(消費税)】
「調整対象固定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例」により「課税事業者選択不適用届出書」を提出することができない期間中に同届出書を提出したため、届出書の提出がなかったものとみなされてしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和元年分の消費税につき、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者になることができたにもかかわらず、「調整対象固定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例」により「課税事業者選択不適用届出書」を提出することができない期間中に、免税事業者が選択できない平成30年からの「課税事業者選択不適用届出書」を提出したため、届出書の提出がなかったものとみなされてしまった。
これにより、免税事業者が選択できた令和元年分の消費税につき過大納付が発生し、賠償請求を受けたものである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。