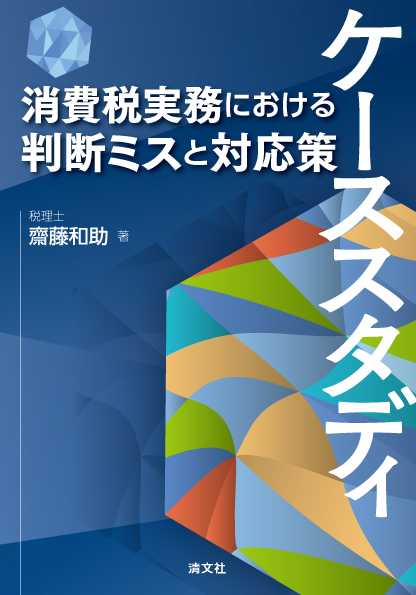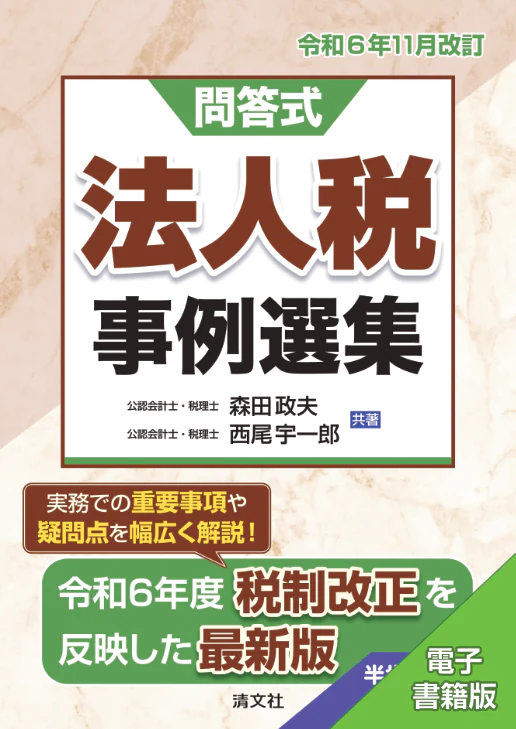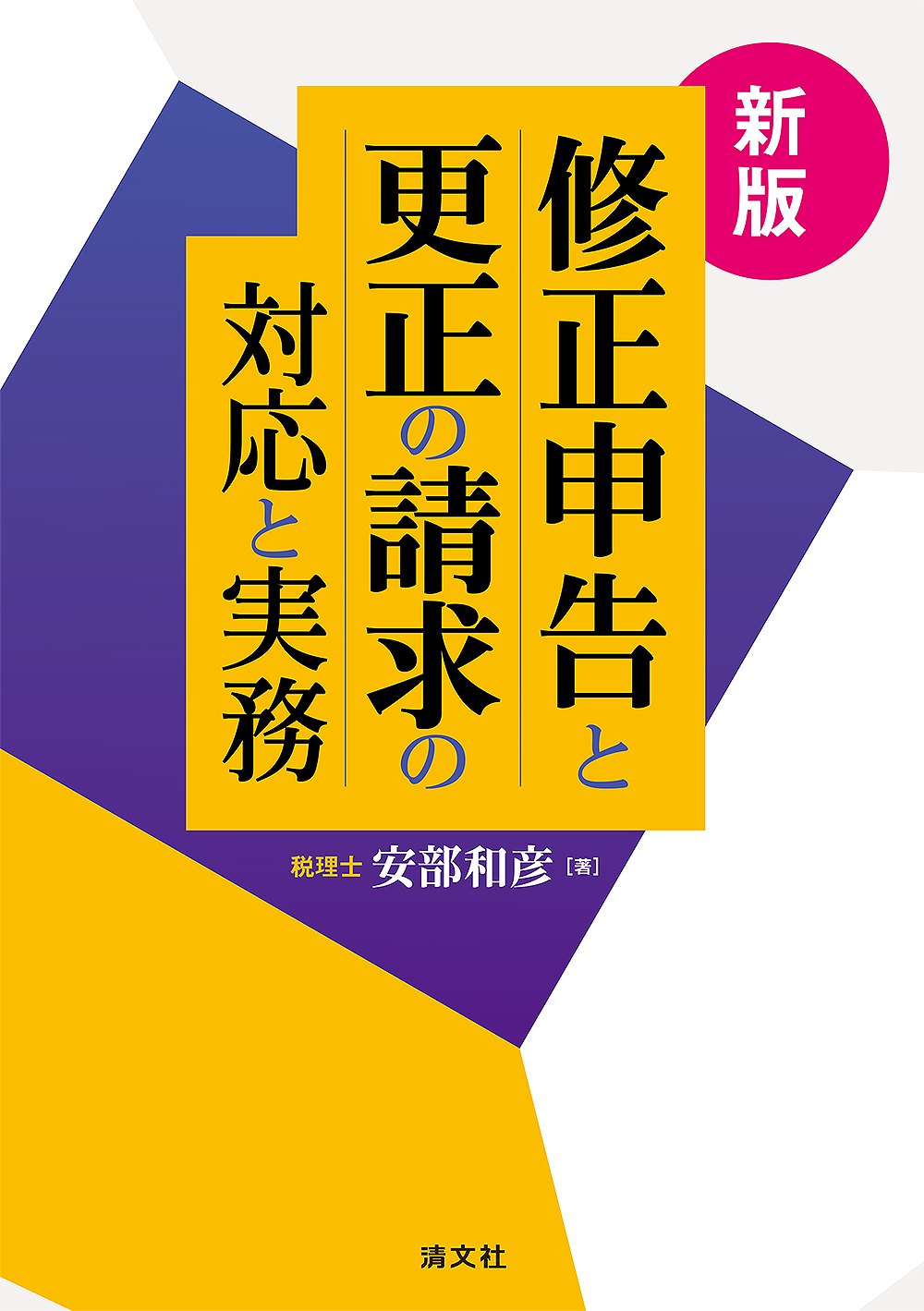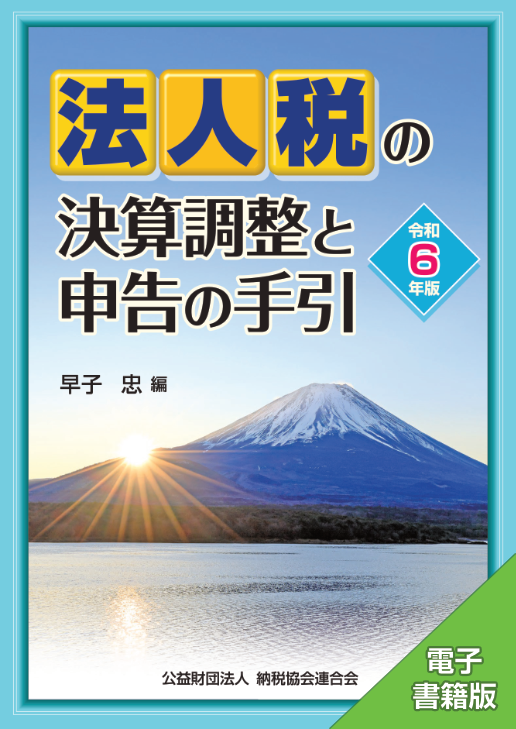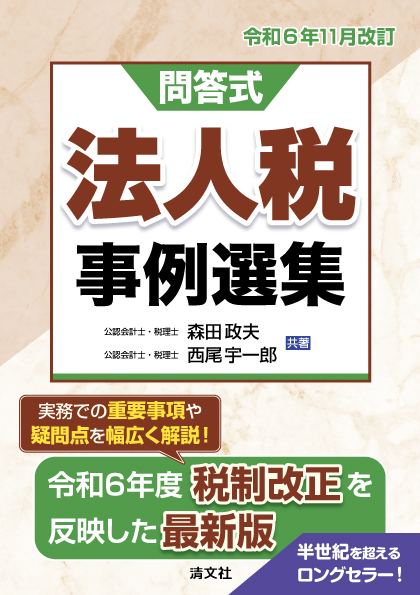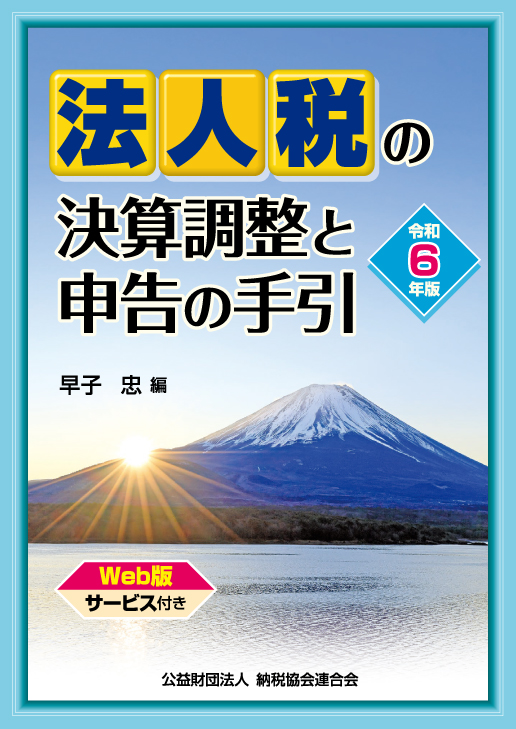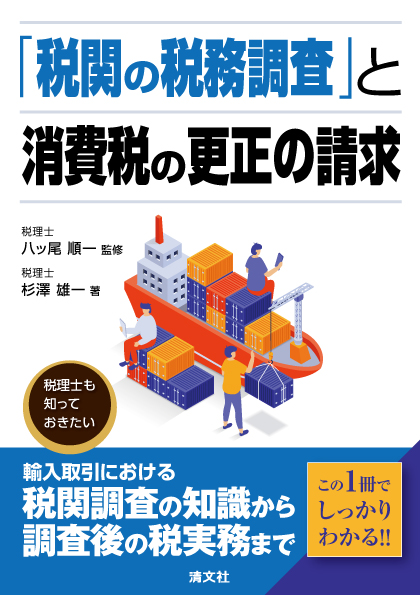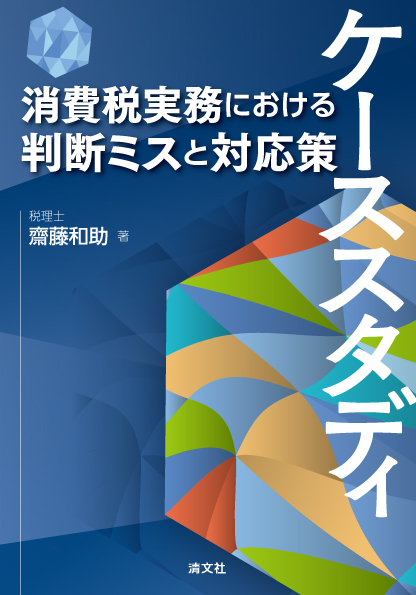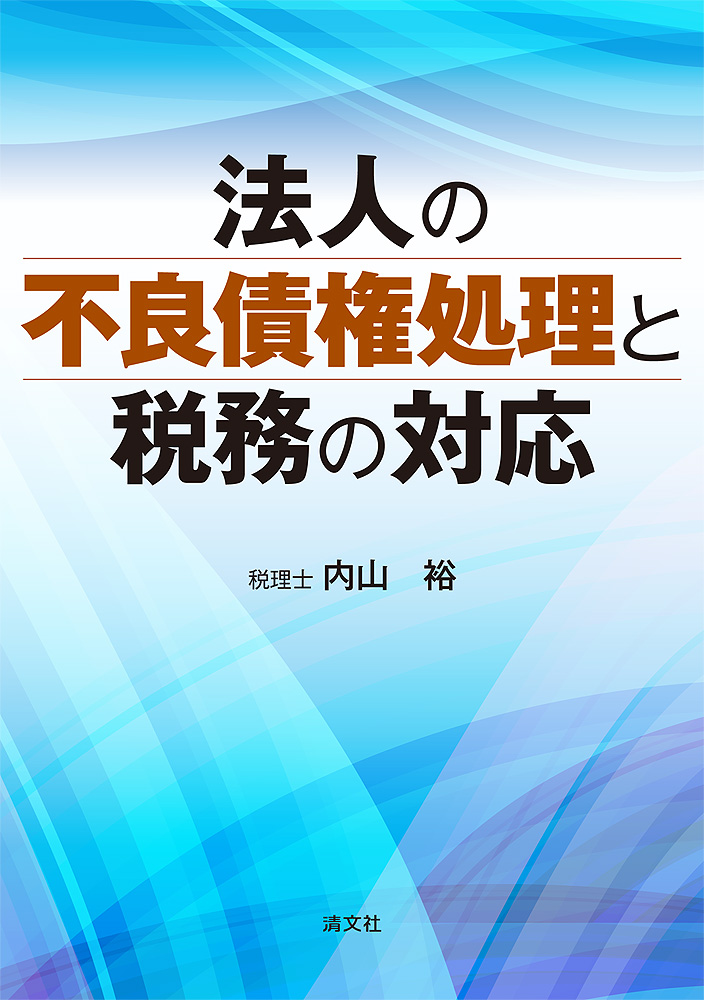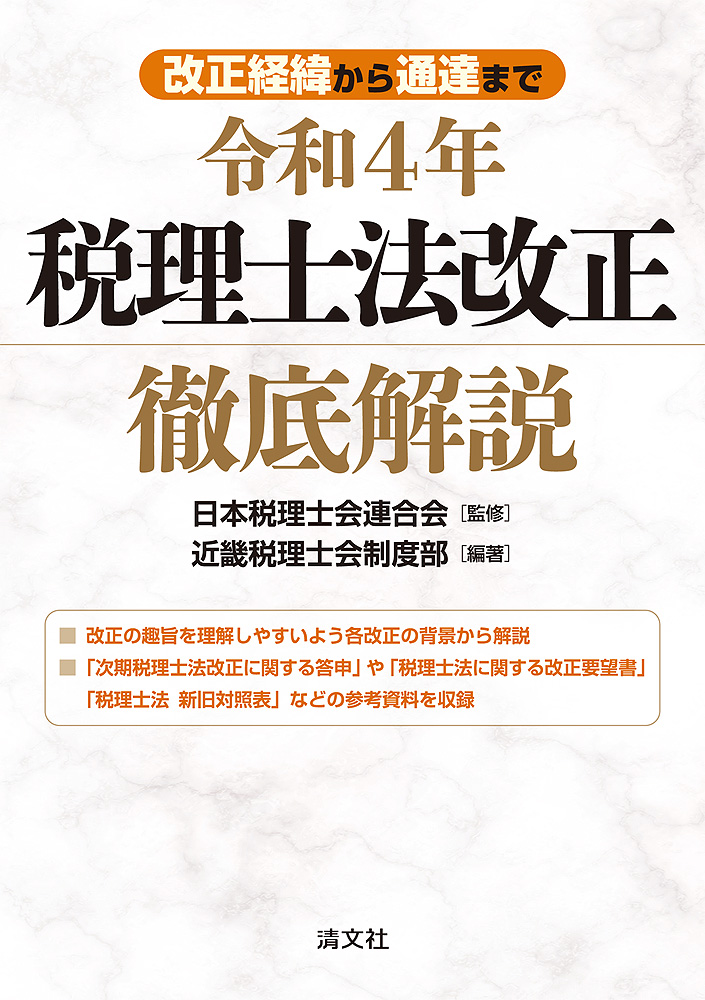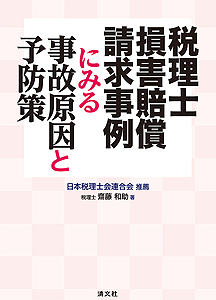「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例8(法人税)】
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成25年3月期の法人税につき、利益圧縮のため、帳簿価額1,500万円(入会金500万円、預託金1,000万円)のゴルフ会員権を時価の10万円で売却し、売却損を計上した。
ところが、このゴルフ会員権は運営会社が平成16年3月の再生計画の認可の決定により、預託金の一部が切り捨てられていた。これを税務調査で指摘され、結果として切り捨てられた預託金部分に係る売却損を否認されてしまった。
これにより、否認された売却損に係る税額300万円につき損害賠償請求を受けた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。