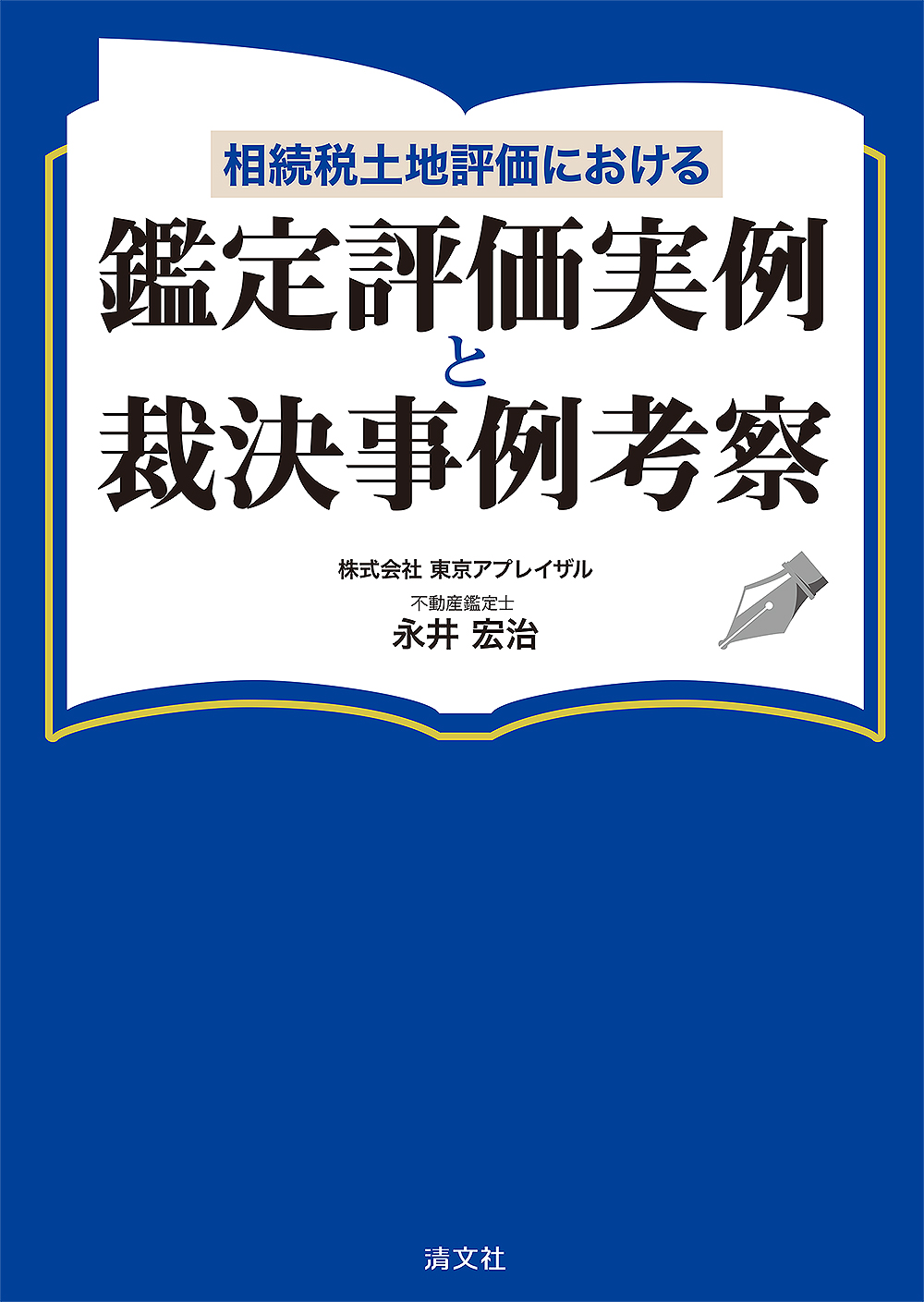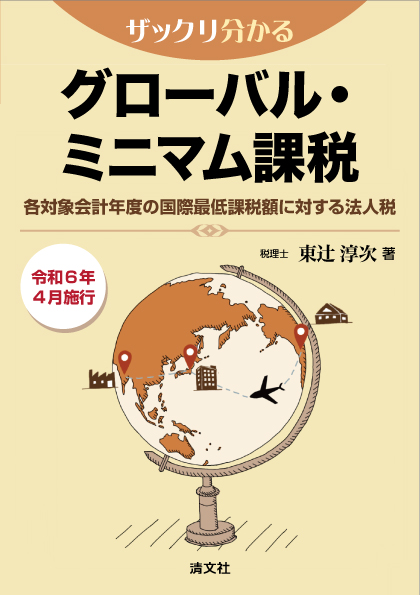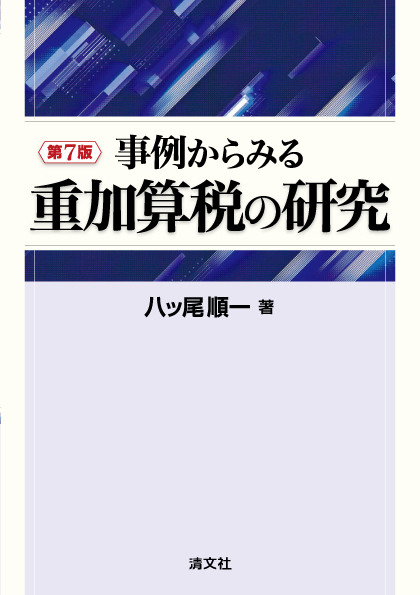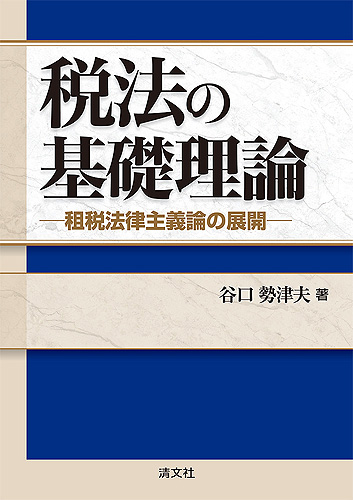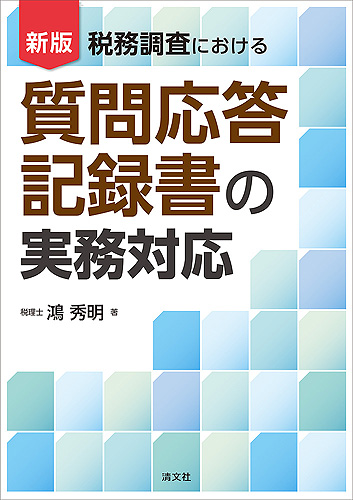〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第80回】
「非居住者期間の所得を合算課税することの可否が問題となった事例
(地判平28.5.13、高判平29.5.25、最判平30.4.12)(その2)」
税理士 柿本 雅一
《(その1)はこちら》
1 事案の概要
2 争点
3 納税者の主張
(1) 制度趣旨について
(2) 非居住者の範囲について
(3) 条文解釈について
4 税務当局の主張
(1) 制度趣旨について
(2) 非居住者の範囲について
(3) 条文解釈について
5 裁判所の判断
(1) 制度趣旨について
(2) 非居住者の範囲について
(3) 条文解釈について
6 検討
外国子会社合算税制に関するこれまでの判例は適用除外要件の充足に係るものが多く、特に正常な海外投資活動を阻害しないこととの関係で管理支配基準と業種判定をどう判断するかが問題になってきた。また、その多くは納税者が日本法人であるケースであり、納税者を個人とするケースは実務的にも少ない。ましてや居住者ステータスが課税年度の途中で変更するという事象は個人の場合でしか起こらないという特殊性が加わる(※1)。
(※1) 内国法人に対しても外国子会社合算税制が適用されるが、内国法人の定義を国内に本店又は主たる事務所を有する法人とし、原則として法人登記で判断するため事業年度の途中で法人ステータスが内国法人と外国法人で入れ替わることは生じない。
本件では納税者ステータスの変更が外国子会社合算税制の適用においてどのように影響を与えるかが制度創設時の資料(※2)では明確ではないため争いとなっている点において先例としての価値はある。本件における条文解釈上の論点を改めて整理すると、税法分野における法令解釈は原則として文理解釈によることに争いはなく、納税者と課税当局との主張の違いは、目的論的解釈が認められる例外的な場合と言えるかどうか、つまり、文理解釈によっては法規定の内容を明らかにすることが困難な場合に該当するかどうかである。
(※2) 税制調査会では、「我が国経済の国際化に伴い、いわゆるタックス・ヘイブンに子会社等を設立し、これを利用して税負担の不当な軽減を図る事例が見受けられる。このような事例は、税負担の公平の見地から問題のあるところであり、・・・我が国においても以下のような考え方に基づき、昭和53年度において所要の立法措置を講ずることが適当である」(昭和53年度の税制改正に関する答申)と述べられており、また、昭和53年改正税法のすべてでは、「このようにして、租税特別措置法の中に新たに2節が設けられ、第4節の2(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)と第7節の3(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)の中でそれぞれ居住者と内国法人が軽課税国所在の子会社等を利用して租税回避を行う場合に対処するための措置が導入されたわけです」と説明されているが、居住者が特定外国子会社等を設立した場合のみを想定しているのかどうかは不明である。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。