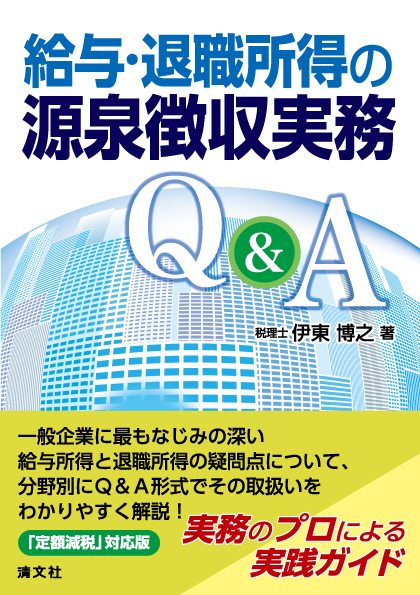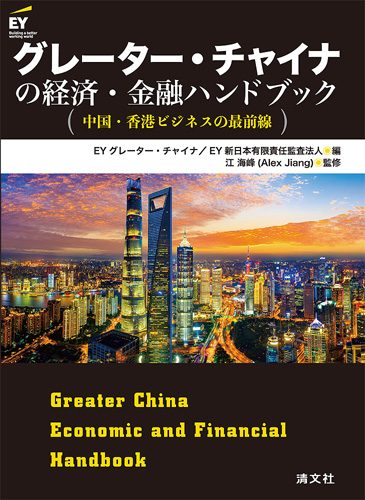〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第69回】
「「技術上の役務に対する料金」の該当性が問題となった事例
(審裁令5.8.15)(その1)」
~日印租税条約12条4項~
井上 眞一
【裁決】
- 国税不服審判所令和5年8月15日裁決(TAINSコード:J132-1-01)
1 はじめに
わが国とインド共和国(以下「インド」という)の租税条約は、1960年に最初の「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定」(※1)が締結された。これは帰属主義を導入した最初の条約である。その後、1989年に「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本政府とインド政府との間の条約」(以下「日印租税条約」という)が締結された。
(※1) 「技術上の役務に対する料金」は1960年租税条約10条(k)に「企業に対して支払われる技術上の役務に対する料金は、その料金が支払われる役務が行われた締結国内の源泉から生ずる所得として取り扱う。」と既に記載されている。
2 本件の概要
本件は、わが国法人の審査請求人(以下「X社」という)が、インド所在企業のJ社、K社及びL社の各社に支払った金員について、原処分庁が、当該各支払金は、日印租税条約12条4項に規定する「技術上の役務に対する料金」にあたり、国内源泉所得に該当するとして、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分等を行ったことに対し、X社が、当該支払金の一部は「技術上の役務に対する料金」に該当しないなどとして、処分の一部取消しを求めた事案である。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。