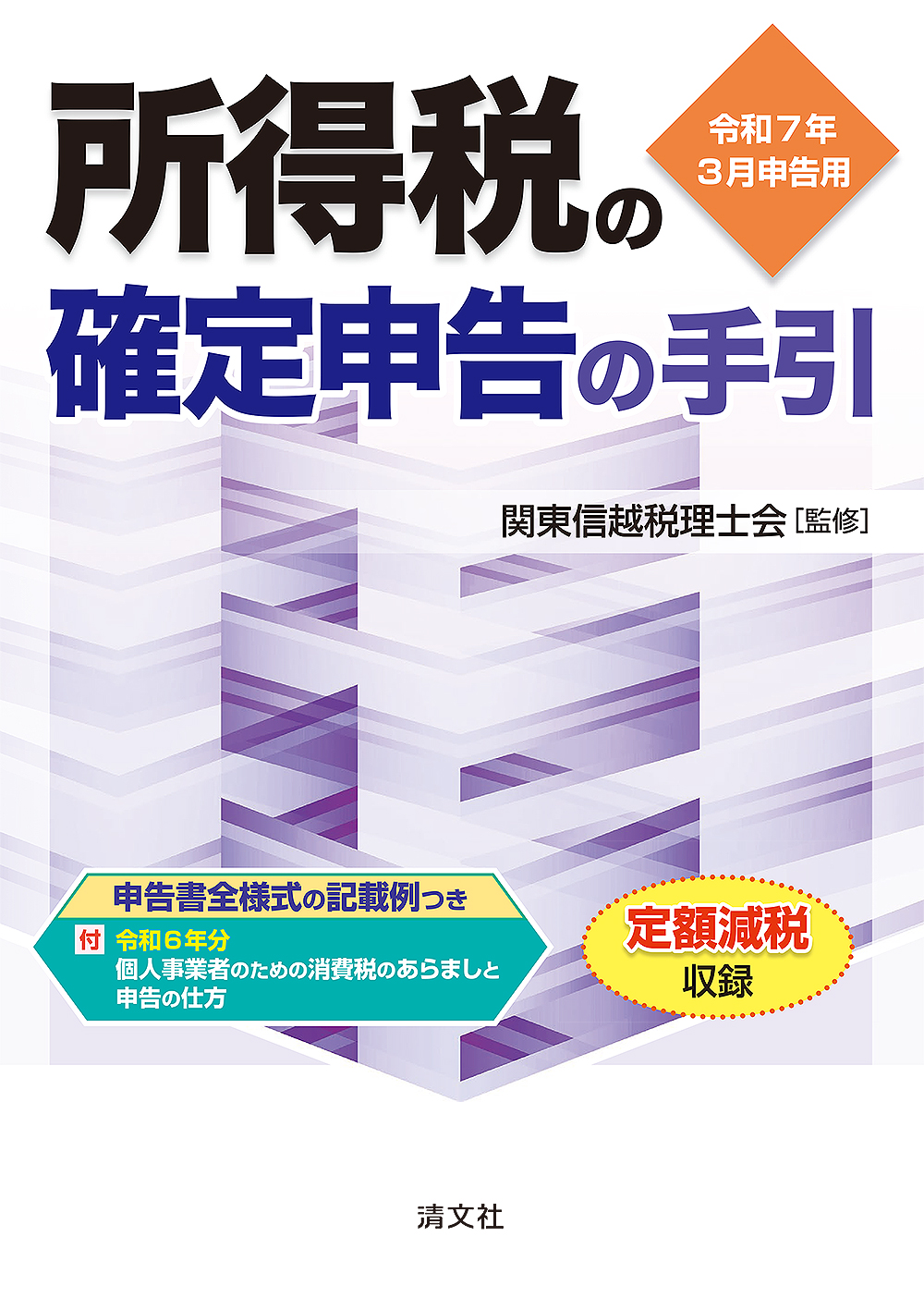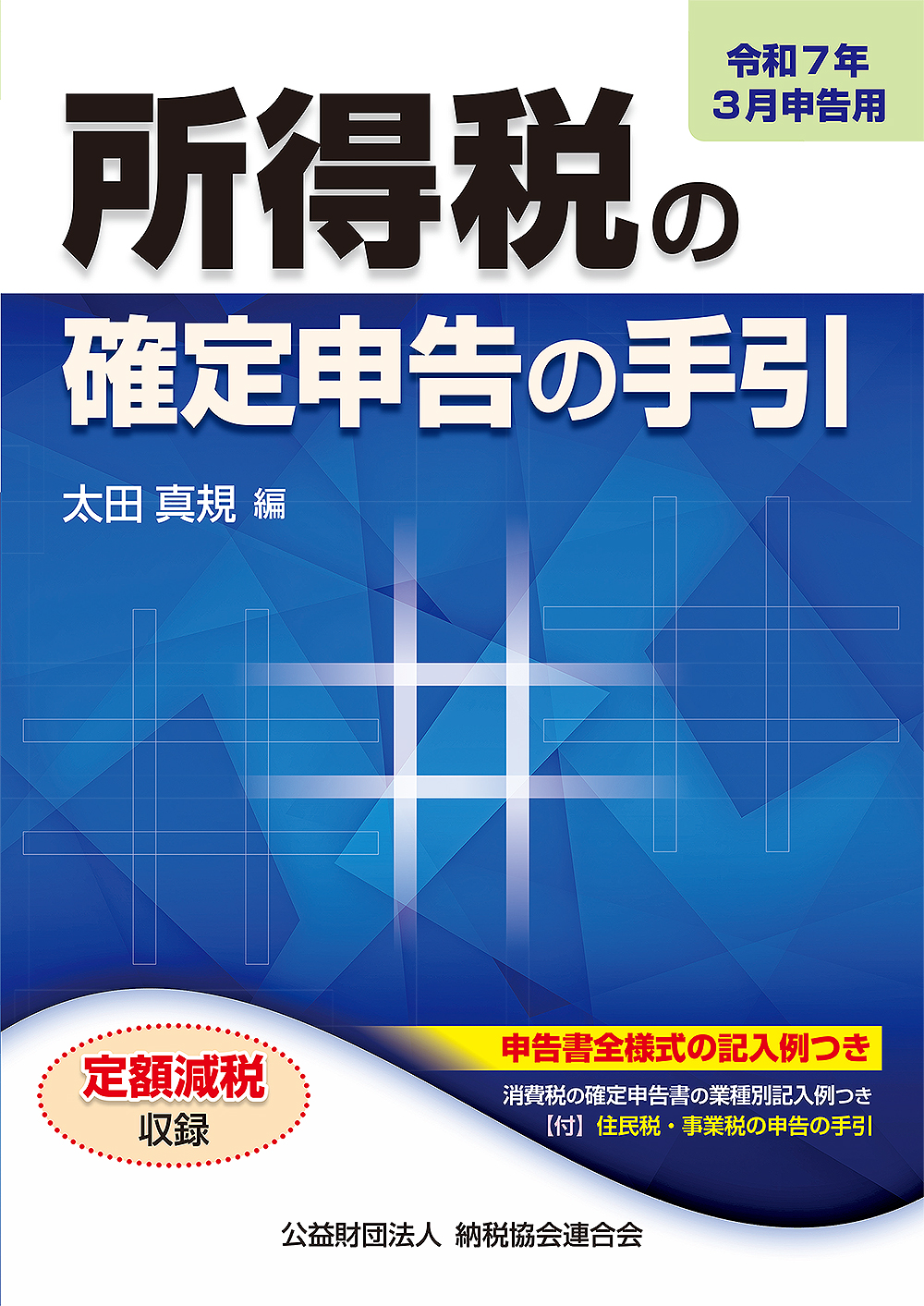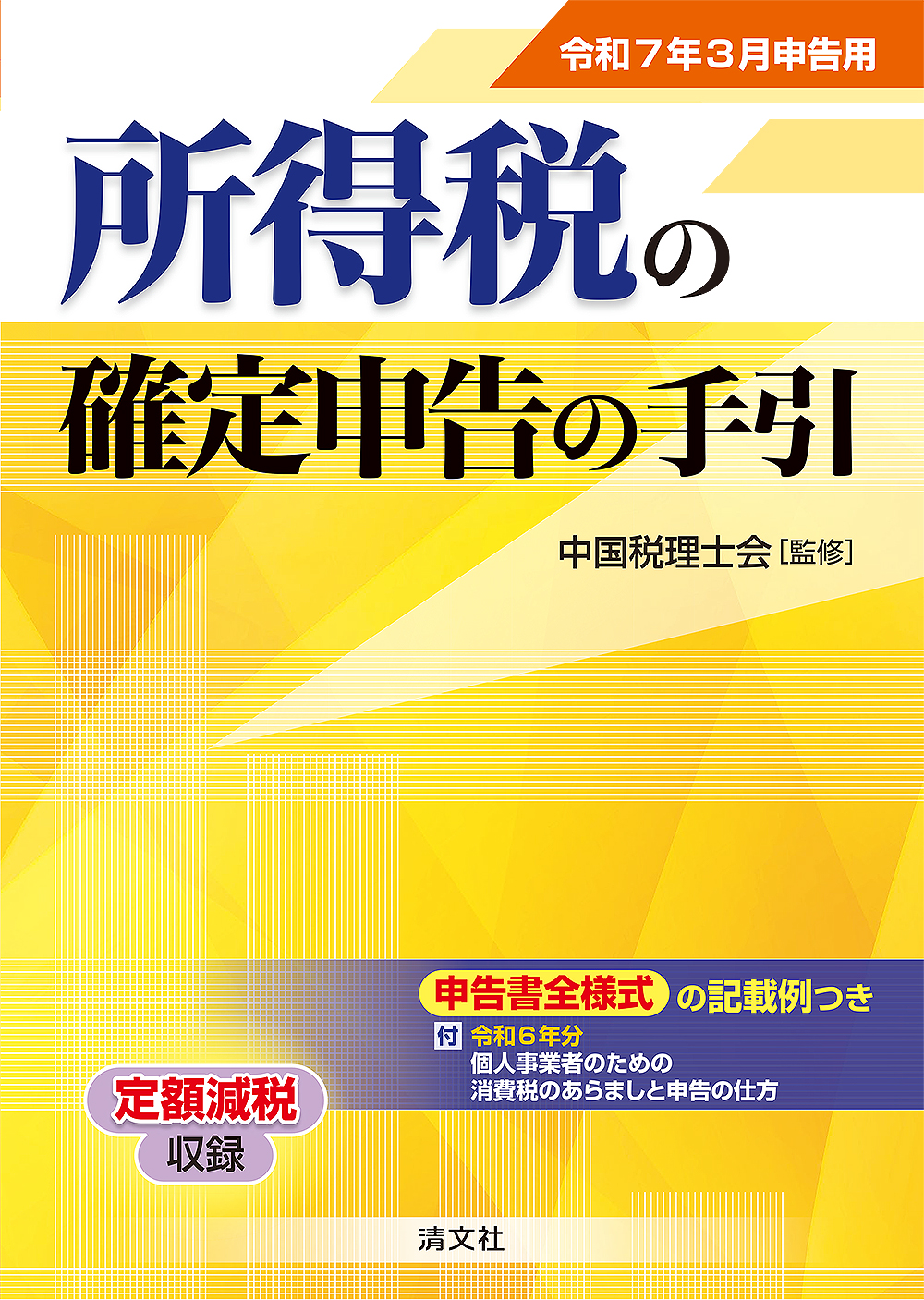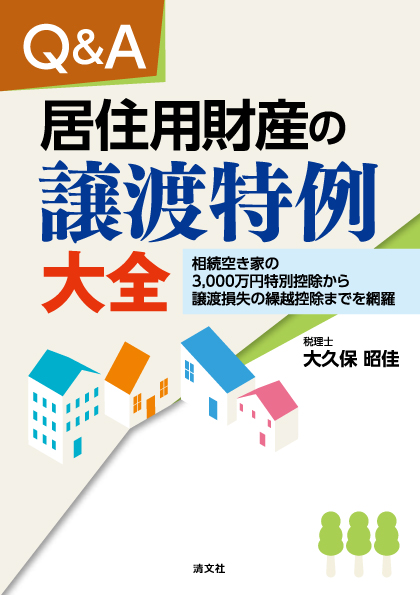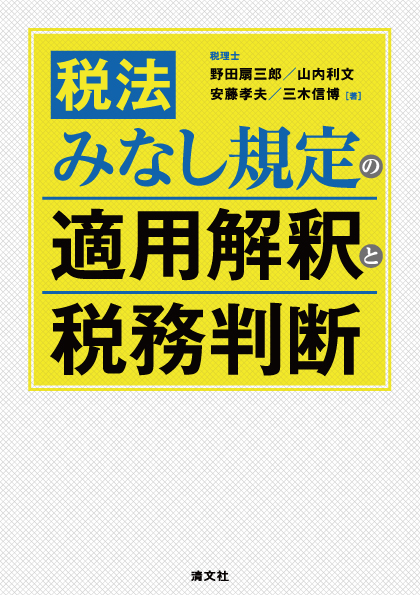〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第75回】
「外国証券会社への売委託による株式譲渡損失に関する繰越控除の適用可否(地判平27.7.3、高判平28.3.17)(その1)」
~租税特別措置法37条の12の2、日本国憲法13条・14条・84条・98条2項、 日米租税条約1条2項(a)~
公認会計士・税理士 西川 浩史
- 京都地裁:平成27年7月3日判決【税資第265号-106(順号12689)】(TAINSコード:Z265-12689)
- 大阪高裁:平成28年3月17日判決【税資第266号-48(順号12826)】(TAINSコード:Z266-12826)
- 最高裁:平成28年9月30日判決【税資第266号-132(順号12910)】(TAINSコード:Z266-12910)
1 はじめに
本件は、確定申告において外国証券会社への売委託により生じた株式譲渡損失の繰越処理を行った納税者に対して、課税庁が当該処理を適用するための要件を満たしていないとして更正処分を行った事案である。
納税者は、憲法違反、日米租税条約違反、規定の解釈及び適用の誤りを主張したが、地裁・高裁ともに納税者の主張を認めず、最高裁も上告を棄却したため、課税庁の勝訴が確定した。
本件の背景には、「貯蓄から投資へ」の政策目的のための税制改正や「投資交流促進」等を目的とした日米租税条約の改正があり、これらの内容の理解が前提になる。また、株式譲渡損失の繰越控除制度の本質についても検討が必要と考える。
本件の争点である憲法14条(平等原則)違反か否かに関して、裁判所はサラリーマン税金訴訟(大島訴訟)(以下「大島訴訟」)(※1)の最高裁判決での判断基準をもとに違憲審査を行い、違憲ではないとの結論を出した。租税立法に対する違憲審査基準のあり方についても検討をしたい。
(※1) 大島訴訟とは、事業所得者に比べて給与所得者は著しく不公平な税負担をしているとして、憲法14条1項違反を争った訴訟である。金子宏教授は「本件判決は、裁判所の租税立法に対する違憲審査の基準、租税法律主義、および租税公平主義と給与所得の課税の3つの問題に関する判例として重要な位置を占めている。租税法の判例の中でも最も重要で興味ぶかい判例の1つである。」と述べられている。金子宏「憲法と租税法-大島訴訟」『租税判例百選[第6版]』別冊ジュリスト228号(2016.6)6頁。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。