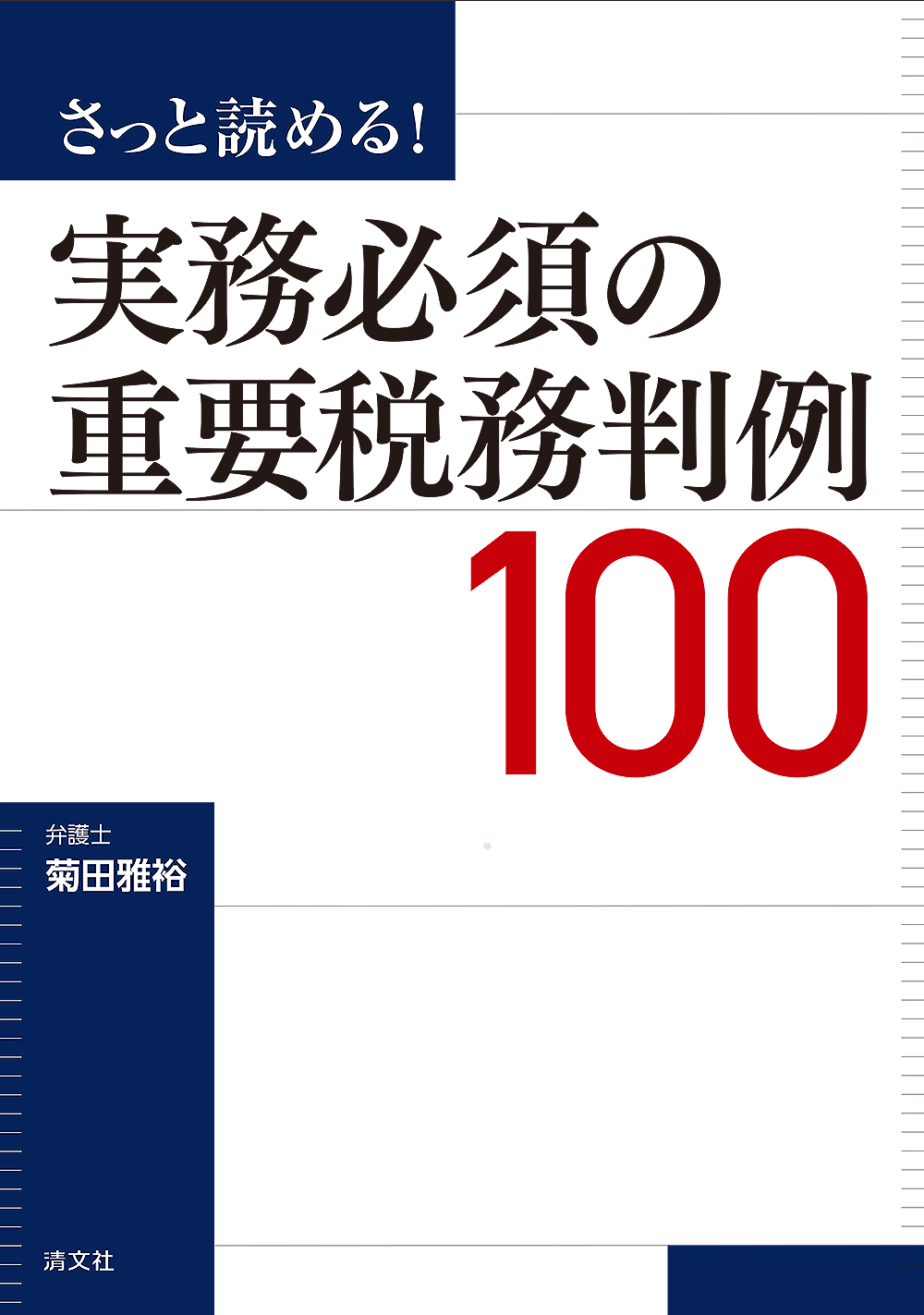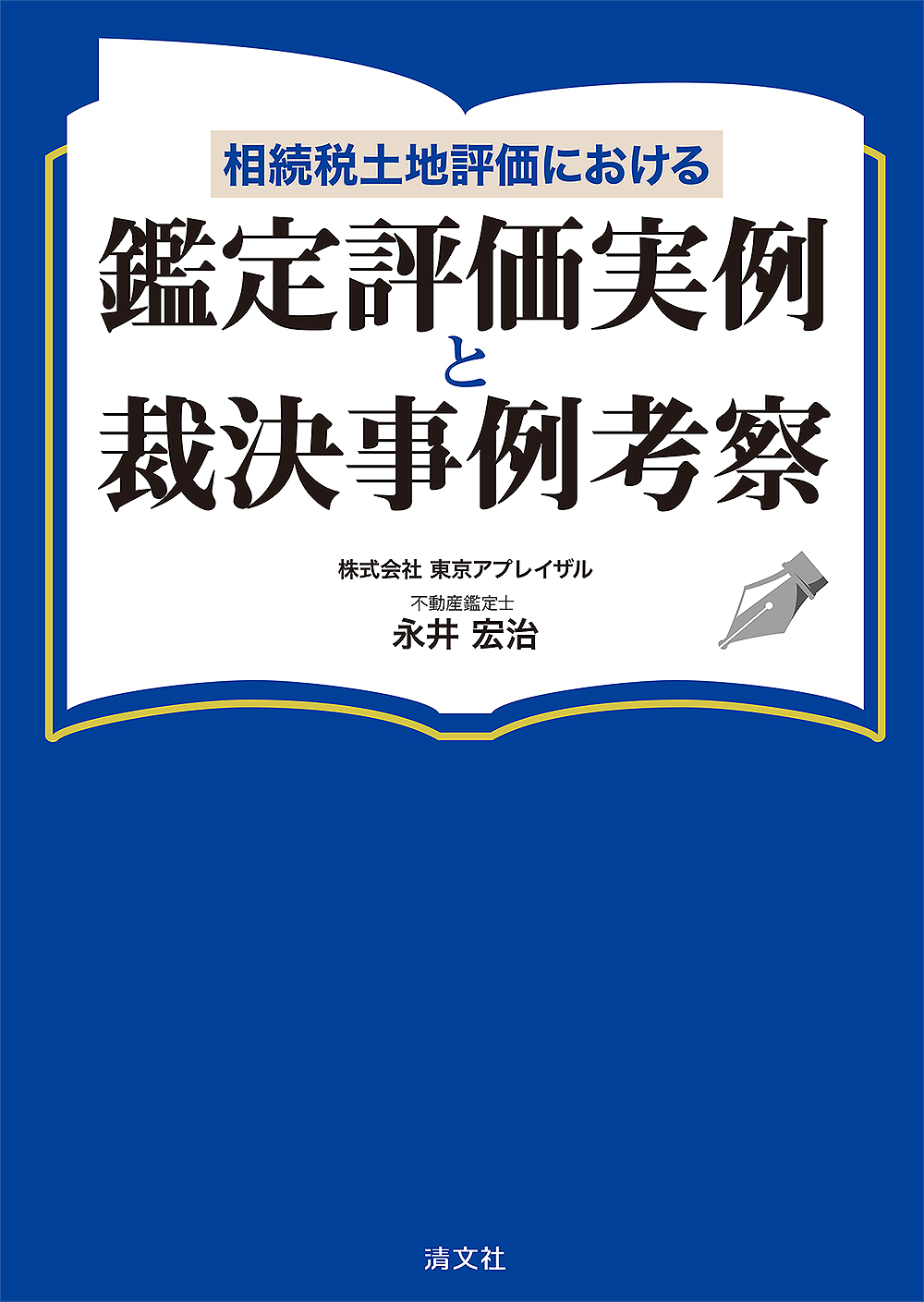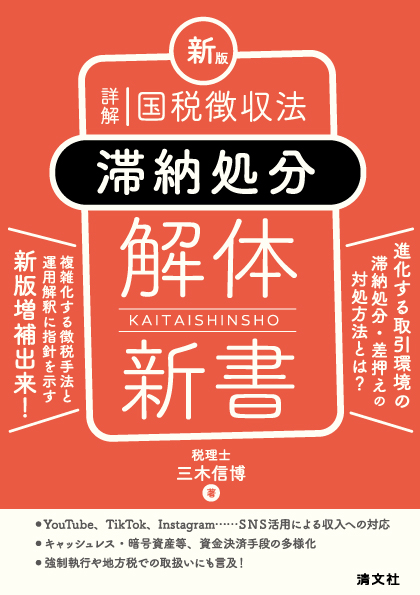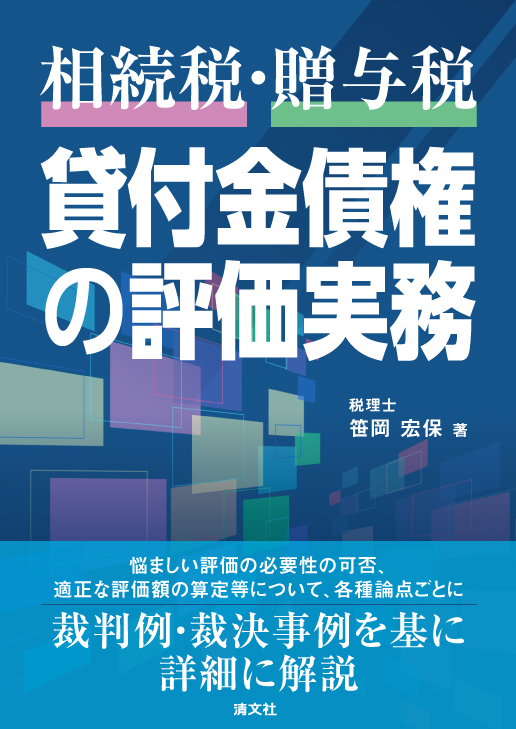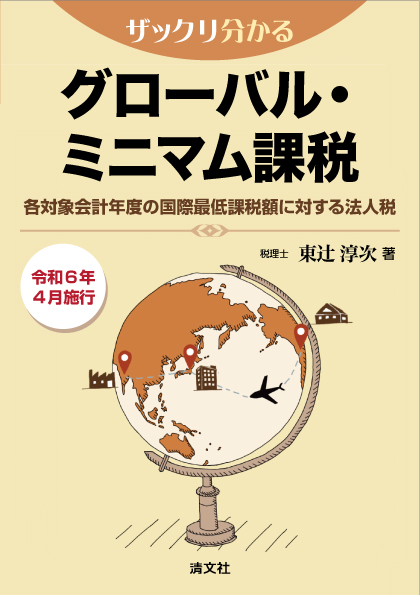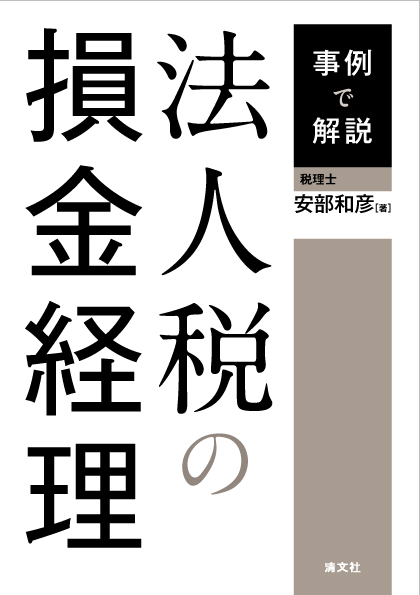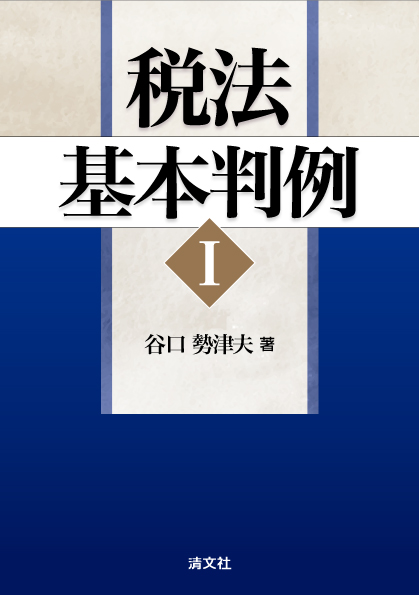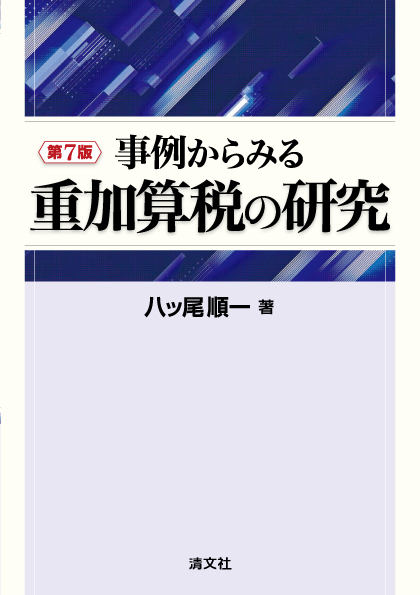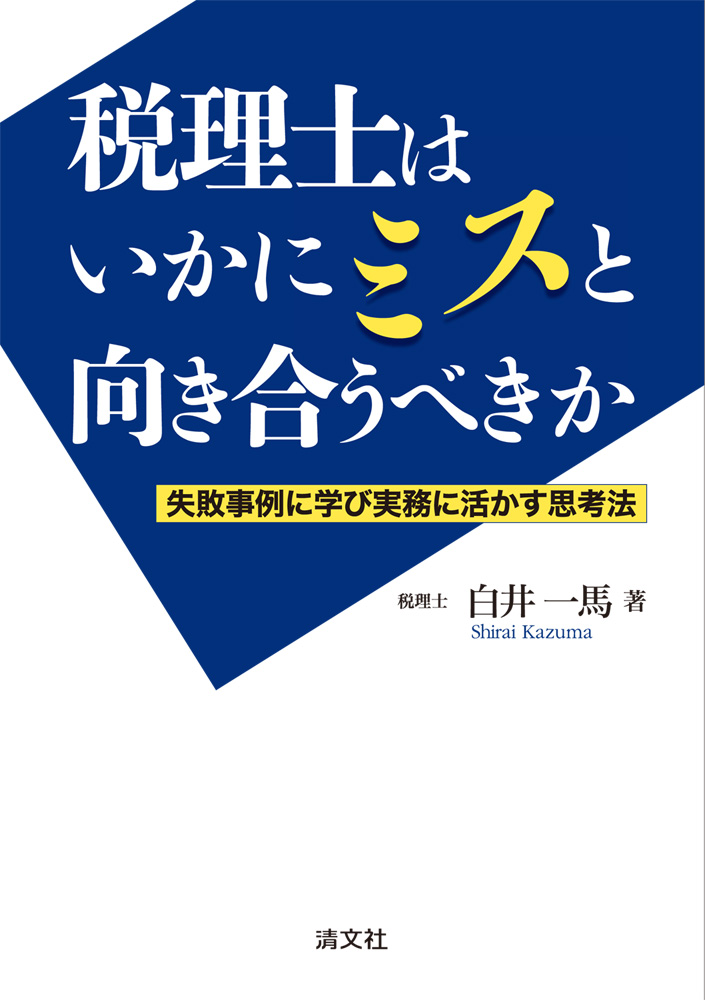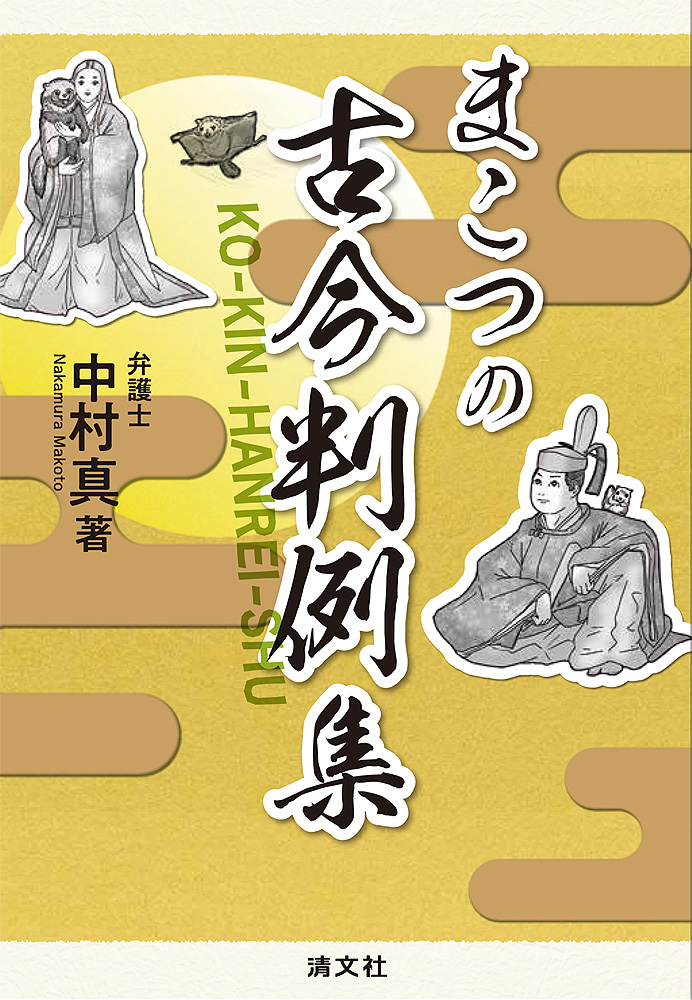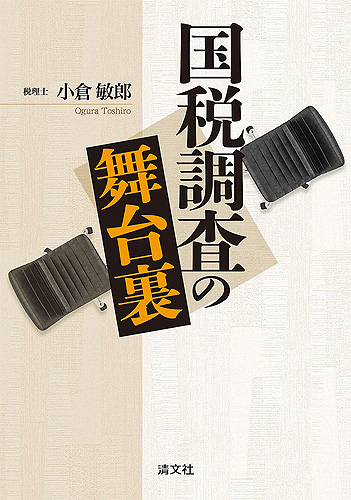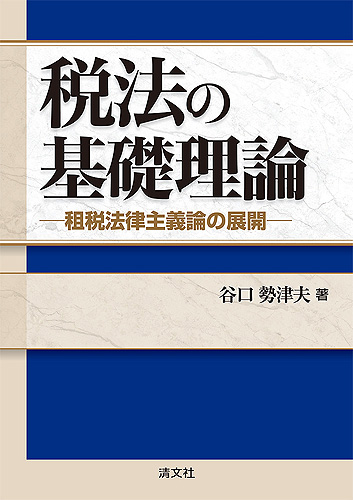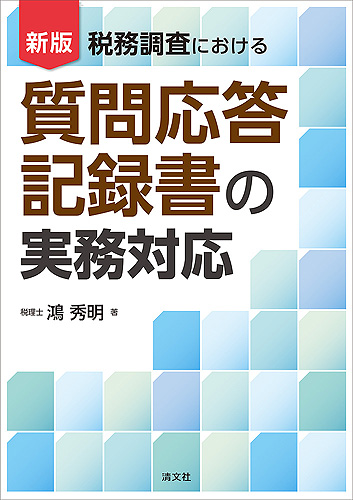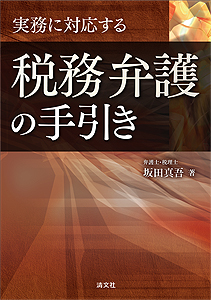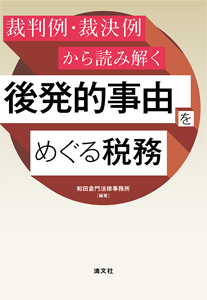〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第65回】
「みずほ銀行事件
(地判令3.3.16、高判令4.3.10、最判令5.11.6)
(その1)」
~旧租税特別措置法66条の6第1項、
旧租税特別措置法施行令39条の16第1項・2項1号~
税理士 松田 祐弥
【判決】
- 東京地裁令和3年3月16日判決(平成31年(行ウ)第42号)(TAINSコード:Z271-13543)
- 東京高裁令和4年3月10日判決(令和3年(行コ)第96号)(TAINSコード:Z272-13683)
- 最高裁令和5年11月6日判決(令和4年(行ヒ)第228号、第229号)(TAINSコード:Z888-2513)
【関連法令】
- 租税特別措置法66条の6第1項(平成29年法律第4号による改正前のもの。以下同じ)
- 租税特別措置法施行令39条の16第1項・2項1号(平成29年政令第114号による改正前のもの。以下同じ)
1 関連法令等
(1) 租税特別措置法66条の6第1項
次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下この条及び次条において「特定外国関係会社等」という。)が、・・・適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうち、その内国法人の有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等・・・の請求権・・・の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額に(以下この款において「課税対象金額」という。)相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(以下省略)
(2) 租税特別措置法施行令39条の16(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の計算等)
第39条の16 法第66条の6第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国子会社等の各事業年度の同項に規定する適用対象金額に、当該特定外国子会社等の当該各事業年度終了の時における発行済株式等のうちに当該各事業年度終了の時における当該内国法人の有する当該特定外国子会社等の請求権勘案保有株式等の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 請求権勘案保有株式等 内国法人が直接に有する外国法人の株式等の数又は金額(当該外国法人が請求権の内容が異なる株式等を発行している場合には、当該外国法人の発行済株式等に、・・・請求権に基づき受けることができる・・・額がその総額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額)及び請求権勘案間接保有株式等を合計した数又は金額をいう。
(以下省略)
※下線筆者
2 事件の概要
(1) 概要
本件は内国法人であるX(原告・控訴人・被上告人)が、平成27年4月1日から同28年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」)の法人税及び地方法人税(以下「法人税等」)の申告をしたところ、処分行政庁から租税特別措置法(以下「措置法」)66条の6第1項の規定(以下「本件委任規定」)により、ケイマン諸島で設立されたXの子会社B及びC(以下「本件各子会社」)の課税対象金額に相当する金額が、Xの本件事業年度の所得金額の計算上、益金の額に算入されるなどとして、法人税等の各増額更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けたものである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。