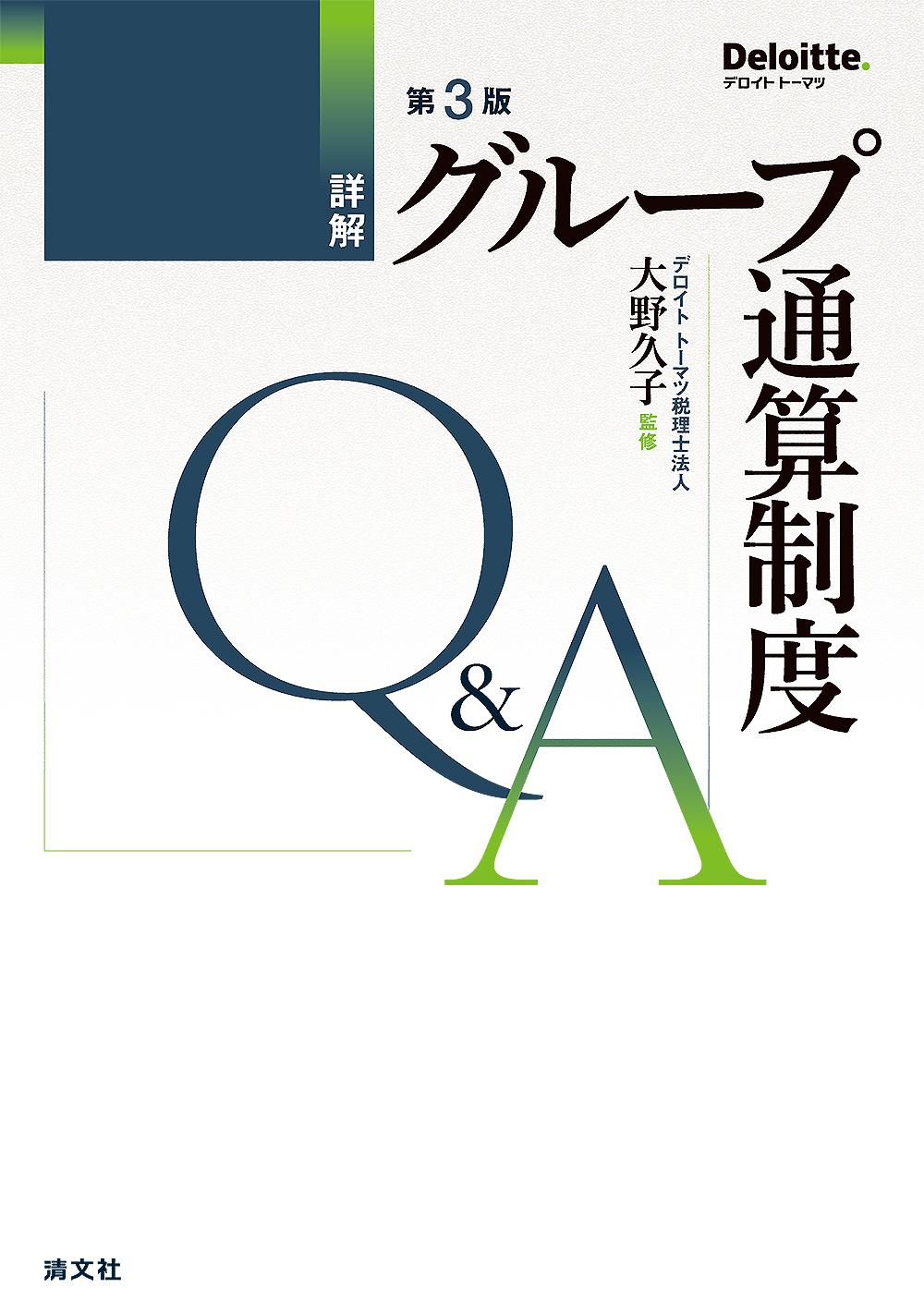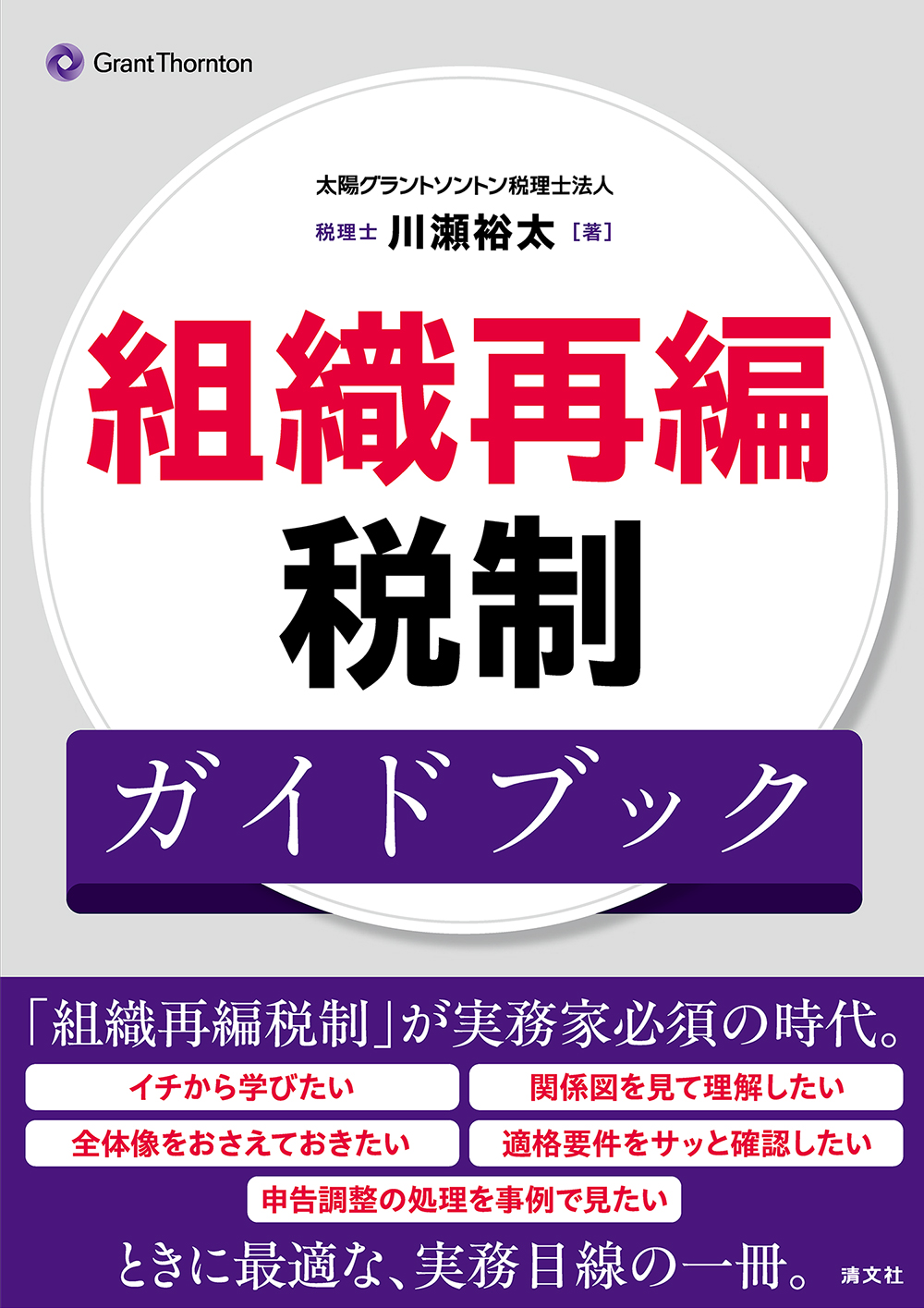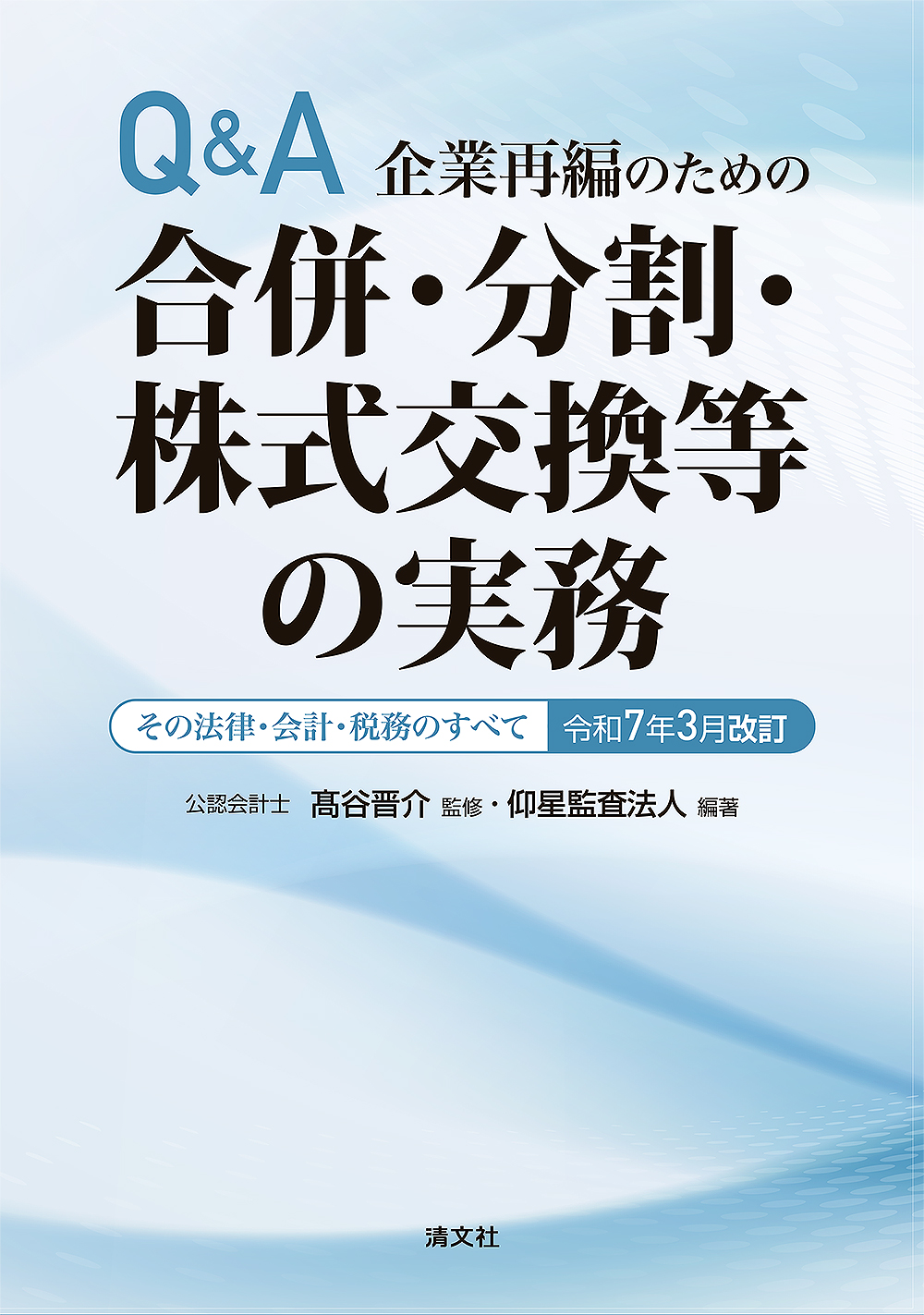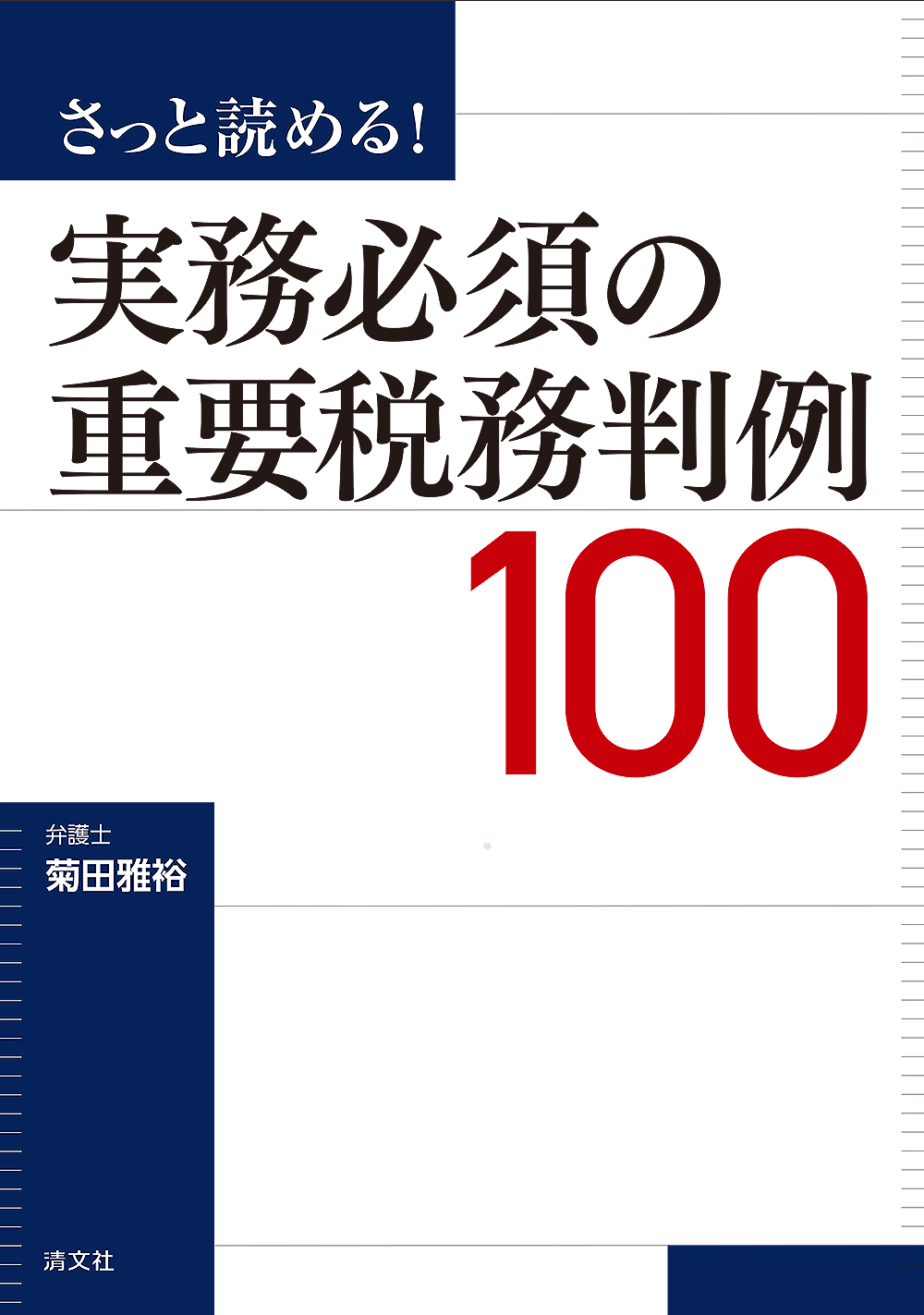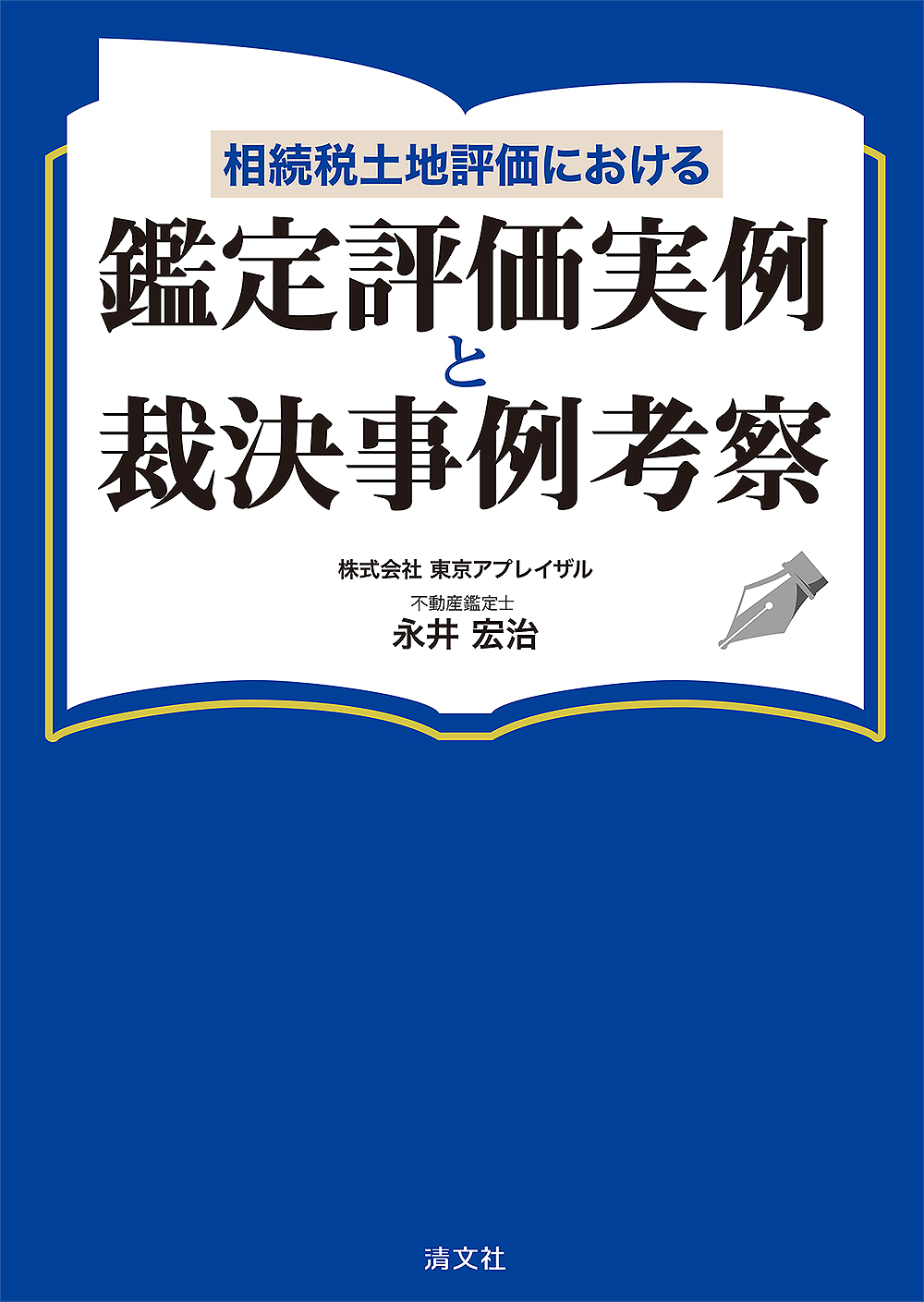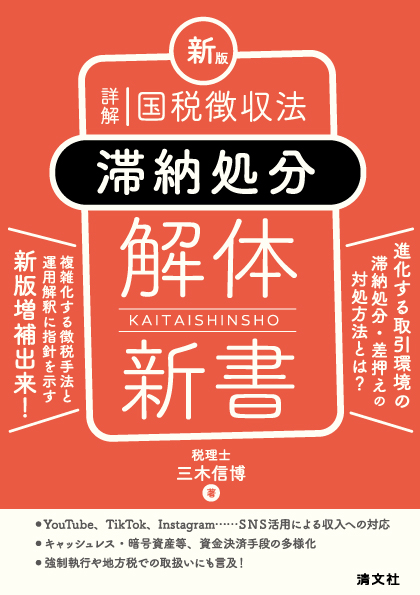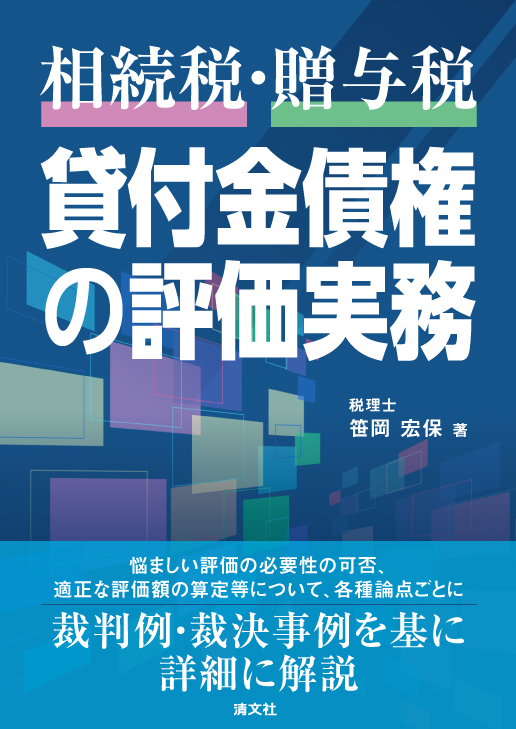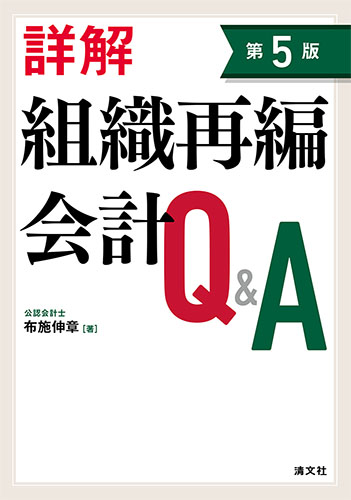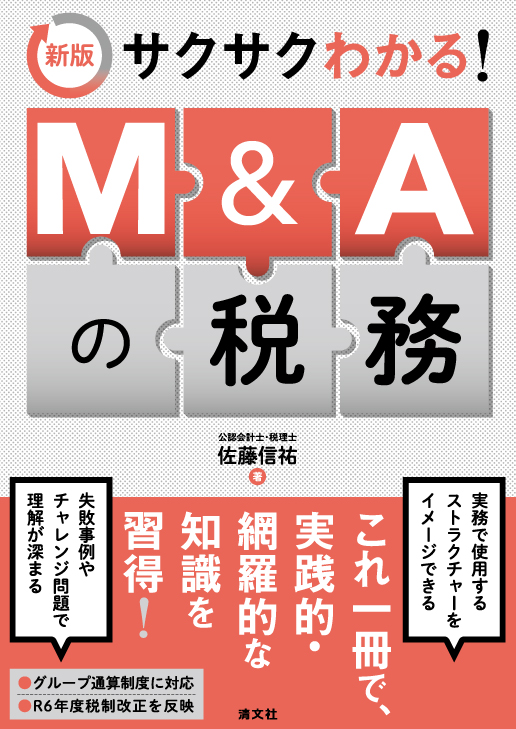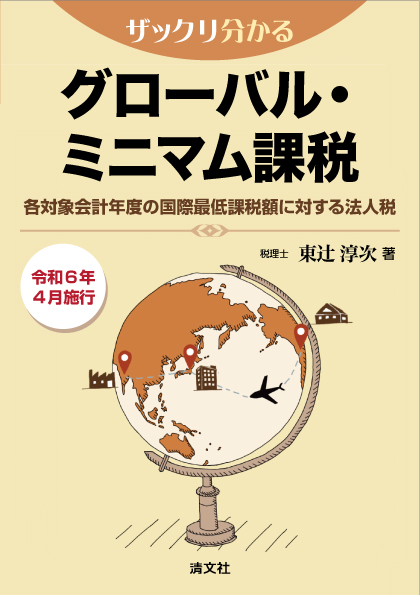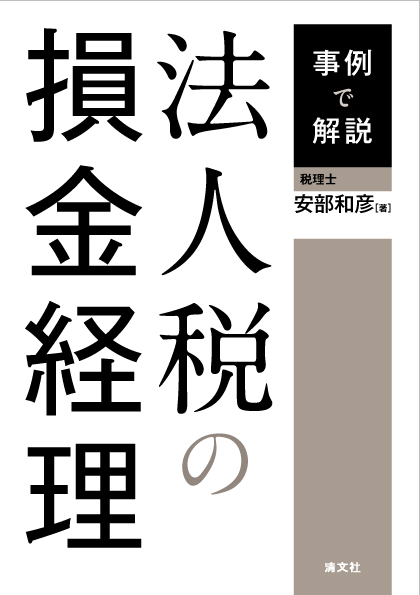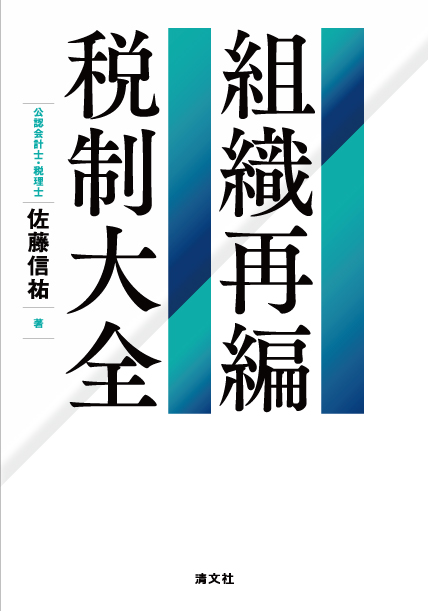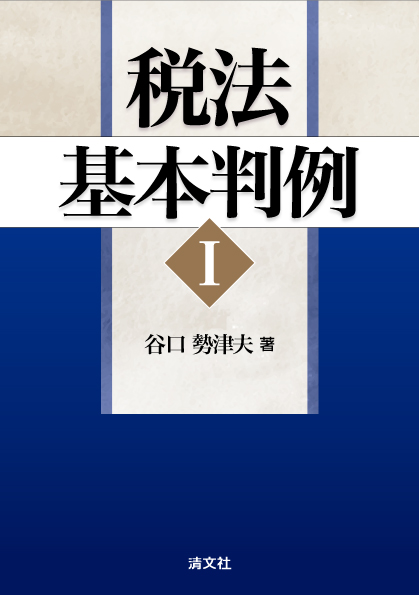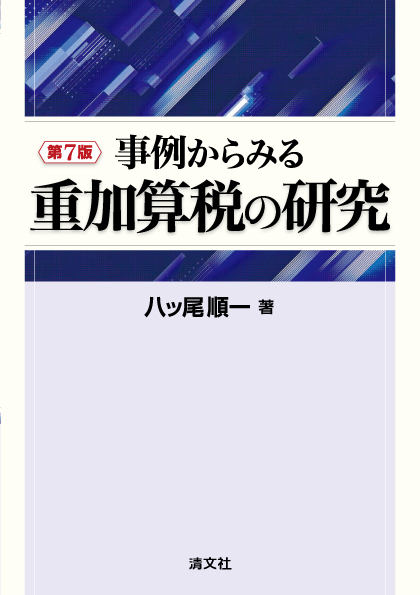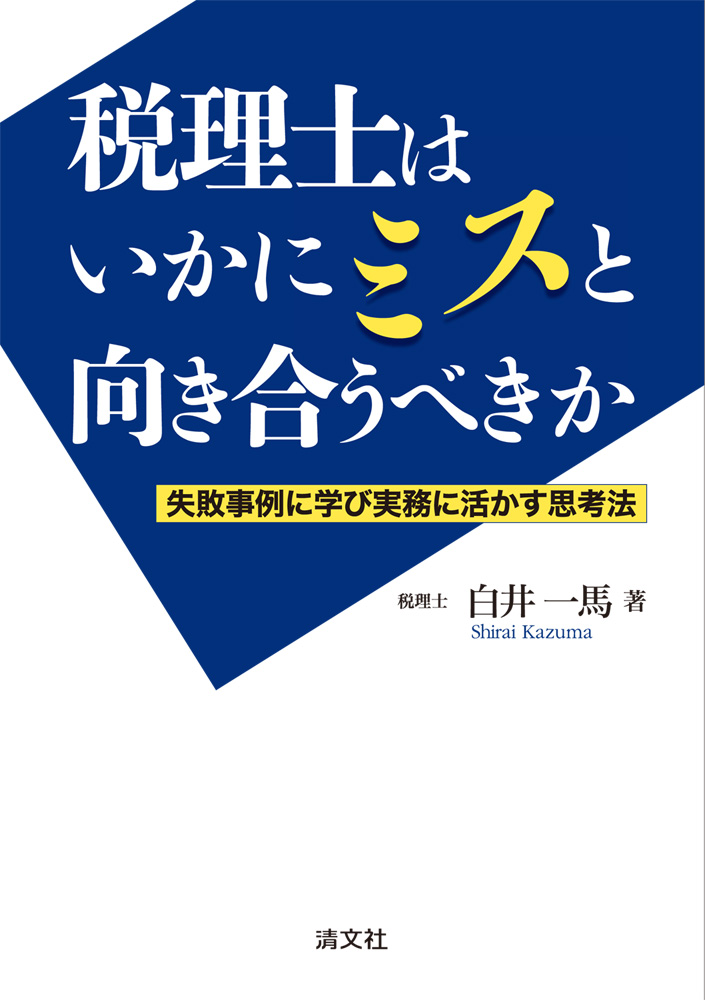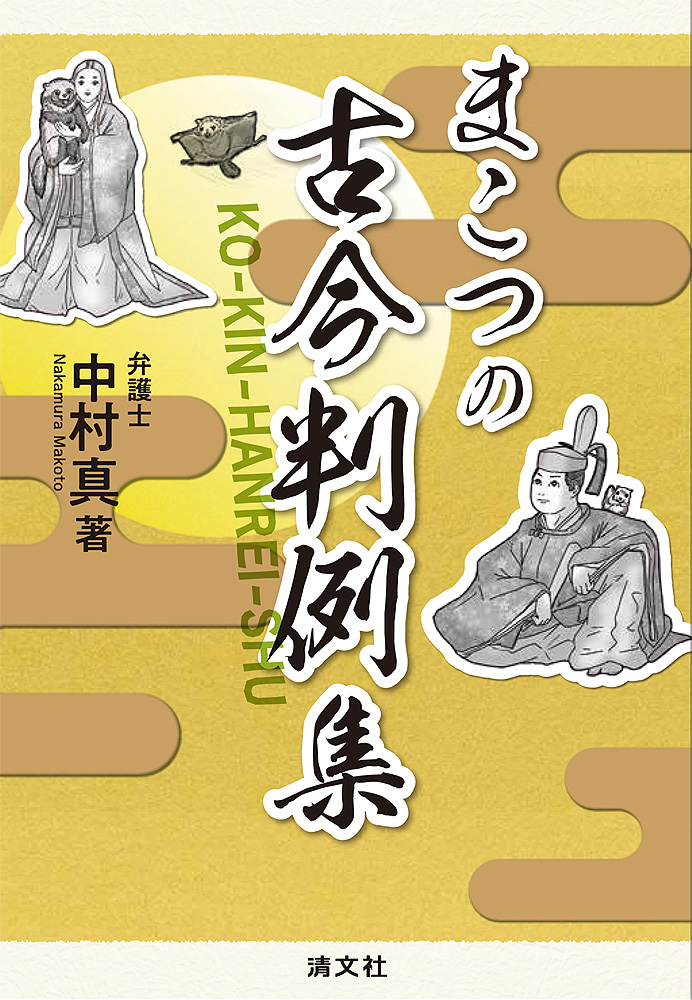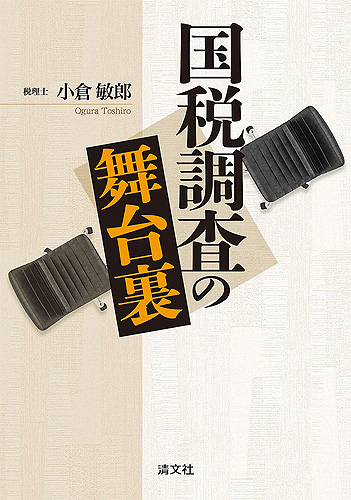〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第71回】
「塩野義製薬事件
-現物出資による国外への資産移転-
(地判令2.3.11、高判令3.4.14)(その1)」
~旧法人税法施行令4条の3第9項(平成28年度改正前)~
滋賀大学准教授・税理士 金山 知明
- 東京地裁令和2年3月11日判決(平成28年(行ウ)第395号)(TAINSコード:Z270-13394)
- 東京高裁令和3年4月14日判決(令和2年(行コ)第89号)(TAINSコード:Z271-13549)
1 はじめに
諸国におけるLLP(Limited Liability Partnership)、LPS(Limited Partnership)やLLC(Limited Liability Company)などは、「課税上透明な事業体(fiscally transparent entity)」(本稿では「透明事業体」と略する)と呼ばれ(※1)、その税務上の取扱いが国によって異なることから問題を生むことが多い(※2)。とりわけ、ある国における透明事業体が税法上の法人に該当するか否かという争点で、わが国でもいくつかの裁判例がある。
(※1) パートナーシップに対する二国間条約の適用関係を解説したOECD(1999年)“The application of the OECD model tax convention to partnerships”においても、パートナーシップの課税上の性質を “fiscally transparent”と表現する。
(※2) OECD (1999年), Id, at 10.
このうち米国デラウェア州のLPSについてわが国における法人該当性が争われた事件(※3)では、当該LPSが権利義務の主体たり得ることから、法人に該当するという判断がなされている。ただし、同じLPSでもケイマンで組成されたものについて、法人には該当しないとした裁判例もある(※4)。
(※3) 最高裁平成27年7月17日判決(民集69巻5号1253頁)。
(※4) 名古屋高裁平成19年3月8日判決(税資257-38順号10647)。
本稿で取り上げる事例(塩野義製薬事件)は、そのケイマン法上のLPSを用いた事業にまつわるわが国課税上の争訟であるが、法人該当性が直接の争点となったわけではなく(法人に該当しない事業体であることに争いはなく)、そのLPSの持分が国内外のいずれに存する資産であるかが問題となったものである。
具体的には、内国法人が外国子会社にケイマンLPS持分を現物出資したところ、そのLPS持分が国外資産であれば適格現物出資として課税繰延べの対象となるが、国内資産であれば非適格として課税に服するという法律関係下において、この内外判定が争われた事案である。透明事業体の税務上の特異な性質により引き起こされる新たな論点を扱うものとして、先例的重要性があるといわれる(※5)。
(※5) 岡村忠生「塩野義製薬事件判決の分析と意義」国際税務40巻6号(2020年)46頁。
本稿ではこの塩野義製薬事件(東京地裁令和2年3月11日判決、東京高裁令和3年4月14日判決)を題材に、外国の透明事業体が有する事業用資産について、その帰属の問題を検討し、判決内容の精査を試みる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。