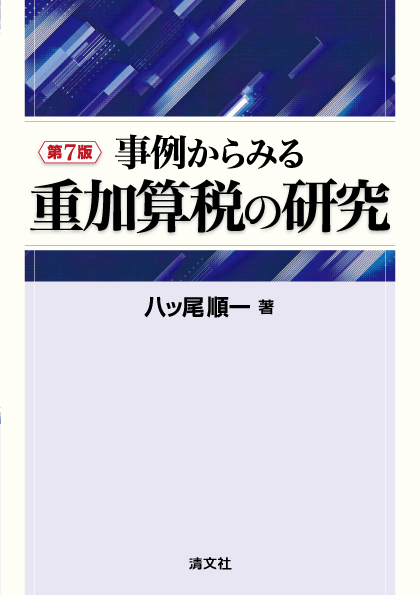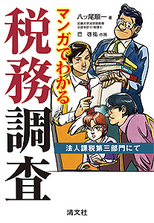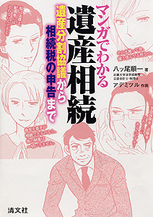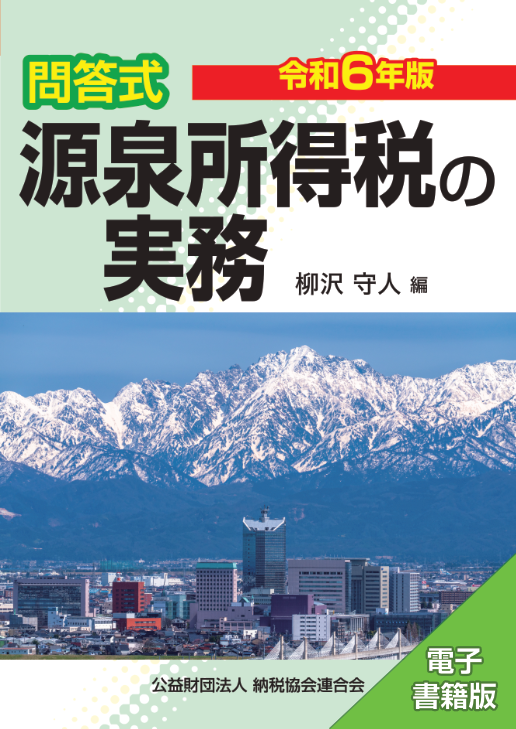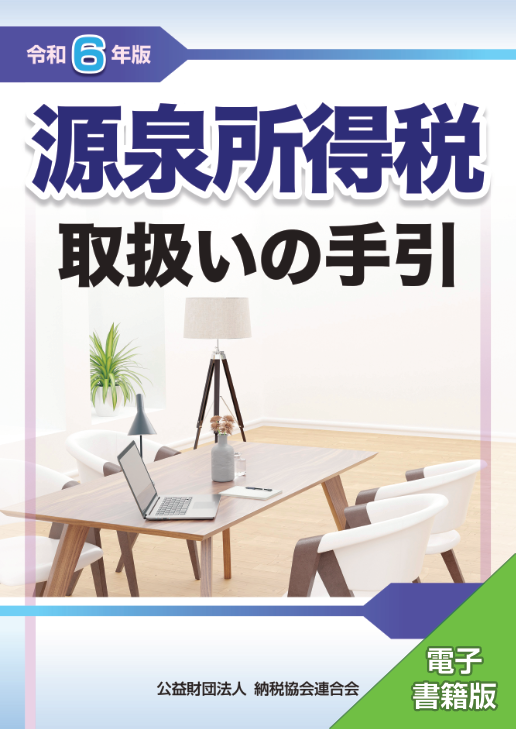〈小説〉
『所得課税第三部門にて。』
【第60話】
「学資金と非課税規定」

公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
「・・・某税理士法人から質問があったのですが・・・」
浅田調査官は、中尾統括官の机の前に立っている。
「・・・どんな?」
中尾統括官は、部下の調査報告書を見ながら尋ねる。
「はい・・・この税理士法人では、職員が税理士資格を取得するために、大学院に通うことを認め、その学資金を貸与する制度があります・・・」
中尾統括官は、調査報告書から目を離して、浅田調査官を見る。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。