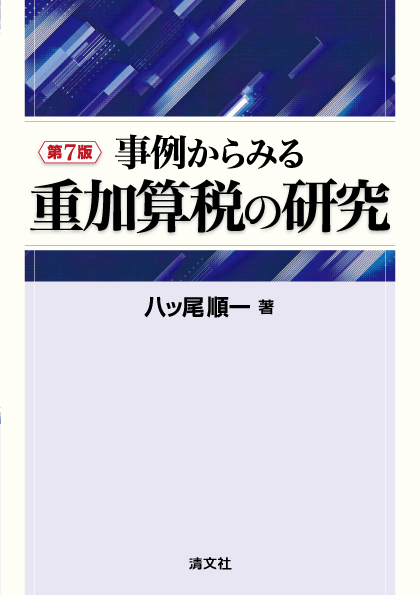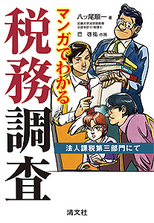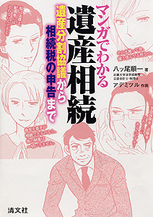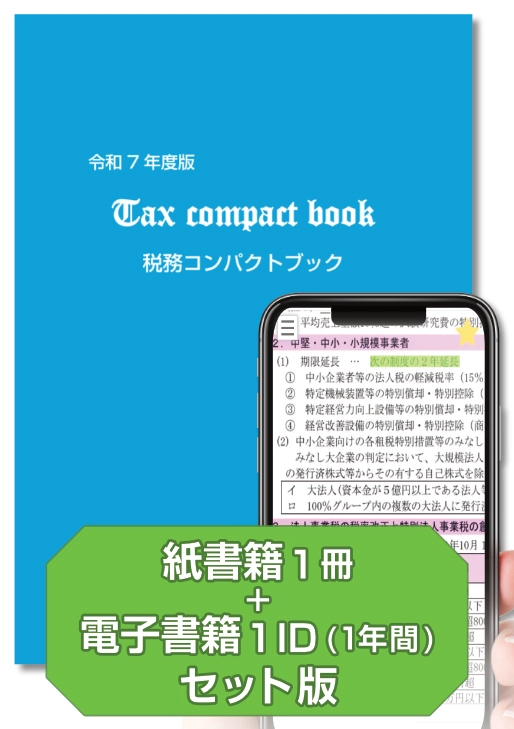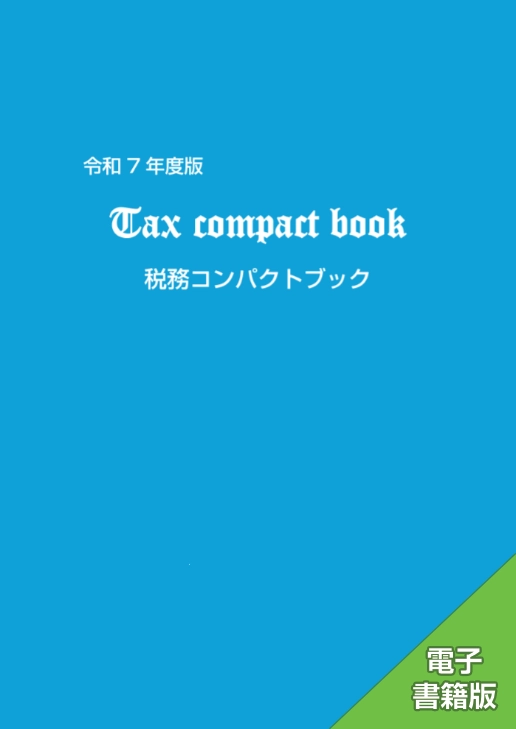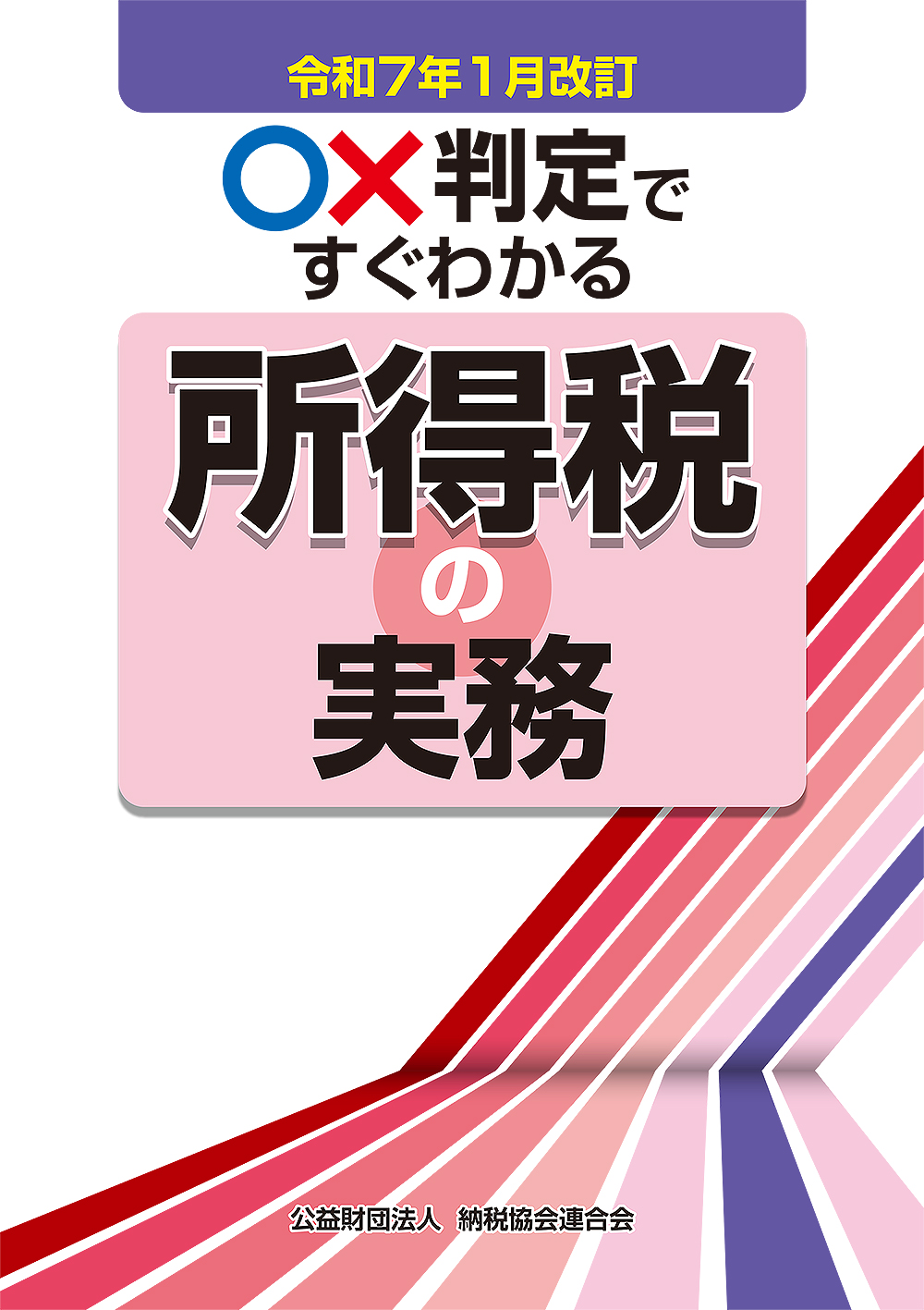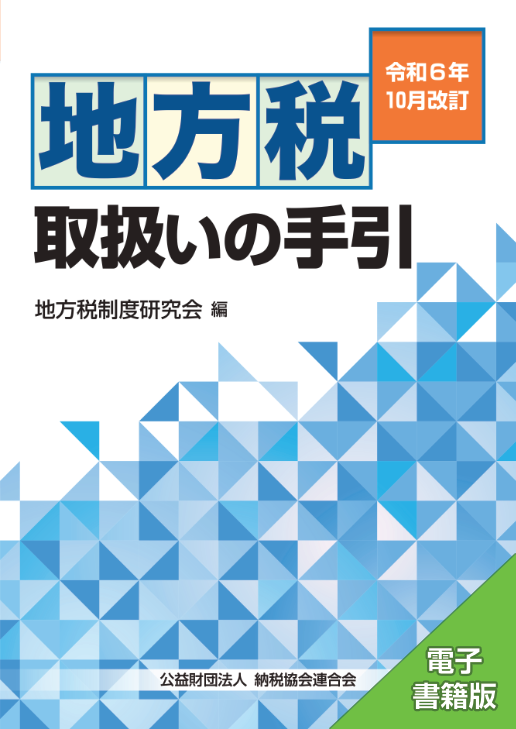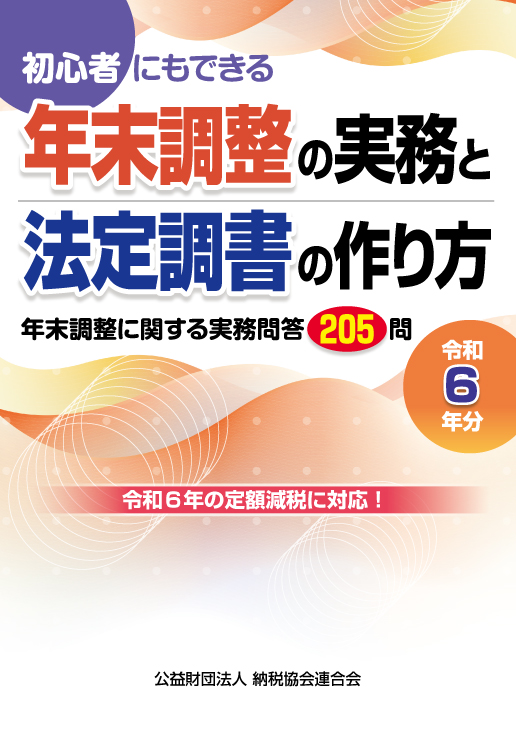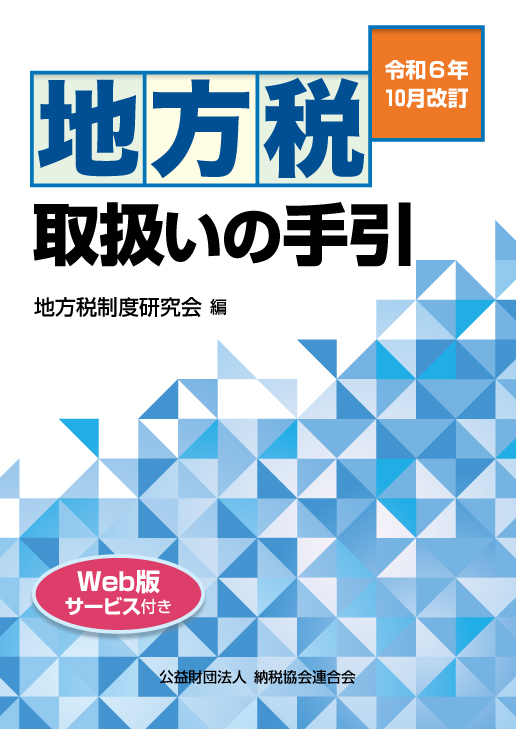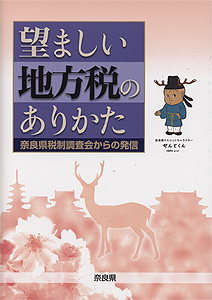〈小説〉
『所得課税第三部門にて。』
【第20話】
「個人住民税の非課税措置」

公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
「子供の貧困対策として・・・未婚ひとり親を支援する・・・」
浅田調査官は、平成31年度の税制改正大綱を見ながらつぶやく。
「これって・・・どう思います?」
昼休みに新聞を読んでいる中尾統括官に尋ねる。
「・・・でもそれは・・・所得税ではなく、個人住民税の非課税措置の話だろう?」
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。