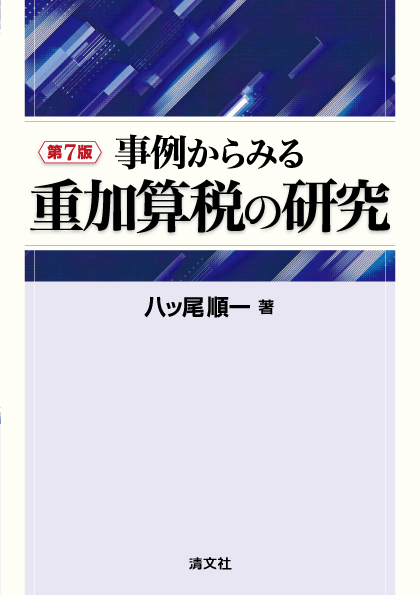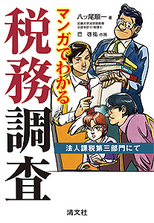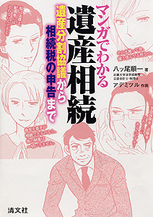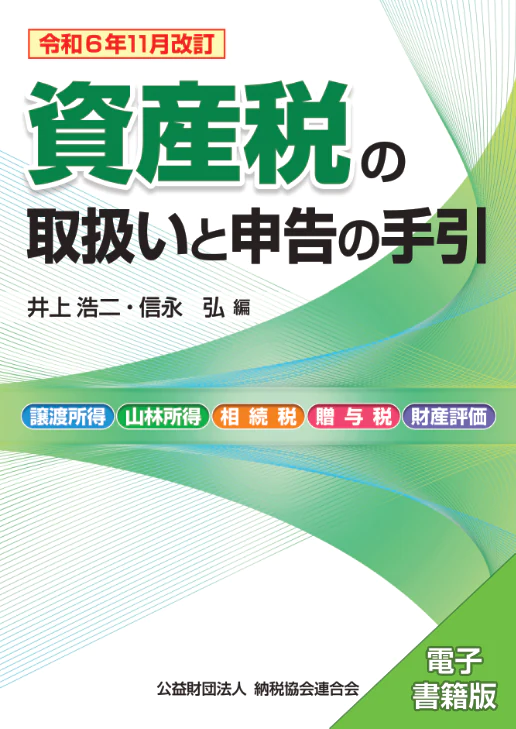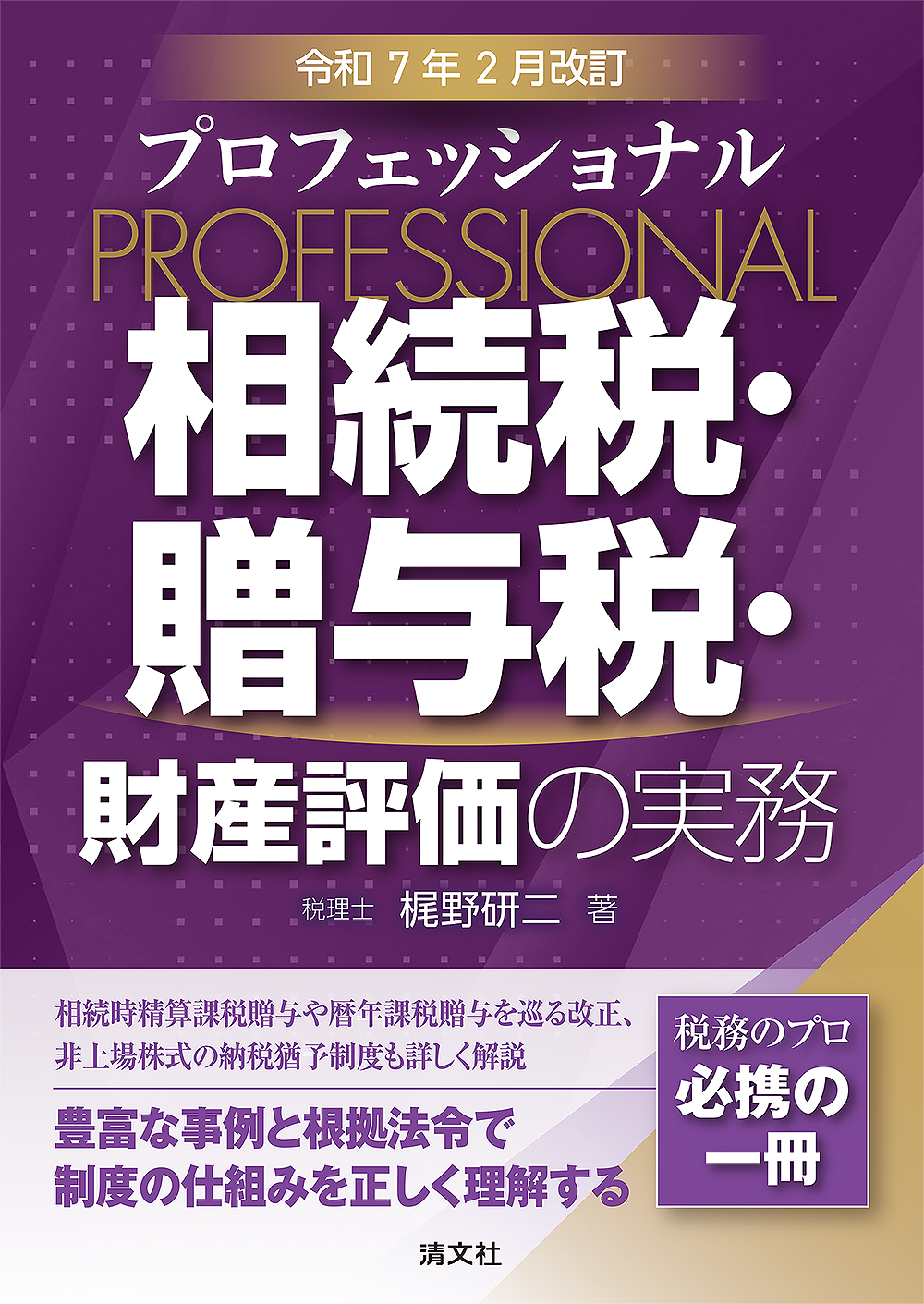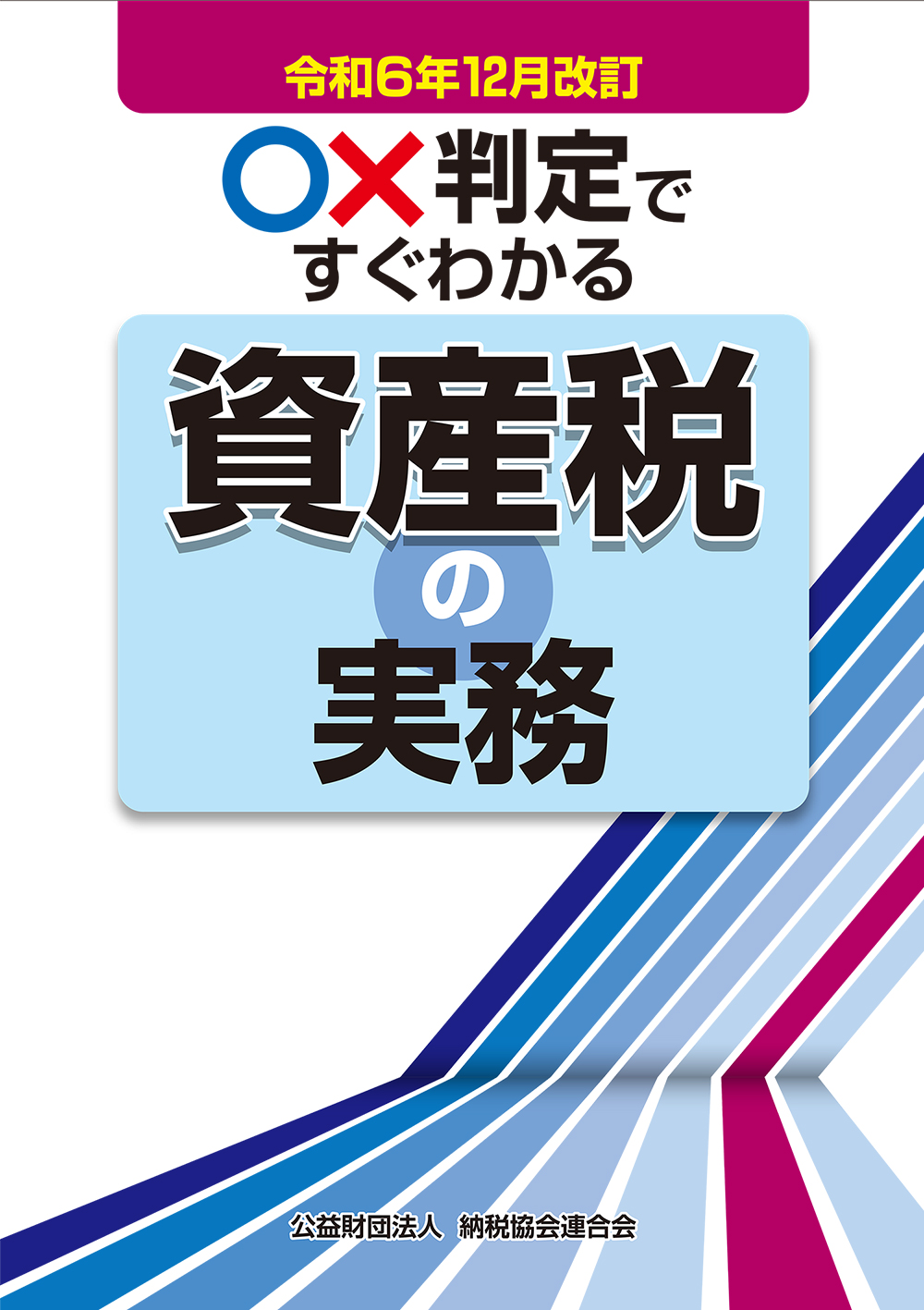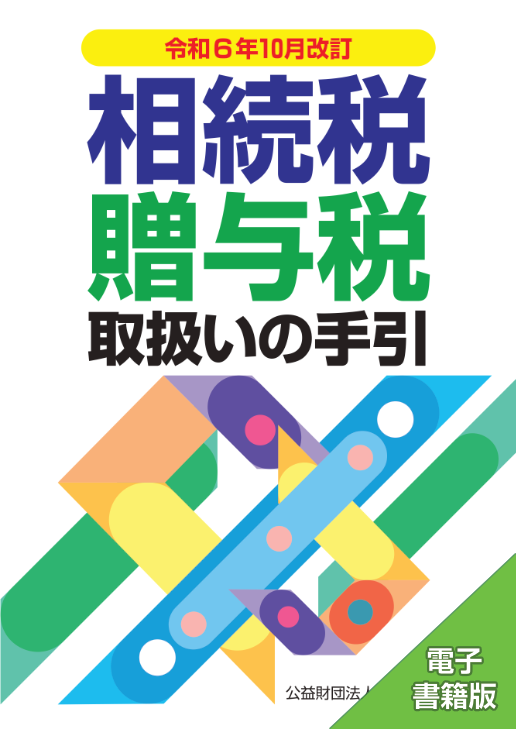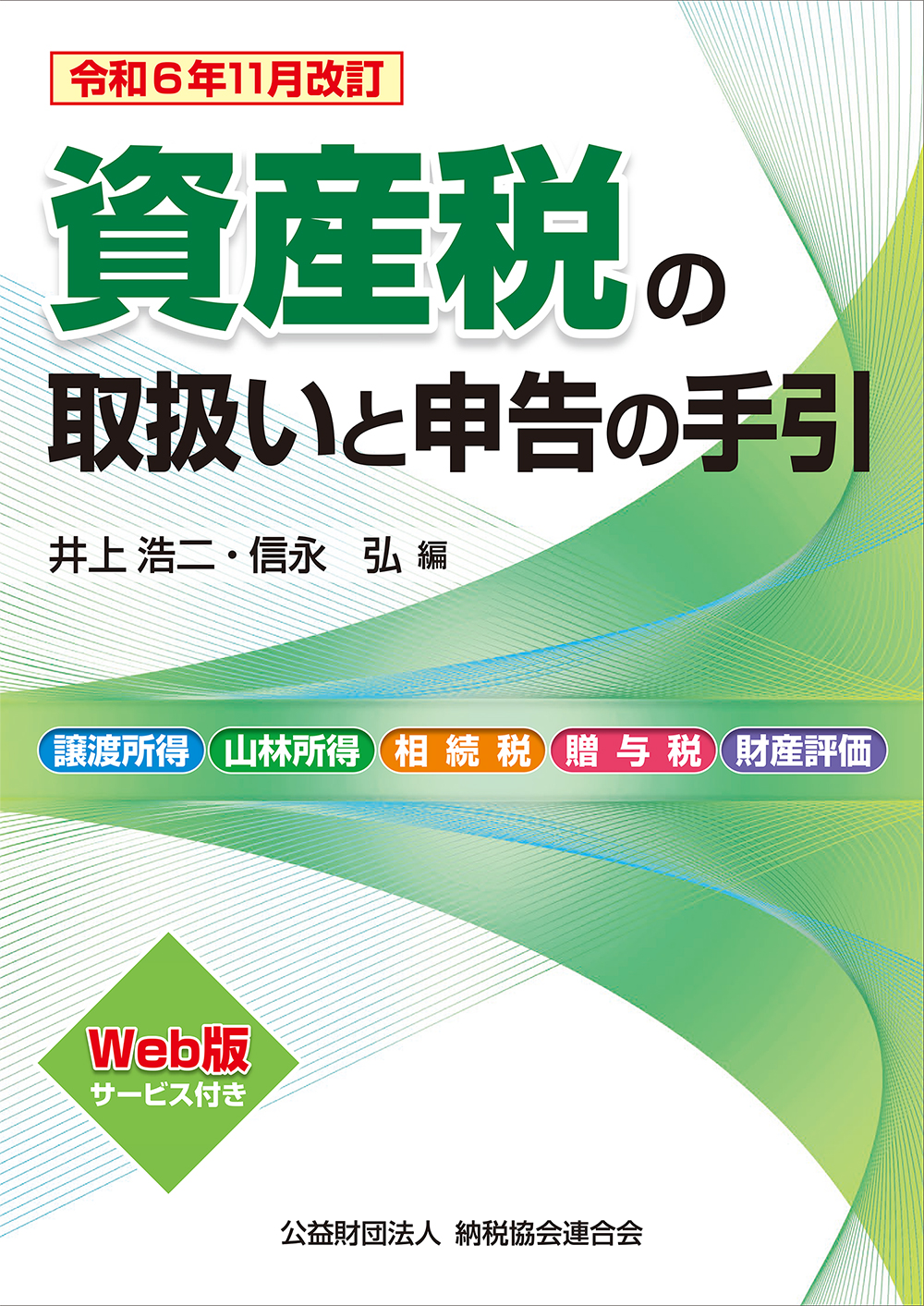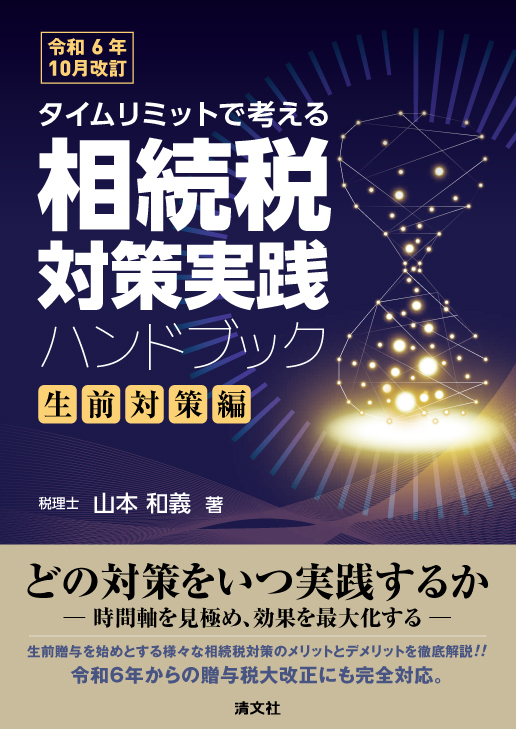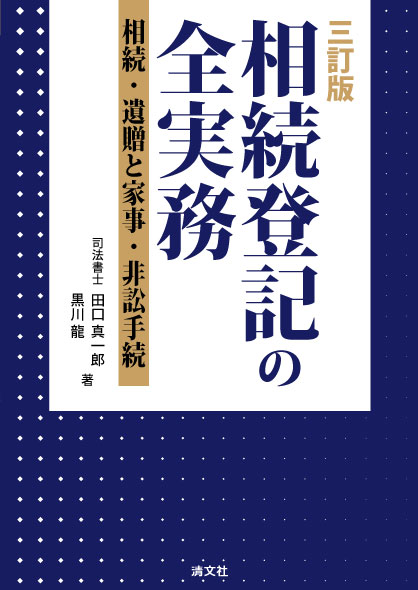〈小説〉
『資産課税第三部門にて。』
【第7話】
「未分割遺産とその法定果実」

公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
「田中統括官!」
田中統括官が顔を上げると、谷垣調査官が相続税の申告書を持ち、机の前に立っている。
「???」
田中統括官は、重そうな瞼で谷垣調査官を見た。
午後3時過ぎの睡魔が忍び寄る時刻である。
「何だい?」 田中統括官は谷垣調査官の真剣な眼差しに一瞬戸惑う。
「実は個人課税部門から質問があったのですが・・・」 谷垣調査官はそう言うと、右手に持った相続税の申告書を田中統括官に見せた。
「この相続税の申告書は未分割で提出されているのですが・・・」
相続税の申告書を見ながら田中統括官はうなずく。
「そんなことは申告書を見れば分かる・・・それで一体、どうしたっていうんだ。」 谷垣調査官の質問の意味が理解できず、田中統括官の声が苛立っている。
「この未分割の相続財産の中に、賃貸マンションがあるのです。」
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。