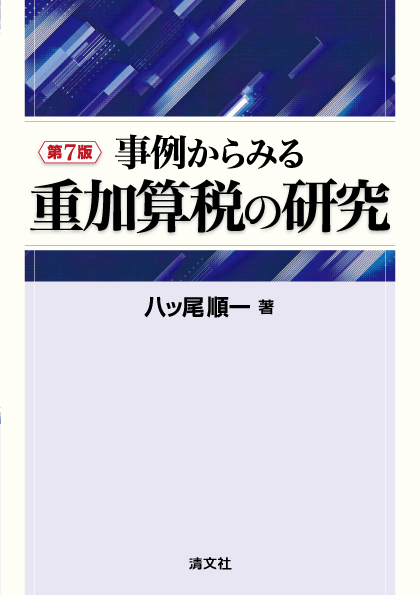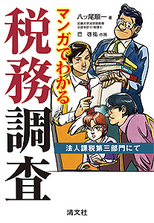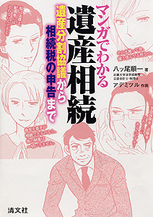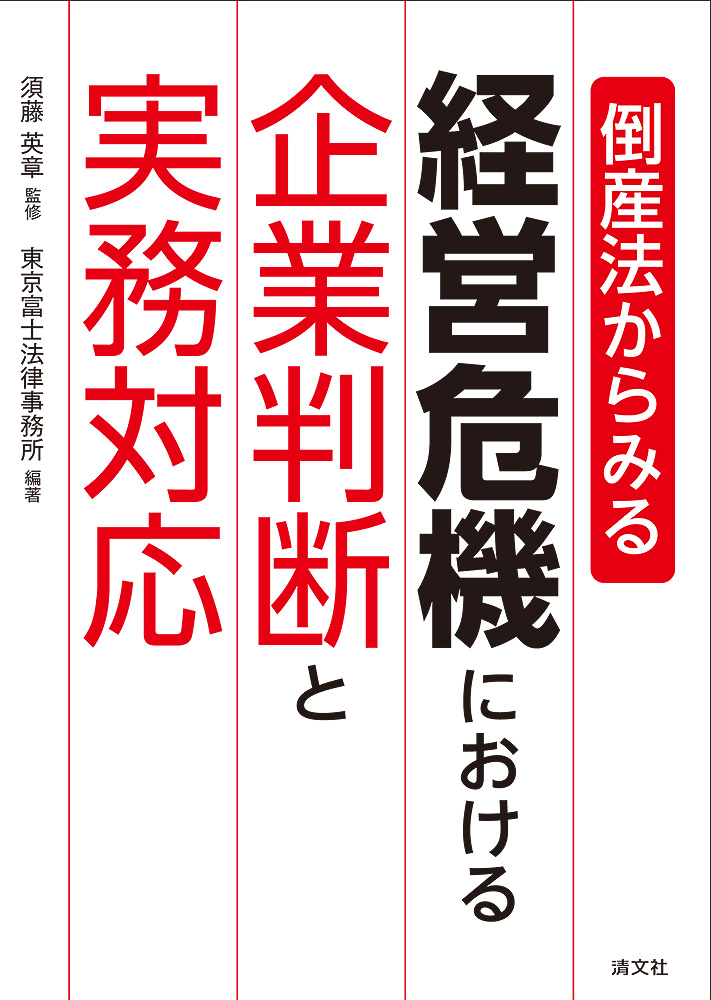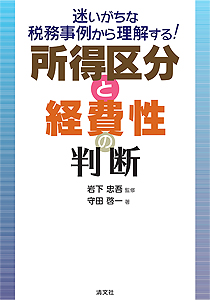〈小説〉
『所得課税第三部門にて。』
【第33話】
「新型コロナウイルスと給付金」

公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
「10万円か・・・」
浅田調査官はそうつぶやくと、振り返って中尾統括官を見る。
中尾統括官は毎月の事務計画の策定で、電卓を叩いている。
「統括官。」
浅田調査官が、声をかける。
「・・・」
しばらくして、中尾統括官は、顔を上げる。
「なんだ?」
少し機嫌の悪そうな返事である。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。