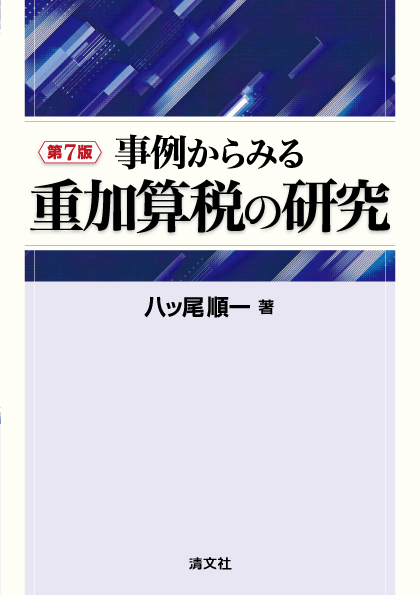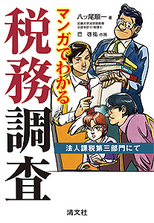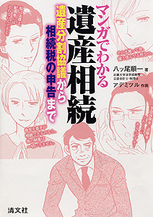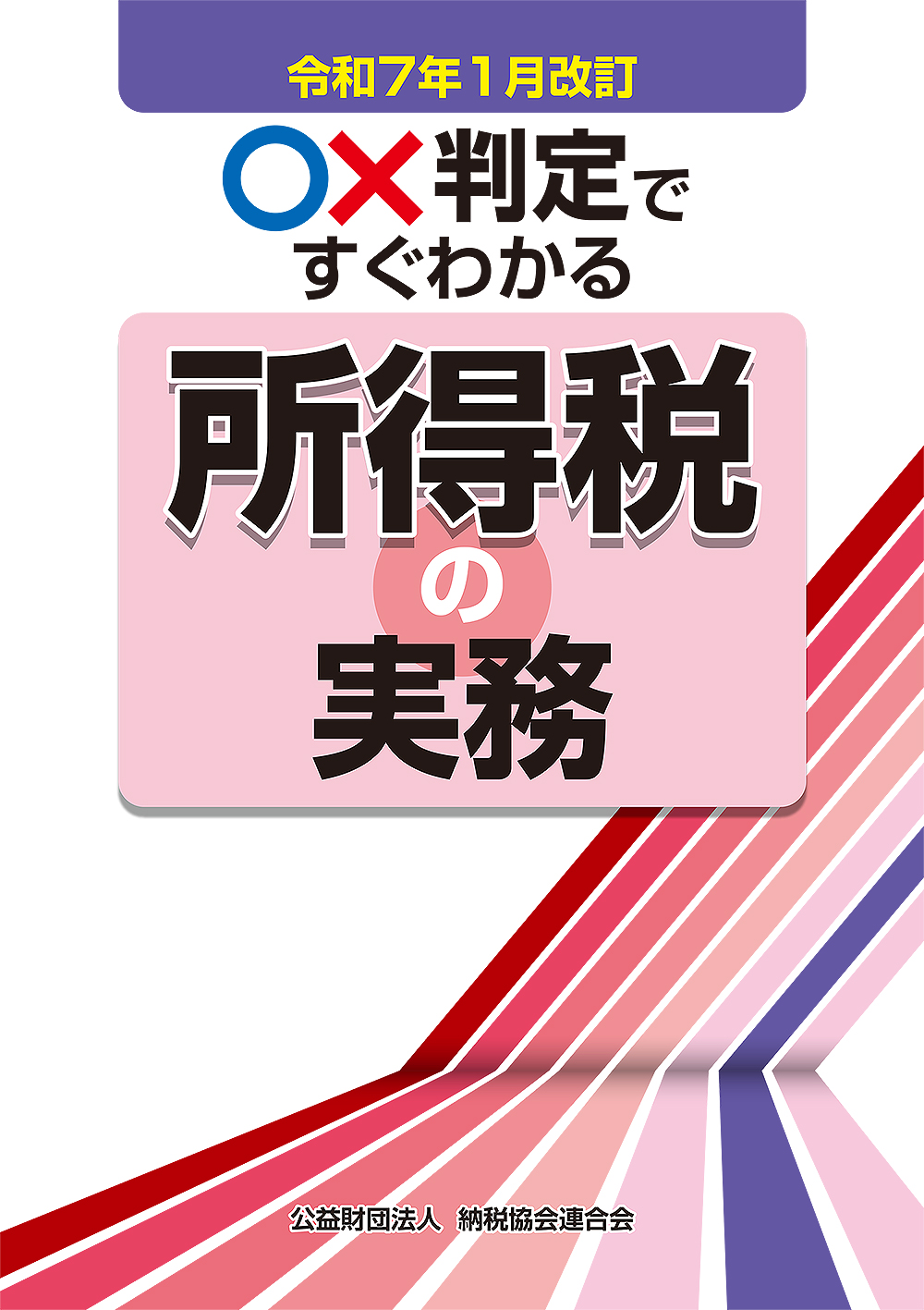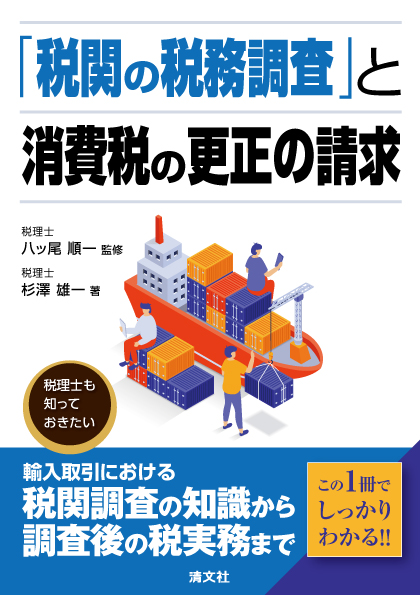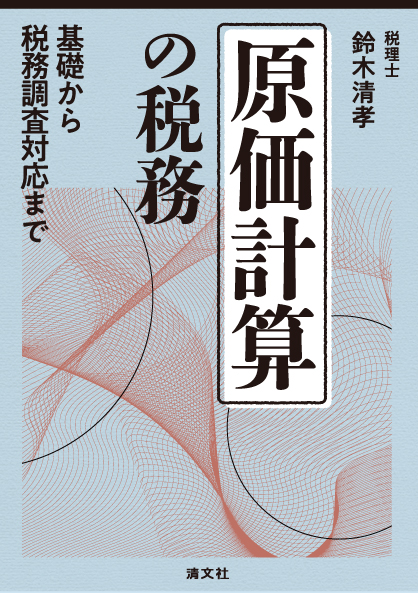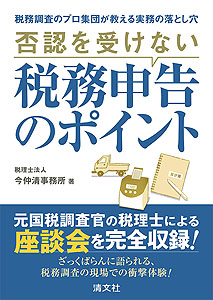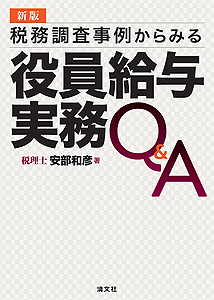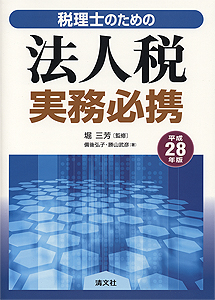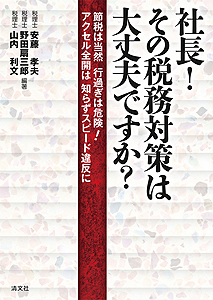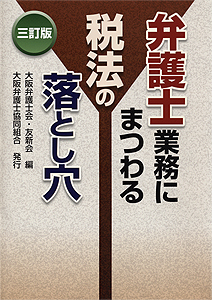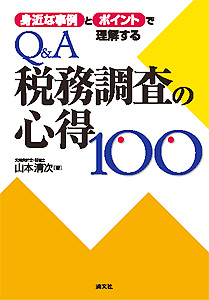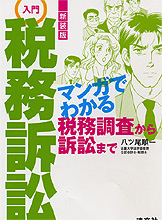〈小説〉
『所得課税第三部門にて。』
【第64話】
「基礎的人的控除について」

公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
「・・・基礎的人的控除か・・・」
浅田調査官は、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を見ながら、呟く。
租税法のテキストには、「基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除は、一括して『基礎的人的控除』といい、これらは本人及び家族の最低限度の生活を維持するために必要な部分は担税力を持たないということを理由とし、憲法25条の生存権の保障の租税法における現れである」と書かれている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。