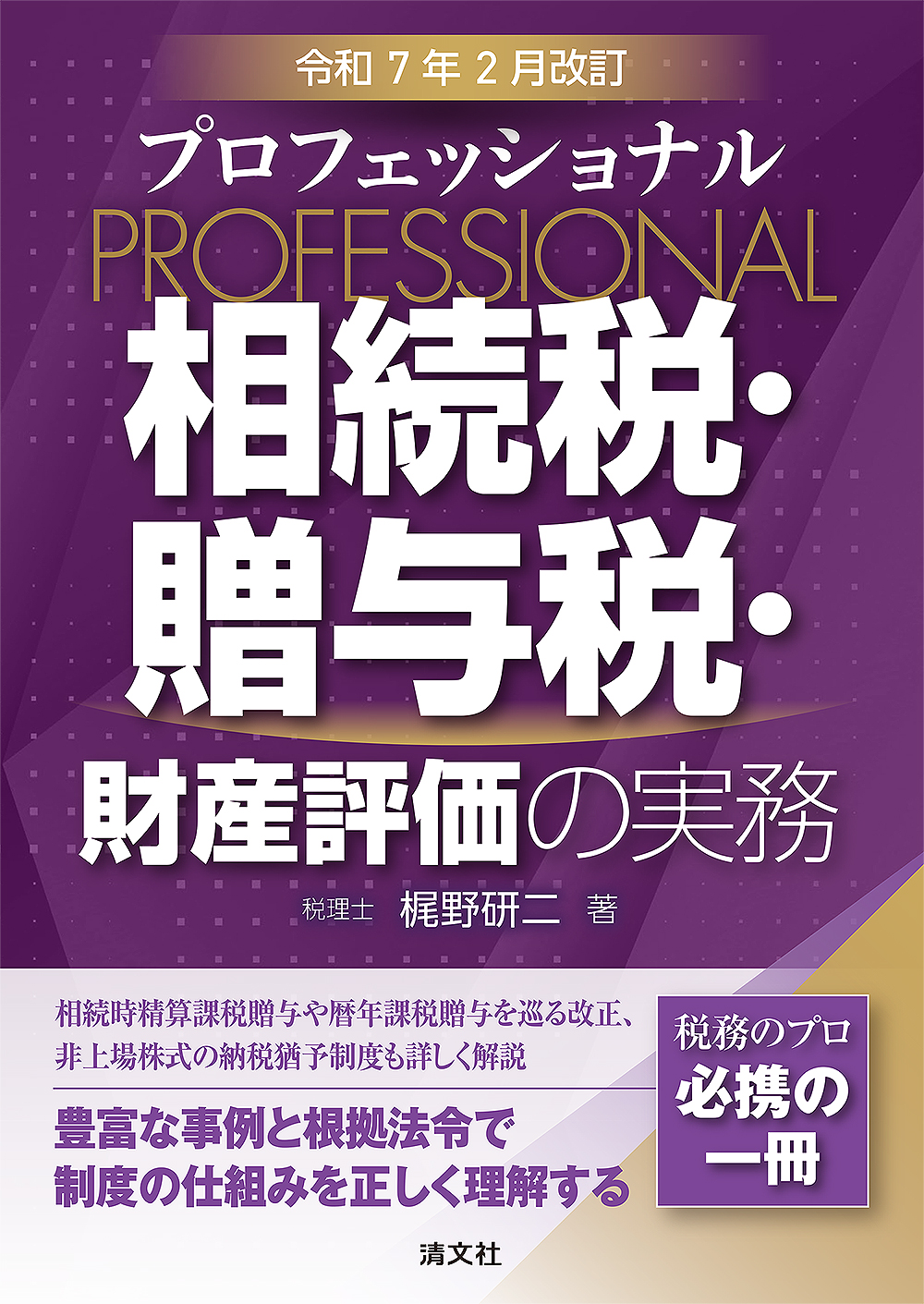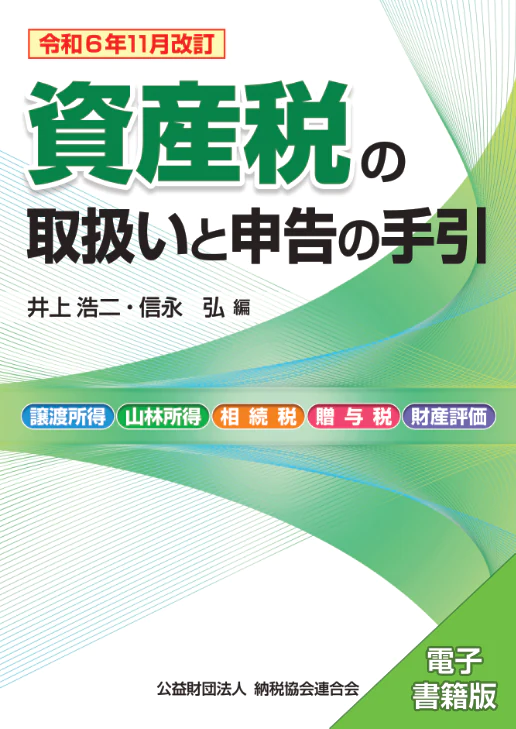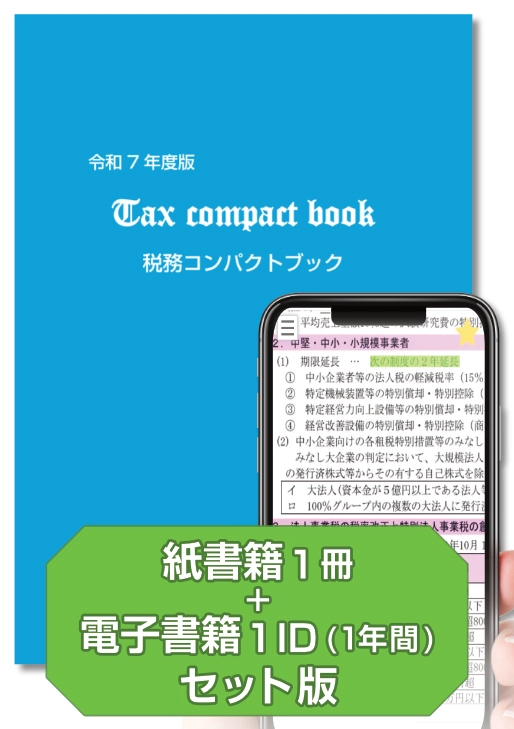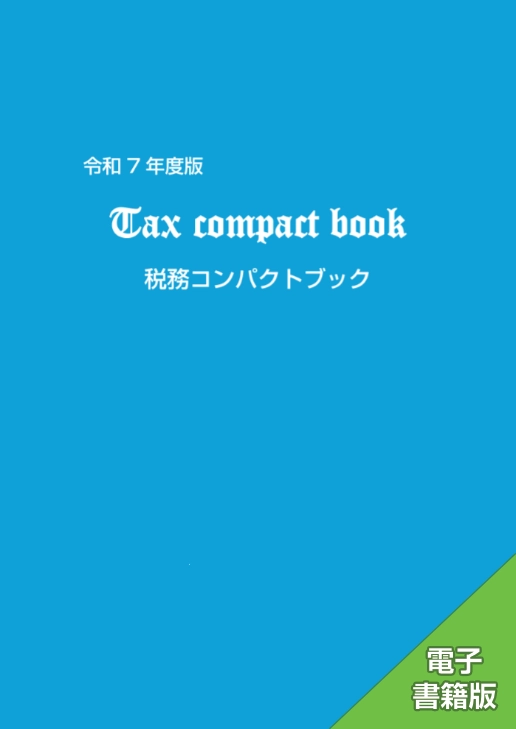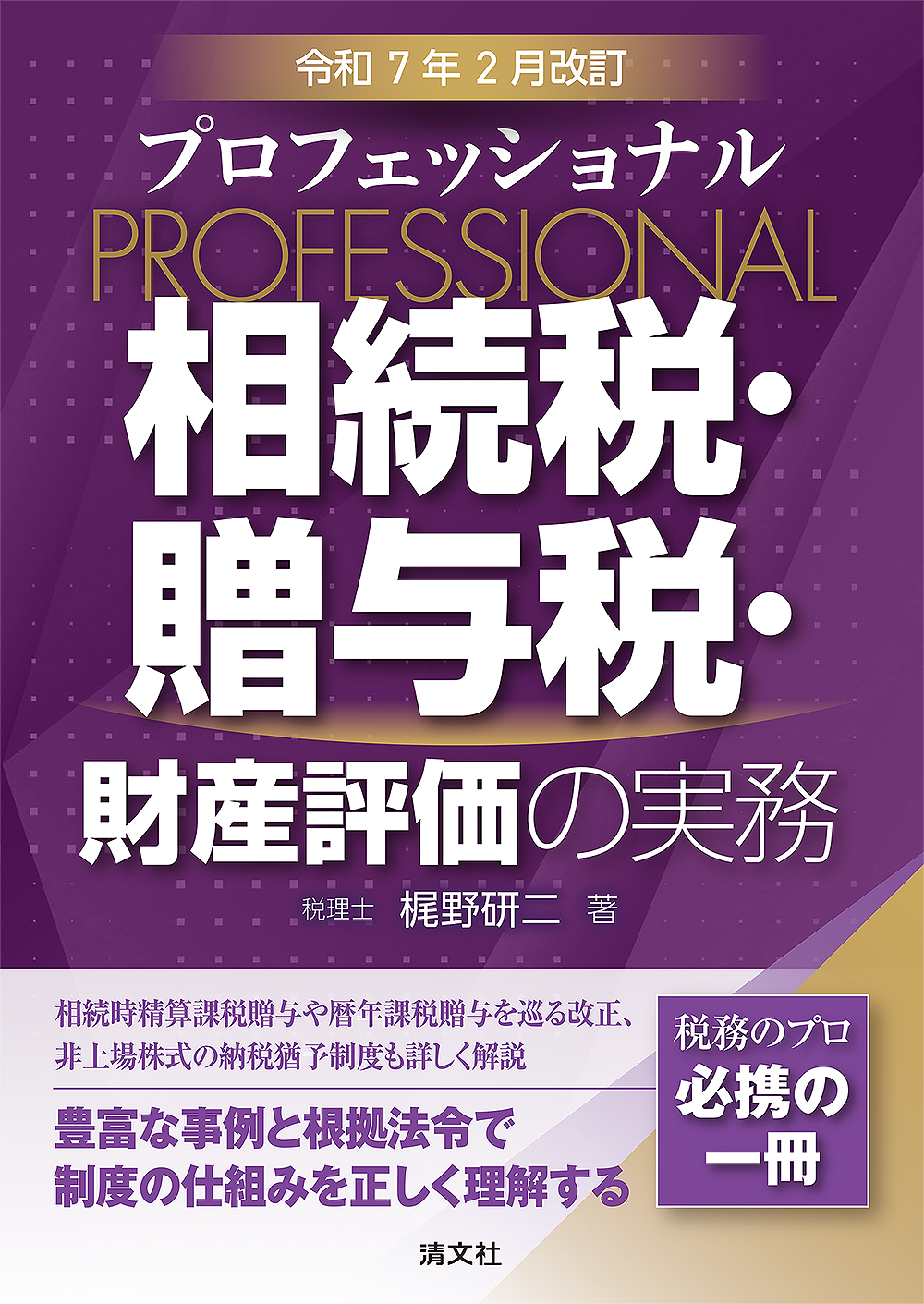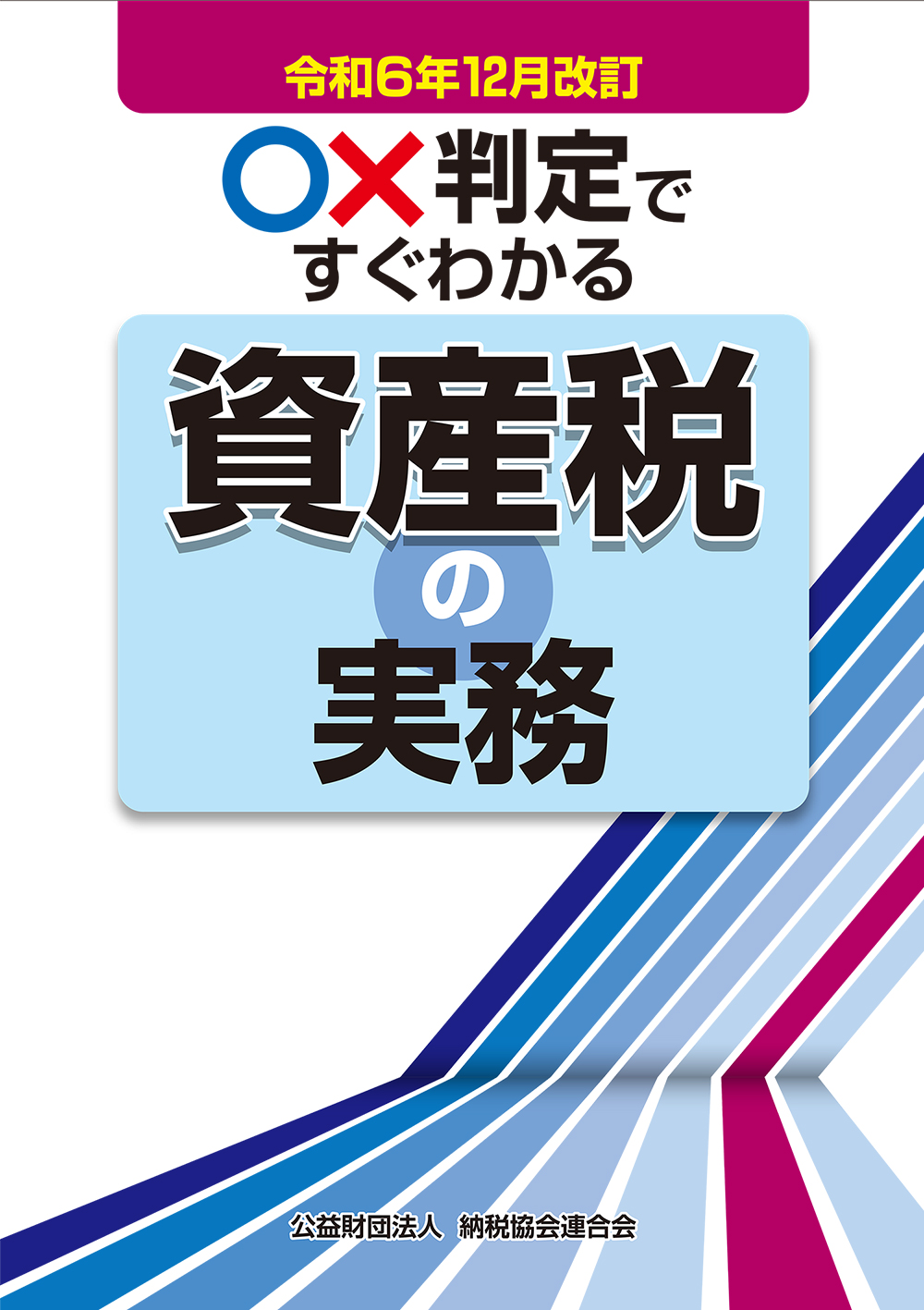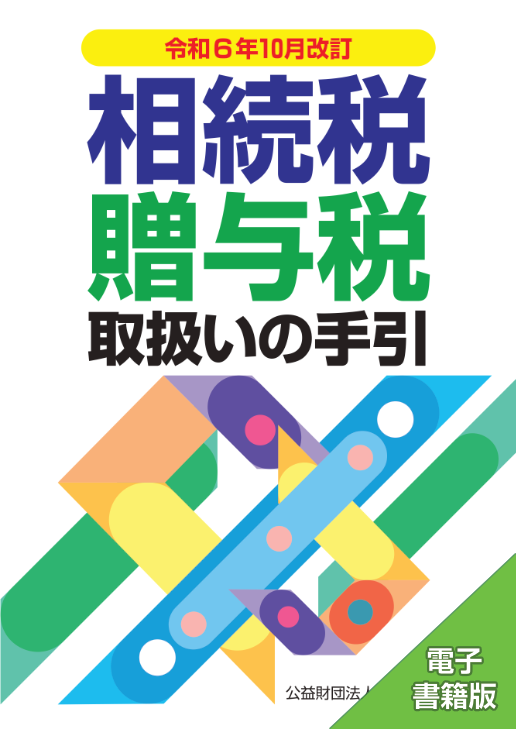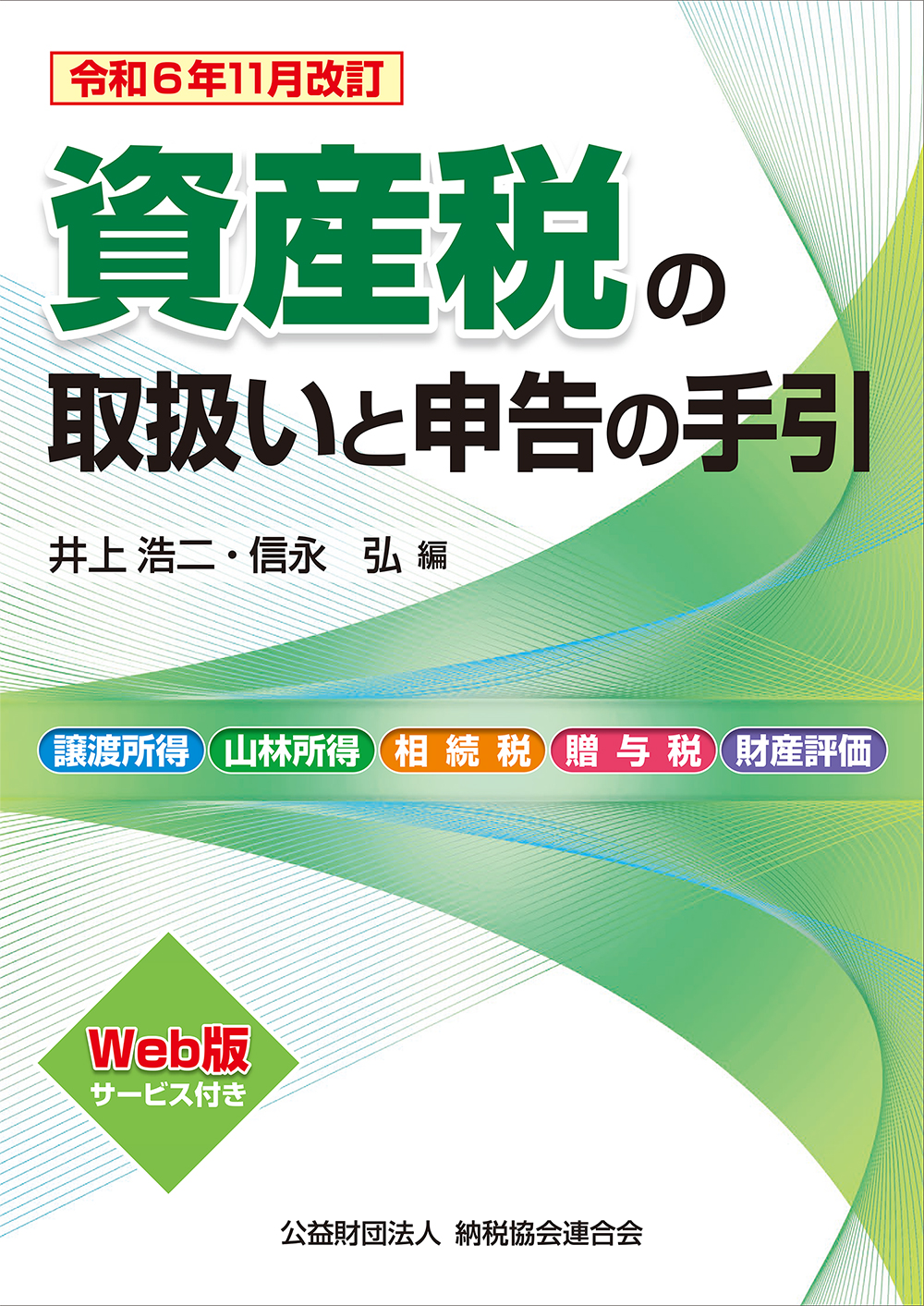相続税の実務問答
【第30回】
「財産の取得の状況を証する書類
(相続分がない旨の証明書を提出する場合)」
税理士 梶野 研二
[問]
平成30年8月20日に母が亡くなりました。相続人は、姉と妹である私の2人です。母の主な遺産は、母と私が居住の用に供していた川口市内の土地及び建物です。
姉と協議をした結果、姉は母から多額の生前贈与を受けていたことから、川口市内の土地及び建物を私が相続することとなりました。土地及び建物の相続登記をするに当たり、遺産分割協議書は作成せずに、姉に「相続分がない旨の証明書」を作成してもらい、これを登記原因を証する書類の一部として相続登記を行いました。
私が取得した土地は特定居住用宅地等に該当することとなりますので、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4第1項)を適用したいと考えていますが、相続税の申告書にこの「相続分がない旨の証明書」を添付することにより、この特例を適用することができますか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。