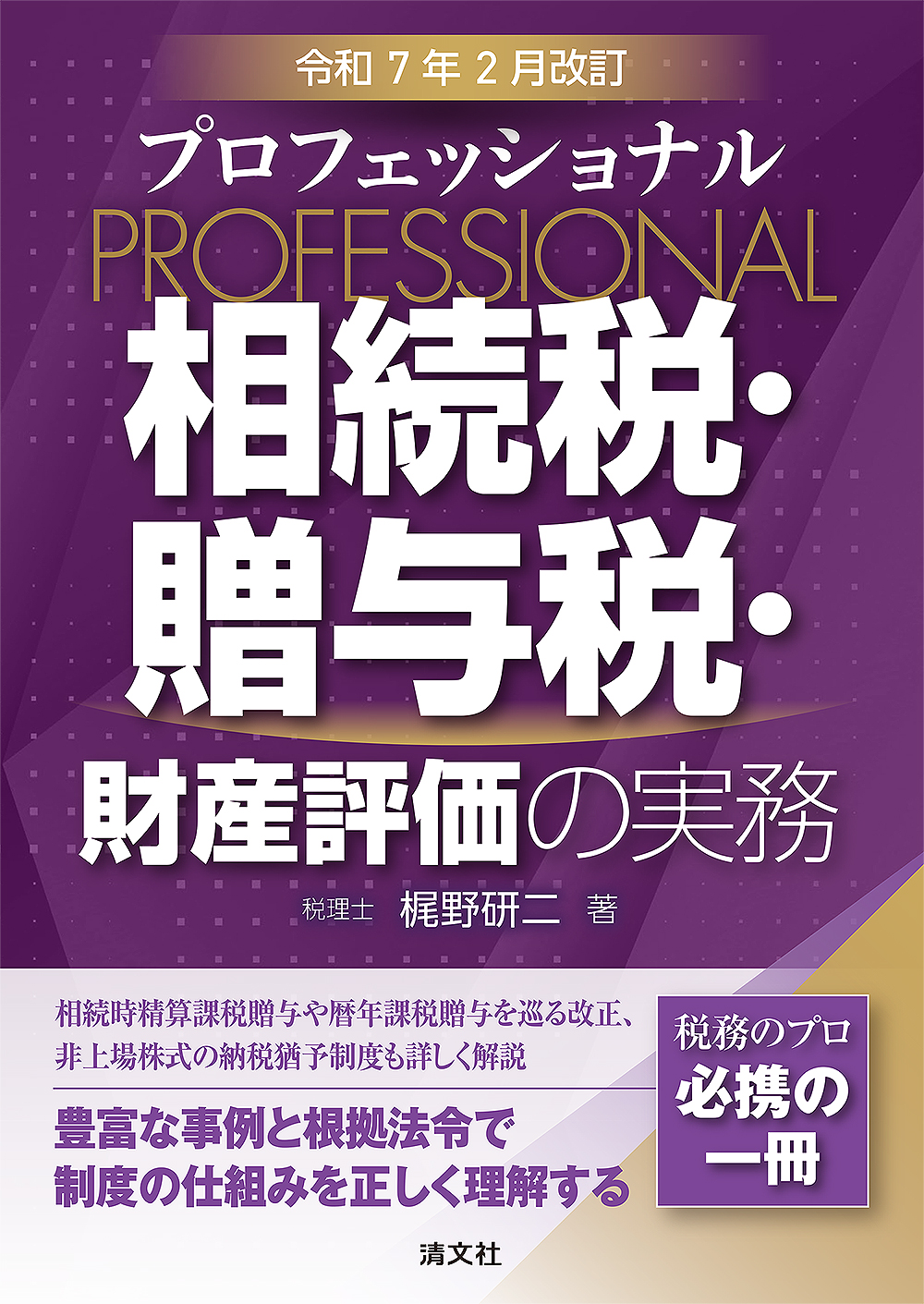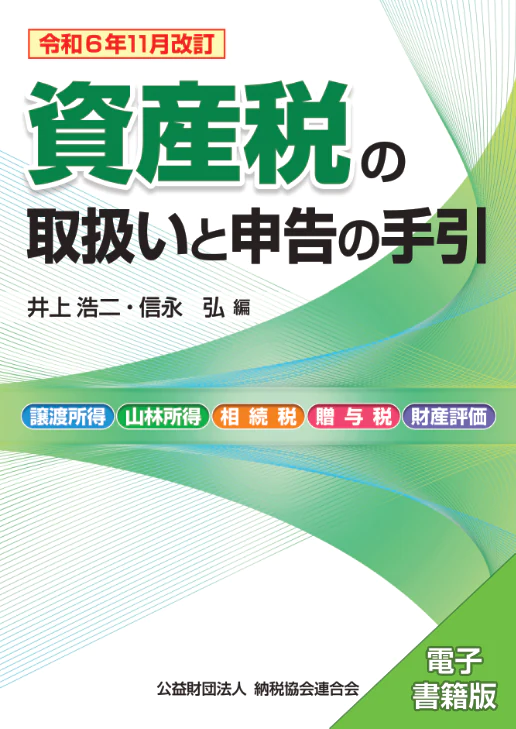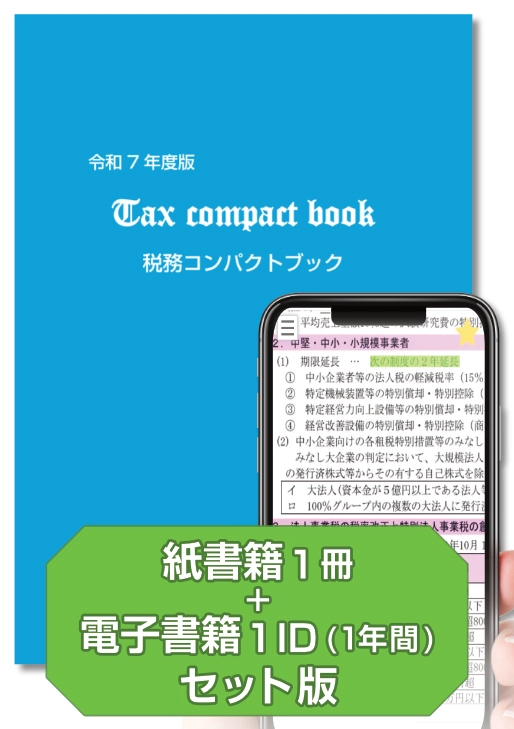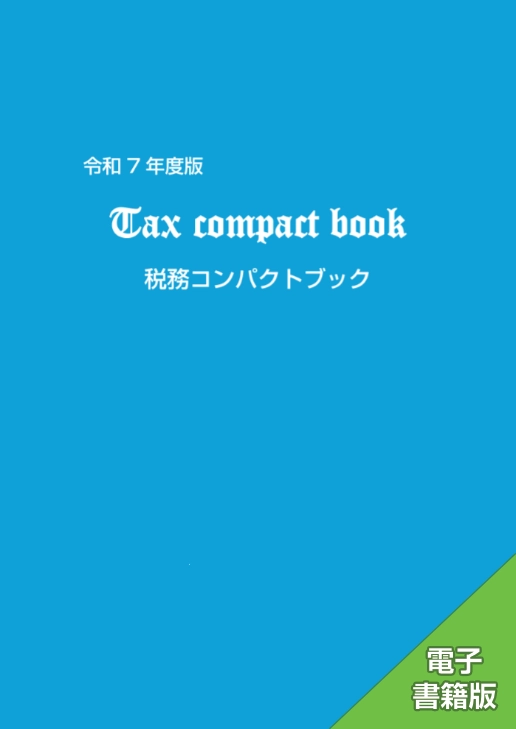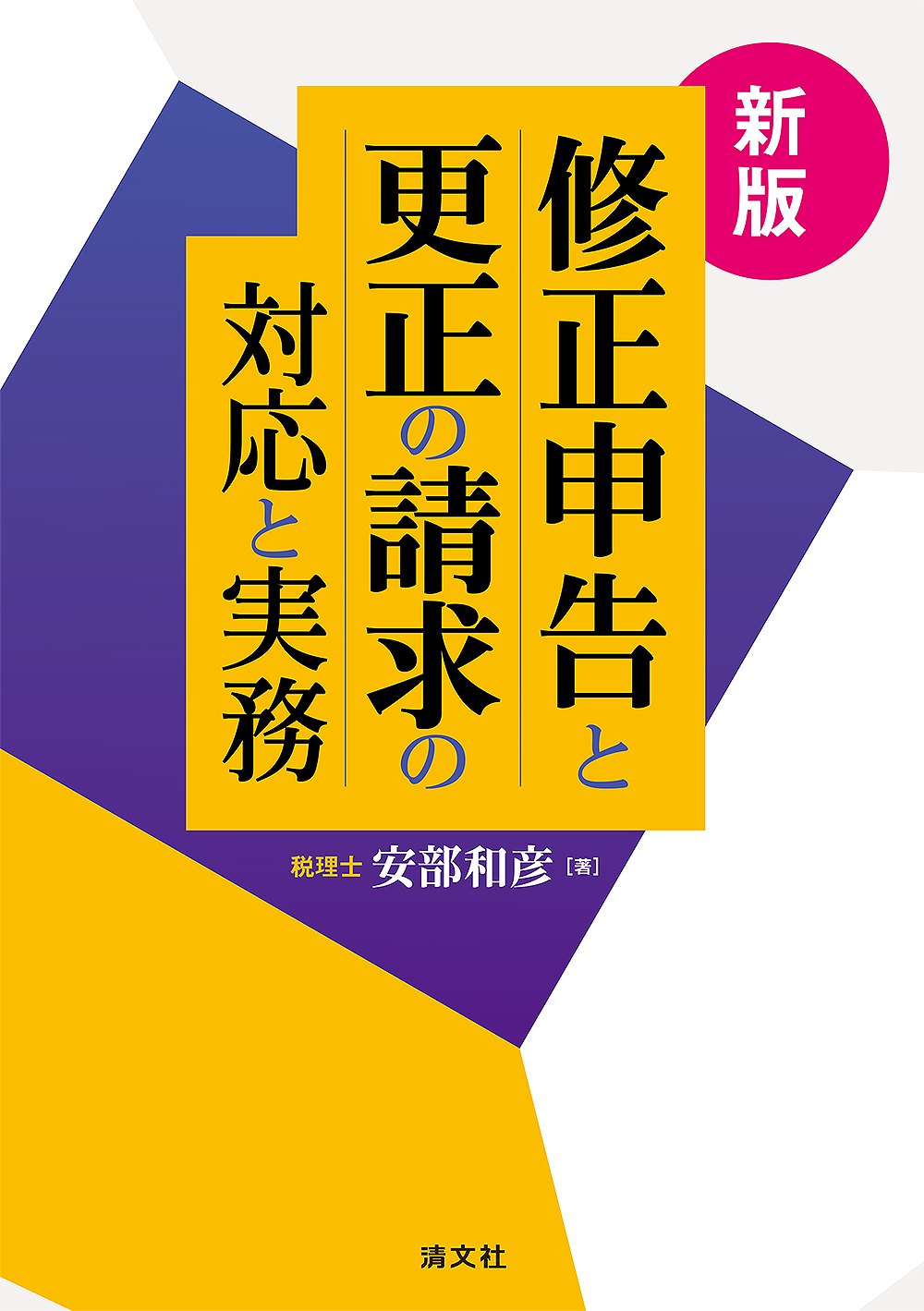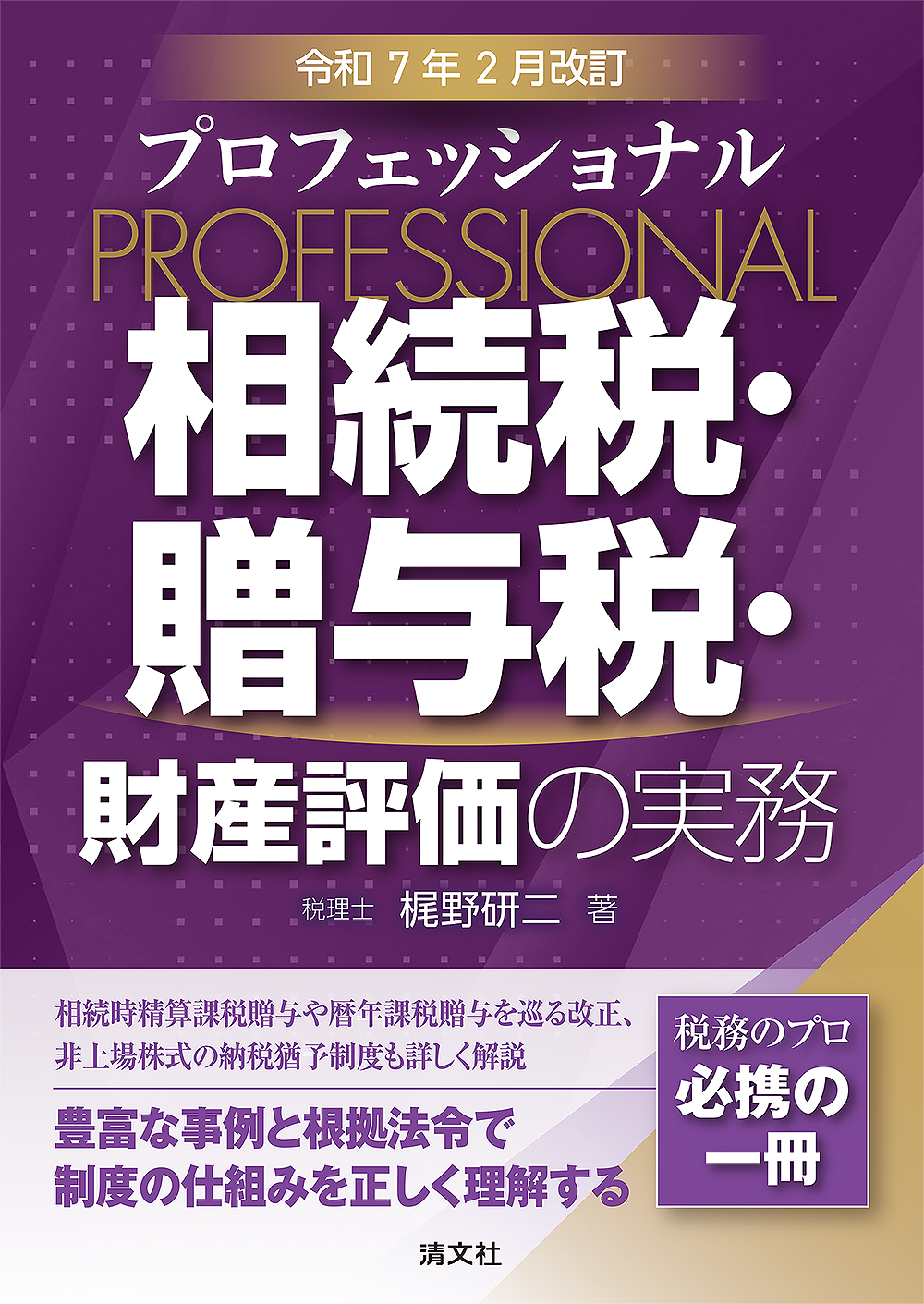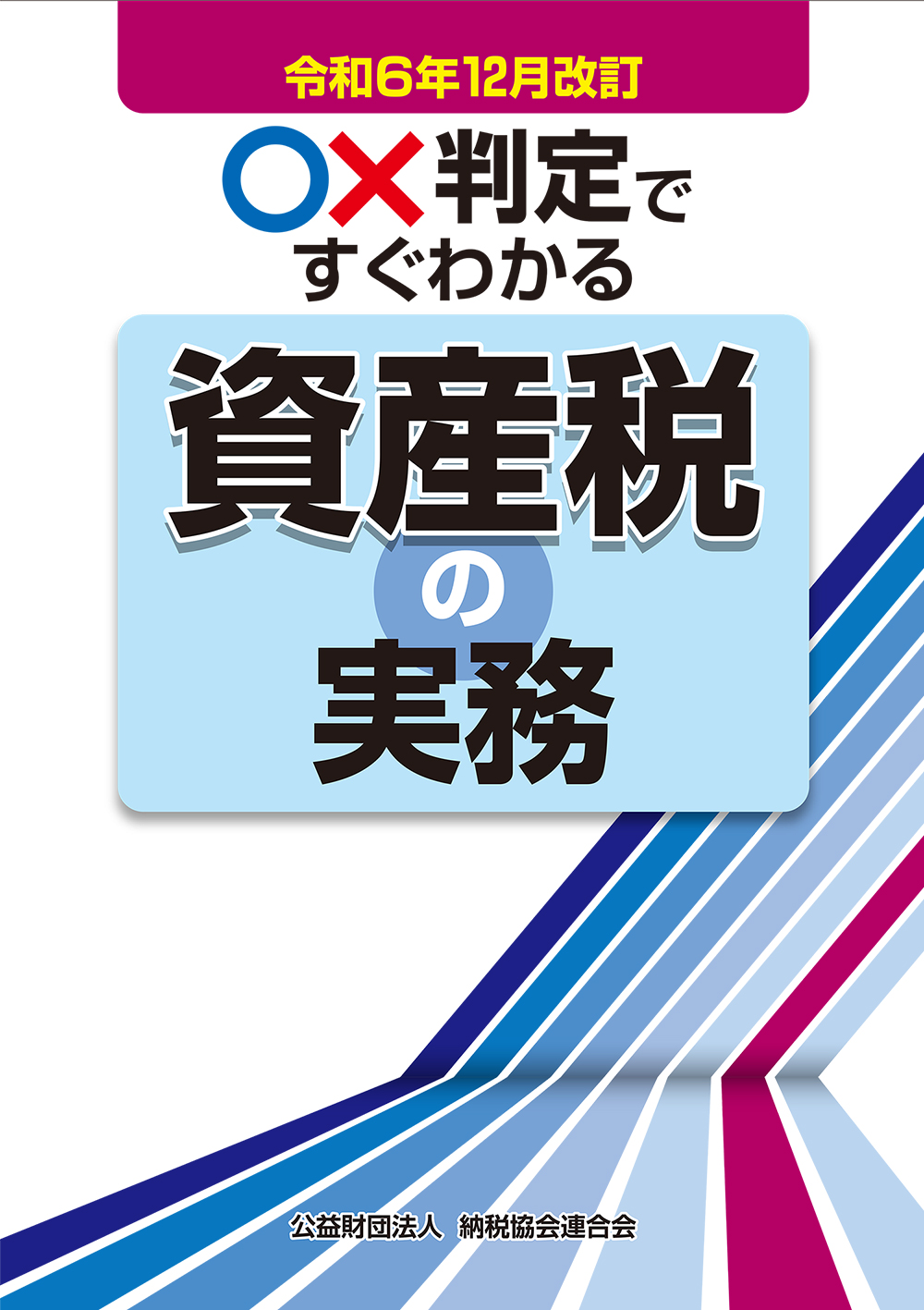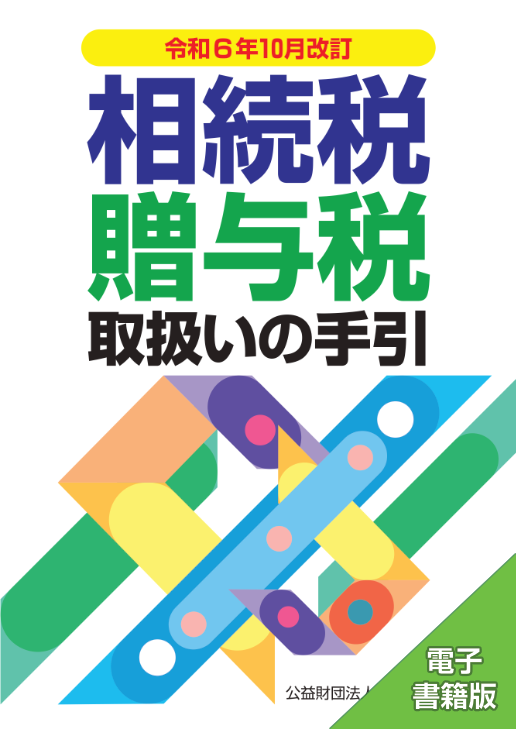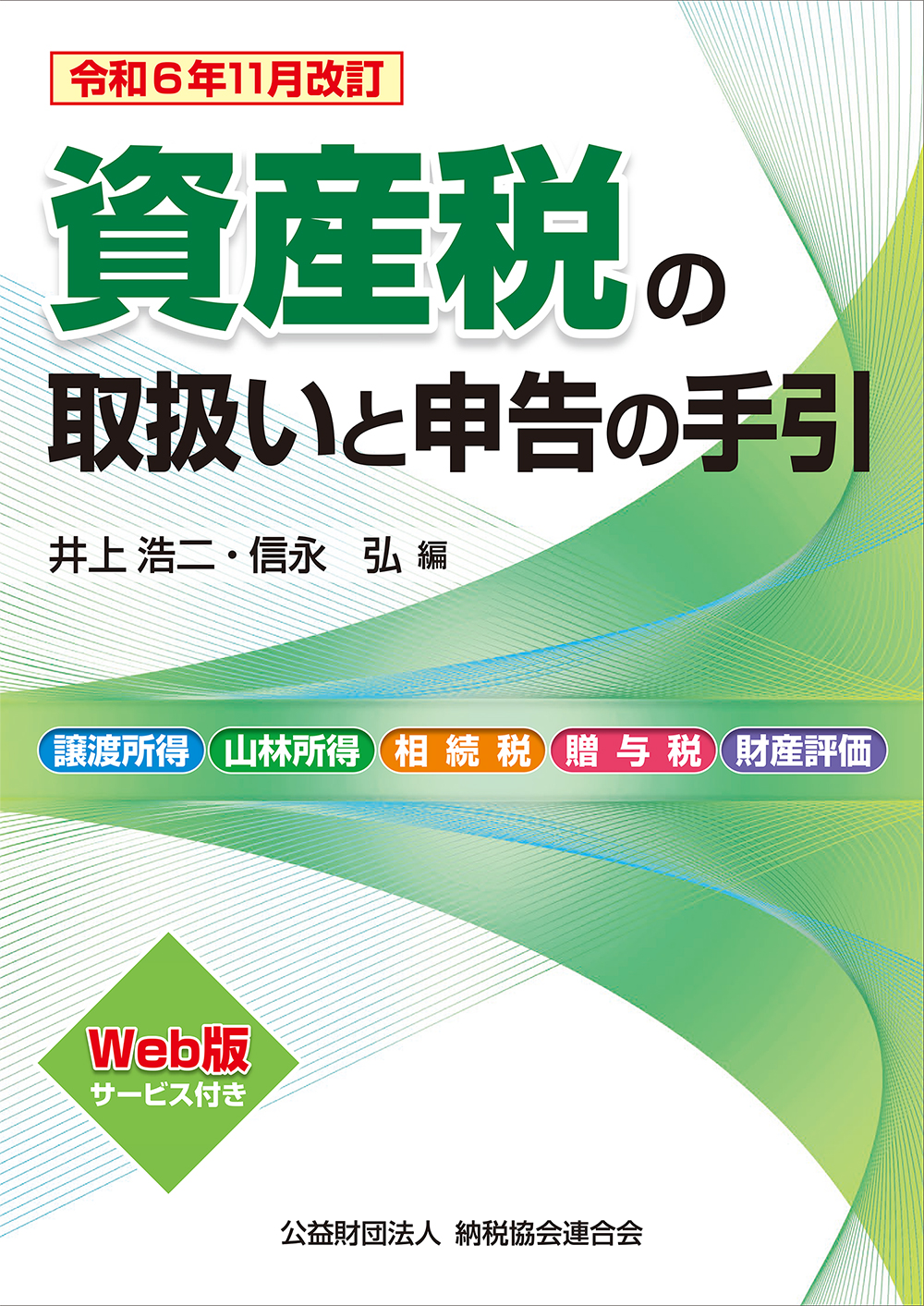相続税の実務問答
【第43回】
「遺産分割協議が成立した後に遺言書が発見された場合」
税理士 梶野 研二
[問]
平成31年2月に父が亡くなりました。相続人は姉と私の2人です。姉と私は父の遺産について、相続税の申告期限までに遺産分割協議を行い、相続税の申告を済ませました。
最近になって、父の日記などを整理していたところ、その中から「遺言書」と書かれた封筒が出てきました。家庭裁判所の検認を受け、その内容を確認したところ、そこには遺産分割協議において私が取得することとなったA銀行B支店の定期預金を従兄の甲に遺贈すると記載されていました。
私は、父の遺志を尊重し、遺言書に記載されていた定期預金を甲に渡したいと思いますが、そうすると甲に贈与税が課税されることになるのでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。