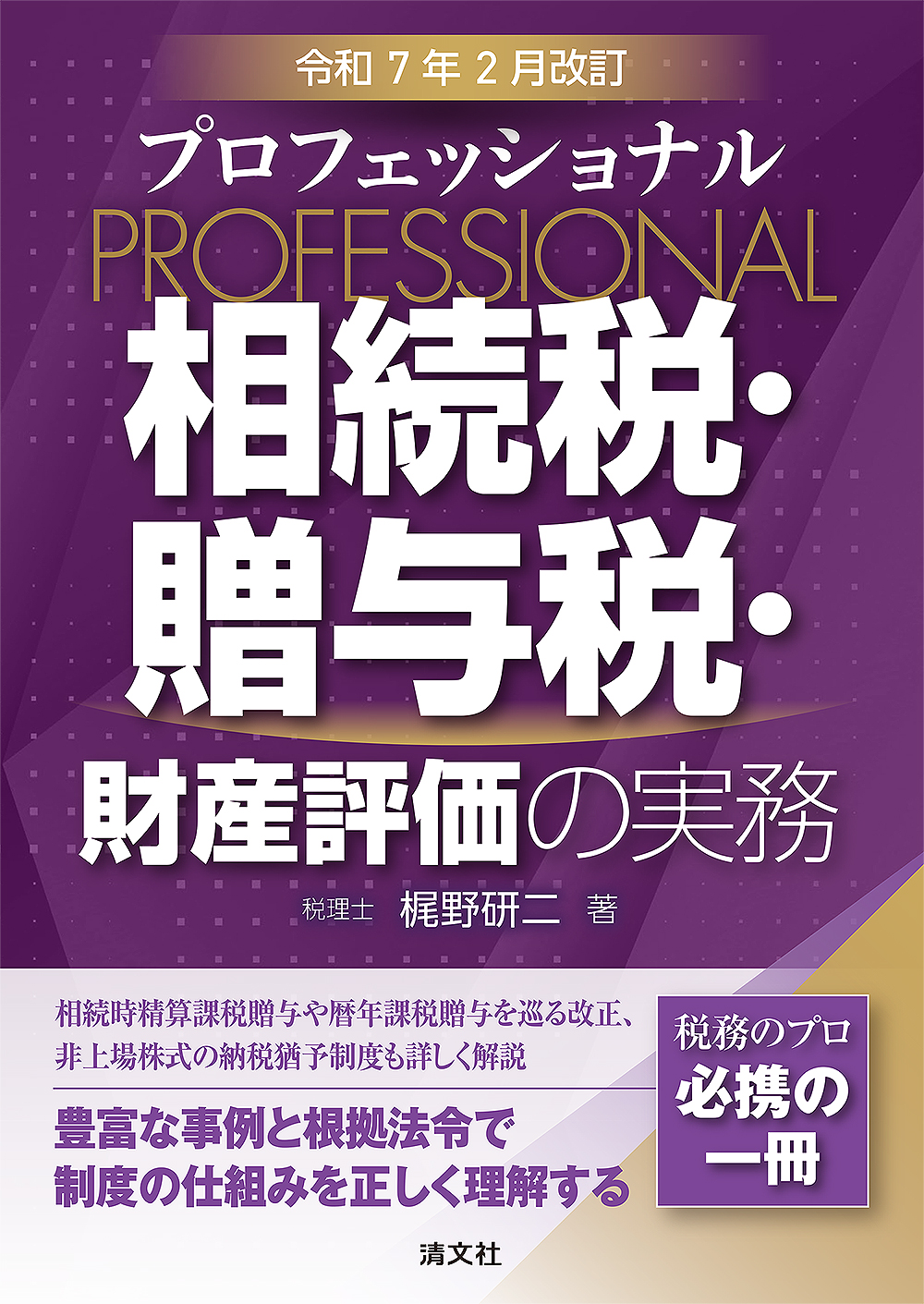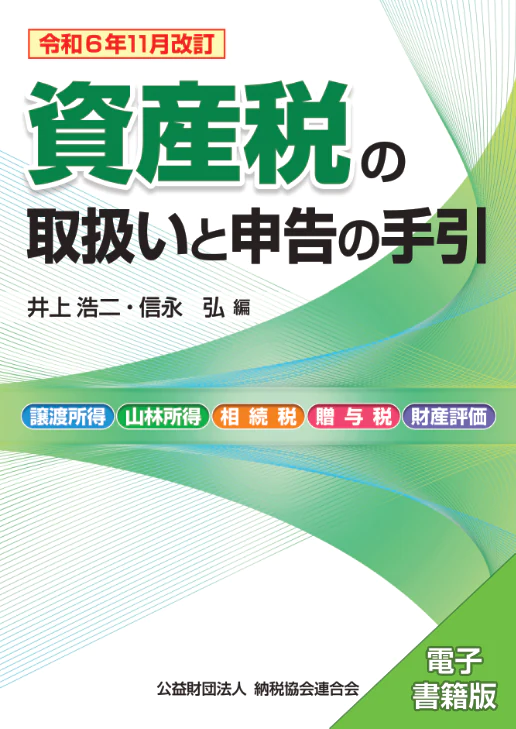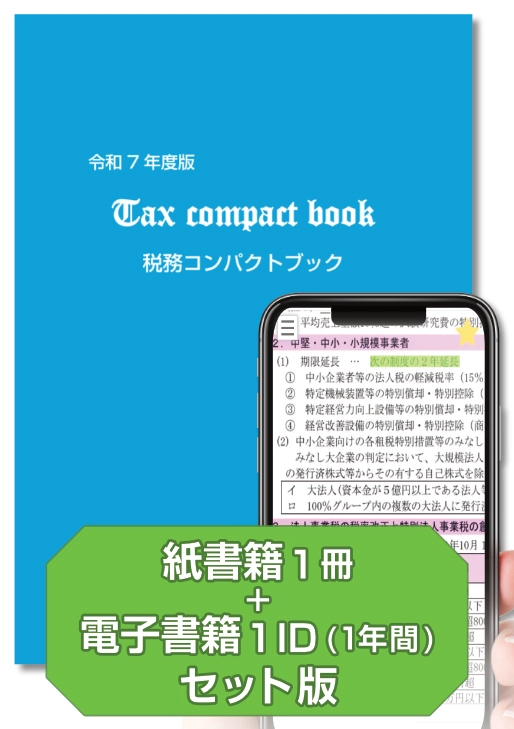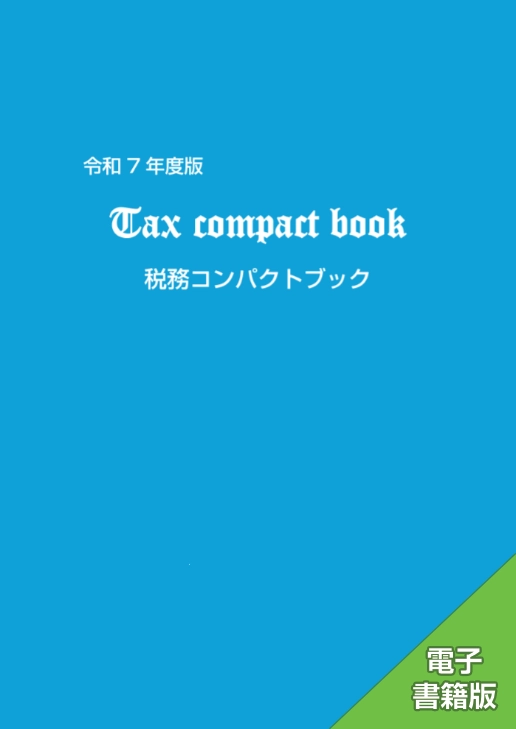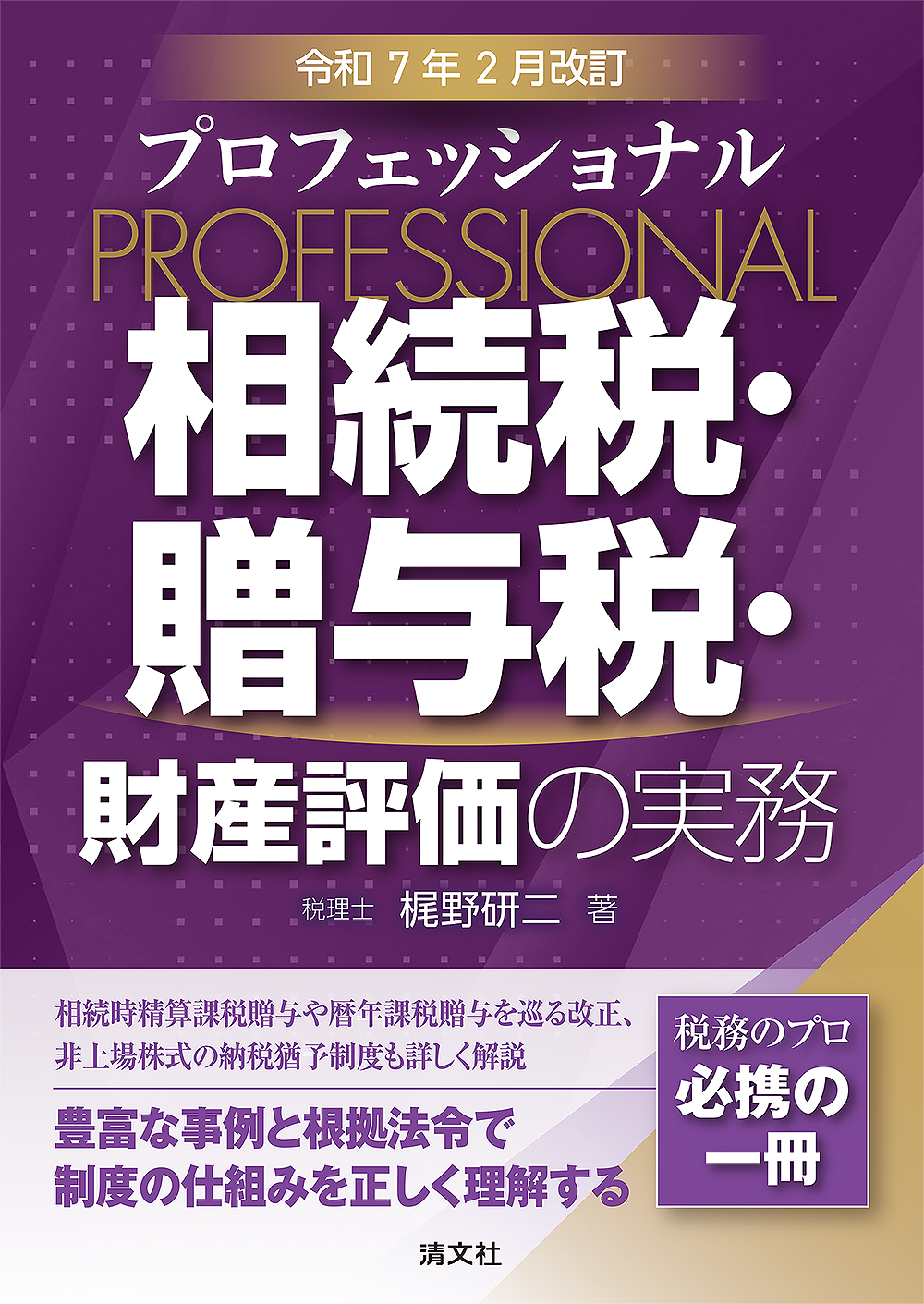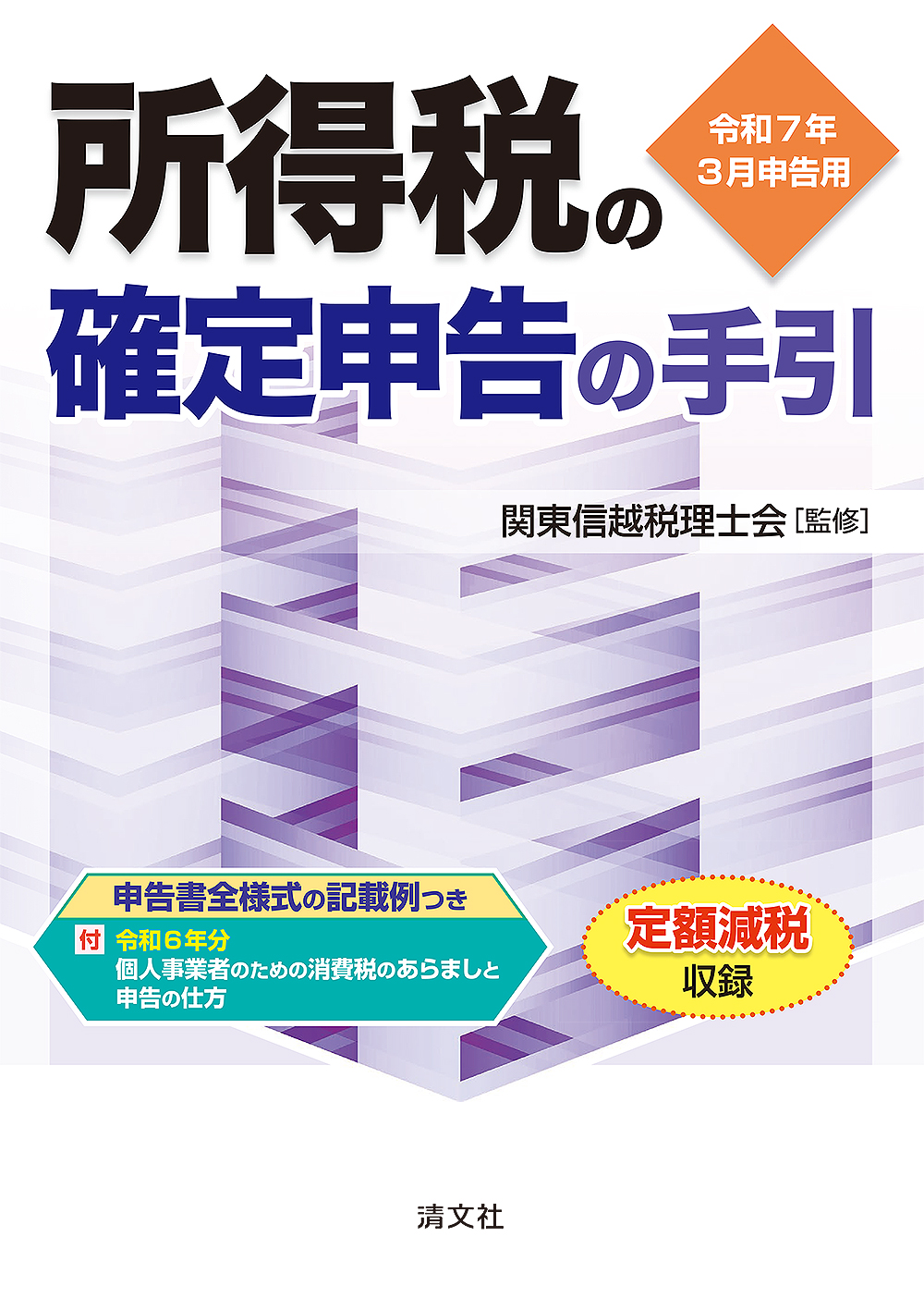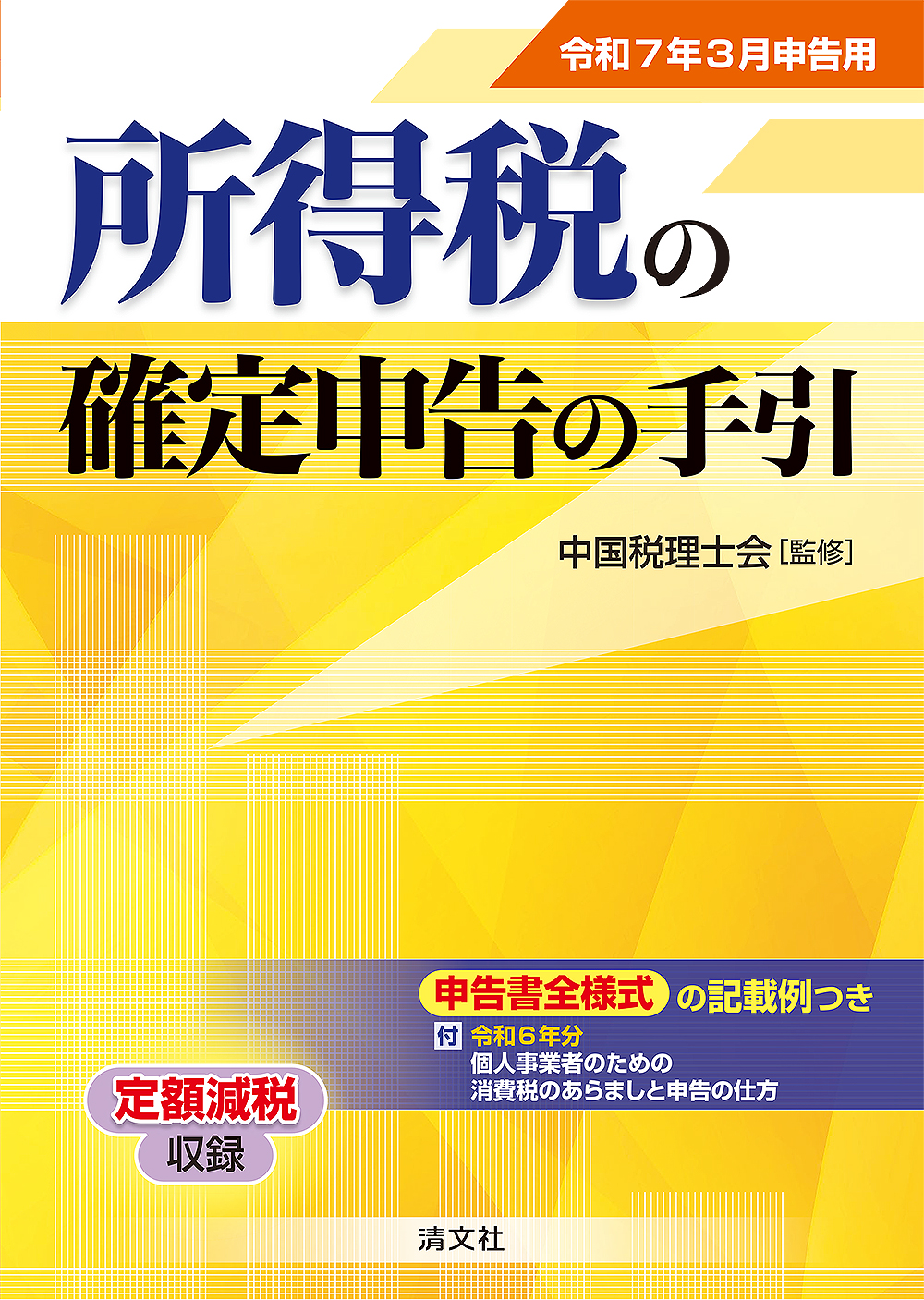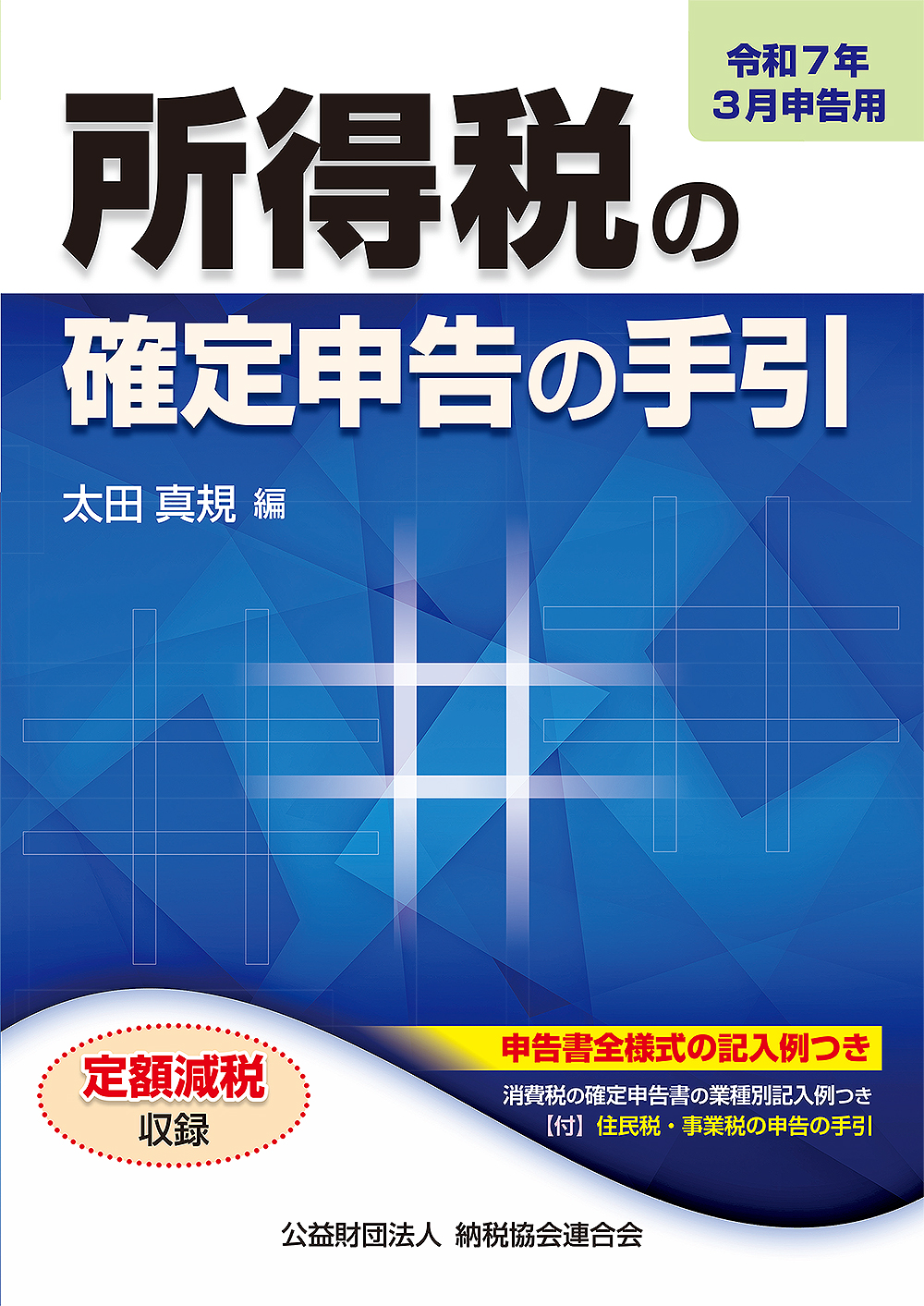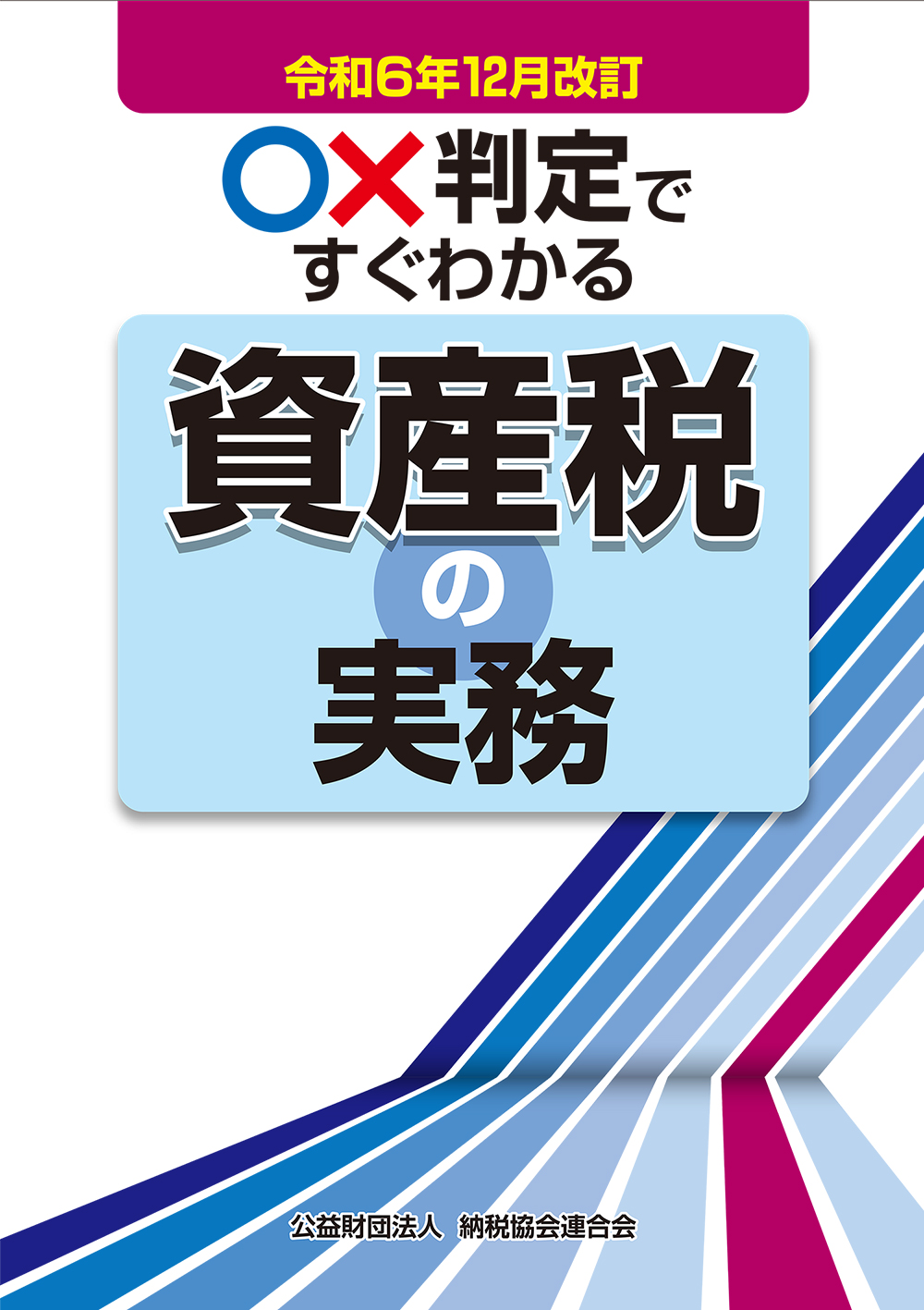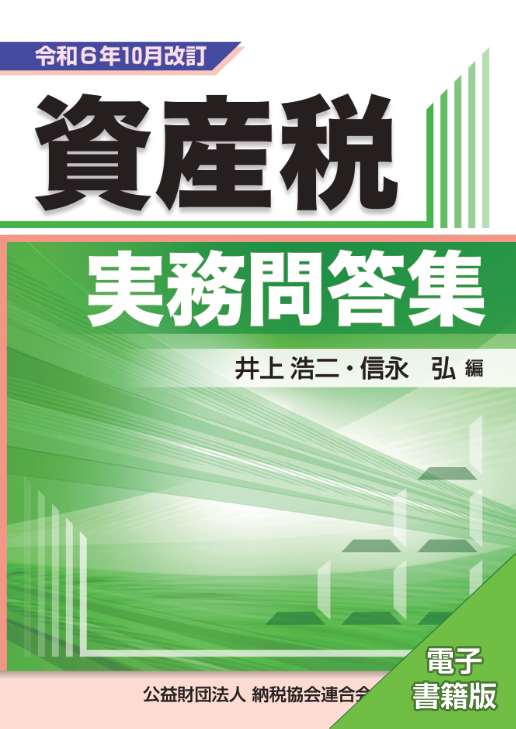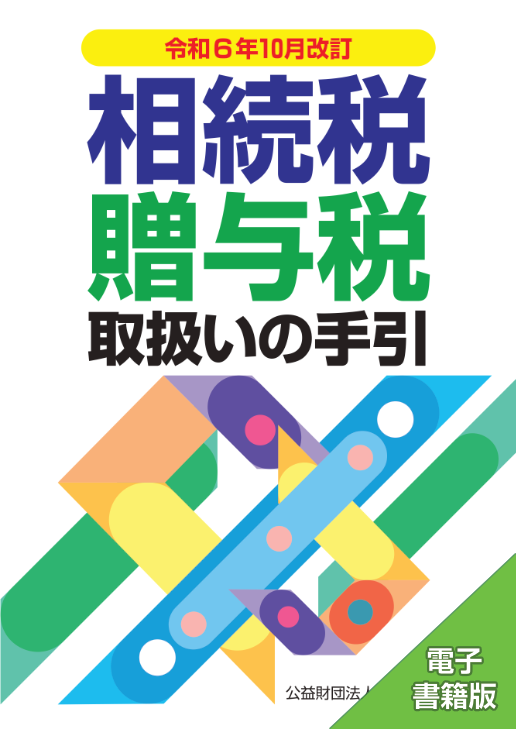相続税の実務問答
【第14回】
「法定相続分とは異なる割合による遺産分割」
税理士 梶野 研二
[問]
父が今年の5月に亡くなりました。遺産は、母が引き続き居住している家屋とその敷地(合わせて時価8,000万円)、A銀行の預金6,000万円及びB銀行の預金2,000万円です。相続人は、母、長女である私、それに弟の3人です。
遺産分割協議の結果、母が居住している家屋及びその敷地は母が、A銀行の預金6,000万円は多額の住宅ローンをかかえている弟が、そして、B銀行の預金2,000万円は私が取得することとなりました。
遺産の総額は、1億6,000万円となりますので、それぞれの法定相続分(母:2分の1、私:4分の1、弟:4分の1)どおりに分割するならば、母は8,000万円、私と弟は4,000万円ずつとなりますが、上記の遺産分割協議の結果、私は法定相続分よりも少ない財産を取得し、逆に弟は、法定相続分を超える財産を取得することになります。
法定相続分と遺産分割協議により実際に取得することとなった財産の価額との差額について、私から弟に対して贈与したものとして、贈与税が課されることになりますか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。