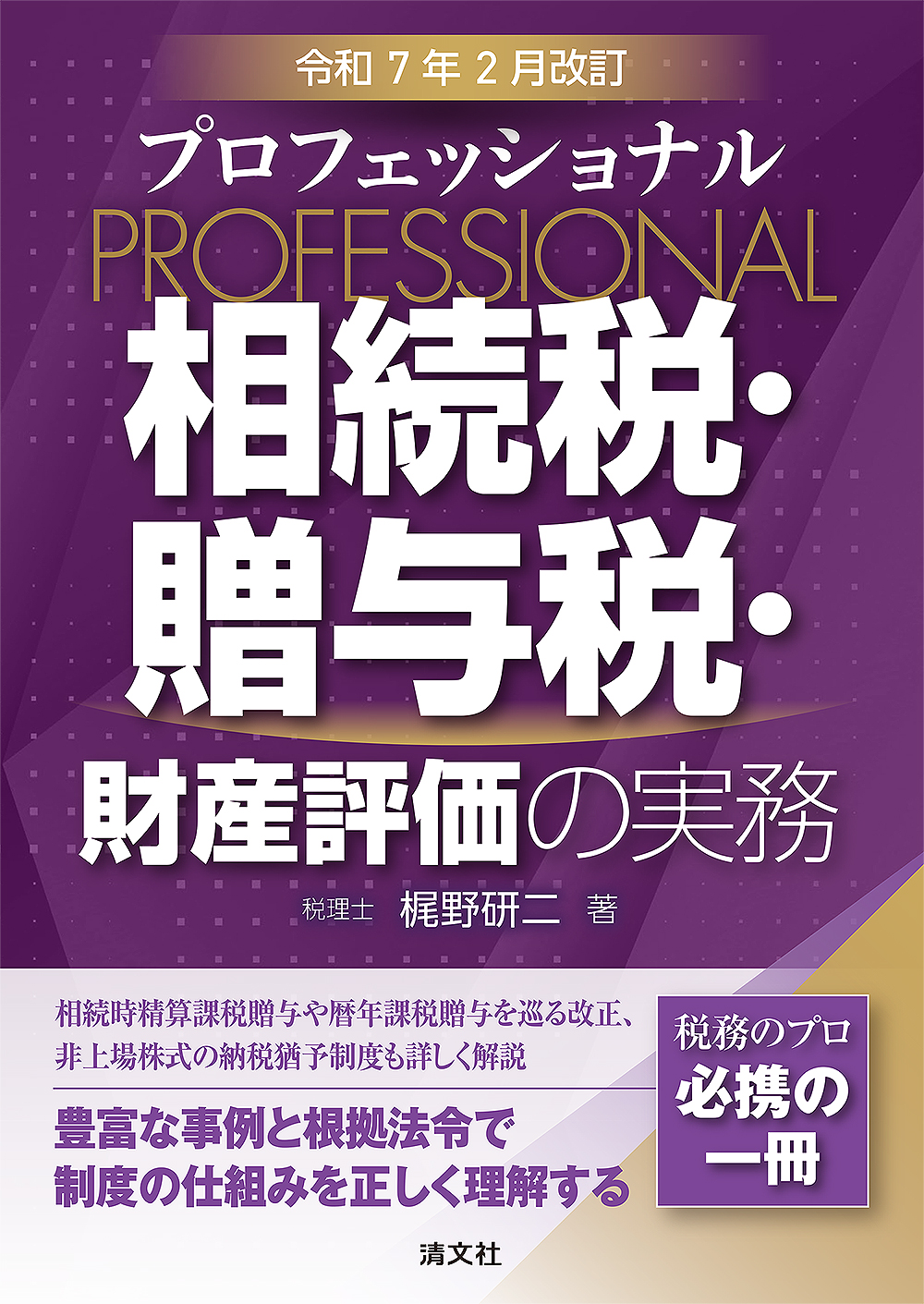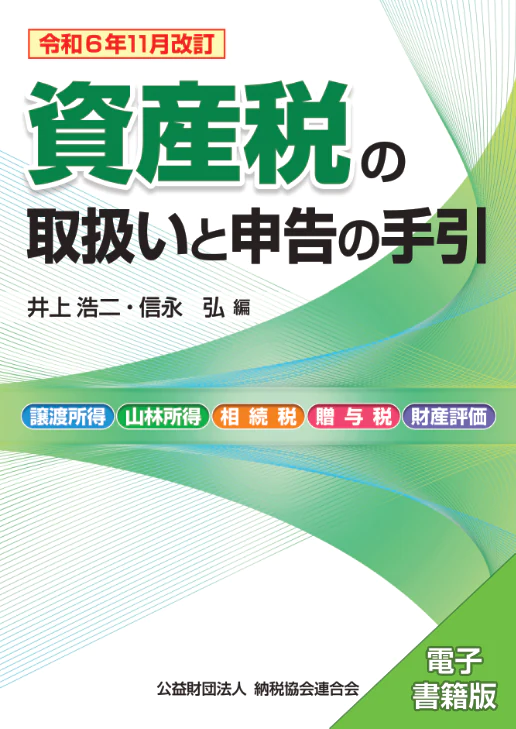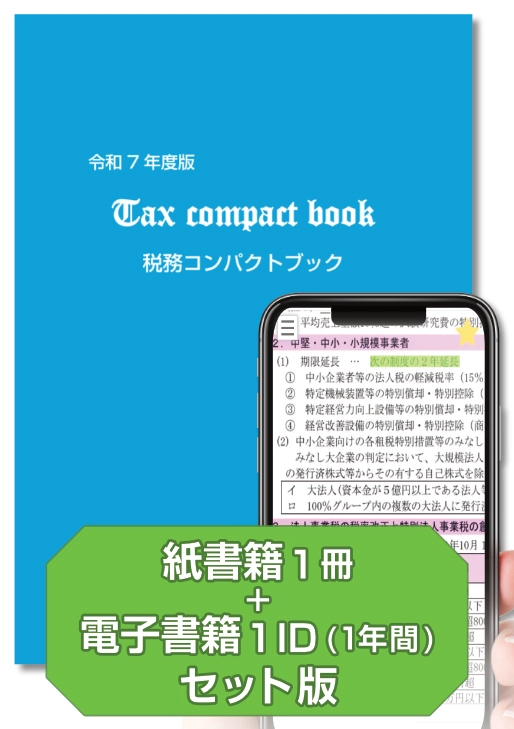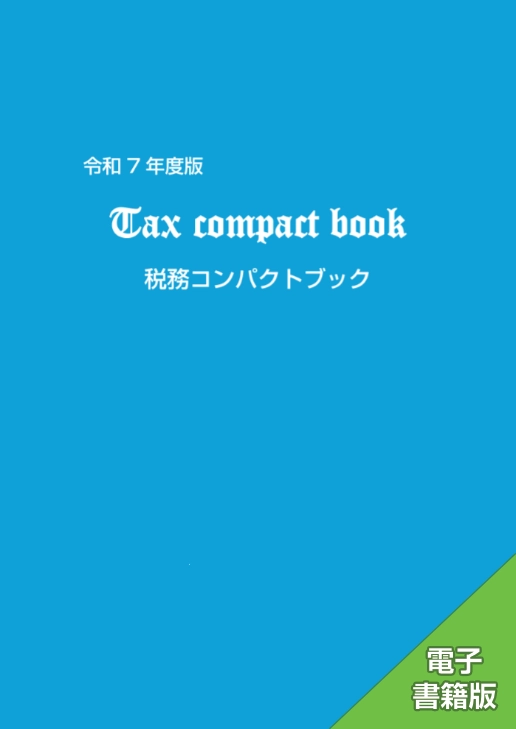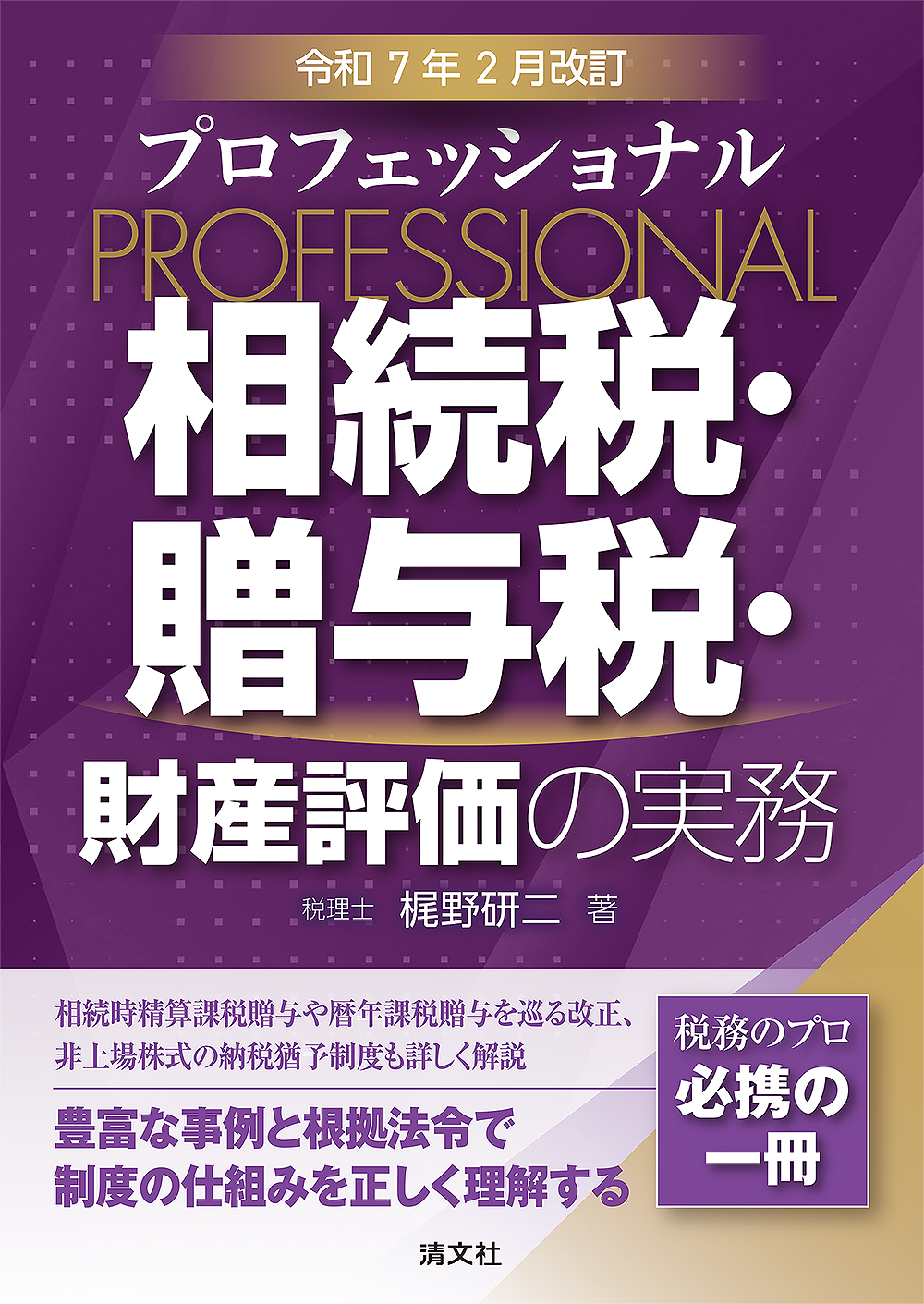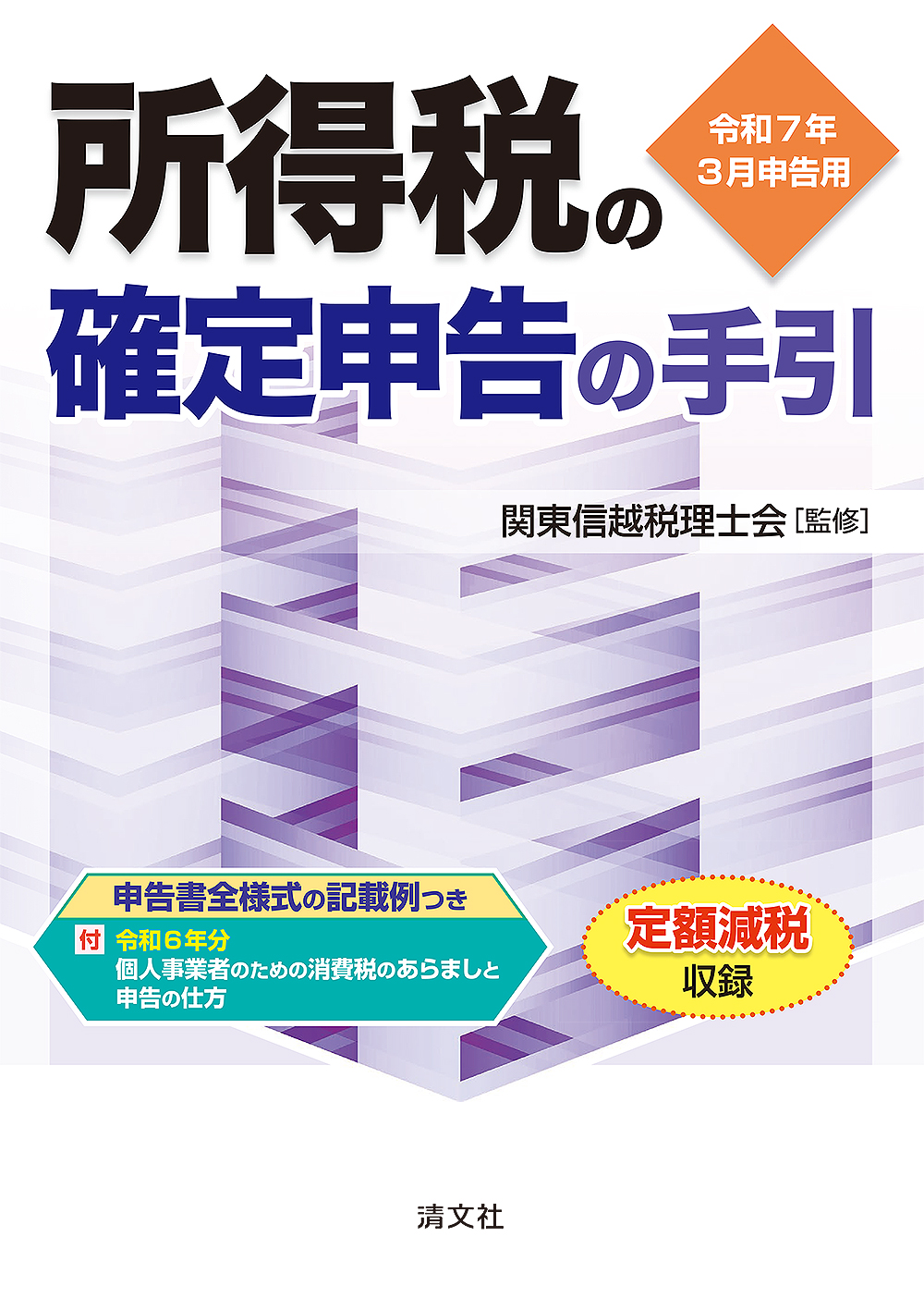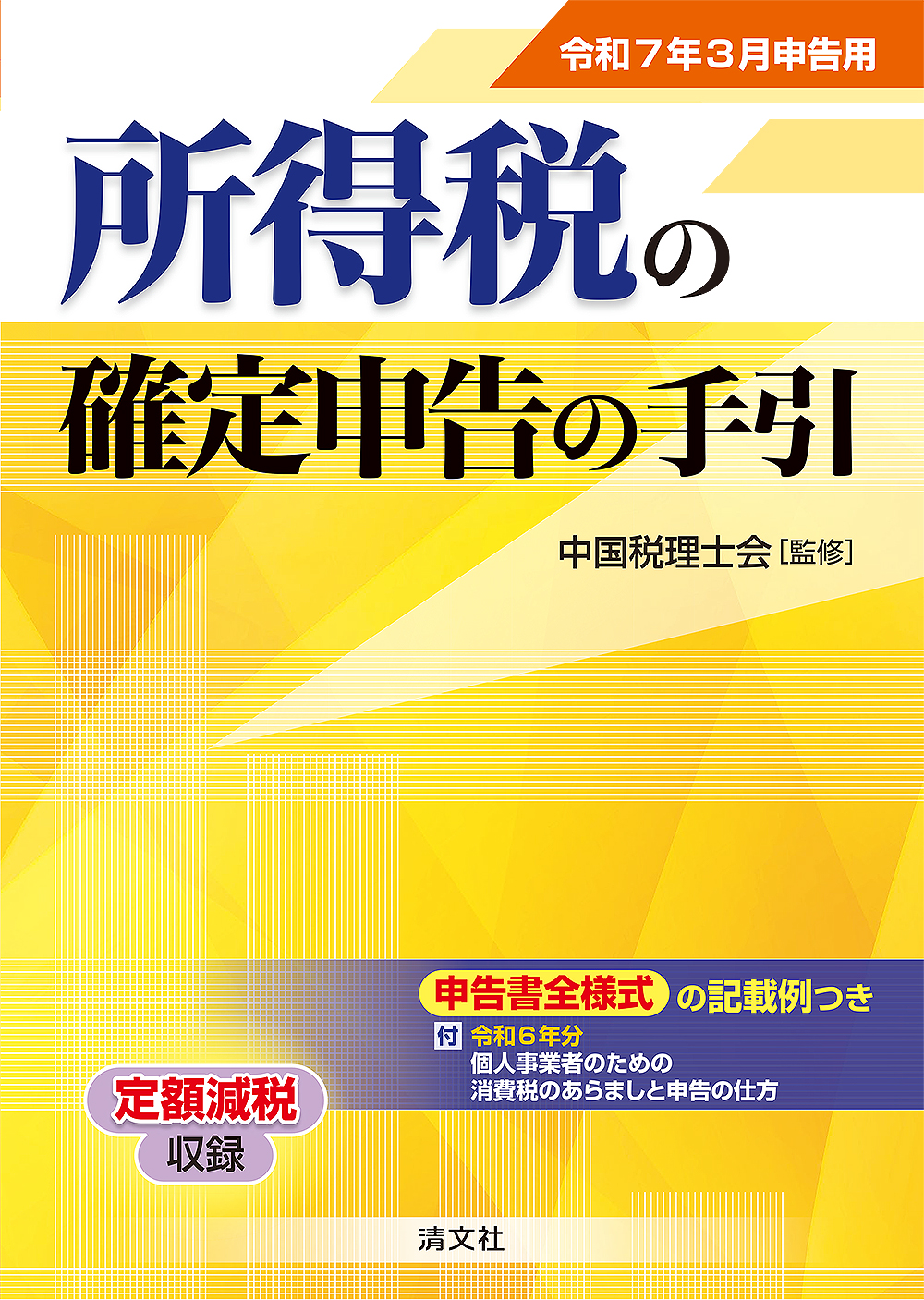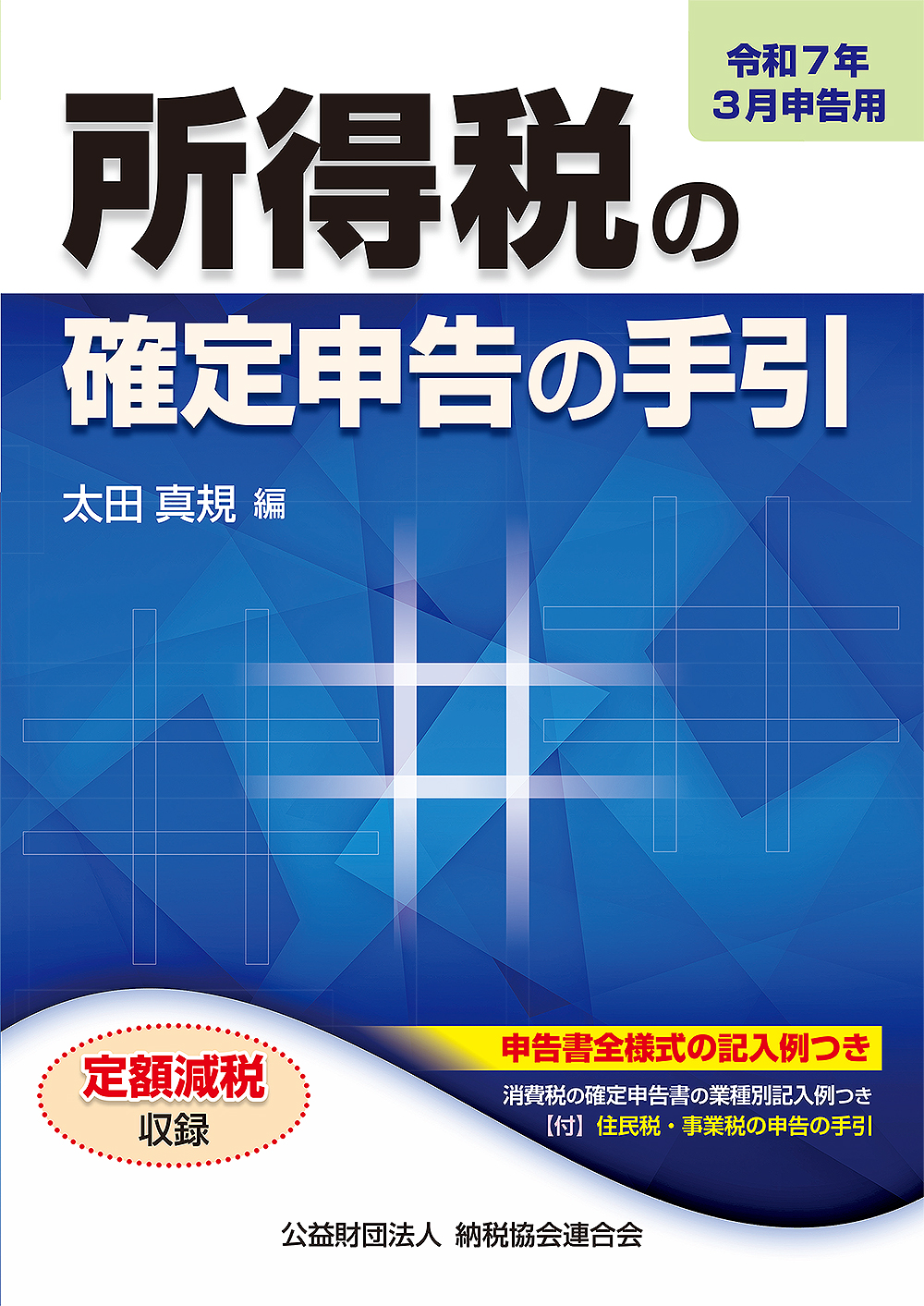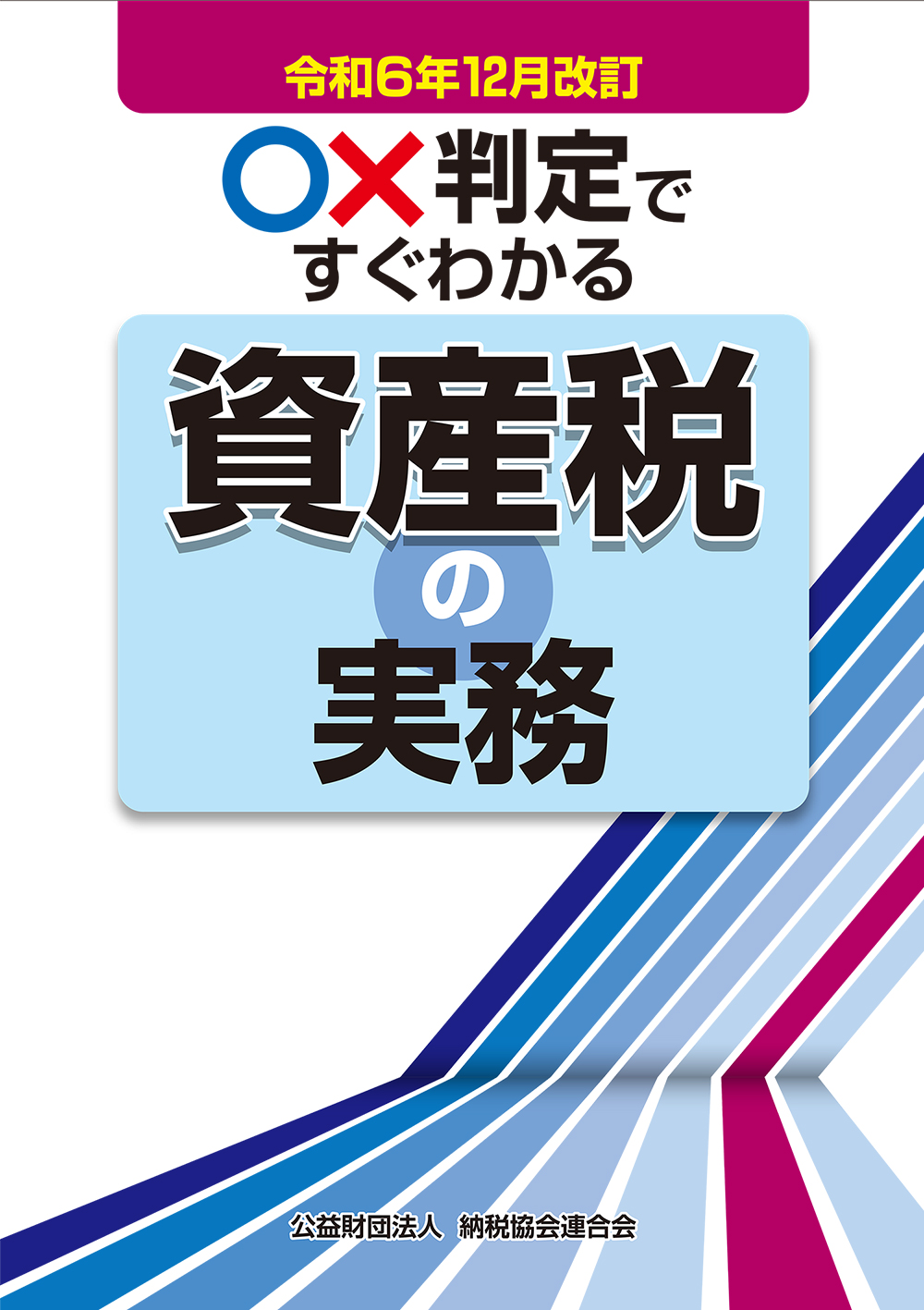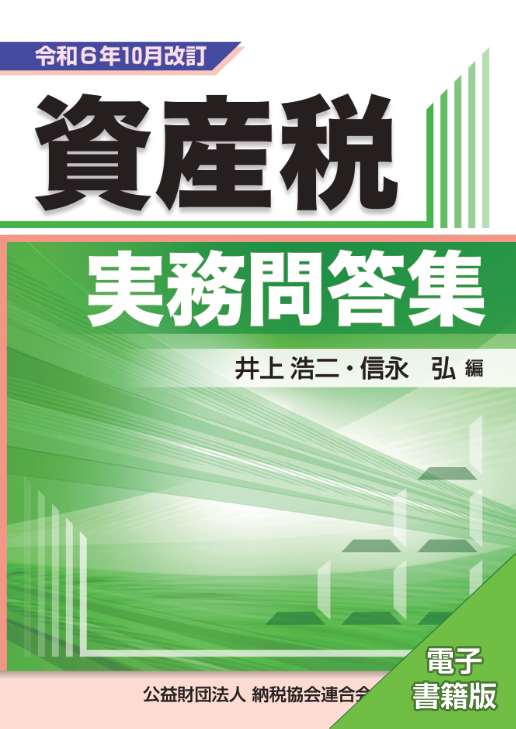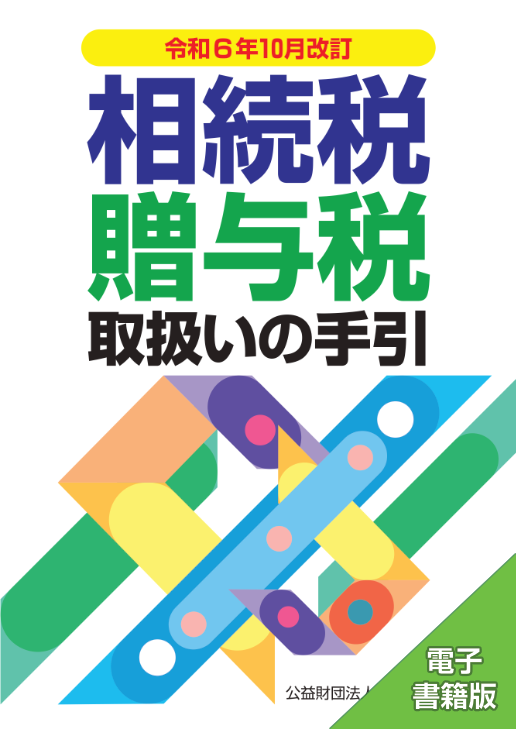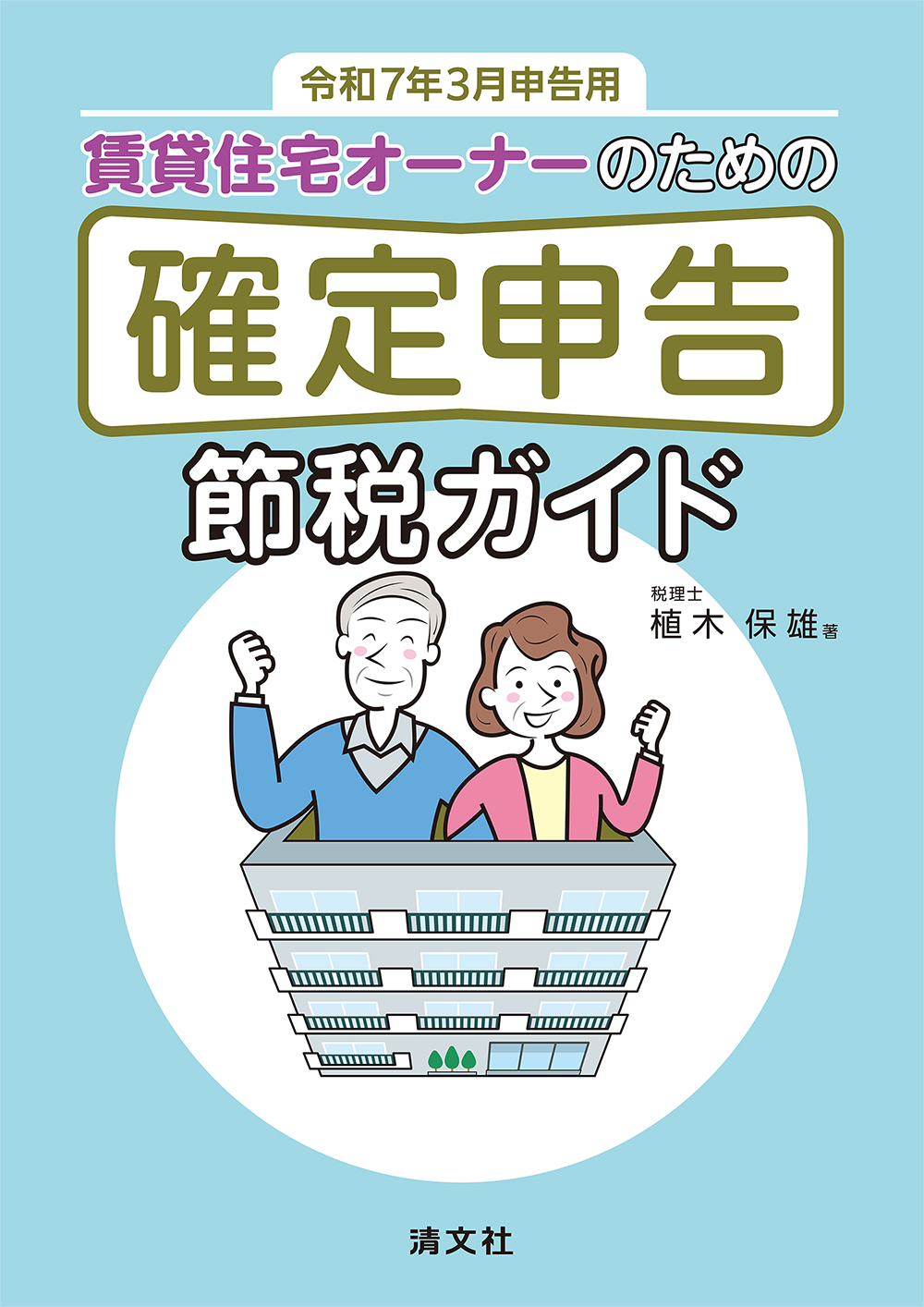相続税の実務問答
【第73回】
「相続時精算課税適用者が養親である
特定贈与者と離縁した場合」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、今から10年前に、A社の創業社長である甲と養子縁組を行いました。その後、私は、A社の専務取締役としてA社の経営に従事し、甲からも私の仕事ぶりを評価してもらい、後継者候補とまでいわれるようになりました。
A社の発行済み株式は20,000株で、そのうちの18,000株は甲が、残りの2,000株を甲の弟乙が保有していましたが、3年前に、私は甲からA社の株式1,000株の贈与を受けました。私が甲から贈与を受けたA社の株式1,000株の評価額は3,000万円になりますが、相続時精算課税を選択しましたので、100万円の贈与税の負担で済みました。
ところが、ある出来事が原因で甲との養子縁組を解消することとなりました。
相続時精算課税制度を適用した贈与については、その贈与者に相続が開始した時には、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に含めて相続税を計算し、算出された相続税を納付しなければならないと聞きました。しかしながら、私の場合には、贈与者である甲との間の養子縁組を解消し、甲との親族関係はなくなりますので、相続時精算課税の選択を撤回したいと思いますが、いかがでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。