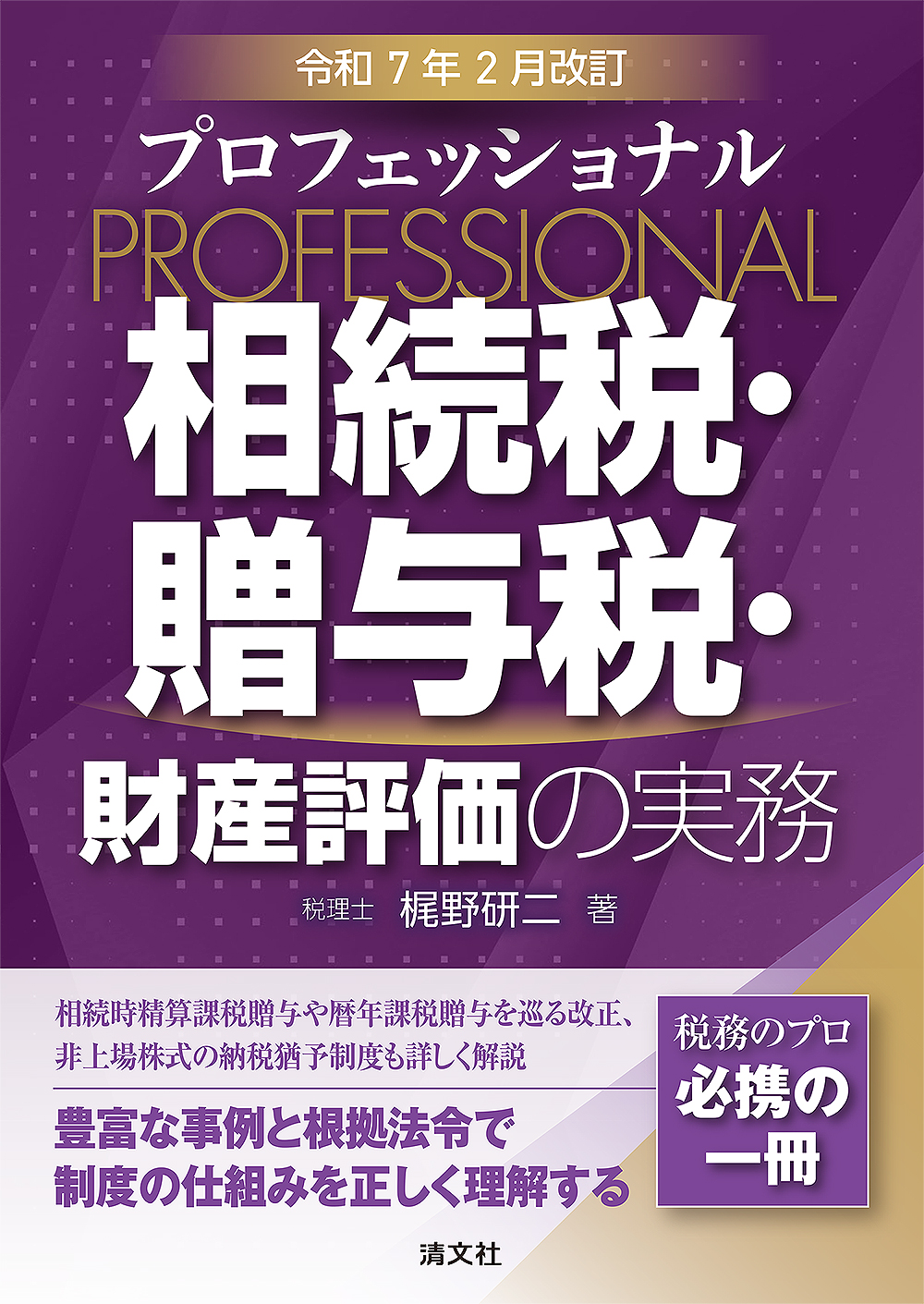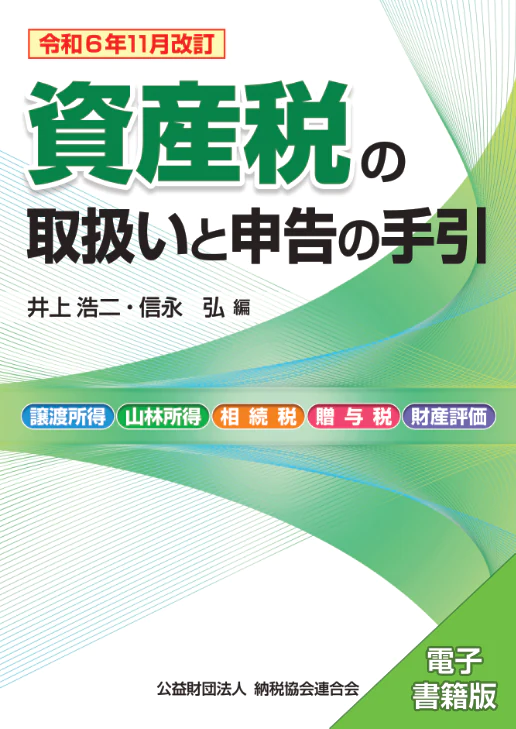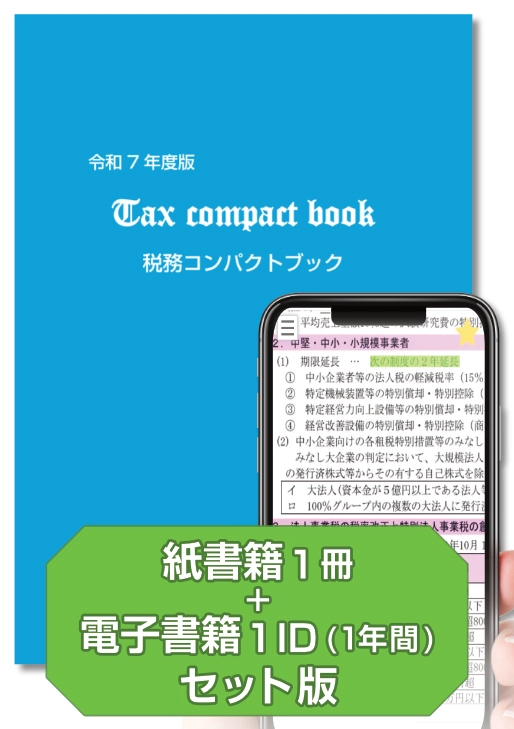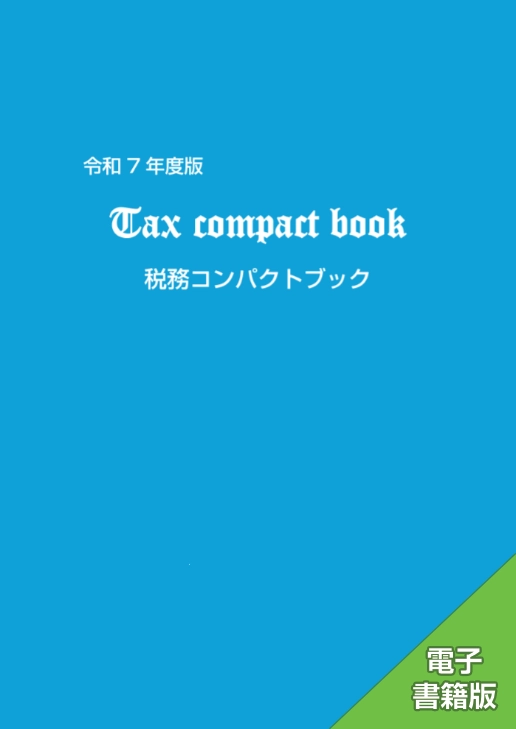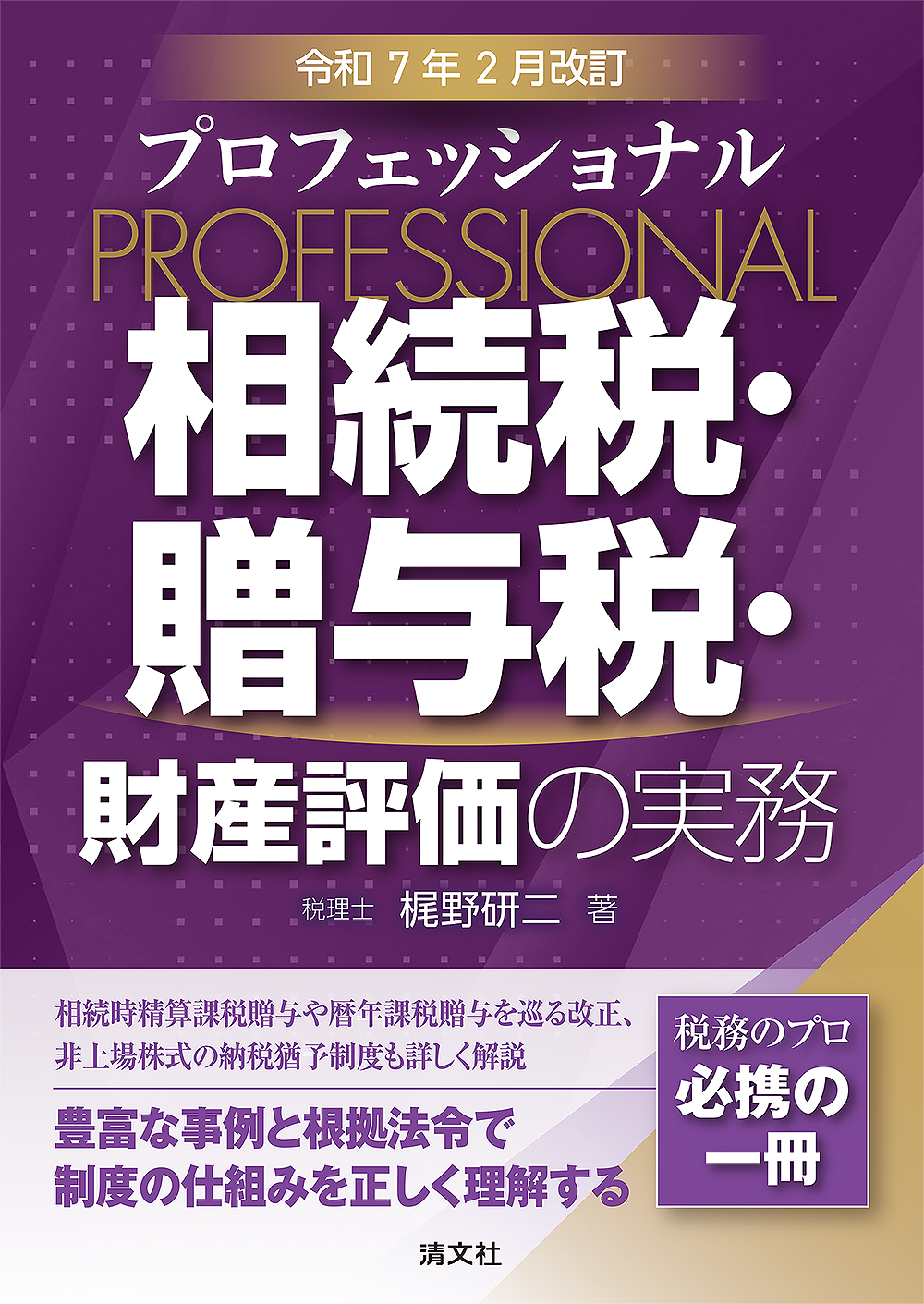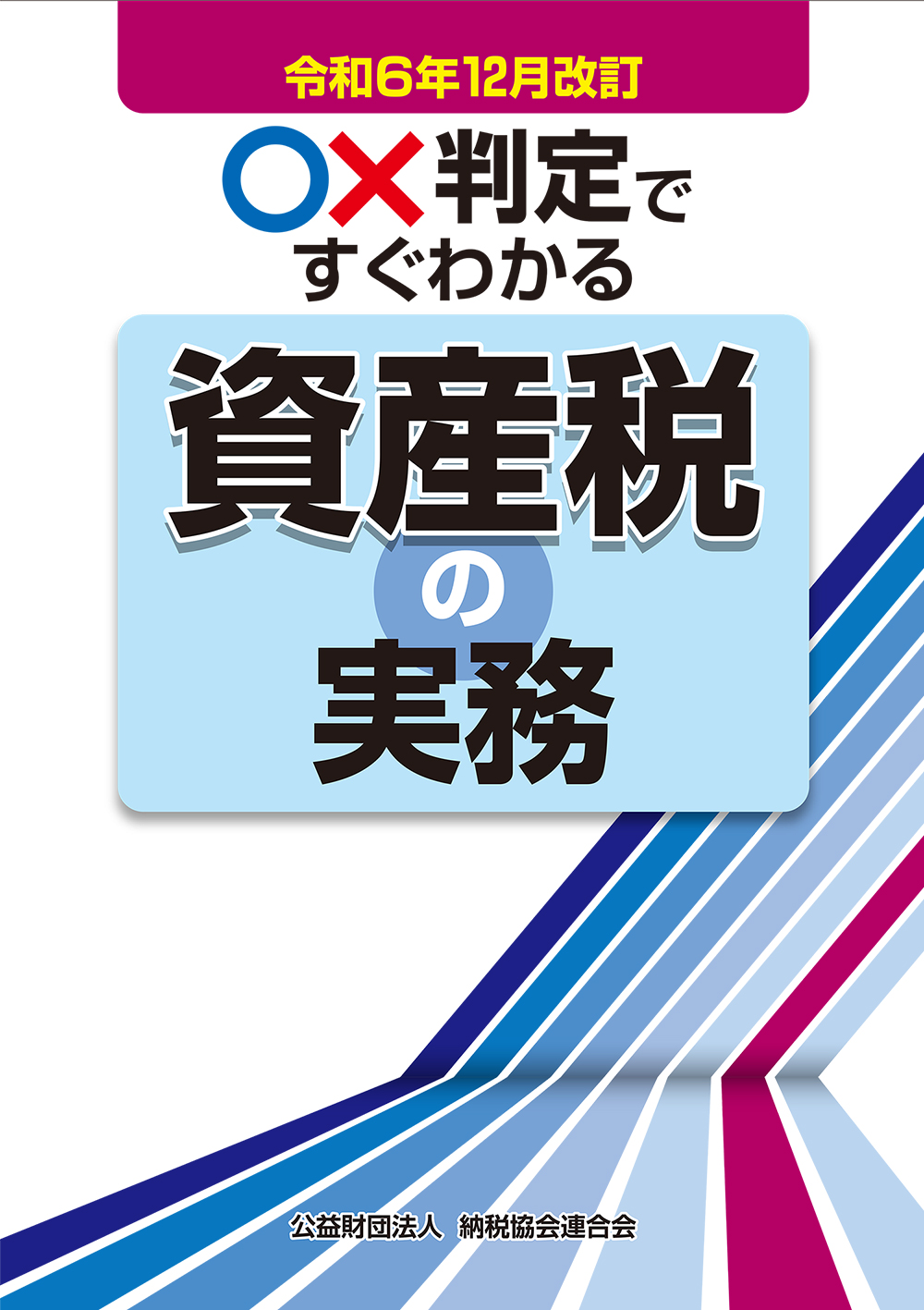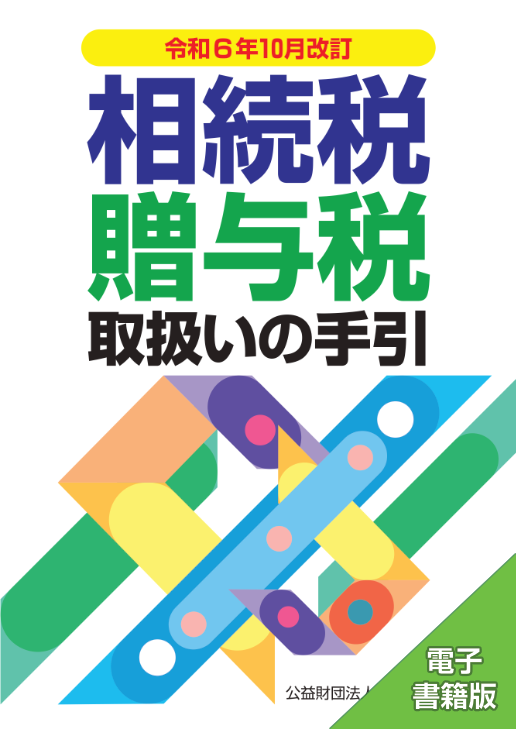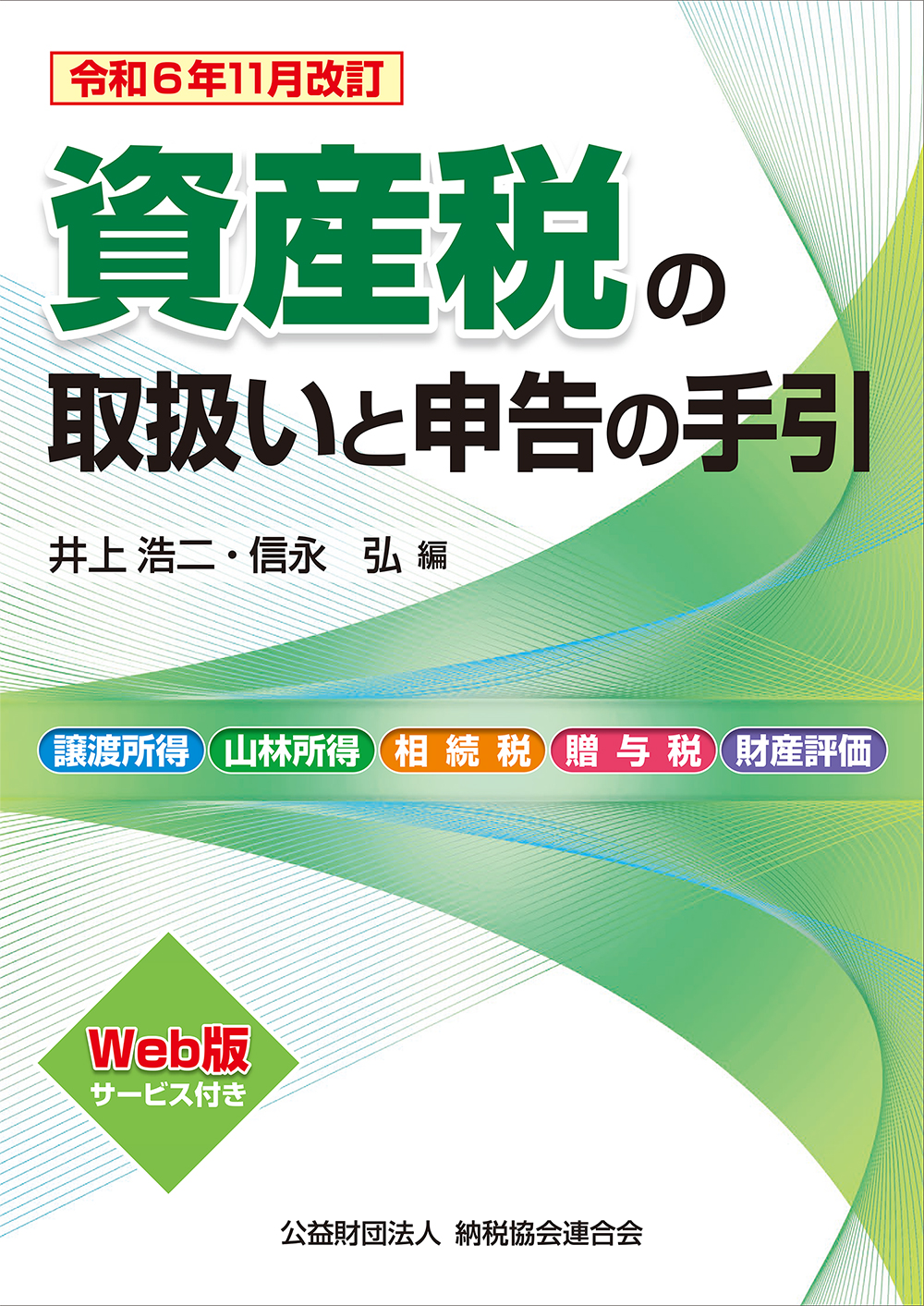相続税の実務問答
【第2回】
「遺産の内容が分からない場合の相続税の申告」
税理士 梶野 研二
[問]
母が半年前に亡くなりました。相続人は、姉と私の2人だけです。母と同居して、長年、母の身の回りの世話をしてきた姉が母の財産のすべてを管理していましたが、これまで私は姉と仲が悪かったこともあり、遺産の内容を教えてもらうことができませんし、遺産分割の協議をすることもできません。
母が居住していた建物とその敷地は母のものであり、この建物と土地だけでも5,000万円を超える価値があると思われますので、相続税の申告が必要だと思われますが、その他の財産がどのくらいあるのか分かりません。
このような場合、どのようにして申告をしたらよいのでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。