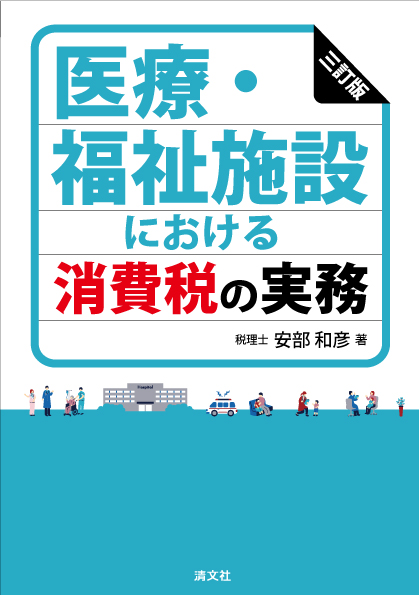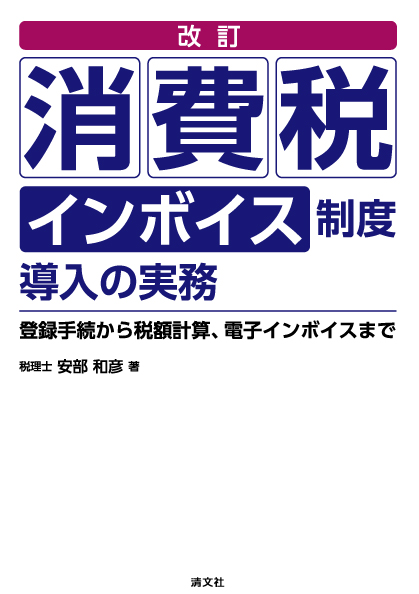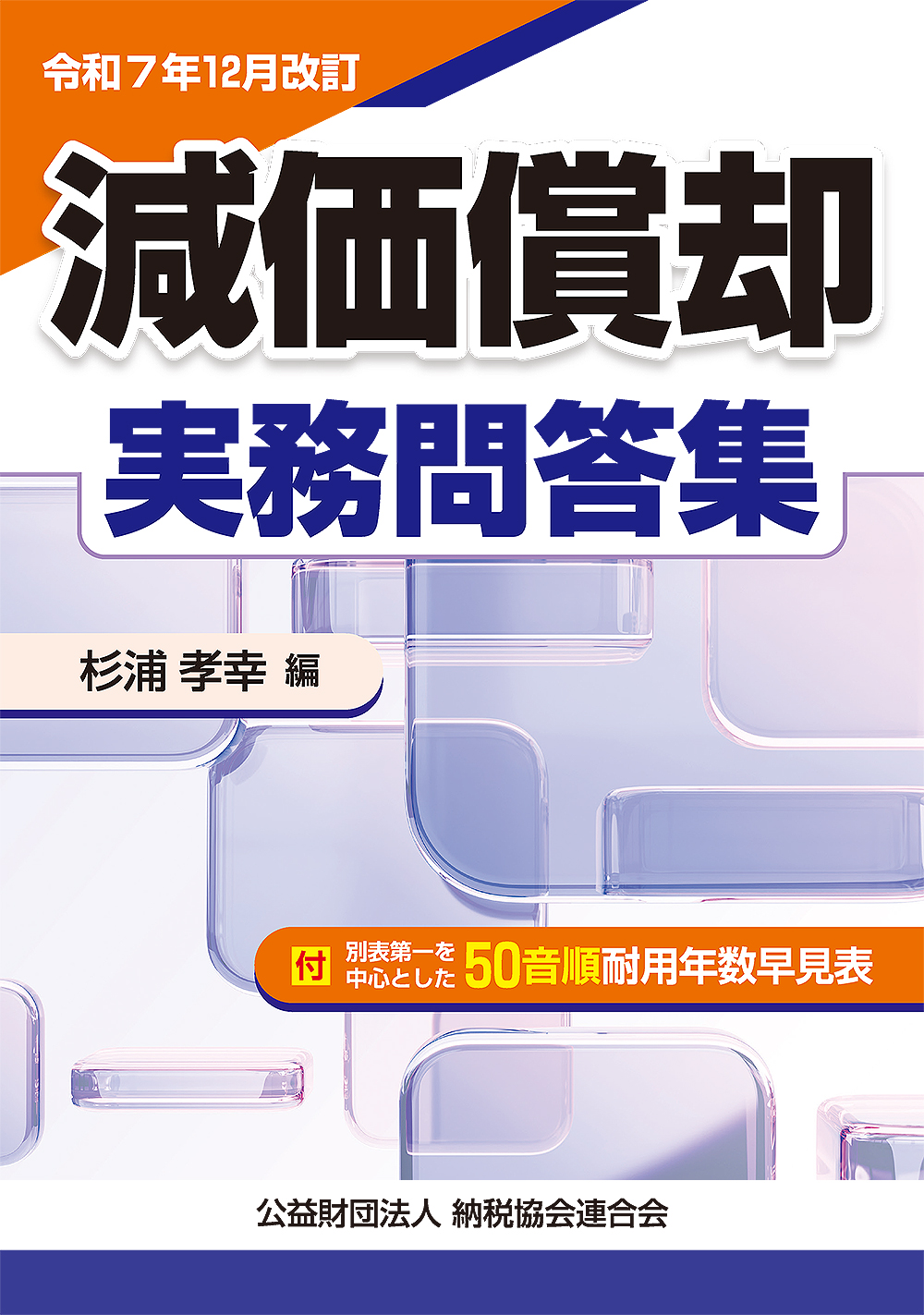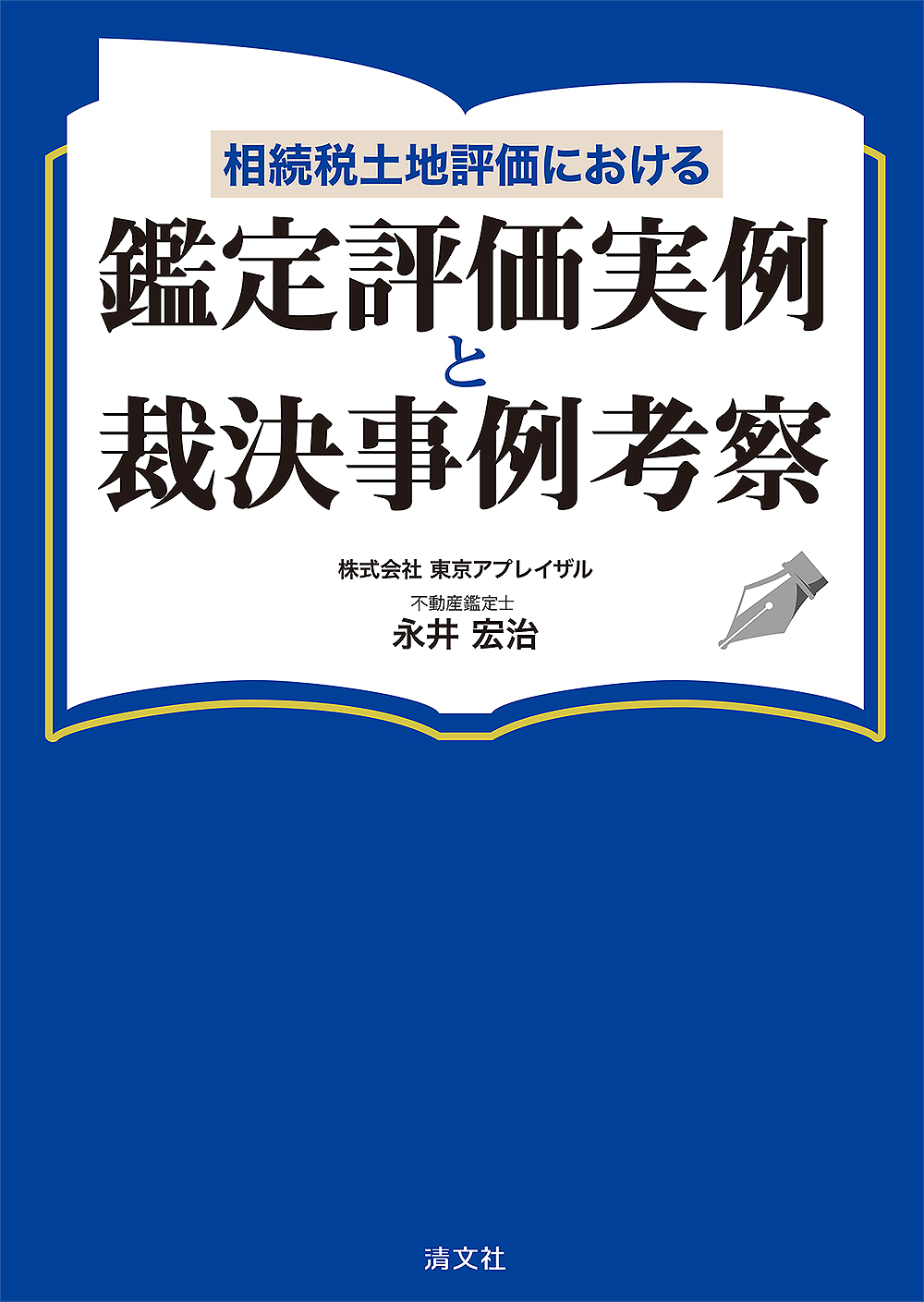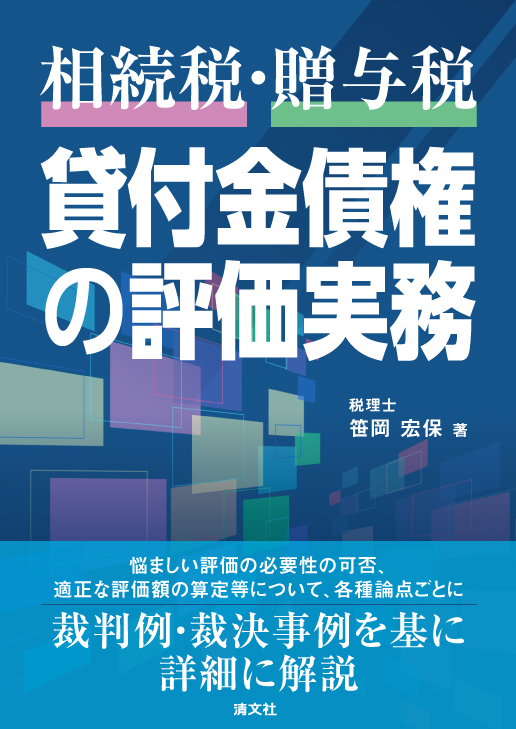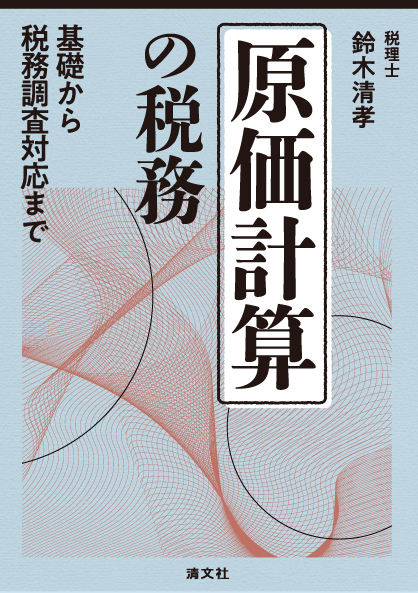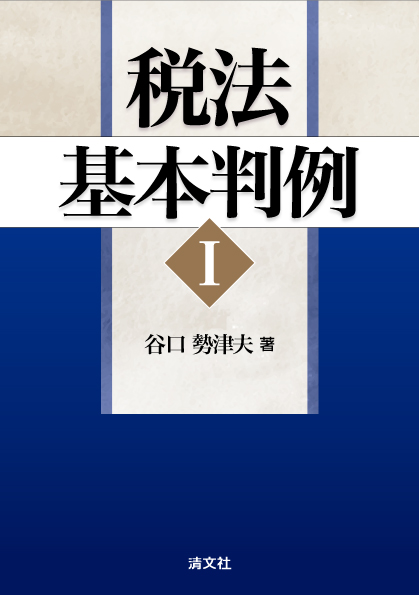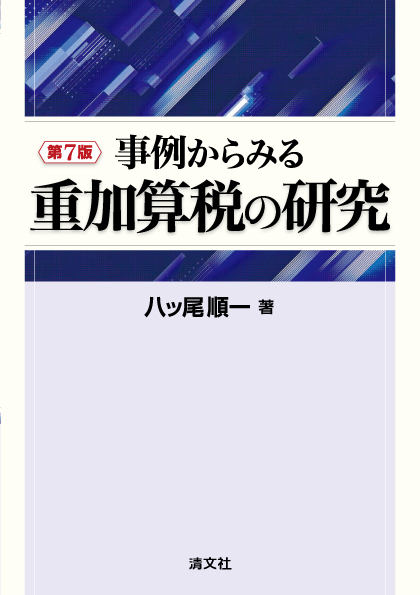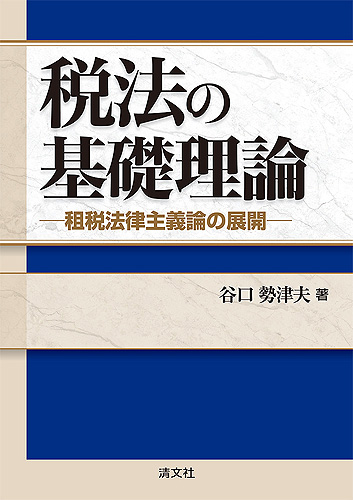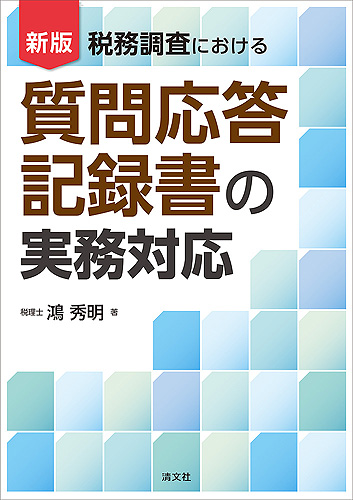法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【事例66】
「中古資産を事業の用に供した後においてその耐用年数を変更することの可否」
拓殖大学商学部教授
税理士 安部 和彦
【Q】
私は、中部地方のある県庁所在地に本社を構え不動産賃貸業を営む株式会社X(資本金3,000万円で3月決算法人)において、経理部長を務めております。
よく知られている通り、わが国の経済は1980年代後半から1990年代前半にかけてのいわゆる「バブル経済」でピークを迎え、株式市場も不動産市場も大いに湧き立ったものですが、バブル崩壊後は長期不況に突入し、現在に至っております。それでも株式市場はバブル崩壊後何度か上昇機運に乗る時期がありましたが、不動産市場は全くもって鳴かず飛ばずで、ジリジリと下がり続ける厳しい時期が続きました。ようやくアベノミクスの効果が出て、株式市場のみならず不動産市場も上昇に転じ、地域的なバラつきはあるものの、都市部やインバウンド人気のリゾート地は不動産取引が活発となり、バブル期を上回る価格をつけるところも見られるようになってきました。
当社が保有する不動産は名古屋市内を中心に中部地方の県庁所在地や政令指定都市に立地しており、ここ数年は地価の上昇を背景に賃貸料についての値上げ交渉が可能となっているため、借入金利息の負担が依然重いものの、業績は持ち直しております。そんな中、先月から税務署の調査を受けており、当社が保有する賃貸物件(建物)の減価償却費について、議論のすれ違いが生じております。すなわち、当社が保有する建物の減価償却については、耐用年数を39年として定額法で計算しておりましたが、そのうち数棟は既存の建物を取得して賃貸物件として事業の用に供したことに気付いたことから、それ以後の事業年度については中古資産の耐用年数(簡便法)の適用により減価償却を行いました。
しかし、税務署の調査官は、中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度において行うことができるものであり、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできないと言い張っております。調査官の当該主張は不当であると考えるのですが、税法上はどのように考えるのでしょうか、教えてください。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。