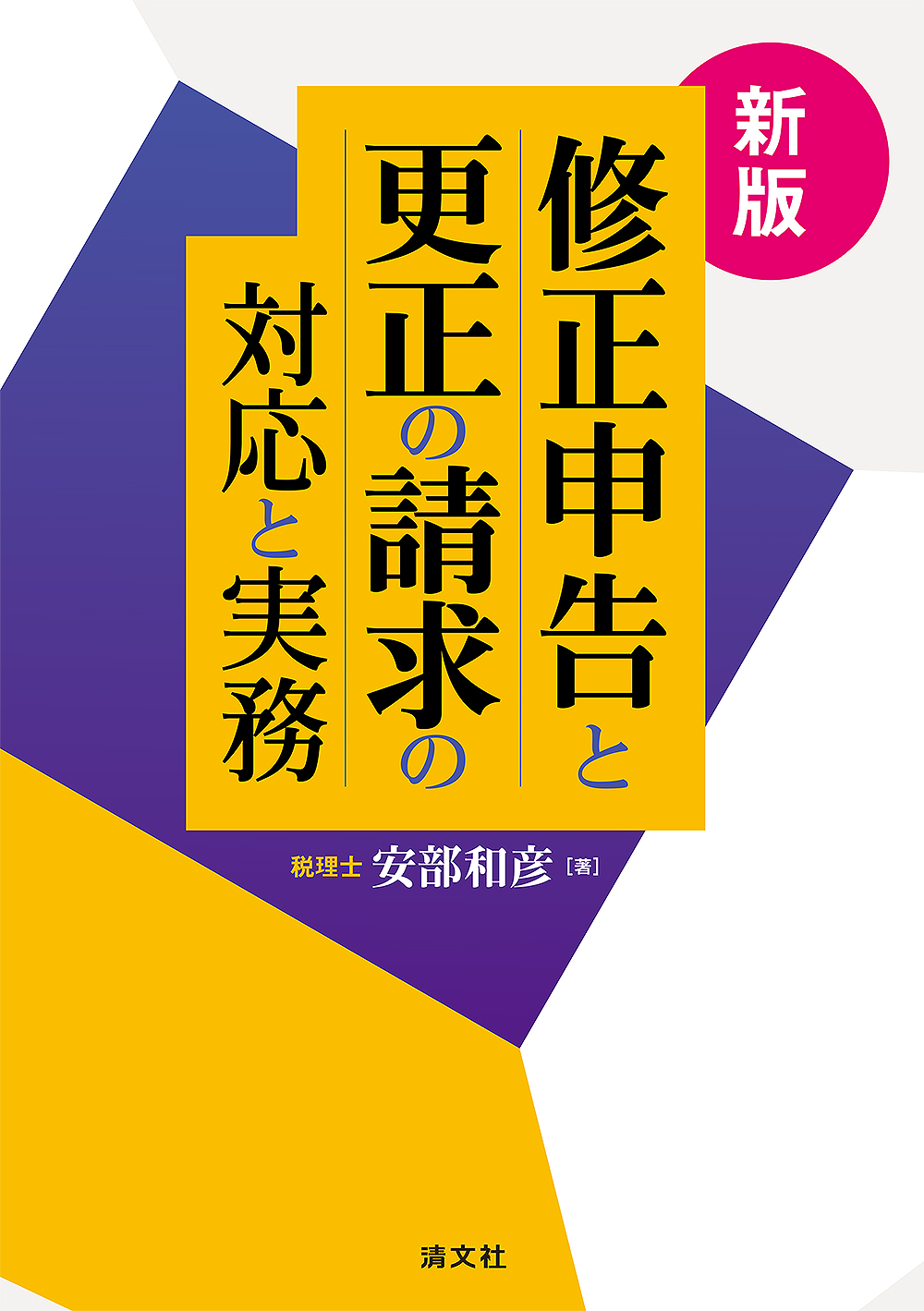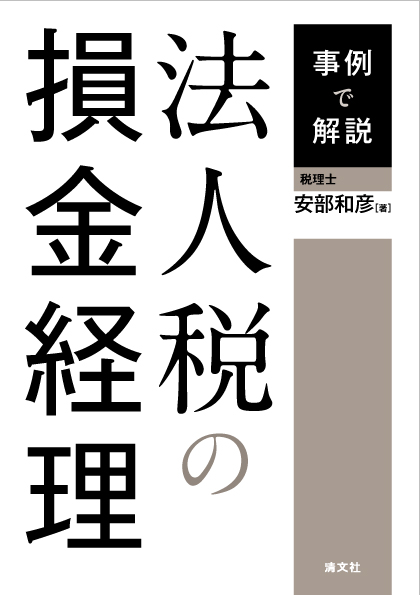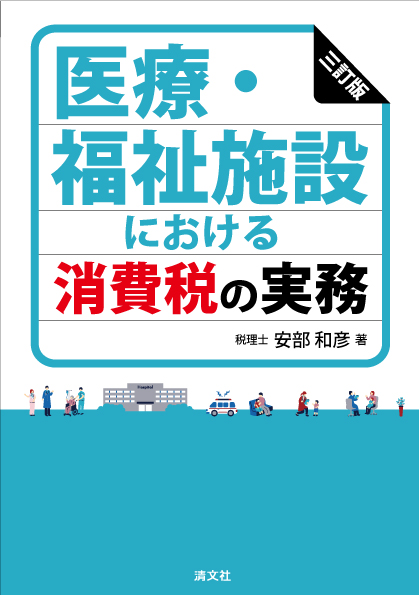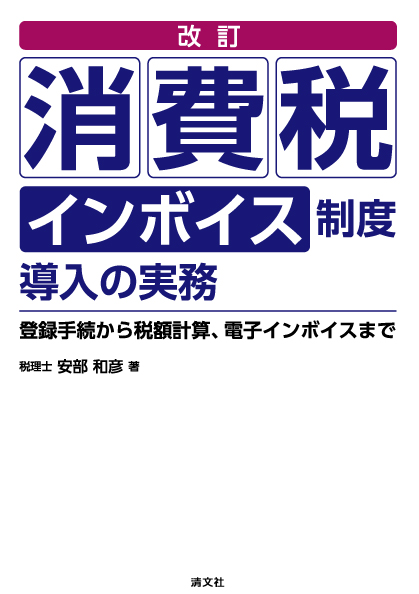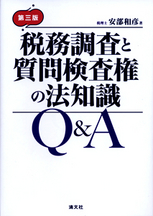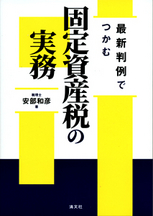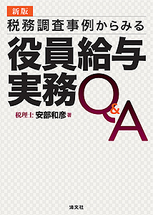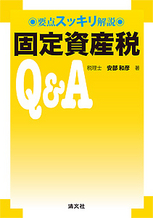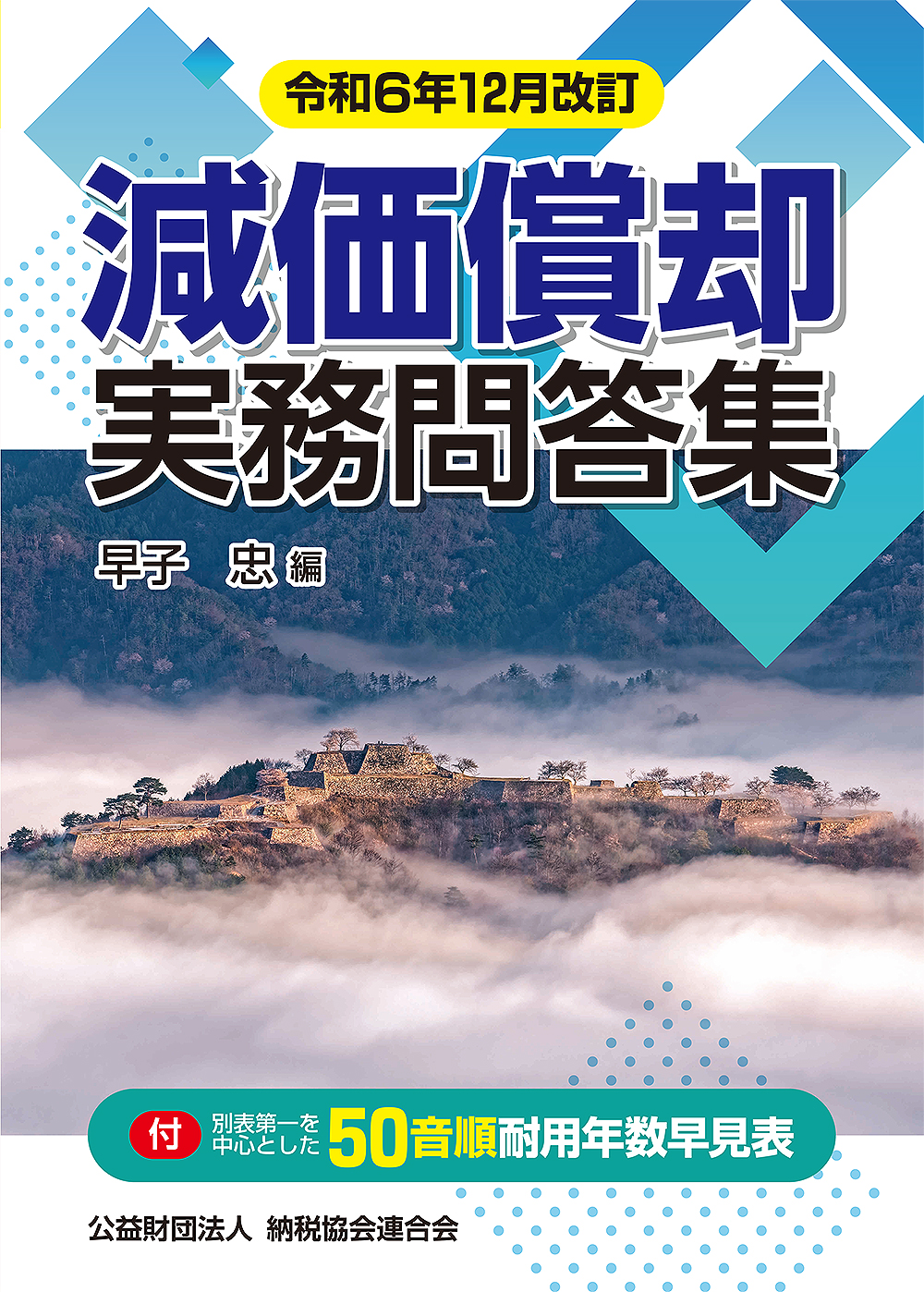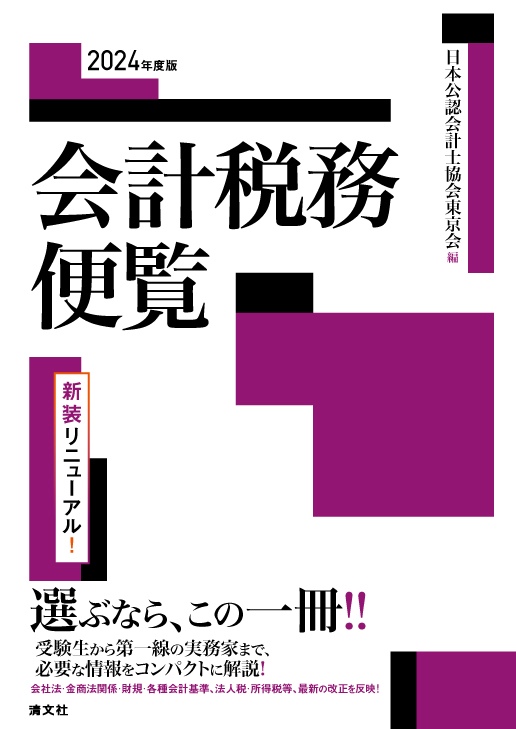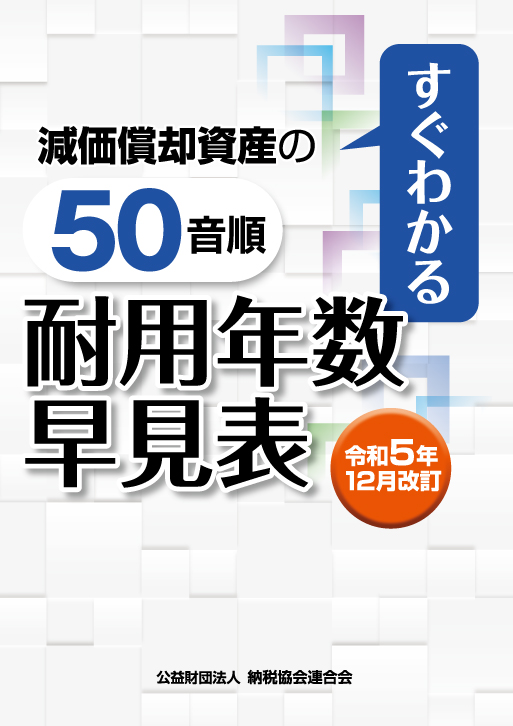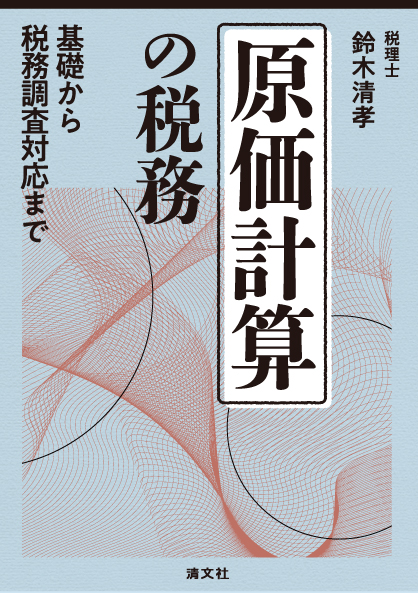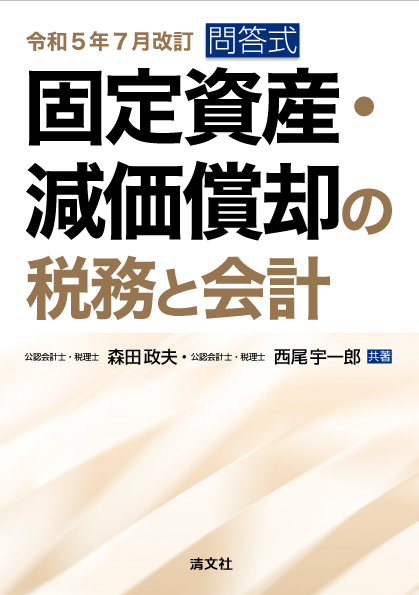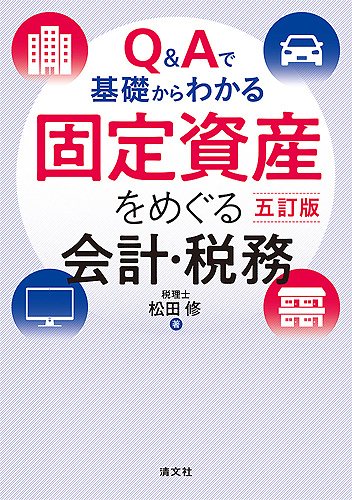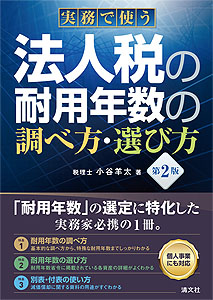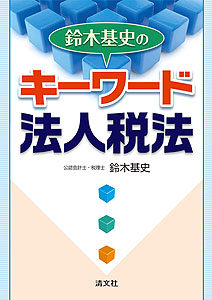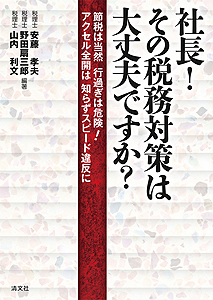法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【事例20】
「売上原価と棚卸資産の評価方法」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
【Q】
私は、北関東において中古車販売業を営む株式会社Aで経理を担当しております。近年、わが国においては若年層の自動車離れが顕著であり、そもそも運転免許すら取得しない若者も都市部においては珍しくないと聞きます。幸いなことに、北関東は東京都内と比較すると公共交通機関が未発達で、自動車なしでは事実上生活が成り立たないため、一家に一台どころか大人は一人一台というのが標準的であり、自動車離れの影響は今のところ軽微といえます。しかし、そうはいってもやはり新車は高額であるため、当地においては私どものような中古車販売業の役割は大きいと言えます。
中古車販売業において重要なのは、棚卸資産である中古車の価格を適正に見積もることであると考えられます。そのため、弊社においては、社員は原則として全員、一般財団法人日本自動車査定協会(以下「査定協会」といいます)が実施する試験に合格することで得られる中古自動車査定士の資格を取るように奨励し、実際に大部分の社員が取得しております。また、弊社における自動車の買取りや譲渡時の価格も、査定協会が定める中古自動車査定基準に則って決定しております。それにより、お客様に対して適正な中古車価額をお示しできるだけでなく、財務諸表上、常に棚卸資産の公正な価格を表示することができるものと考えております。
このような考え方に基づき、弊社においては法人税の申告についても、棚卸資産の期末評価は中古自動車査定基準に則った手法、すなわち加減点基準により行っております。ところが、先日受けた税務調査で所轄税務署の調査官は、弊社は税務署長宛てに棚卸資産の評価方法に関して特に届け出ていないことから、法人税法施行令第31条第1項により、最終仕入原価法により評価すべきこととなるため、期末棚卸資産の評価額が過少(売上原価が過大)であるとして、修正申告の勧奨を受けました。
弊社は「適正な中古車価格とは何か」を長年追求してきておりますが、その結論として、査定協会が定める中古自動車査定基準に則って査定した金額こそがそれにあたるとしてきたものであり、当該価格は恣意的に決定されたものではなく、極めて公正な価格であると自信をもって言えます。したがって、それに反するような課税庁の判断にはおおよそ根拠がないと考えるところでありますが、弊社の考え方は税法に照らして誤りといえるのでしょうか、教えてください。
なお、査定協会が定める中古自動車査定基準に則った査定額は、棚卸資産の評価方法を定めた法人税法施行令第28条第1項のいずれにも該当しないこととなります。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。