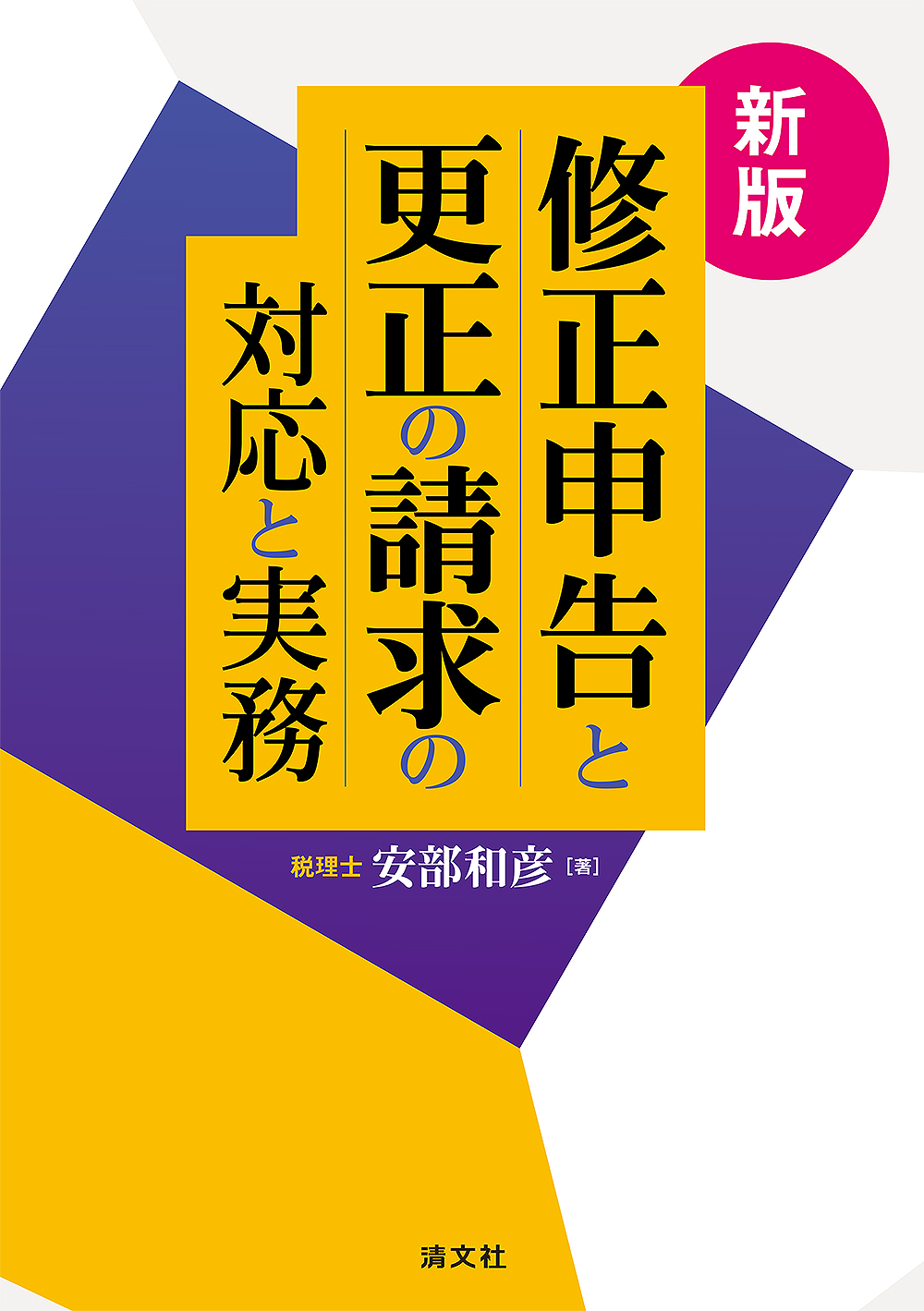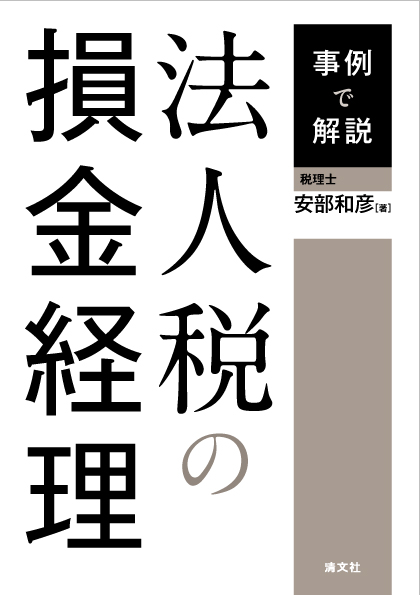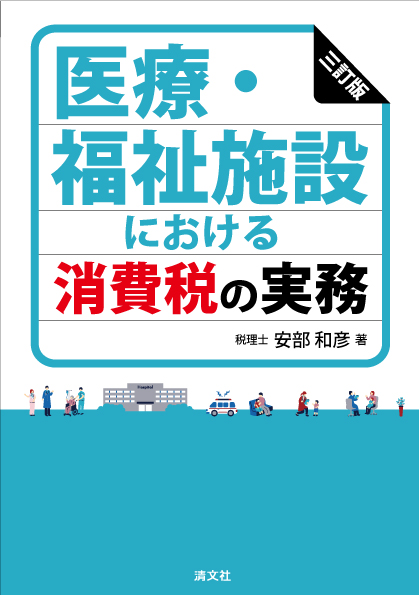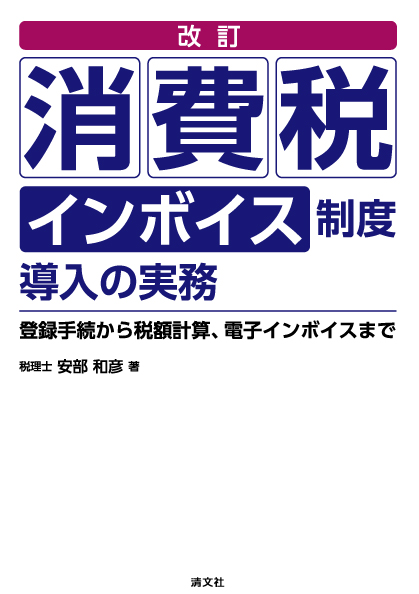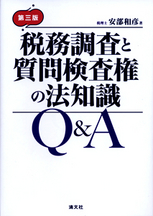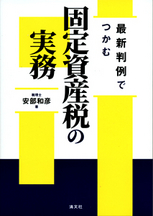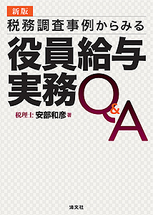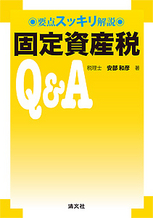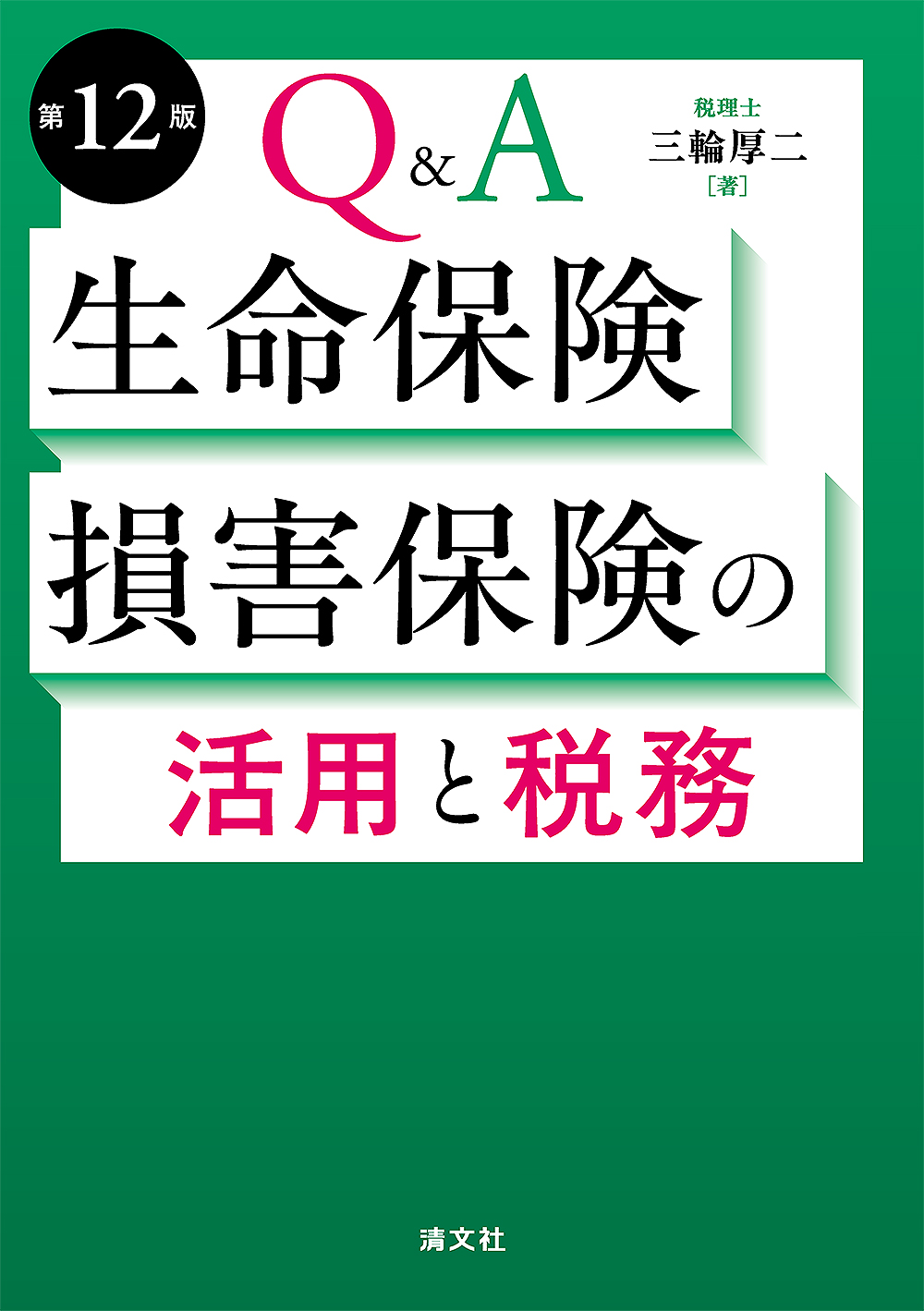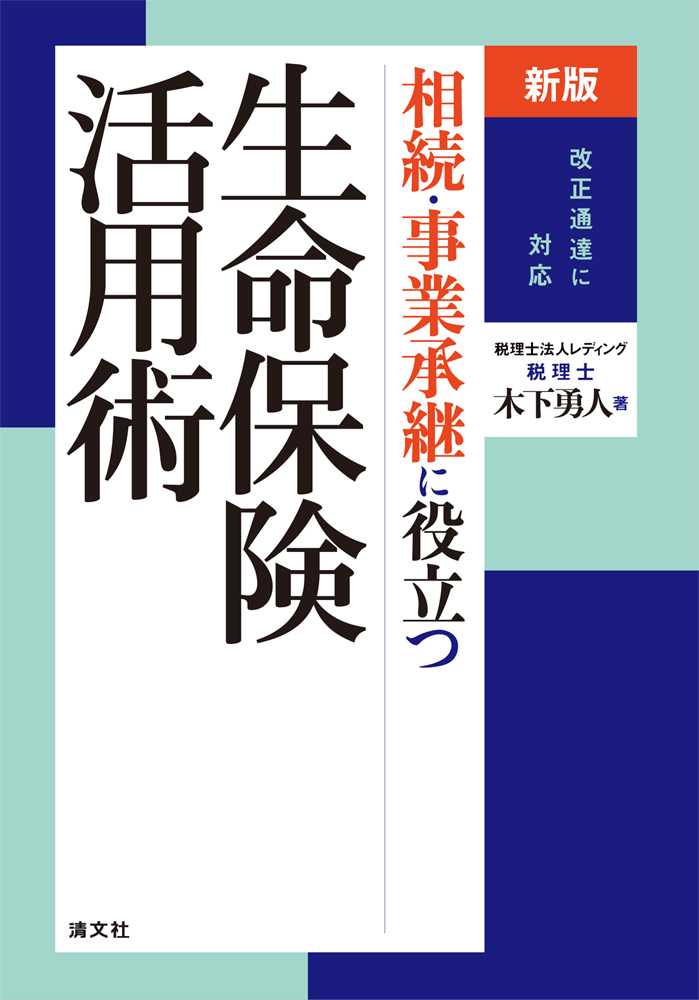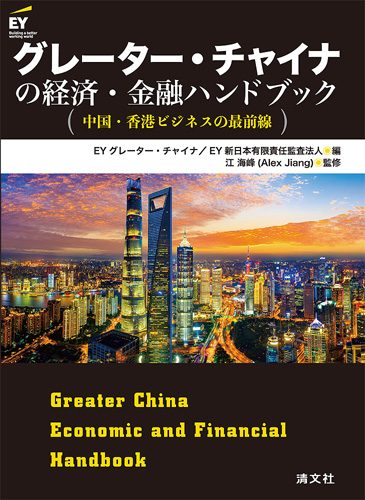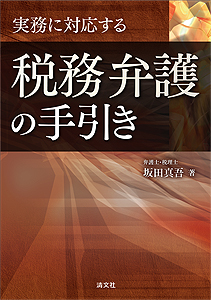法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【事例74】
「海外の保険業を営む子会社へ支払う地震保険再保険料の損金性」
拓殖大学商学部教授
税理士 安部 和彦
【Q】
私は、東京都内に本社を置き損害保険業を営む東証プライム市場に上場する株式会社で経理部長を務めております。
保険業界は就職する学生の人気が高く、高給で福利厚生が整っているホワイトな企業といったイメージを持たれがちですが、業界内にいる人間からすると損害保険業界で働くことは決して楽ではないということを強調したいと思います。
そもそも保険というものは、将来起こり得る様々なリスクに備えるため、同じような不安を抱える方から一定の保険料を支払ってもらい、その貯まった金額から将来の支払いに充てるという機能を有するものです。当社も顧客の抱える多様なリスクに備えるため、様々な保険商品を開発し顧客の要望に応えようと努力しておりますが、近年、企業活動のグローバル化や気候変動等により、そのリスクが予想外に多額になることも珍しくなく、当社1社でその支払いに対応するというのは、極めて困難なケースもみられるところです。
そこで、当社1社では抱えきれないリスクに備えるため、従来からある再保険というスキームを活用して、そのような事態に備えようとしております。
さて、わが社の場合、ほぼ毎年税務調査を受けておりますが、今回は再保険について課税庁との間で激しい議論が交わされております。すなわち、国税局の主査は、わが社が引き受け、海外子会社に再保険に出した保険契約につき、再保険料のうち一部は海外子会社を利用した単なる「預け金」に過ぎず、租税回避目的のスキームであるため、損金性はないと主張しております。
わが社としては、契約の解釈上、再保険料を預け金とその他のものとに合理的に区分することなどそもそもできず、主査の主張は課税せんがための無理筋の理屈と反論しておりますが、税法上どのように考えるべきでしょうか、教えてください。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。