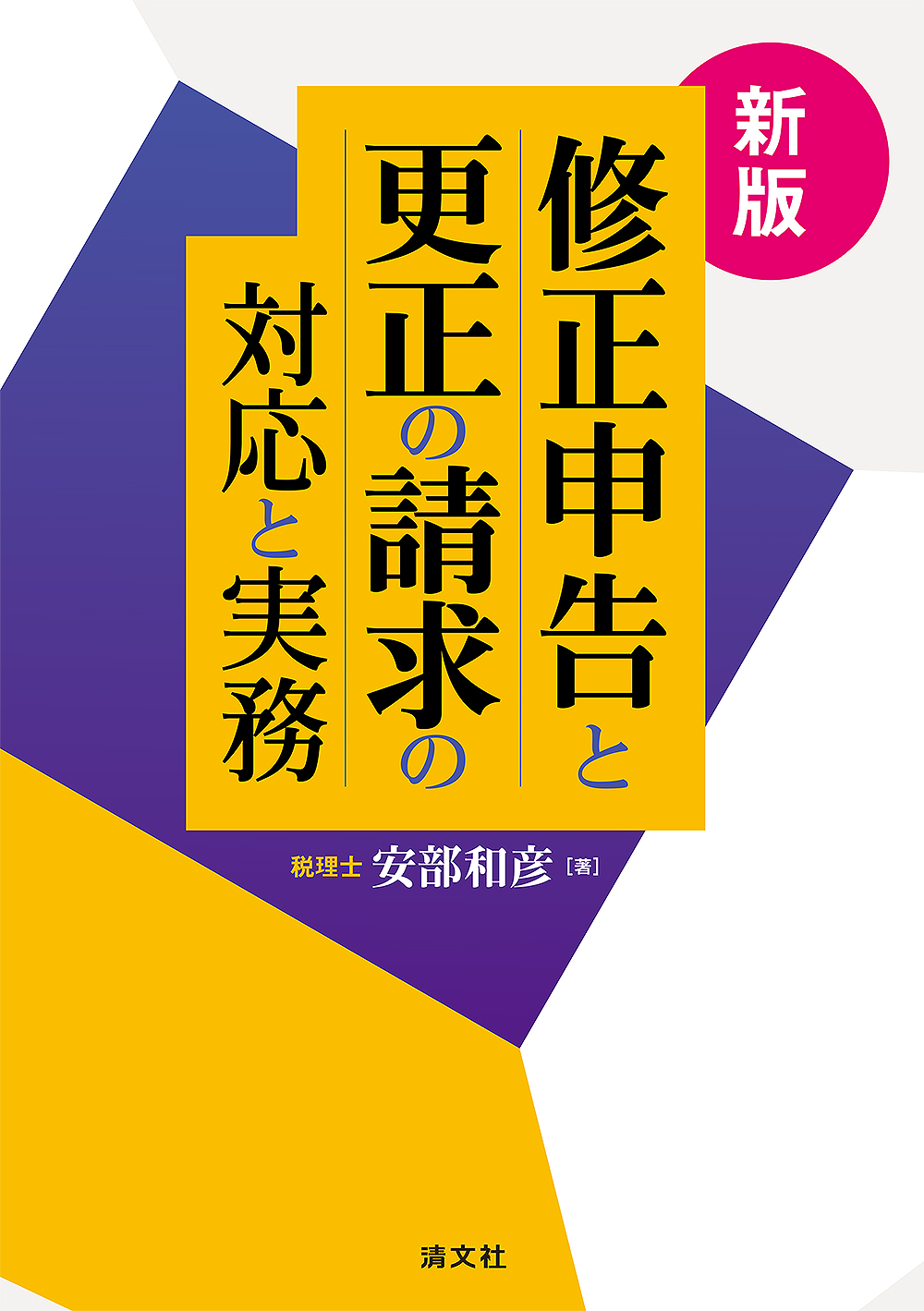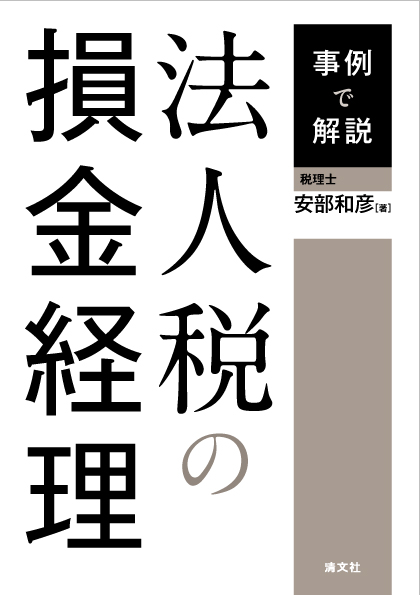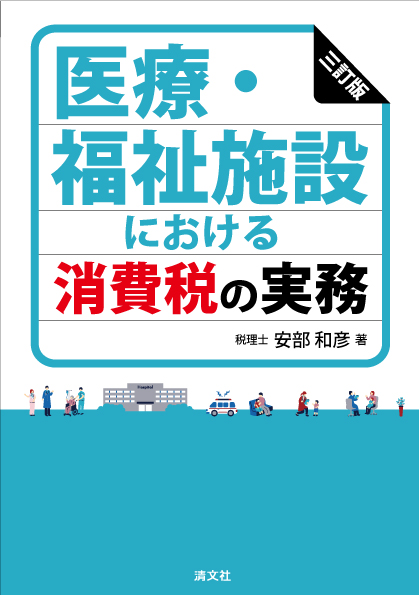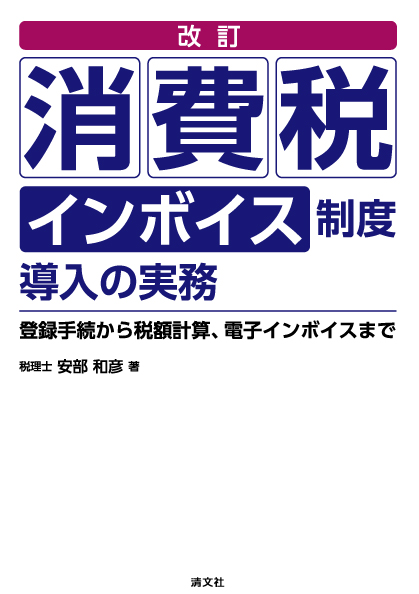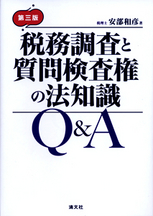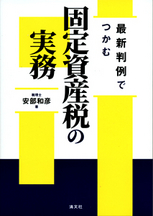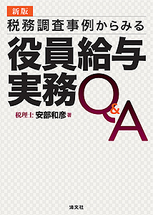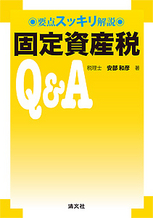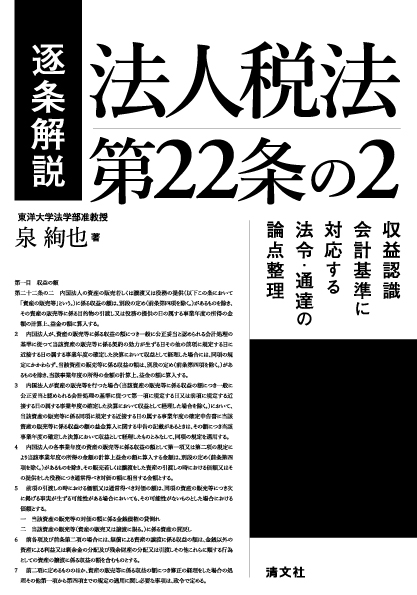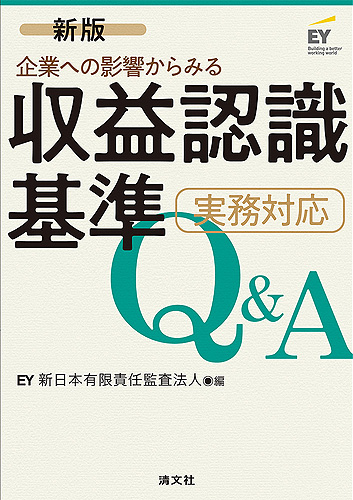法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【事例76】
「関係会社の実質的な費用収益の帰属主体」
拓殖大学商学部教授
税理士 安部 和彦
【Q】
私は、中部地方のとある県の県庁所在地に本社を置き、土木建築工事の設計、施工等を行うX株式会社(資本金5億円の3月決算法人)において、経理部長を務めております。
地方の土木・建築系の企業はどこでも同じかと思いますが、21世紀に入って国・地方問わず公共事業が減少し続けているあおりを受け、その発注に頼ってきたところの業績はどこも厳しい状況だと思われます。わが社もご多分に漏れず10年くらい前まで厳しい状況が続き、高齢の先代社長が引退する機会に関連会社も含めすべての事業を畳もうという方向で話が進んでいました。ところが、ここ数年、個人が所有する比較的広めの宅地に、戸建て住宅レベルの品質と住み心地を提供する低層の賃貸住宅の建設需要が高まっており、わが社は中部地方においてそのような賃貸マンション建設事業を手広く受注することとなり、業績が一気に上向きとなりました。そのため、先代社長の後を東京に出て銀行員をしていた息子さんが継いで、現在さらなる事業拡大を目指して頑張っているところです。
さて、そのような中、赤字の時は見向きもされなかったのですが、黒字転換した途端なのでしょうか、先週から久方ぶりに国税局の税務調査を受けております。最初は和やかな雰囲気で始まったのですが、調査開始3日目から突如関連会社との取引関係につき厳しいやり取りが続き、かなり険悪な雰囲気となっております。国税局の主査が言うことには、わが社の関連会社がそれぞれ売上や所得を稼得しているとした法人税の申告につき、それらはすべて実質的にその親会社であるわが社に帰属しているとして、修正申告をするよう迫ってきているのです。連結納税を行っているわけでもないのに、法人格が異なる関連会社の損益につき、その法人格を否認して本社で取り込むような主査の主張には全く納得がいかないのですが、税法上はどのように考えるべきなのでしょうか、教えてください。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。