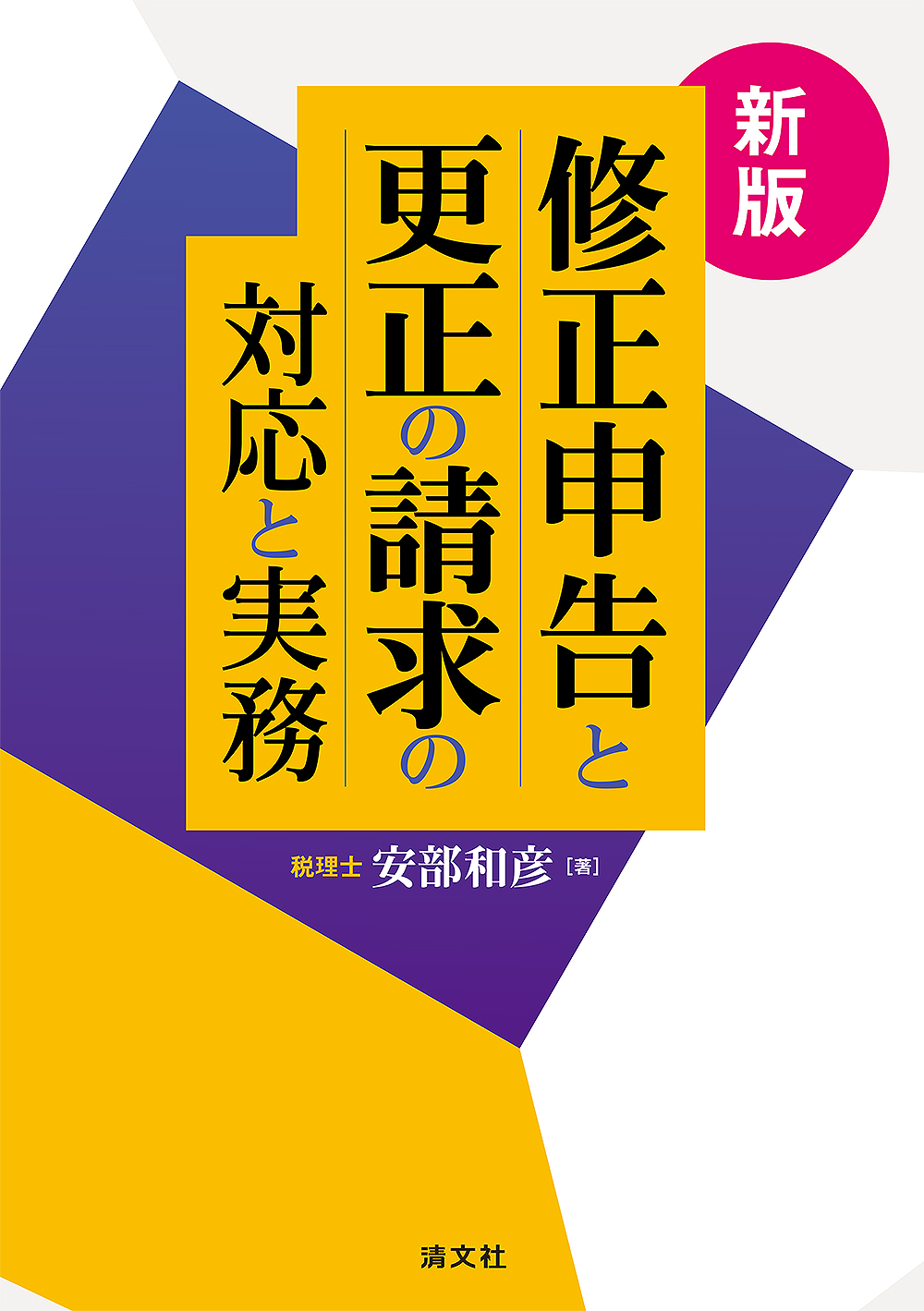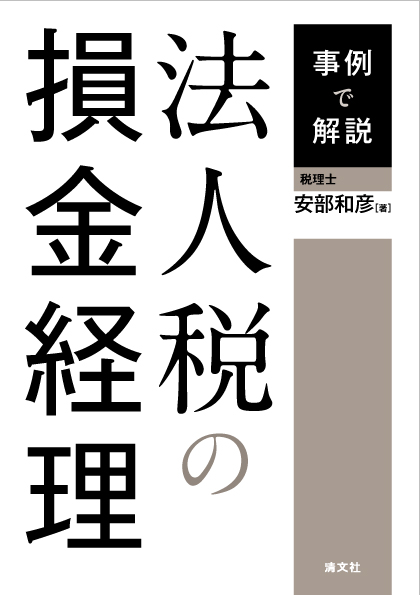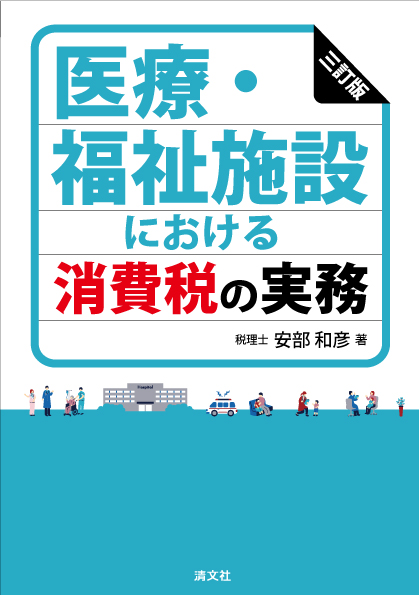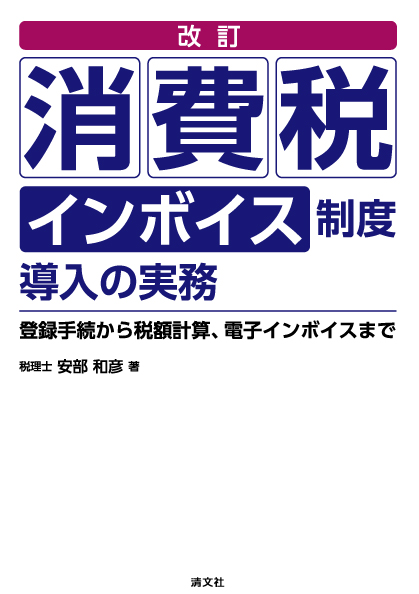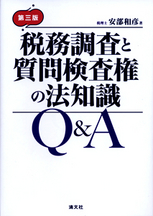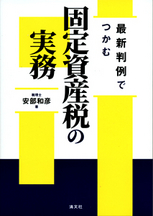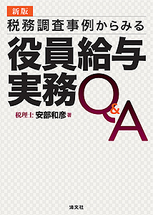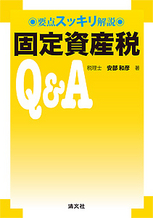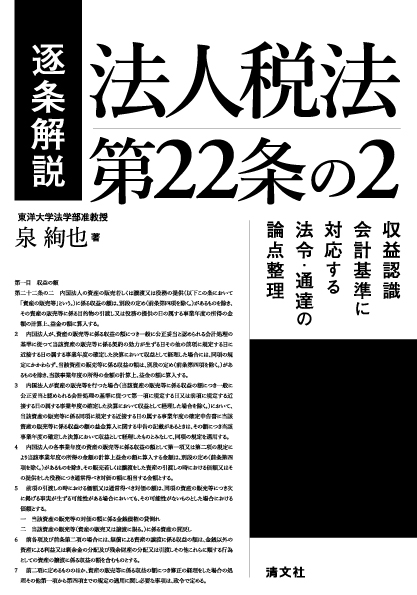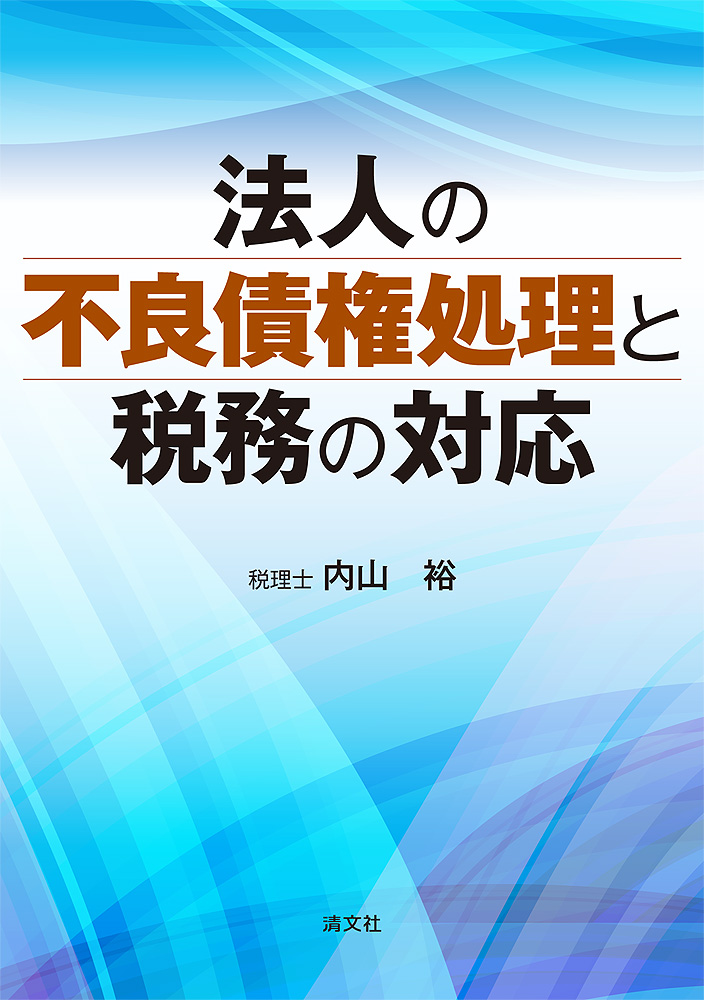法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【事例71】
「自己破産した債務者に対する債権の損金算入時期」
拓殖大学商学部教授
税理士 安部 和彦
【Q】
私は、東北地方のある県庁所在地に本社を構え貸金業を営む株式会社X(資本金5億円で3月決算法人)において、経理部長を務めております。
わが国の貸金業を取り巻く全般的な経営環境は、2020年以来のコロナ禍がようやく収束に向かう中で、新規貸出はやや持ち直してきているものの、急激な物価上昇等の影響による事業コストの増大、デジタル化の進展等を背景とした顧客ニーズの変化に直面するといったこともあり、引き続き厳しい状況に置かれています。わが社は、消費者(個人)向け無担保融資を行い貸付残高が100億円に満たない中小規模の貸金業者ですが、これまでわが社の経営に厳しい影響を及ぼしてきた、少子高齢化に伴うマーケットの縮小が主たる原因である収益性(利息収入から営業費用を差し引いたもの)の下落傾向には、ようやく歯止めがかかってきたところです。一方で、最近新たに浮上してきた経営リスクとして、人員不足の問題が深刻化しており、頭痛の種は尽きないところです。
さて、そのような中、新たな頭痛の種となっているのが、先週から受けている税務調査です。今回は、個人向けの貸金の中に、自己破産した債務者(故人)のものがあり、当該債務者に相続人がいないことから、債務者が死亡した時点で損金処理したところ、調査官がそれは認められないと主張しているというものです。調査官は、故人が自己破産したのは死亡する2期前の事業年度であり、その時点で直ちに貸倒損失に係る損金算入をすべきところ、死亡した事業年度まで損金算入を繰り延べたのは、利益調整のためであると決めつけています。債務者の自己破産の時点では貸倒損失が確定したとはいえず、死亡時点においてそれが確定し損金算入するのが妥当と考えますが、税法の観点からはどのように考えるべきなのでしょうか、教えてください。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。