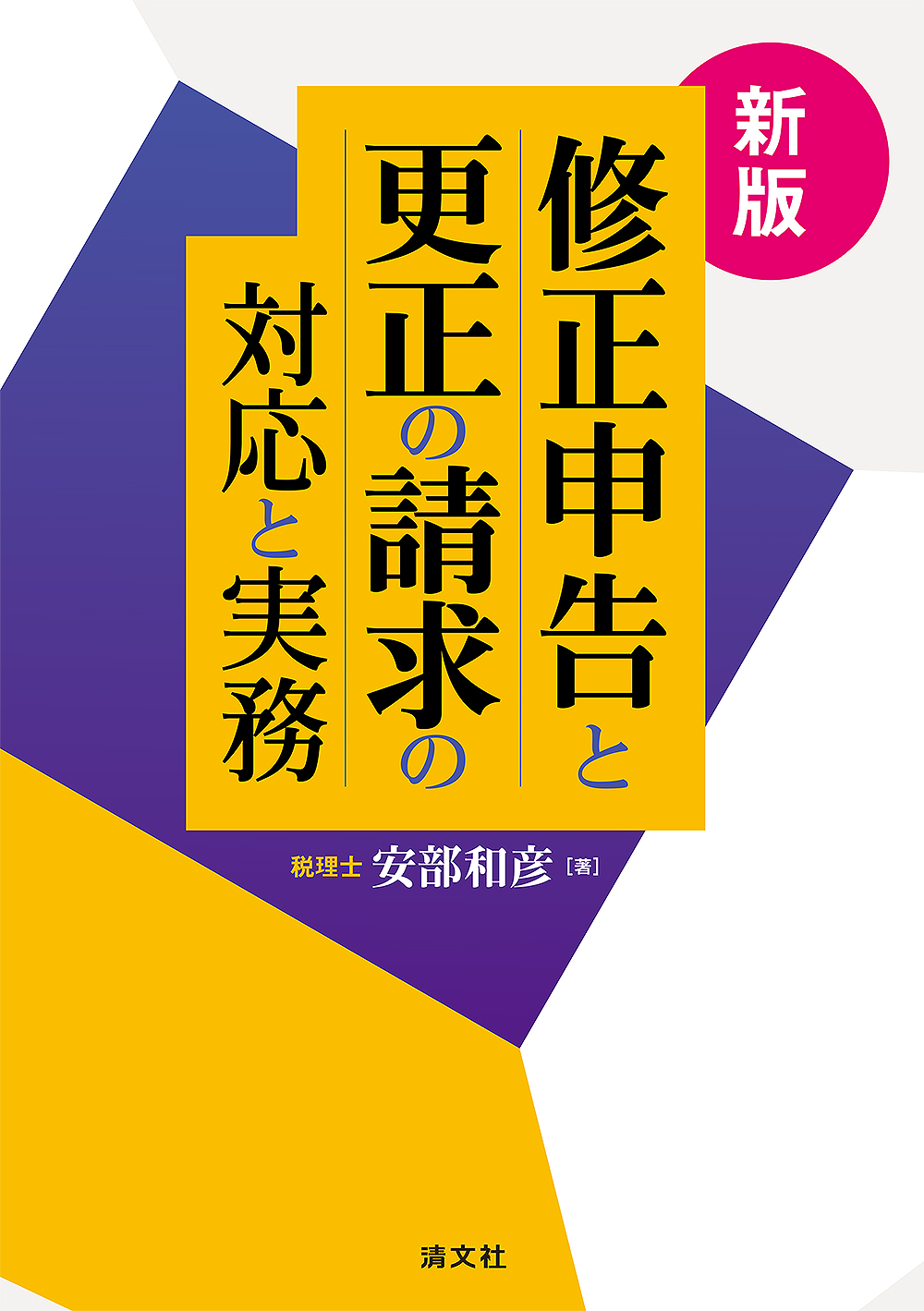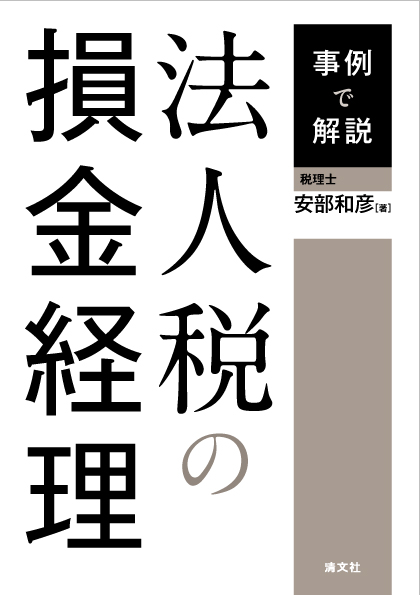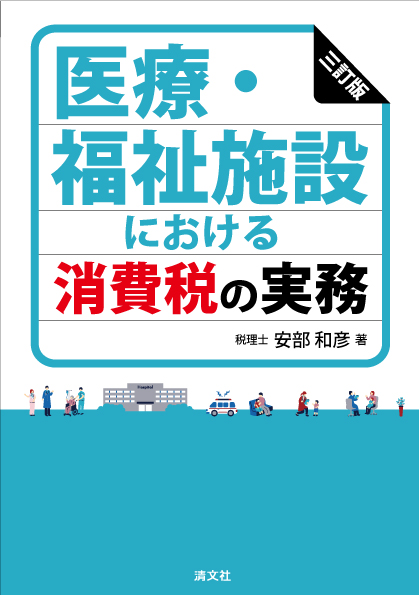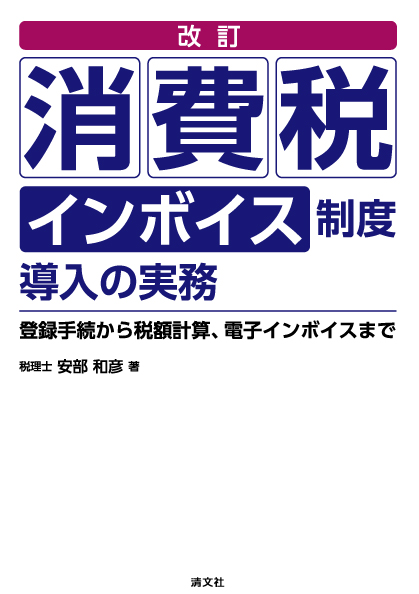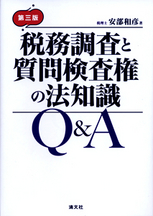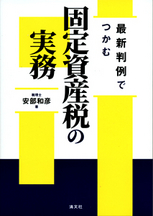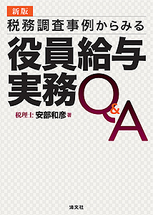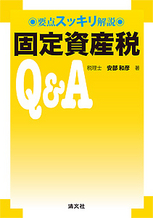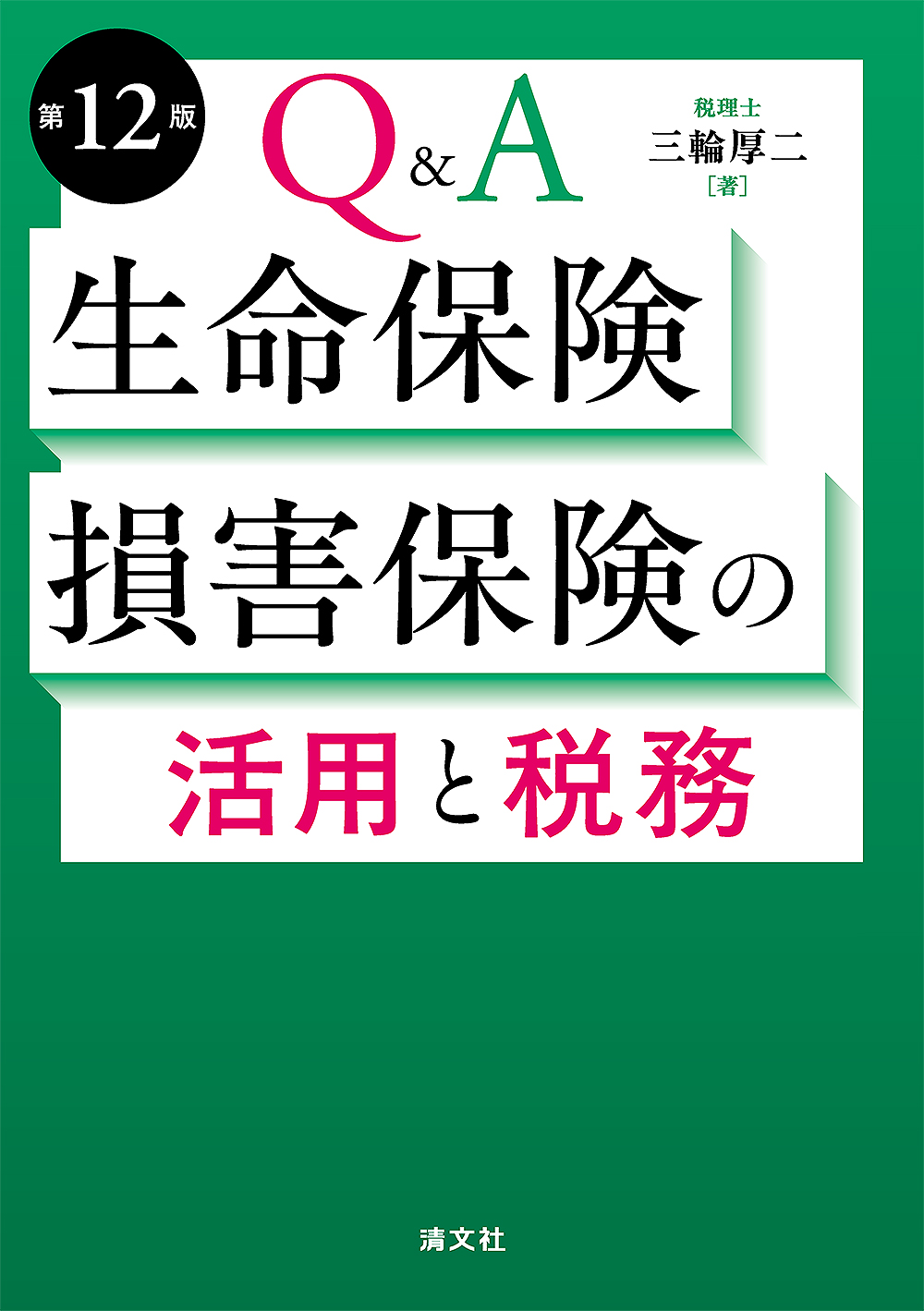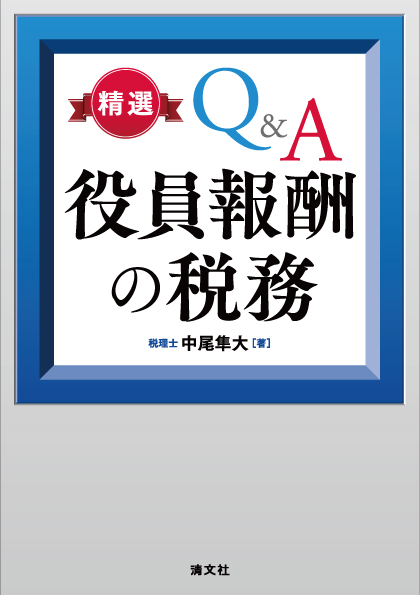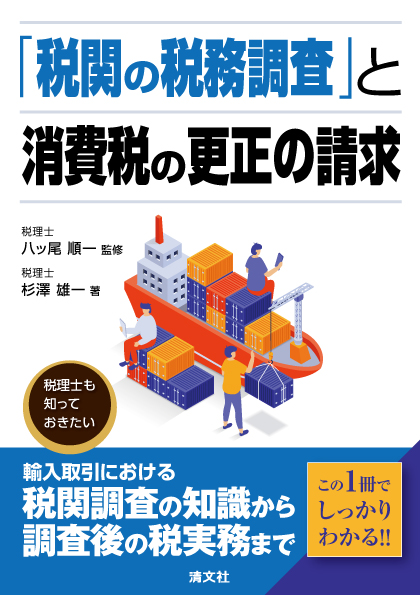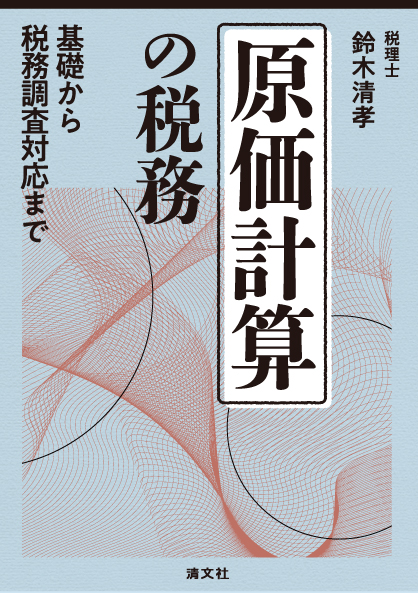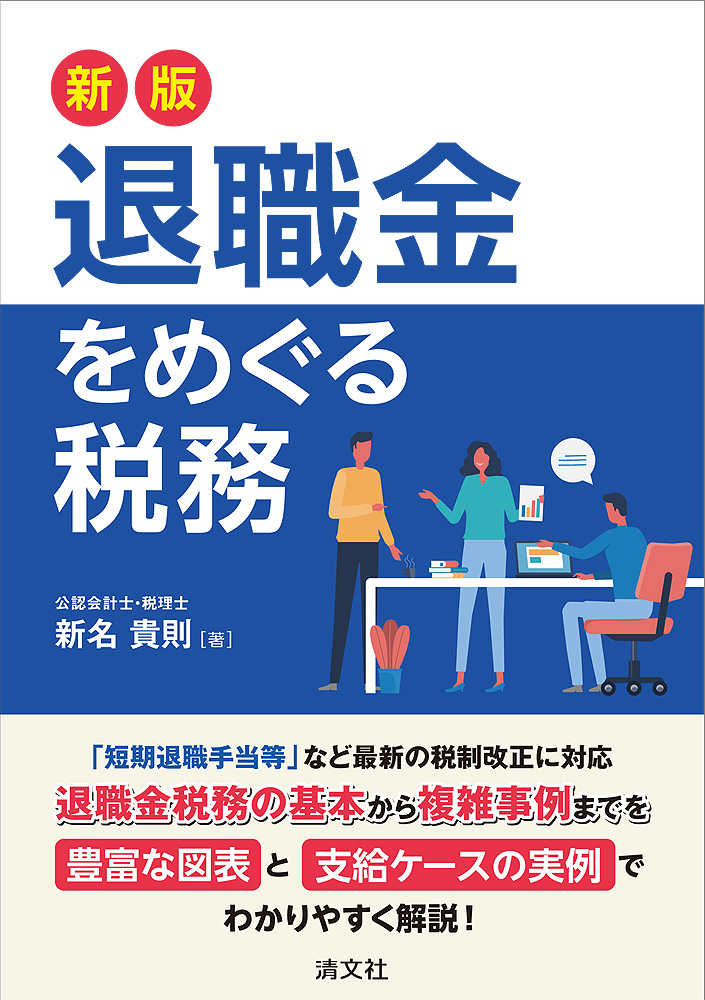法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【事例3】
「役員退職給与に係る「不相当に高額」の意義」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
【Q】
わが社はある首都圏のある都市において精密部品の機械加工を主たる業務とする株式会社(3月決算)です。わが社の取締役だったAが昨年死亡したため、役員退職慰労金を支払いましたが、その際、ある民間団体が公表している役員退職給与のデータから、同業類似他社のものを抽出し、それを参考にして金額を算定したところです。
ところが、現在わが社が受けている税務調査において、課税庁は、同業類似法人の役員退職給与の支給事例における平均功績倍率に、当該退職役員の最終月額報酬及び勤続年数を乗じて求める「平均功績倍率法」を用いて算定した金額より支給額が多いことから、その差額は「不相当に高額な部分」に該当し、損金の額に算入されないと主張してきました。
当方が役員退職給与算定の際に用いたデータは、民間企業が調査した結果をまとめた冊子から抽出したものであり、当社の関与税理士によれば、当該データは課税実務においてよく使用されているものであると聞きます。しかしながら、課税庁は当該冊子のデータはアンケート調査で得られた結果から作成されていることから網羅性に疑義があり、また当方が行った同業類似法人の抽出方法にも問題があるとして、課税庁が部内データに基づき別途役員退職給与の適正額を算定したものを提示してきました。
このような場合、わが社はどのように対応すればよいのでしょうか、教えてください。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。