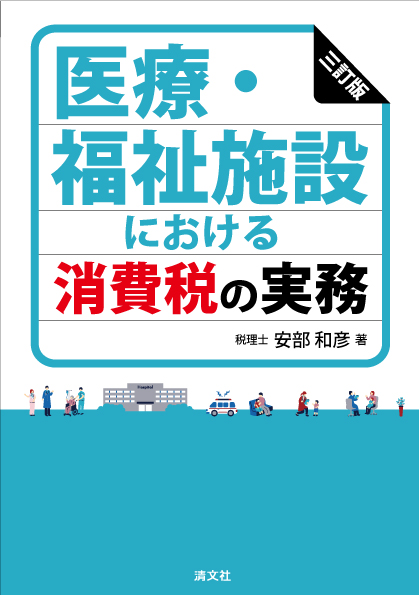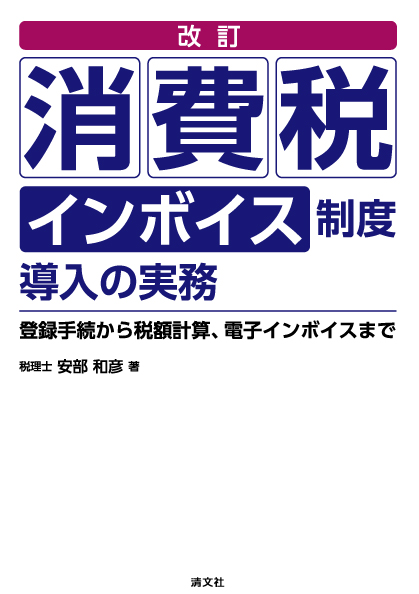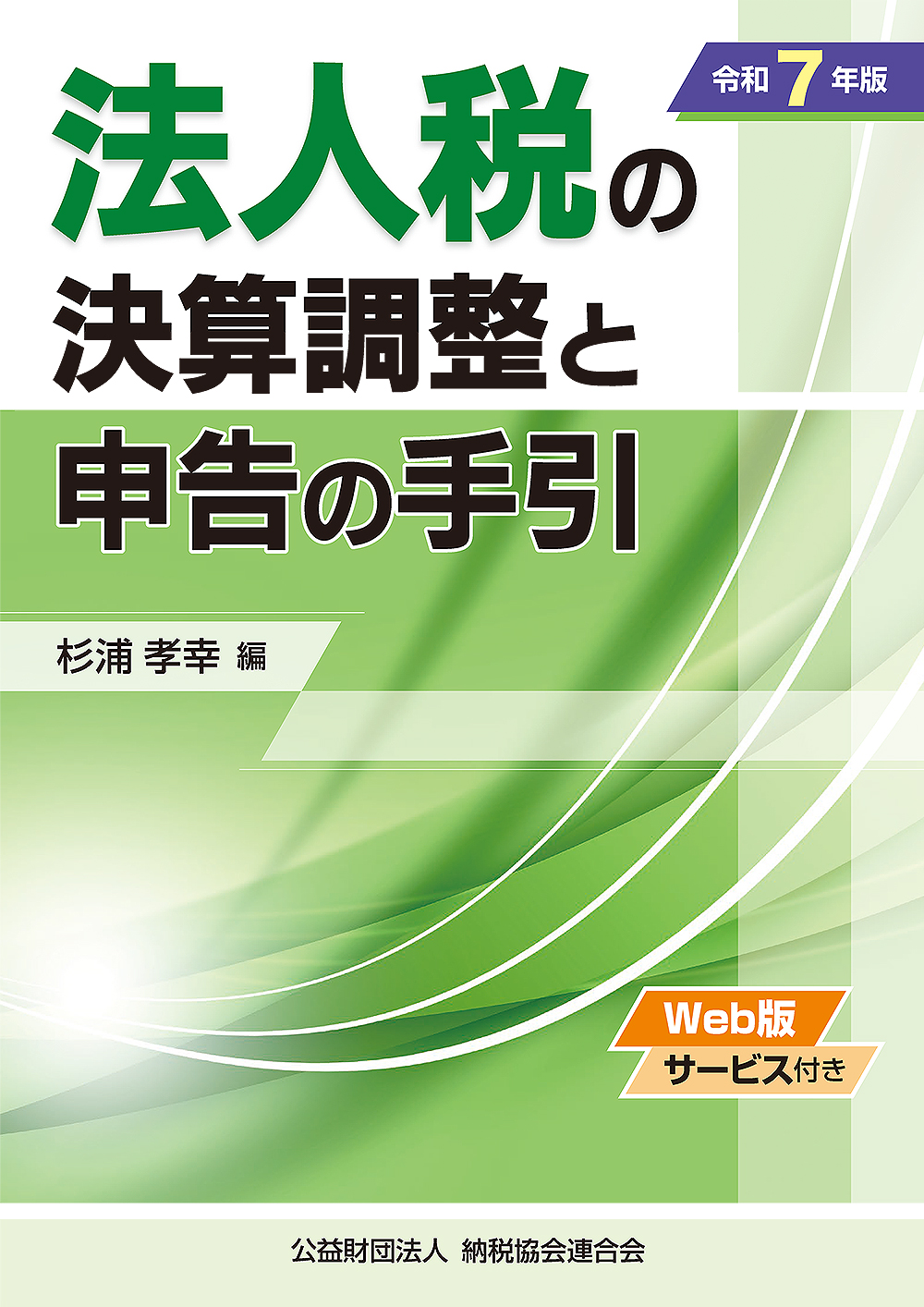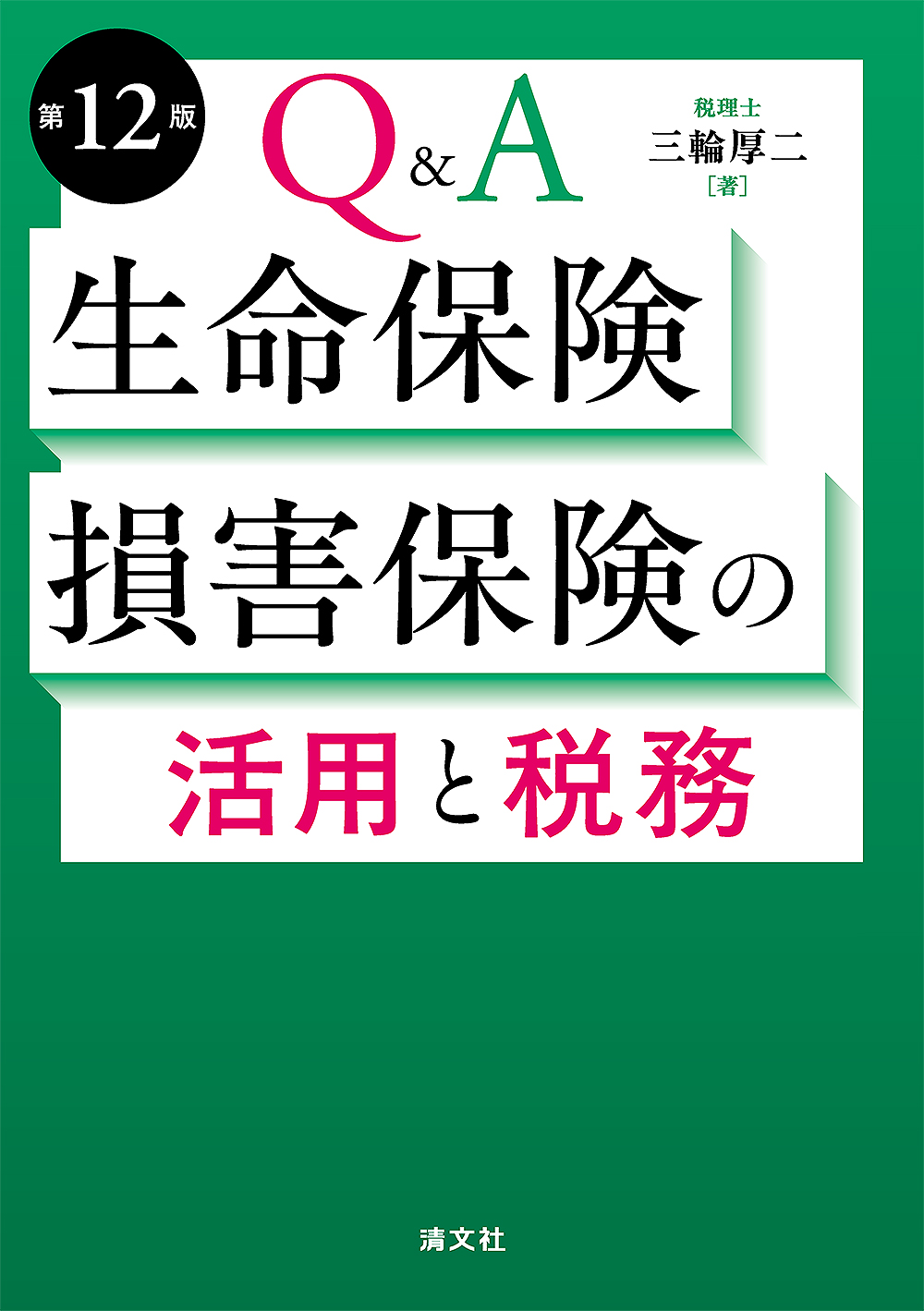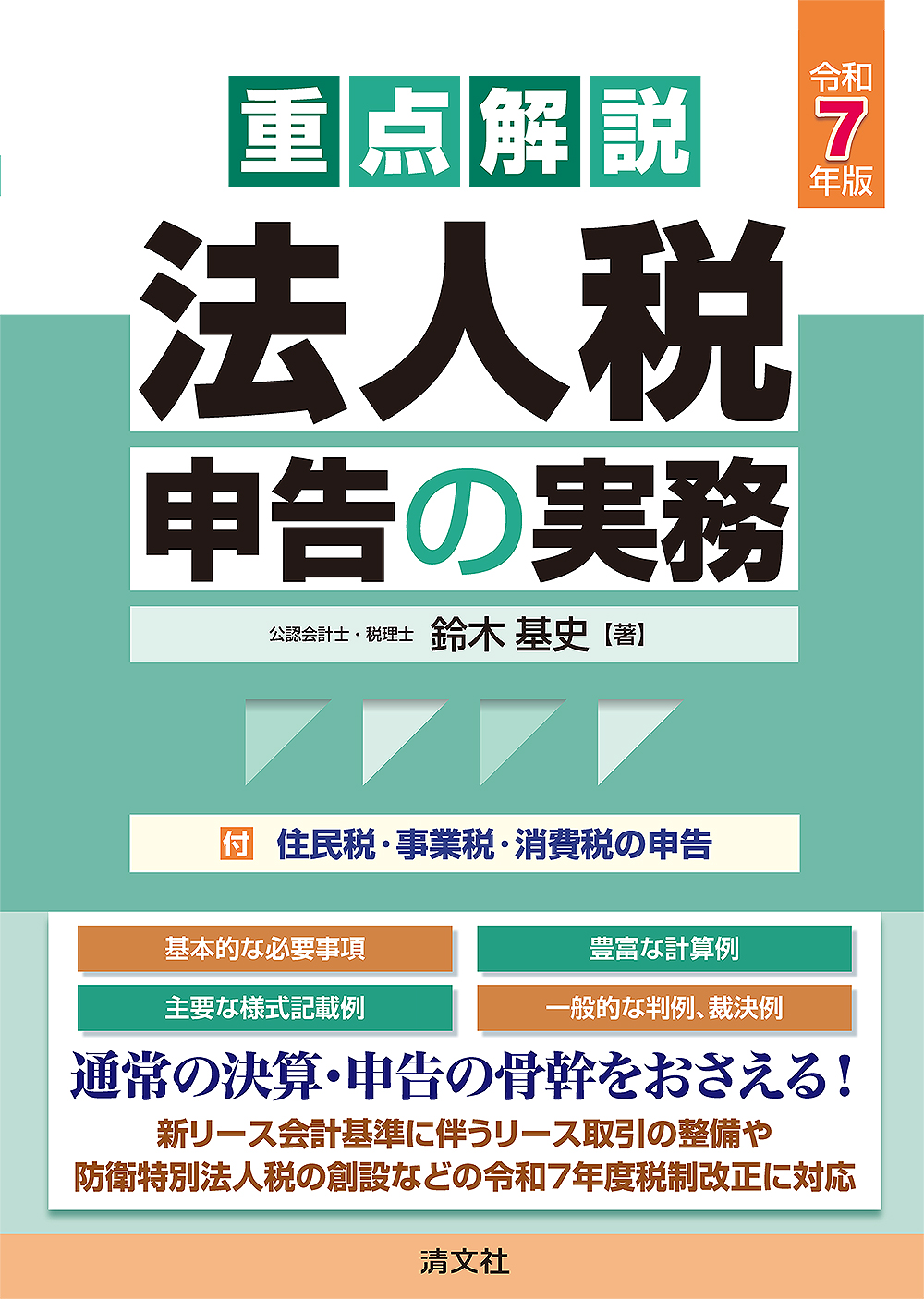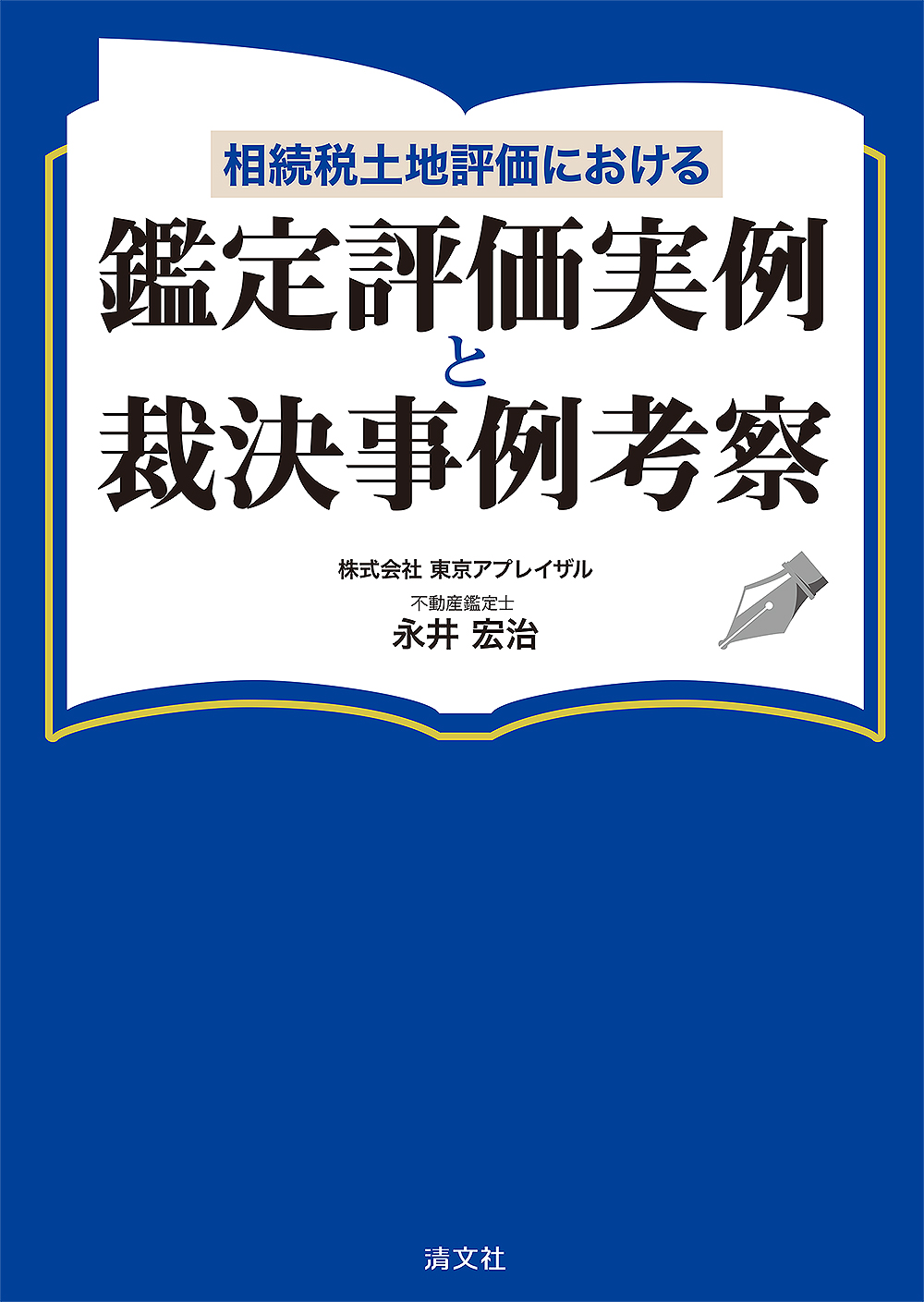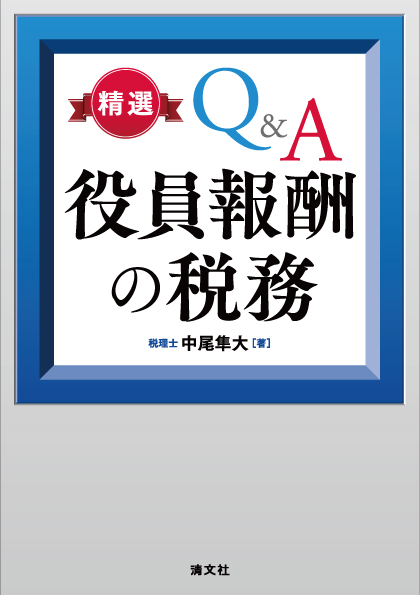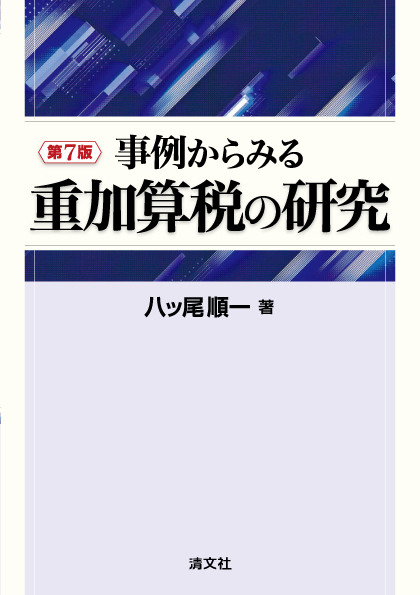法人税の損金経理要件をめぐる事例解説
【事例15】
「特許業務法人の社員は使用人兼務役員に該当するのか」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
【Q】
私は都内で個人の税理士事務所を経営しております。今回のご相談は、その中のクライアントで、高校時代のサッカー部の仲間Aが経営するある特許業務法人Bの法人税の取扱いに関するものです。
特許業務法人というのは、弁理士法に基づき設立される特殊法人(弁理士法37)で、弁護士法に基づく弁護士法人や税理士法に基づく税理士法人に類似する制度です。特許業務法人Bには4名の社員がおり、そのうちの1名(A)が代表社員となっています。
代表社員Aの給与は固定給で、前年度の法人全体の収益の状況を基に算定した金額を12等分し、毎月同額ずつ支払っております。残りの社員はいずれも弁理士で、その報酬たる給与は固定給部分(月額20万円)と歩合給部分で構成されています。このうち歩合給は、各社員が担当した案件につき、法人Bが顧客に請求する金額の一定割合を乗じた金額としています。当該歩合給は、年2回、他の従業員に対して賞与を支払う時期と同じタイミングで各社員に支給しています。
私は特許業務法人Bの法人税の申告書を作成するにあたり、代表社員AとA以外の社員に対する給与の支払い内容を確認しました。その結果、A以外の社員は優秀な弁理士で科学技術には滅法明るいのですが、事務作業には興味がなく、事務所の経営にタッチする意欲もないことから、勤務実態は使用人としての色彩が強いといえます。勿論、特許業務法人の社員であるので、法律上業務執行権を有していることから、法人税法上は、使用人兼務役員に該当するものと考えました。そこで、特許業務法人Bの社員になる一歩手前の職種であるディレクター3名の給与と比較し、それを上回る部分の金額は損金不算入としましたが、それ以下の部分の金額については全額損金に算入しました。
ところが、最近特許業務法人Bが受けた税務調査で、特許業務法人の社員は使用人としての立場でその職務に従事するものではないため、法人税法上、使用人兼務役員には該当せず、代表社員A以外の社員に対して支払った給与のうち、歩合給部分は全額損金不算入である旨を調査官から言い渡されました。
既に説明したとおり、A以外の社員はいわば「技術オタク」で事務所の経営にタッチする意欲はなく、おおよそ役員や経営者としての役割を果たしておらず、実際、事務所経営はAが1人で担っているのが実態であることから、調査官の主張には納得がいきません。法人税法上、A以外の社員が使用人兼務役員に該当する余地はないのでしょうか、教えてください。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。