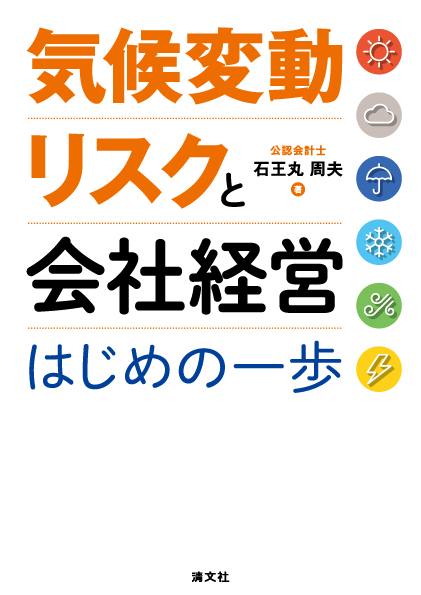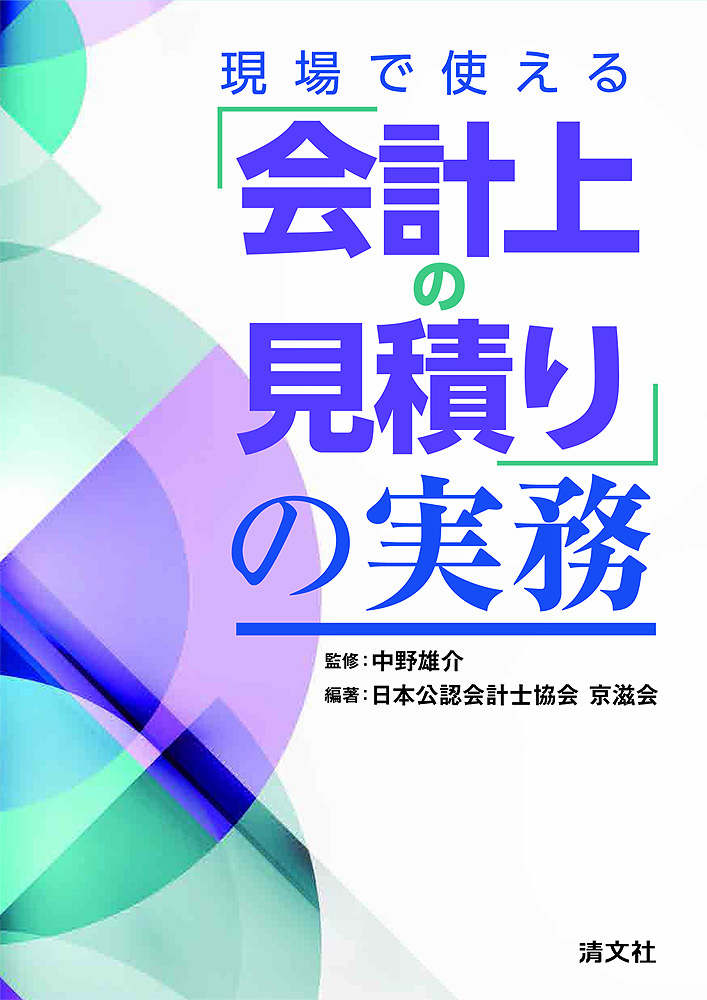減損会計を学ぶ
【第7回】
「減損の兆候の例示②」
~使用範囲・方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合~
公認会計士 阿部 光成
「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「減損適用指針」という)では、減損の兆候として、資産又は資産グループ(以下「資産等」という)の使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化があるケースを例示している。
なお、資産グループについては、減損適用指針13項なお書き及び87項に注意する。
資産又は資産グループが使用されている範囲又は方法について、例えば、以下のような当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、又は、生ずる見込みである場合には、減損の兆候となる(減損会計基準 二 1②及び注解(注2))。
以下では、上記の減損の兆候を識別する際の留意点を解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
1 事業の廃止又は再編成
資産等が使用されている事業を廃止又は再編成する場合、減損の兆候に該当する(減損適用指針13項(1))。
事業の再編成には、重要な会社分割などの組織再編のほか、事業規模の大幅な縮小などが含まれる(減損適用指針13項(1))。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。