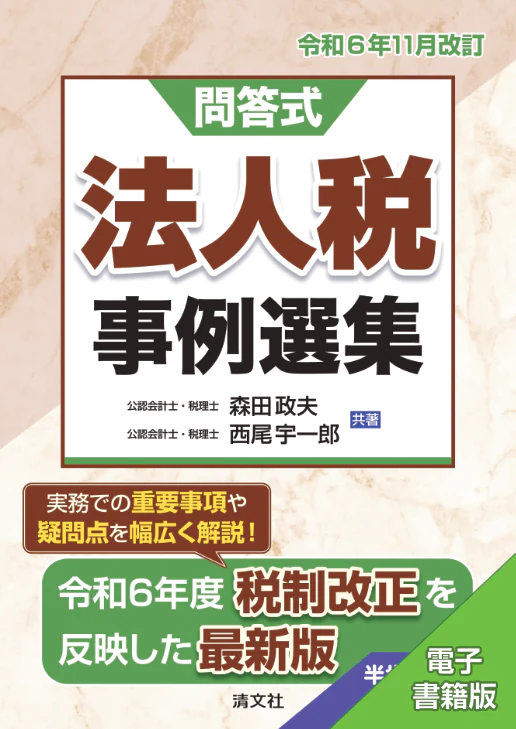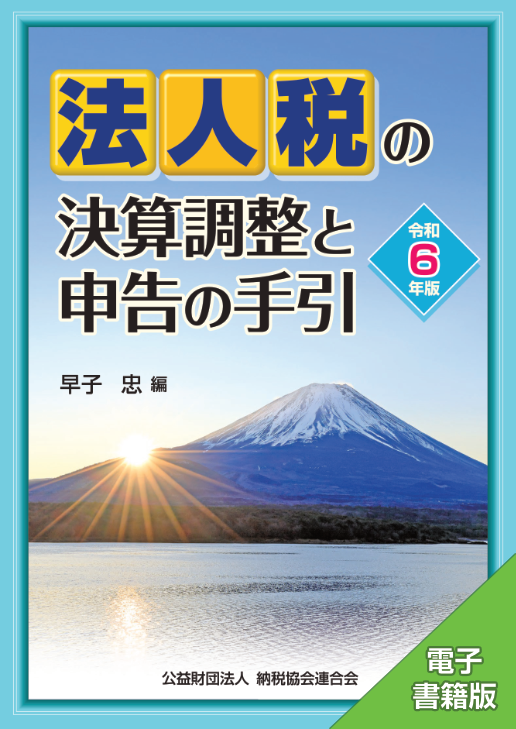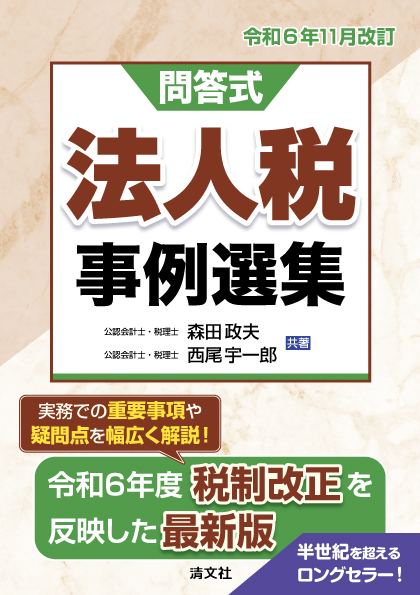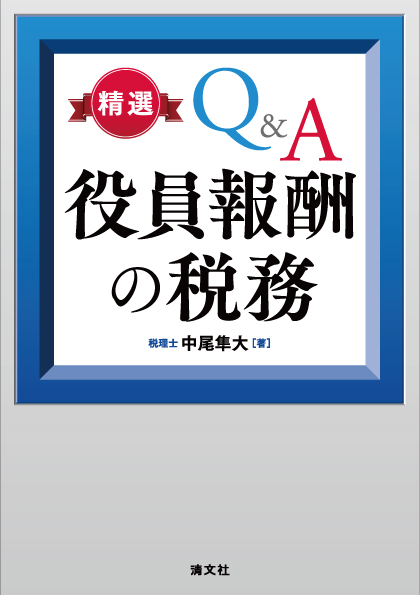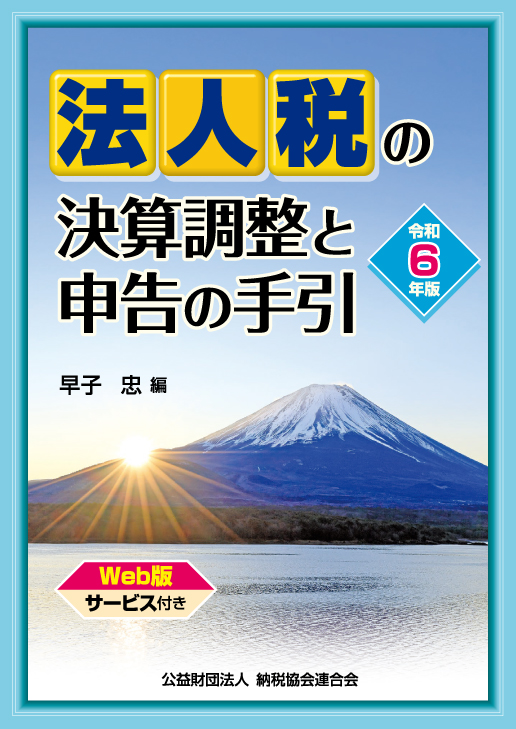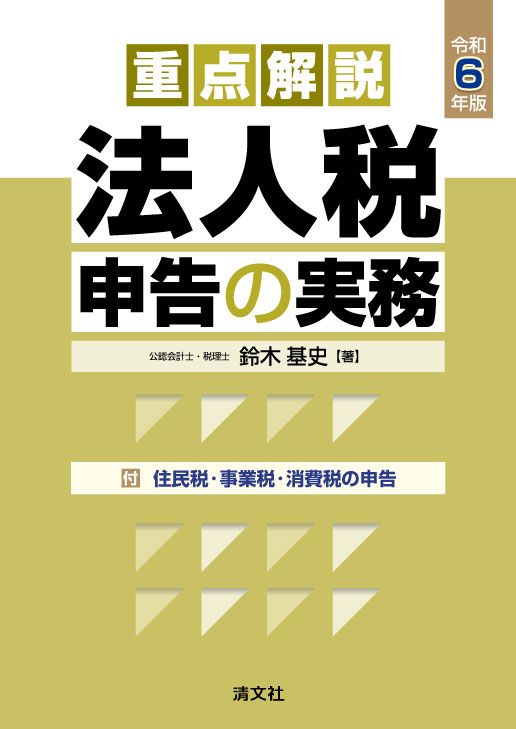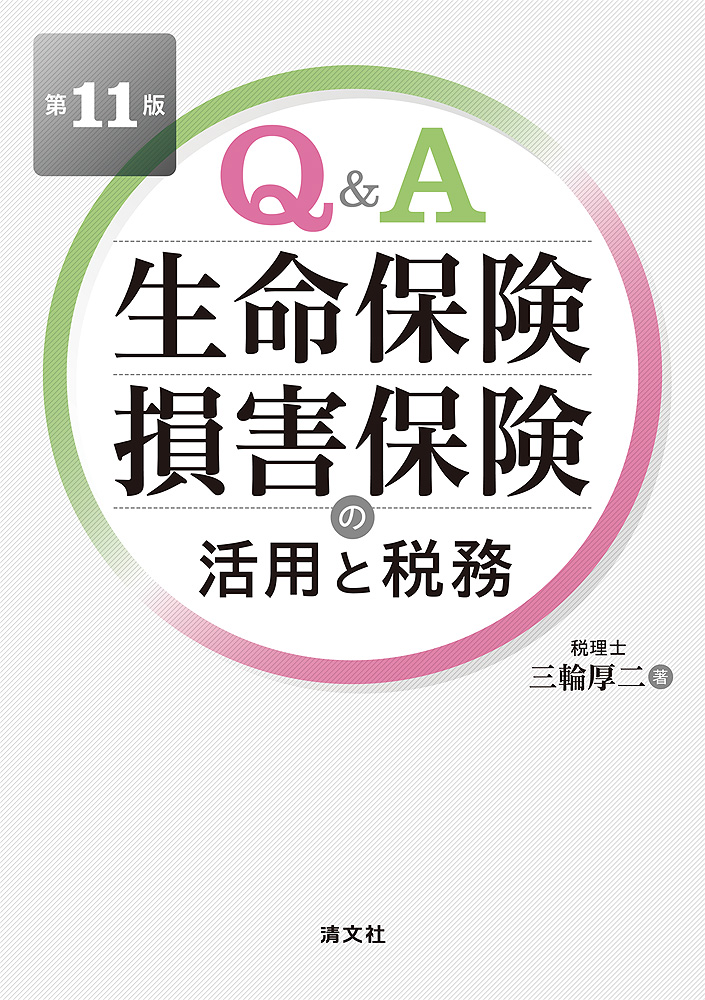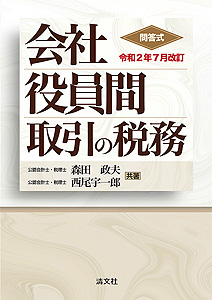ストック・オプション会計を学ぶ
【第12回】
(最終回)
「財貨又はサービスの取得の対価として自社株式オプション又は自社の株式を用いる取引の会計処理」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
連載最終回となる今回は、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号。以下「ストック・オプション会計基準」という)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第11号。以下「ストック・オプション適用指針」という)にしたがって、財貨又はサービスの取得の対価として自社株式オプション又は自社の株式を用いる取引について解説する。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。