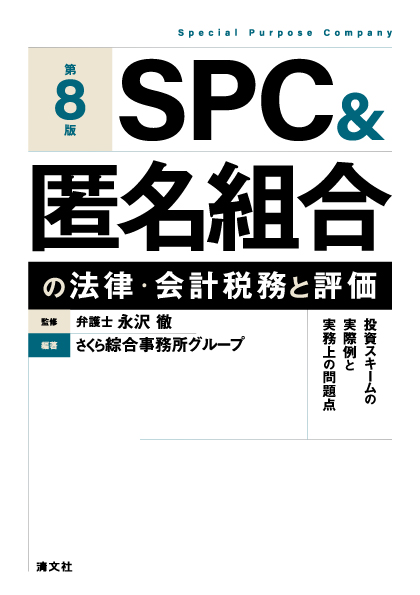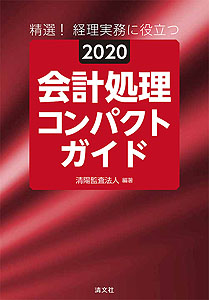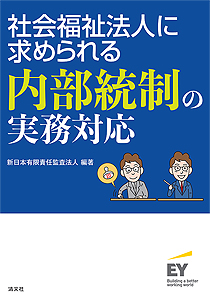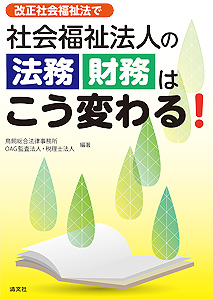金融商品会計を学ぶ
【第22回】
「ヘッジ会計③」
公認会計士 阿部 光成
前回に引き続き、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)におけるヘッジ会計について述べる。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅰ リスク管理方針文書の記載事項
金融商品会計基準等は、ヘッジ会計を実行するに際して、ヘッジ取引時において、ヘッジ取引が企業のリスク管理方針に従ったものであることが客観的に認められることを要件として規定している(金融商品会計基準31項(1)、金融商品実務指針144項)。
リスク管理方針は、経営者が企業活動においてさらされているリスクの種類と内容を識別し、これらを許容し得るレベルに管理するために策定したものであって、取締役会等の意思決定機関において、原則として毎期、承認を受け文書化したものである(金融商品実務指針315項)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。