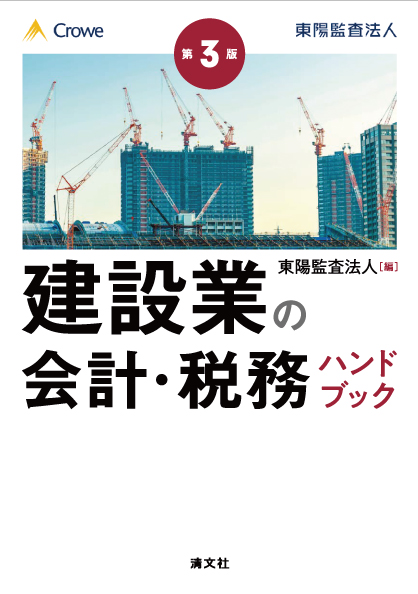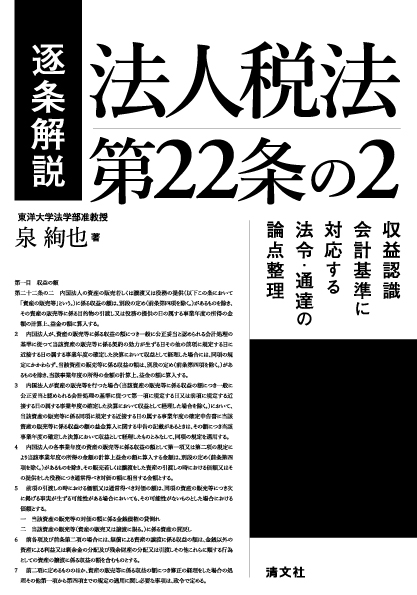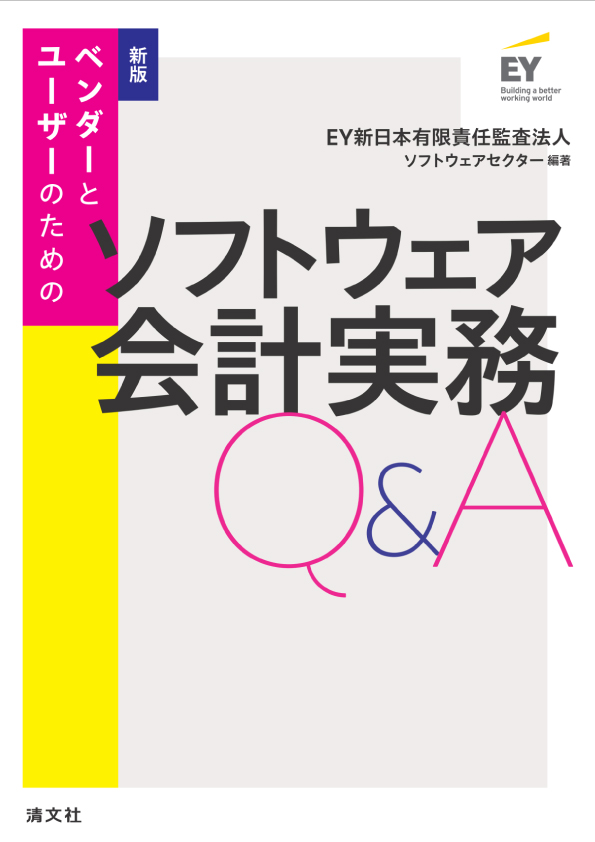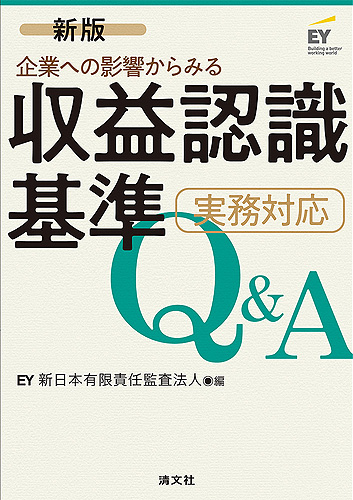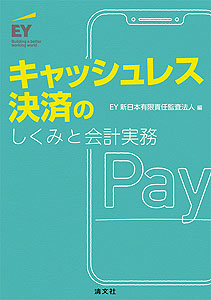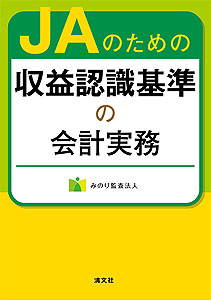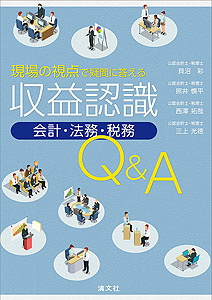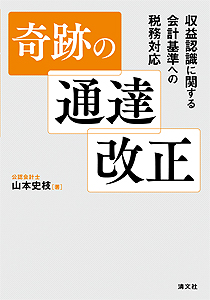収益認識会計基準(案)を学ぶ
【第1回】
「範囲と定義」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
本シリーズでは、平成29年7月20日から意見募集が開始された「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「収益認識会計基準(案)」という)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「収益認識適用指針(案)」という)についての解説を行う。
収益認識会計基準(案)は、わが国における収益認識に関する包括的な会計基準の開発として公表されたものである。意見募集は平成29年10月20日までである。
今回は、収益認識会計基準(案)における「範囲と定義」について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 範囲
1 収益認識会計基準(案)の対象
収益認識会計基準(案)は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示に適用される(3項)。
次の事項に注意する(95項)。
◆収益認識会計基準(案)の対象となるのは「顧客との契約から生じる収益」である。
◆顧客との契約から生じるものではない取引又は事象から生じる収益は、収益認識会計基準(案)では、取り扱わない。
◆契約の相手方が、対価と交換に企業の通常の営業活動により生じたアウトプットである財又はサービスを得るために当該企業と契約した当事者である顧客である場合にのみ、本会計基準が適用される(「契約」、「顧客」などの定義は下記の「Ⅲ 定義」を参照)。
次の取引は収益認識会計基準(案)の適用範囲から除かれている(3項、96項~100項)。
① 「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)の範囲に含まれる金融商品に係る取引
② 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)の範囲に含まれるリース取引(貸手の会計処理。97項)
③ 保険法に定められた保険契約
④ 顧客又は潜在的な顧客への販売を容易にするために行われる同業他社との商品又は製品の交換取引(例えば、2つの企業の間で、異なる場所における顧客からの需要を適時に満たすために商品又は製品を交換する契約。わが国では、棚卸資産の交換取引に関する会計処理の定めが明示されていないが、IFRS第15号と同様に、同業他社との棚卸資産の交換について収益を認識することは適切ではないと考えられる。99項)
⑤ 金融商品の組成又は取得に際して受け取る手数料
⑥ 「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」(会計制度委員会報告第15号)の対象となる不動産の譲渡
収益認識会計基準(案)の適用範囲については、次の事項にも注意する(101項~102項)。
(a) 固定資産の売却については論点が異なり得るため改正の範囲に含めていない。
(b) 棚卸資産や固定資産等、コストの資産化等の定めがIFRSの体系とは異なるため、IFRS第15号における契約コスト(契約獲得の増分コスト及び契約を履行するためのコスト)の定めを範囲に含めていない。
(c) IFRS又は米国会計基準を連結財務諸表に適用している企業が当該企業の個別財務諸表に本会計基準を適用する場合には、契約コストの会計処理を連結財務諸表と個別財務諸表で異なるものとすることは実務上の負担を生じさせると考えられるため、個別財務諸表においてIFRS第15号又はTopic 606における契約コストの定めに従った処理をすることは妨げられない。
なお、参考までに記載すると、固定資産の売却に関しては、平成16年2月13日に、企業会計基準委員会から「不動産の売却に係る会計処理に関する論点の整理」が公表されており、不動産の売却の会計処理の考え方などが述べられている。
2 留意点
収益認識会計基準(案)は「企業会計原則」に優先することから(1項)、今後は、実現主義の原則(「企業会計原則」 第二 損益計算書原則 三 B)とは異なる考え方で会計処理及び開示を行うことになると考えられるので、収益認識会計基準(案)の全体像を理解することが必要になると考えられる。
収益認識会計基準(案)の開発に当たっての方針は次のとおりであり(91項~94項)、その適用に当たっては、下記(2)の重要性等に関する代替的な取扱い(収益認識適用指針(案)91項から102項)を用いるかどうかなどを含めて、実務上の適用方法を早めに検討することが考えられる。
〈方針(1)〉
IFRS 第15号「顧客との契約から生じる収益」の定めを基本的にすべて取り入れる。
▷具体的な規定
・収益認識会計基準(案)の13項から76項
・収益認識適用指針(案)の4項から88項及び103項
〈方針(2)〉
適用上の課題に対応するために、代替的な取扱いを追加的に定める。
代替的な取扱いを追加的に定める場合、国際的な比較可能性を大きく損なわせないものとすることを基本とする。
▷具体的な規定
・収益認識適用指針(案)の91項から102項(次の事項)
① 契約変更(重要性が乏しい場合の取扱い)
② 履行義務の識別(出荷及び配送活動に関する会計処理の選択)
③ 一定の期間にわたり充足される履行義務(期間がごく短い工事契約及び受注制作のソフトウェア、船舶による運送サービス)
④ 一時点で充足される履行義務(出荷基準等の取扱い)
⑤ 履行義務の充足に係る進捗度(契約の初期段階における原価回収基準の取扱い)
⑥ 履行義務への取引価格の配分
⑦ 契約の結合、履行義務の識別及び独立販売価格に基づく取引価格の配分(契約に基づく収益認識の単位及び取引価格の配分、工事契約及び受注制作のソフトウェアの収益認識の単位)
〈方針(3)〉
基本的には、連結財務諸表と個別財務諸表において同一の会計処理を定める。
3 廃止される会計基準等
収益認識会計基準(案)等が会計基準等として確定した場合、次の会計基準等は廃止される予定である(86項、90項)。
① 「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号)
② 「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号)
③ 「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第17号)
このため、従来、これらの会計基準等を適用している会社は、収益認識会計基準(案)に従って会計処理等をする場合の影響について検討することが必要と考えられる。
Ⅲ 定義
収益認識会計基準(案)は、次の定義を設けている(4項~12項)。
契約、顧客、債権、契約資産及び契約負債など重要な定義が規定されている。
『契約』
【定義】
法的な強制力のある権利及び義務を生じさせる複数の当事者間における取決めをいう。
『顧客』
【定義】
対価と交換に企業の通常の営業活動により生じたアウトプットである財又はサービスを得るために当該企業と契約した当事者をいう。
『履行義務』
【定義】
顧客との契約において、次の①又は②のいずれかを顧客に移転する約束をいう。
① 別個の財又はサービス(あるいは別個の財又はサービスの束)
② 一連の別個の財又はサービス(特性が実質的に同じであり、顧客への移転のパターンが同じである複数の財又はサービス)
『取引価格』
【定義】
財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額(ただし、第三者のために回収する額を除く)をいう。
(※1) 収益認識適用指針(案)の「Ⅲ.我が国に特有な取引等についての設例」の「[設例28]消費税等」では、その前提条件において、「売上に係る消費税等は、第三者である国や都道府県に納付するため、第三者に支払うために顧客から回収する金額に該当することから、取引価格には含まれない(会計基準第44項)」と記載されている。
(※2) 第348回企業会計基準委員会(2016年11月4日)の「審議事項(3)-7」の11項では、第三者に代わって回収する金額に該当するか否かの判断に迷う可能性がある事項として、次のものが検討されている。
① 消費税等(消費税及び地方消費税)
② 電気事業における再生可能エネルギー発電促進賦課金
③ クレジットカード会社に支払う手数料
④ 小型家電等のリサイクル費用
⑤ パートナー企業と収益の配分割合を取り決めている契約
⑥ 旅行業界における燃油サーチャージや空港利用税等
⑦ 航空業界における共同運航に関する収益
①消費税等については、国内において広く見られる重要な取引であるため、我が国の実務における会計処理の多様性を軽減する観点から、今後検討すべき課題の候補とすることが考えられるがどうかとする一方、②から⑦の「判断の困難さがあるケース」については、いずれも「審議事項(3)-7」の14項に記載の趣旨に当たるほどの重要性はないと考えられるがどうかと述べられている。
『独立販売価格』
【定義】
財又はサービスを独立して企業が顧客に販売する場合の価格をいう。
『契約資産』
【定義】
企業が顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利(ただし、債権を除く)をいう。
(※) 契約資産及び契約負債に関する会計処理については、収益認識適用指針(案)の設例を参照していただきたい。
『契約負債』
【定義】
財又はサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が到来しているものをいう。
『債権』
【定義】
企業が顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利のうち無条件のもの(すなわち、対価に対する法的な請求権)をいう。
対価に対する企業の権利が無条件である(収益認識会計基準(案)11項)とは、当該対価を受け取る期限が到来する前に必要となるのが時の経過のみであるものをいう(129項)。
『工事契約』
【定義】
仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものをいう。
「受注制作のソフトウェア」とは、契約の形式にかかわらず、特定のユーザー向けに制作され、提供されるソフトウェアをいう。
(※) 「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号)を踏襲している(104項)。
(了)
この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。