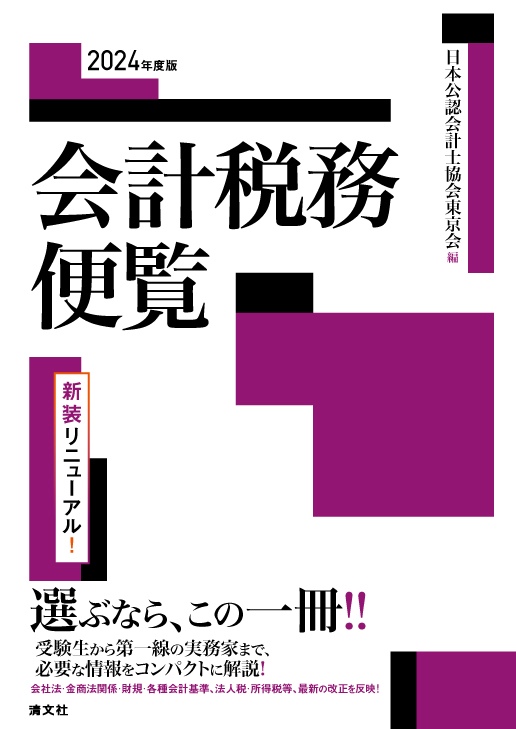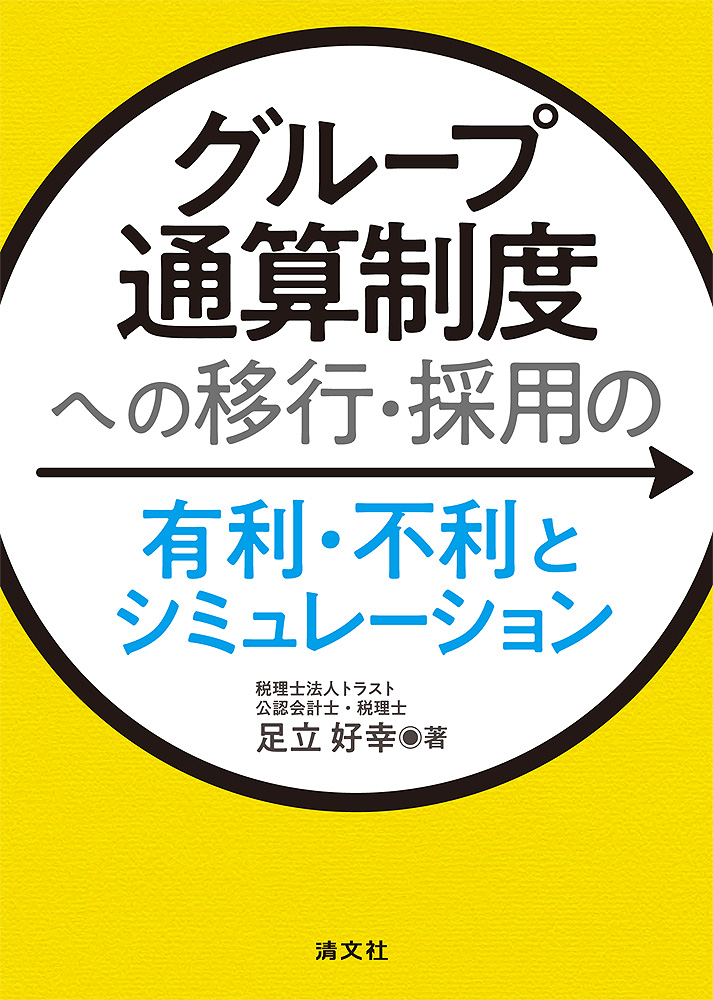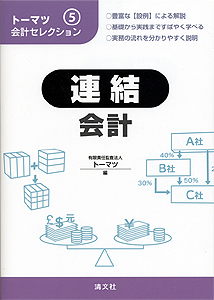連結会計を学ぶ
【第6回】
「連結の範囲に関する重要性の原則」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
連結財務諸表の作成において、親会社は、すべての子会社を連結の範囲に含めることが原則である(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)13項)。
ただし、連結会計基準は、重要性の原則を規定しており、子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができるとしている(連結会計基準注1、注3)。
今回は、連結の範囲に関する重要性の原則について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 連結の範囲の重要性の原則に関する監査上の取扱い
連結の範囲の重要性の原則に関する監査上の取扱いについては、「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等に係る監査上の取扱い」(監査・保証実務委員会実務指針第52号。以下「実務指針52号」という)が公表されている。
1 基本的な考え方
連結の範囲に係る重要性の判断としては、通常、該当要件の影響割合が所定の基準値より低くなれば、それで重要性は乏しいと判断されるものである(実務指針52号3項)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。