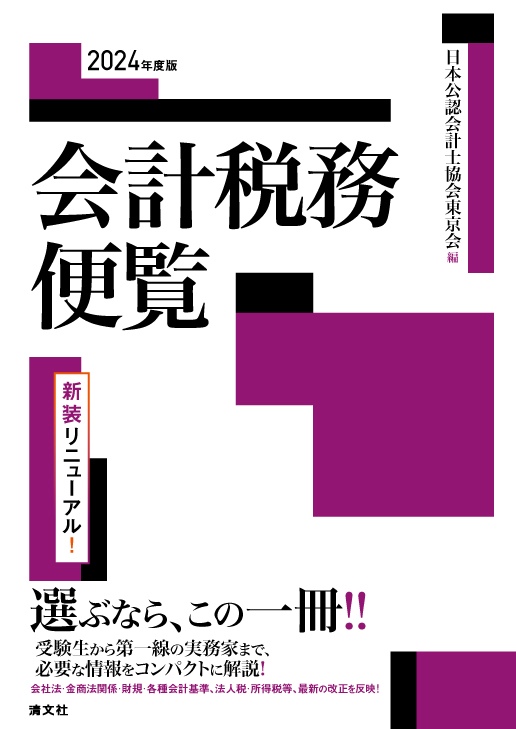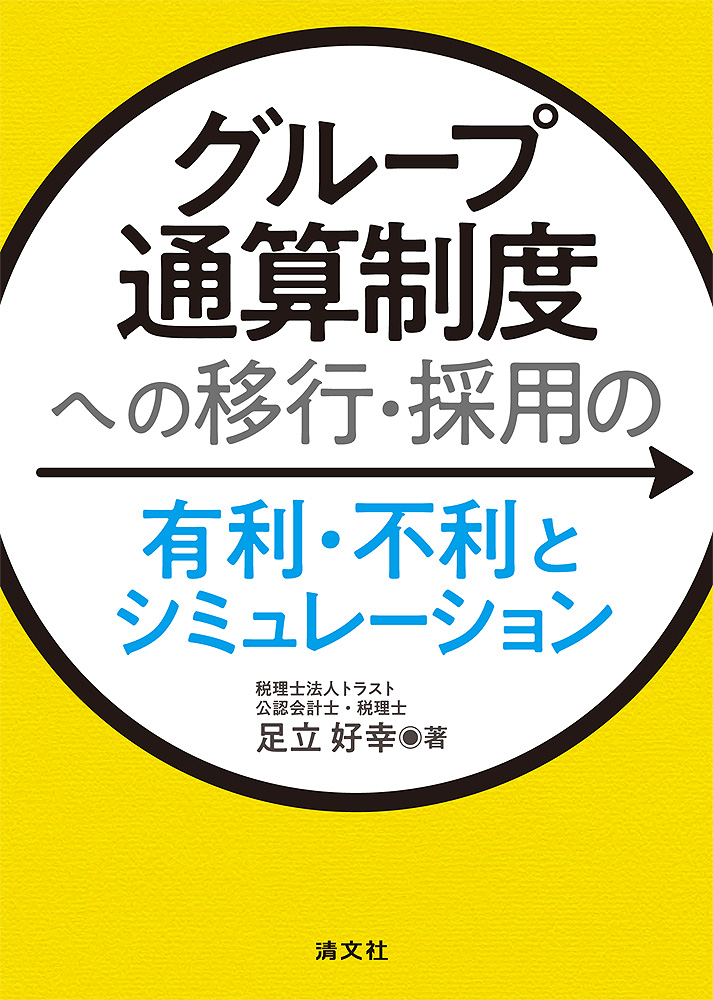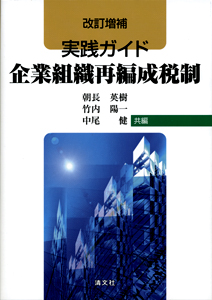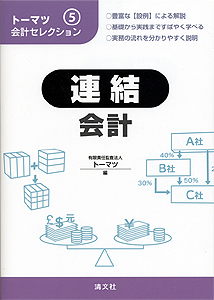連結会計を学ぶ
【第11回】
「のれんと負ののれんの会計処理」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
資本連結では、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本は相殺消去され、消去差額が生じた場合には当該差額をのれん又は負ののれんとして会計処理することになる(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)24項、59項)。
今回は、のれん及び負ののれんの会計処理について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 投資と資本の相殺消去
支配獲得時における資本連結の手続には次のものがある(「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号。以下「資本連結実務指針」という)3項)。
① 子会社の資産及び負債の評価
② 親会社の投資と子会社の資本との相殺消去
③ のれんの計上
④ 非支配株主持分の計上
なお、連結貸借対照表の作成に関する会計処理における企業結合及び事業分離等に関する事項のうち、連結会計基準に定めのない事項については、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号。以下「企業結合会計基準」という)や「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号)の定めに従って会計処理する(連結会計基準19項、資本連結実務指針7-2項)。
1 基本的な考え方
投資と資本の相殺消去に際して、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本が同額の場合には、差額が生じず、のれん又は負ののれんは計上されない。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。