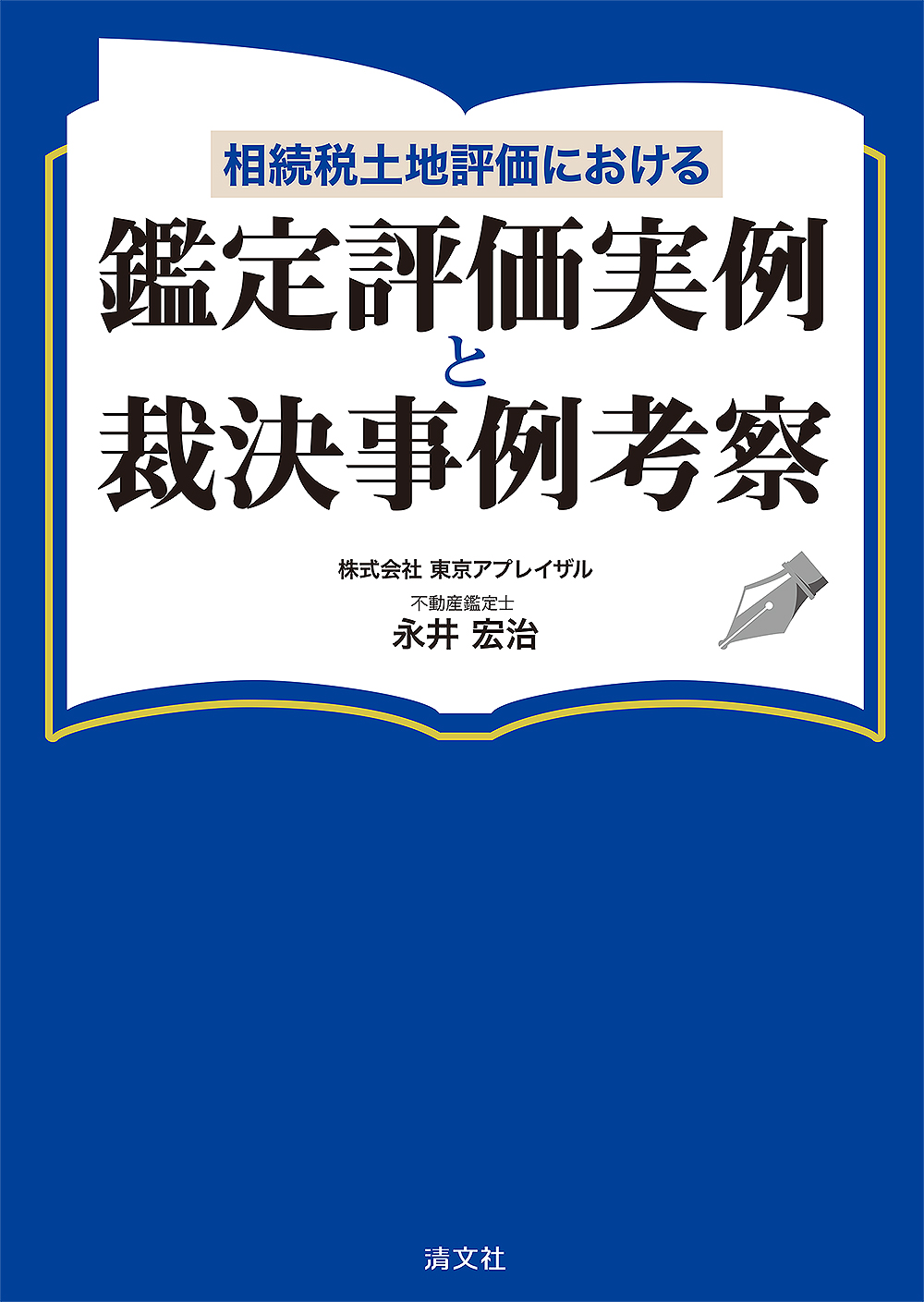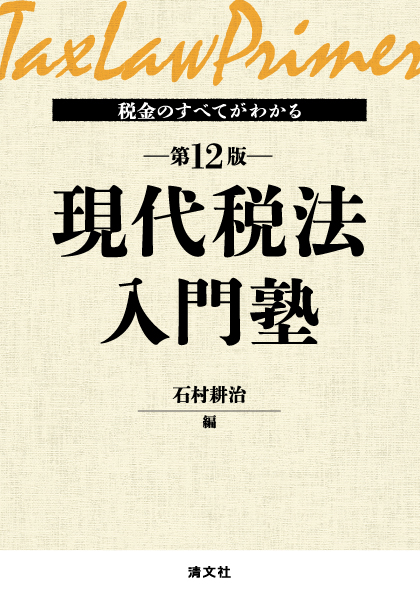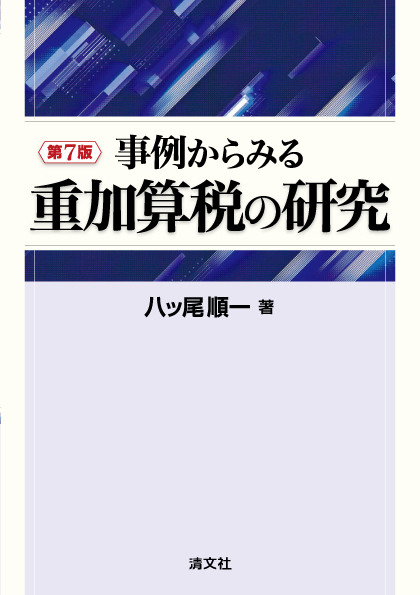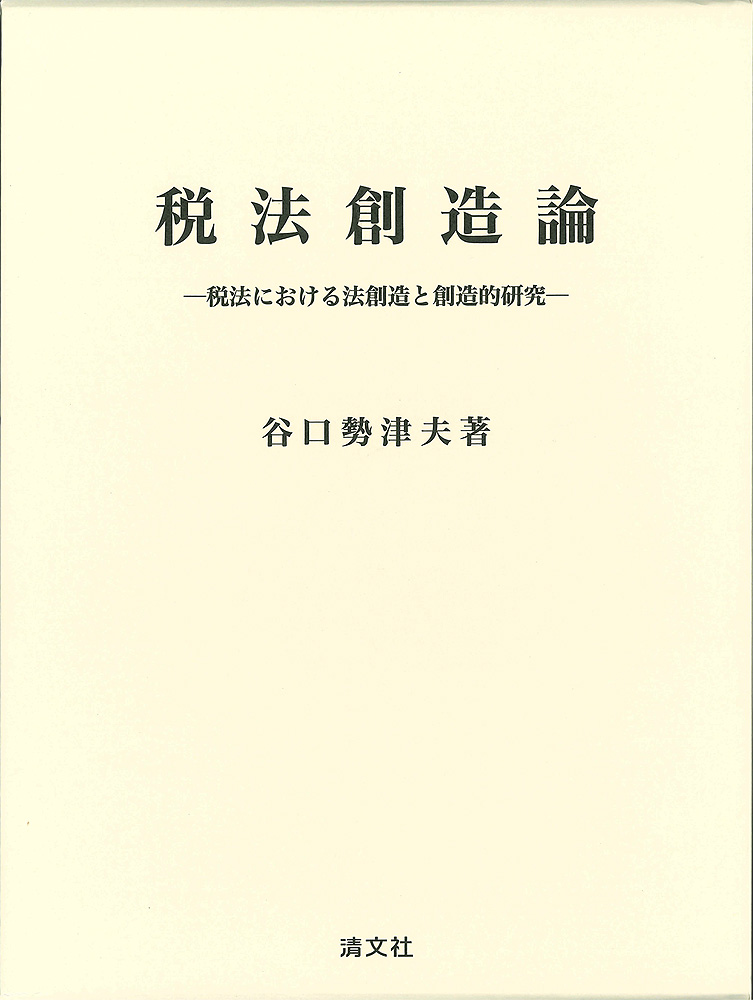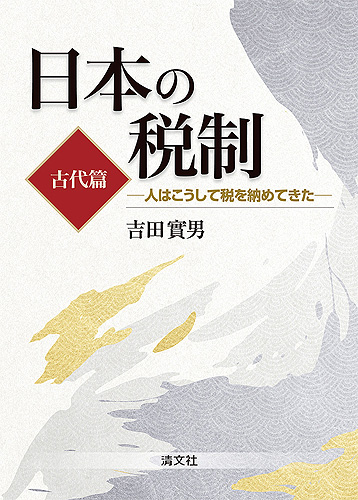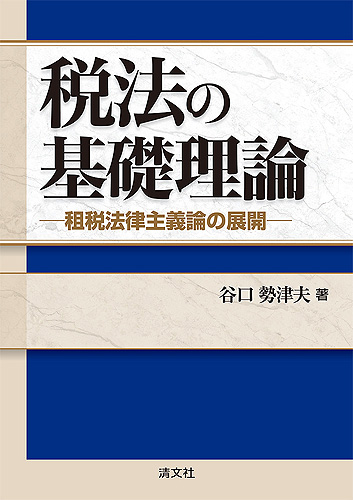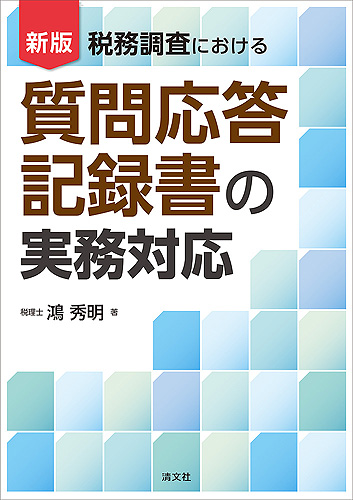酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第34回】
「公正処理基準の形成過程と税務通達(その1)」
中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦
法人税法は、益金に算入する金額や損金に算入する金額の計算について、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(以下「公正処理基準」ともいう。)に従うこととしている(法法22④。企業会計準拠主義)。
法人税法22条《各事業年度の所得の金額の計算》
内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4 第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。〔下線筆者〕
こうした法人税法の構造がいかなる意味を持つのかを解明することは、同法を理解するにあたり極めて重要な意味を有するといえるだろう。
他方、この企業会計準拠主義が租税法律主義に反するのではないのかという問題も従来から議論されてきた。
もっとも、この点は、商法(会社法)にいう「一般に公正妥当と認められる(企業)会計の慣行」に準拠したものであると考えれば、租税法律主義に反するものではないといえるだろう。すなわち、法人税法は商法(会社法)に準拠しているのであって、その商法(会社法)が企業会計に委任をしているとの理解である。法人税法22条4項は企業会計に白紙委任をしたものではなく法的根拠を有する基準であると論じることができるだろう(中里実「租税法と企業会計(商法会計学)」商事1432号26頁)。
しかし、それでも、企業会計準拠主義には租税法律主義を脅かす問題が伏在しているのではないだろうか。以下では、この点について、組合課税における通達の機能と商法(会社法)における「一般に公正妥当と認められる(企業)会計の慣行」を素材として、これまでの議論とはやや異なる角度から検討を加えてみたい。
Ⅰ 問題点の所在
企業会計準拠主義を採用する法人税法22条4項における公正処理基準にかかる問題点について以下の2点に着目してみたい(金子宏『租税法〔第20版〕』318頁参照(弘文堂2015))。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。