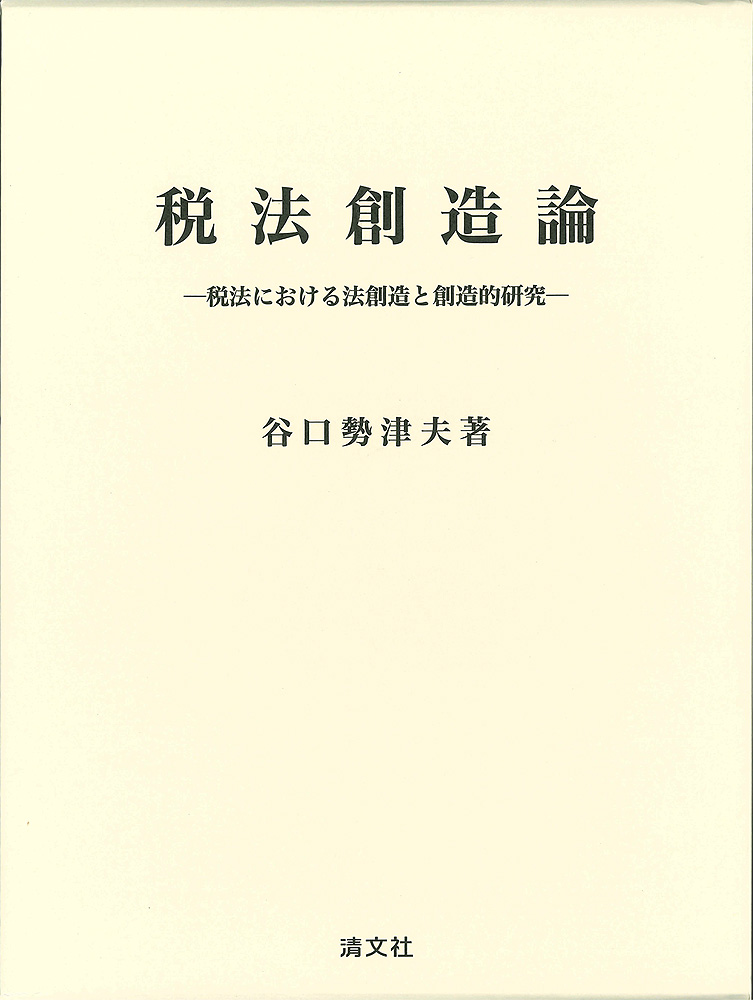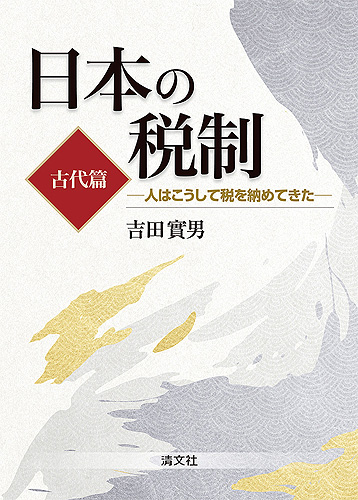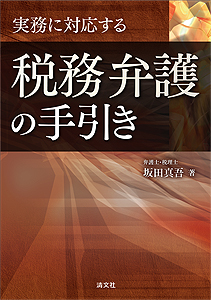酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第76回】
「日本標準産業分類から読み解く租税法解釈(その1)」
中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦
はじめに
統計が租税法の解釈適用において重要な意味をもつことがあるという点については、既に、この連載においても解説したところである(「統計数値が租税法解釈に与える影響(その1〜3)」【第67回】~【第69回】)。
統計はしばしば産業を分類した上で分析がなされるが、そこで使われる産業の分類が「日本標準産業分類」(JSIC)である。
租税法においては、産業ごとに課税上の取扱いを異にすることがあり、この日本標準産業分類は、個別税法の解釈等の局面においてもたびたび顔を出す。そこで、今回は、日本標準産業分類が租税法の解釈に及ぼす影響について考えてみたい。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。