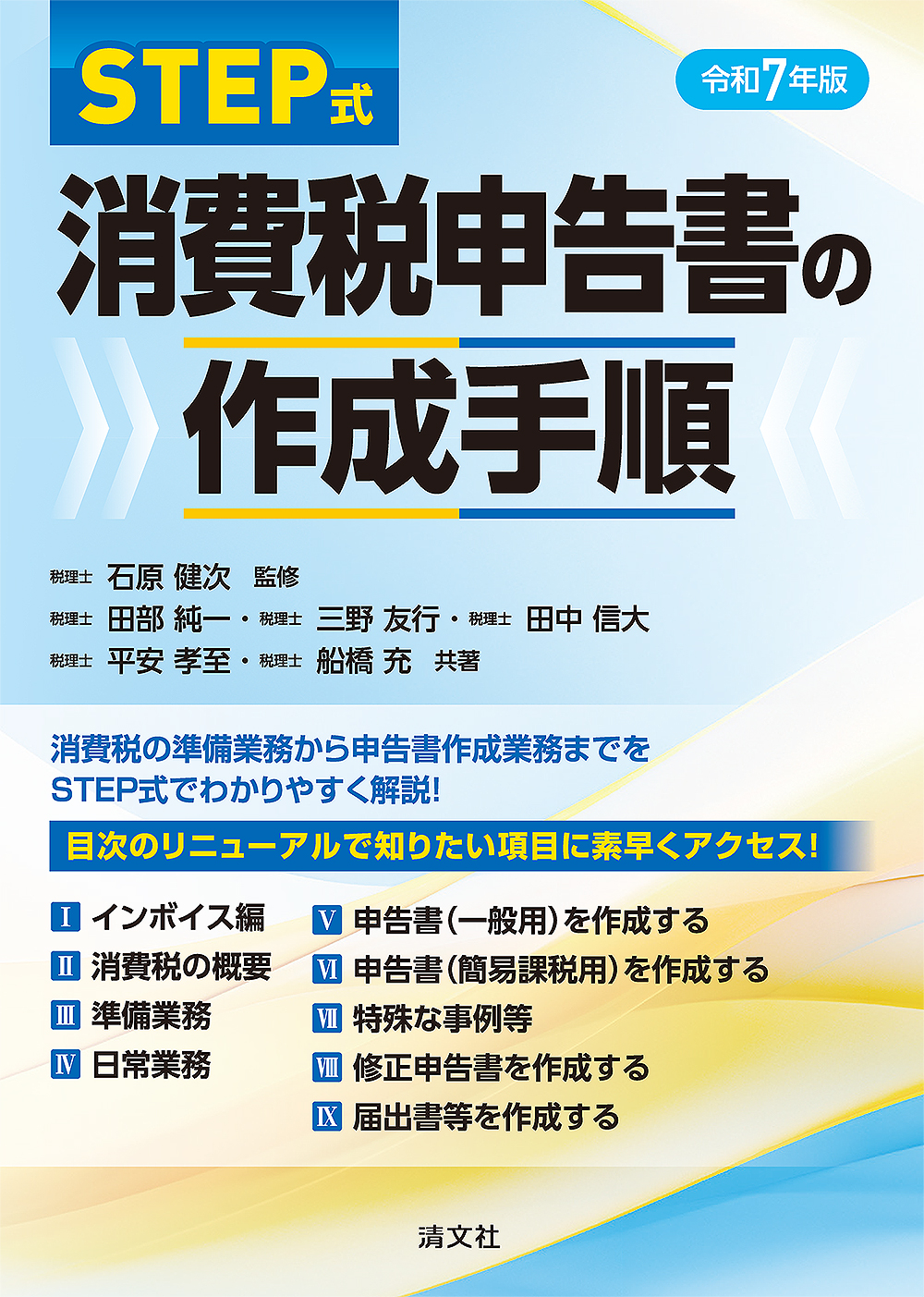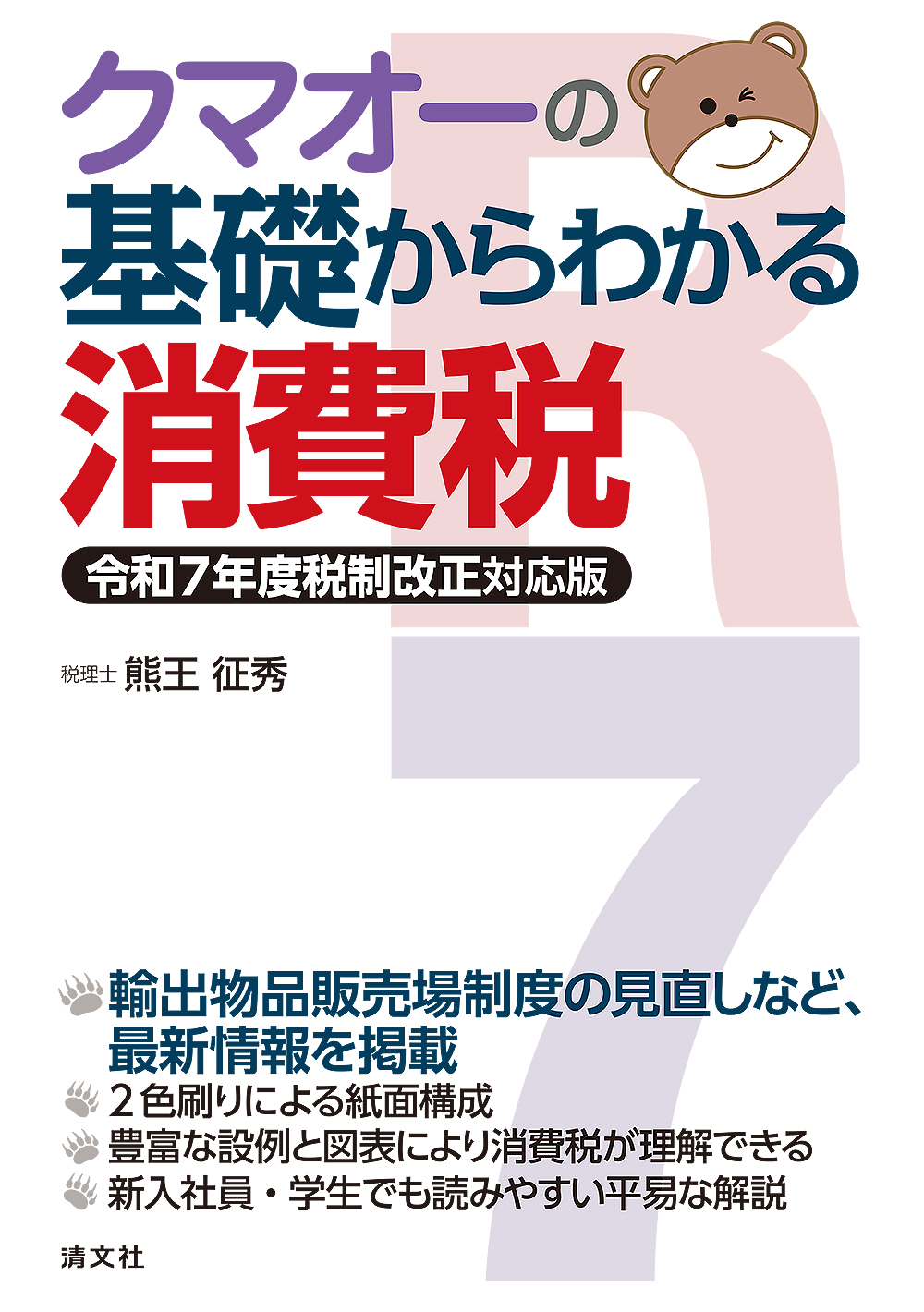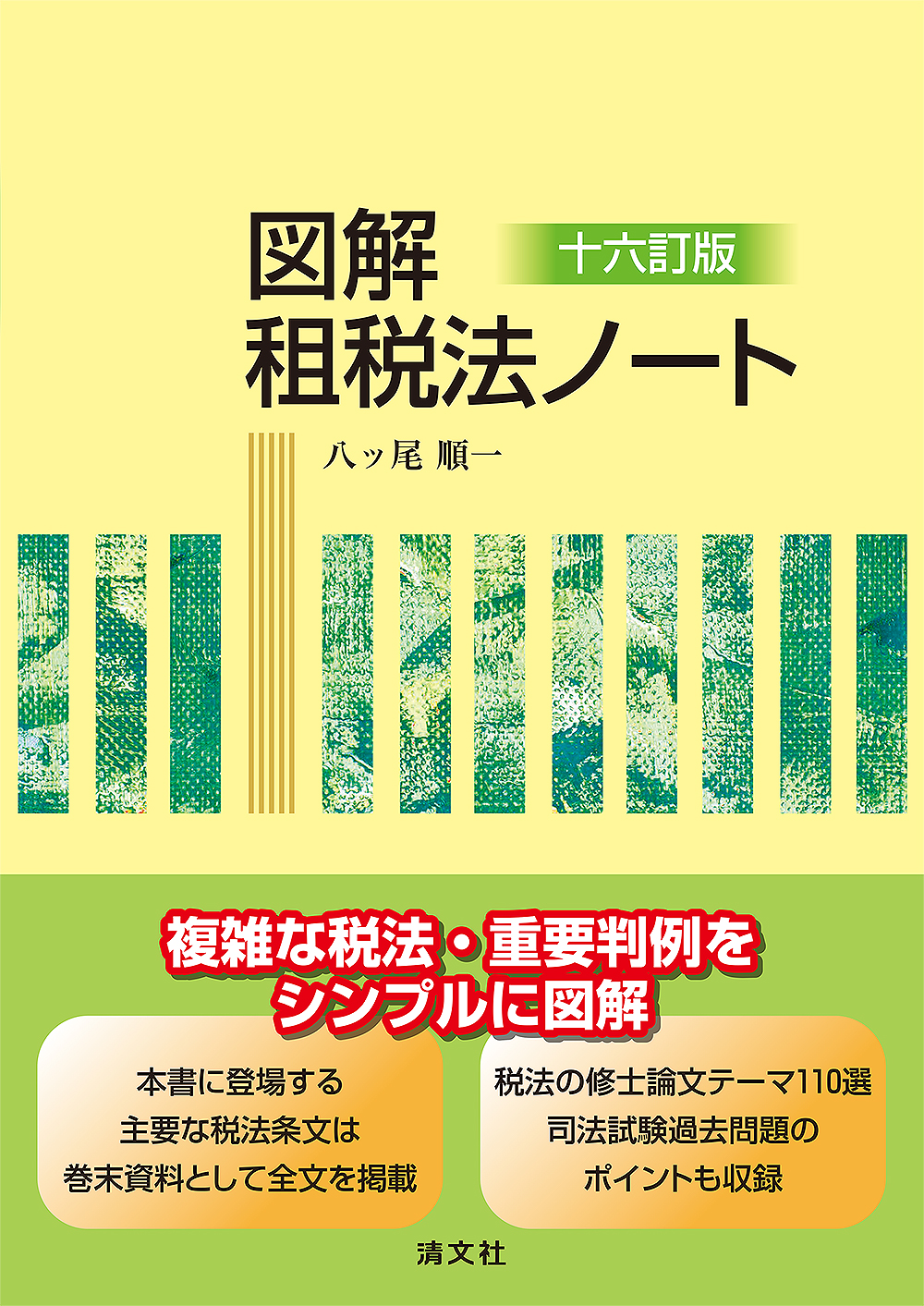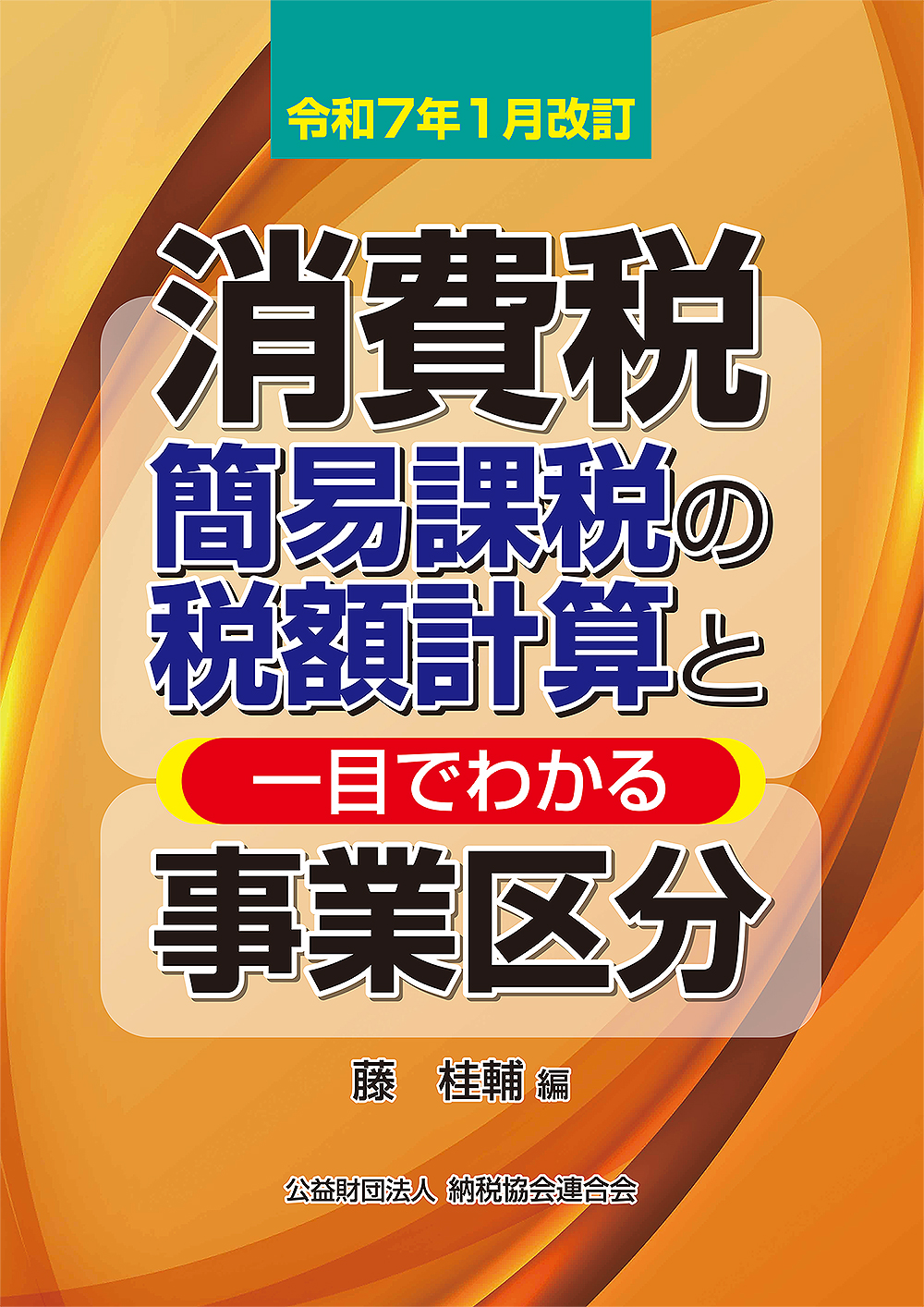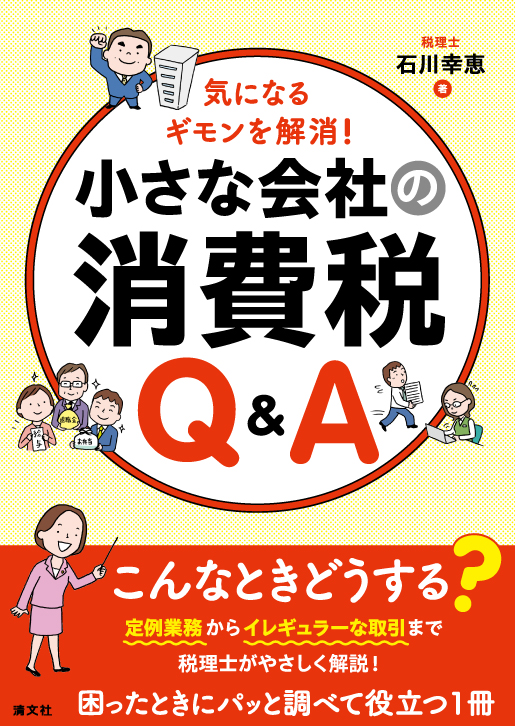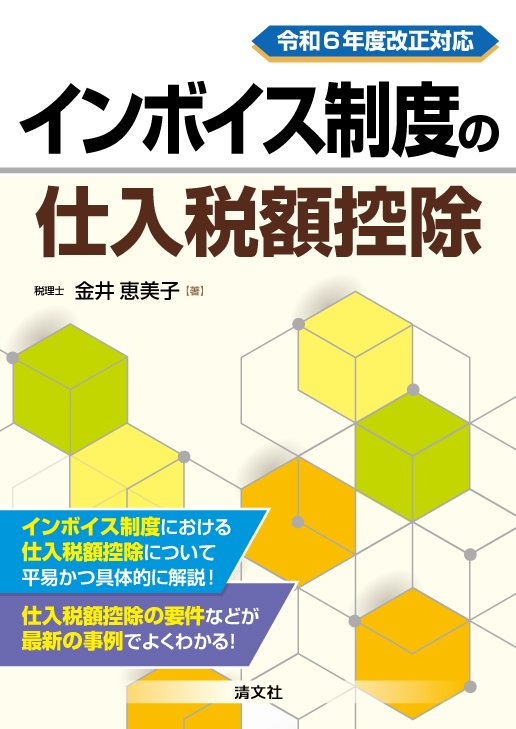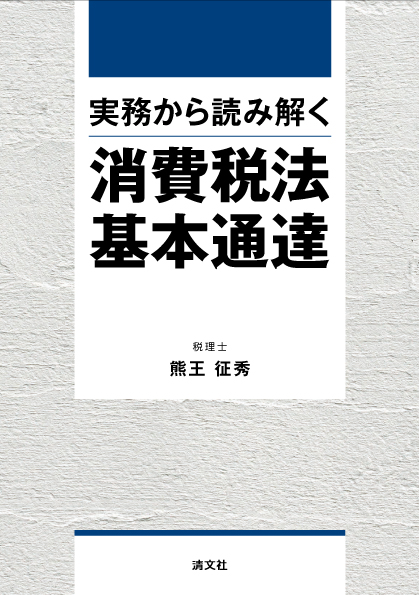酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第137回】
「消費税法における「課税仕入れの日」(その1)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
はじめに
消費税が「消費」に対する課税であるとするならば、消費の段階で課税がなされるべきことになろう。例えば、消費者が商品(アイスクリーム)を購入したとすると、それを食べた時に課税がなされるべきであるように思われる。
しかしながら、実際問題として、消費者がアイスクリームを購入してそれを持ち帰ったとしても、自宅の冷蔵庫の中に入れっぱなしにして賞味期限が切れてしまってゴミ箱行きになるかもしれないし、そもそも、購入してお店から出た時に袋の開け方をミスして中身が地面に落ちてしまって食べることができなくなってしまうかもしれない。
「消費」を食べることと理解するとすれば、結局上記の場合には消費はなされなかったということになるし、そもそも、口に入ることを消費というのではなく、胃の中で消化・吸収されたときに初めて消費というのかもしれない。もっとも、持ち帰ったことや冷蔵庫に入れたことや、ごみ箱行きになったことをもって「消費」という理解もあり得るが、いずれにしても、持ち帰ったタイミングや冷蔵庫に入れたタイミング、ごみ箱行きになったタイミング、胃の中で消化・吸収されたタイミングはどう捉えればよいのであろうか。例えば、商品は買ったものの、持ち帰るのを忘れて店内に置いてきてしまった場合はどのように考えるべきなのであろうか。さらにいえば、購入したことが既に「消費」であるという考え方はあり得るであろうか。
しかし、一般的にいえば支出は消費のために行われるのであるから、支出=消費と考えて、支出時に課税するというのは難しそうである。本当に消費に対する課税というのであれば、消費税法においても、いわば減価償却のような購入資産の効用に応じた課税が観念されてしかるべきである。むしろ、より現金主義に接近した考え方を消費税法は採用しているように思われる。
消費課税ではなく、消費支出課税であると捉えることもできそうであるが、そうであるとすると、「支出」に関心を寄せることになるが、支出というものが現金主義的なものとなると未払いや掛けによる購入の場合には支出のタイミングが遅れることになろう。そのような際には、即時払い決済の取引よりも課税のタイミングが遅れるということで問題ないのであろうか。
いずれにしても、消費税とはどうも「消費」のタイミングで課税されているようではなさそうである。単に、代金を支払ったときをいうのであろうか、あるいは商品なりの引渡しを受けたときをいうのであろうか。売買契約締結の日をもって、消費税の課税のタイミングを考えるべきなのであろうか。
他方、消費税額の計算において、税の累積を排除するために仕入税額控除が設けられているが、かかる税額控除のタイミングが議論されることもある。
そこで、これら消費税法におけるタイミングの問題を考えることとしたい。
まずは、仕入税額控除のタイミングの問題が争点となった事例(大阪地裁令和2年3月11日判決(税資270号順号13393)及びその控訴審大阪高裁令和2年11月26日判決(税資270号順号13485))を素材として、これらの論点に踏み込んでいくこととしよう。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。