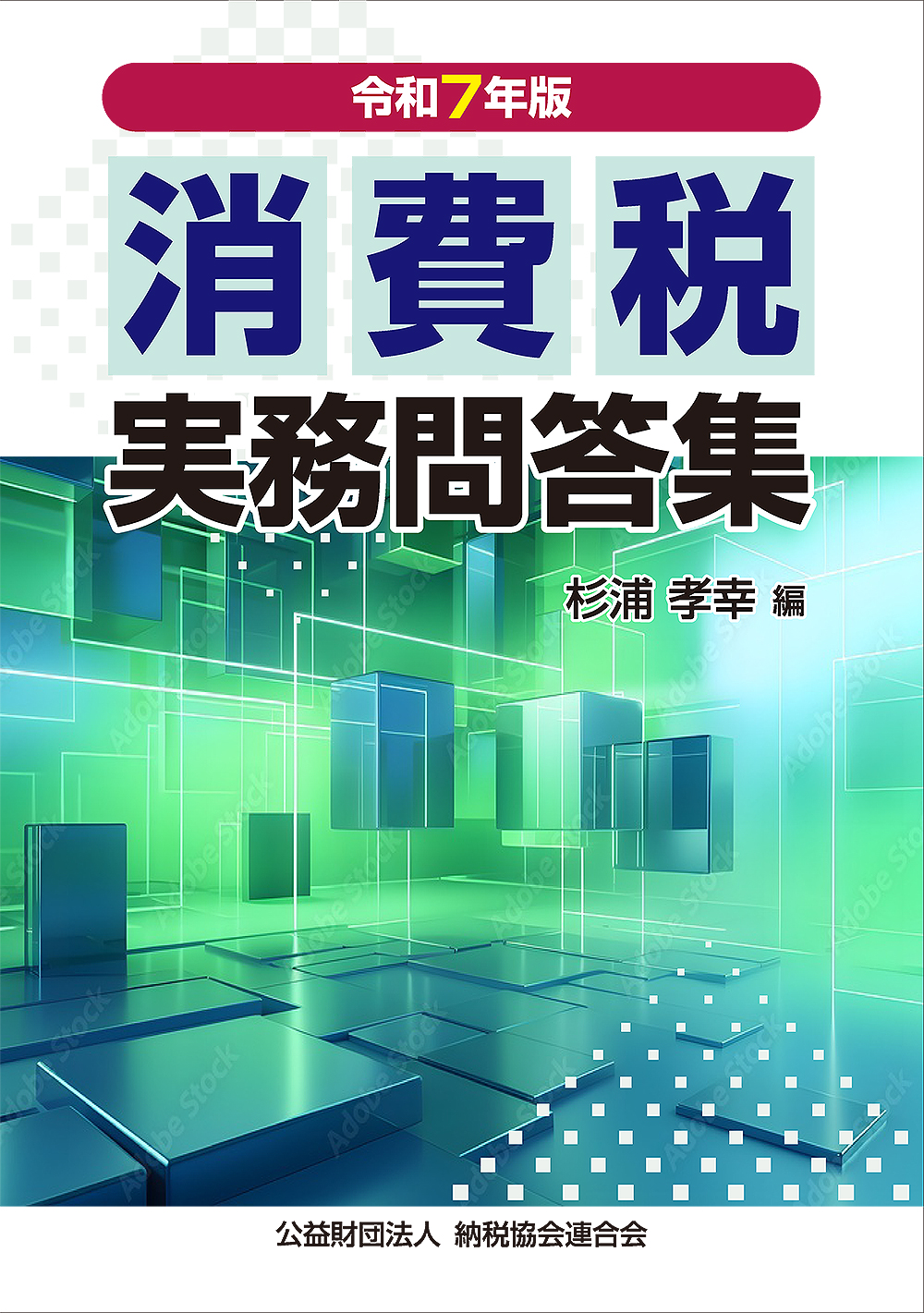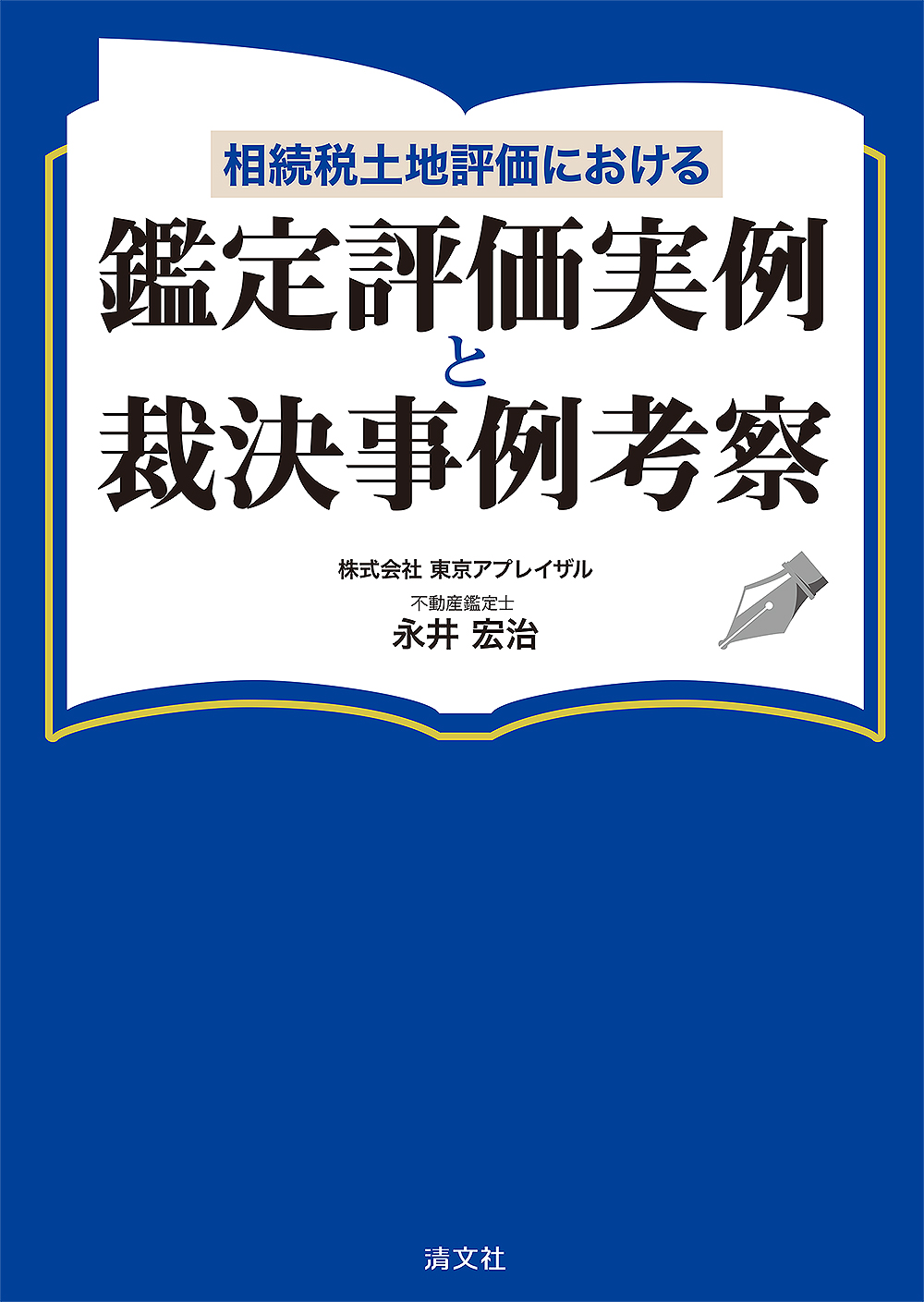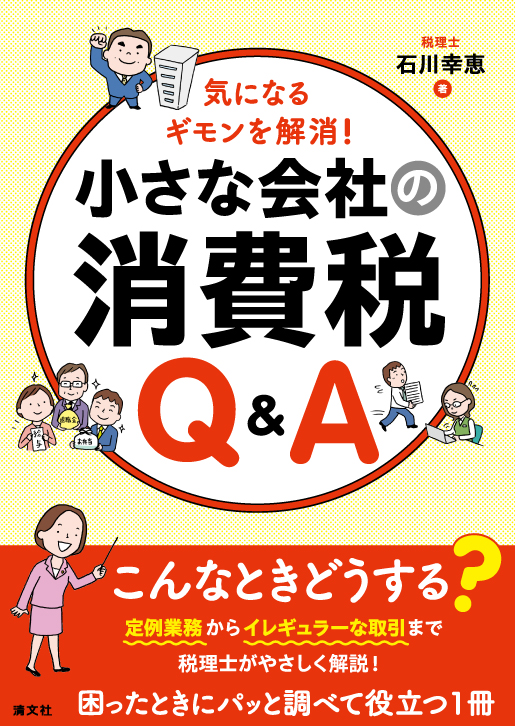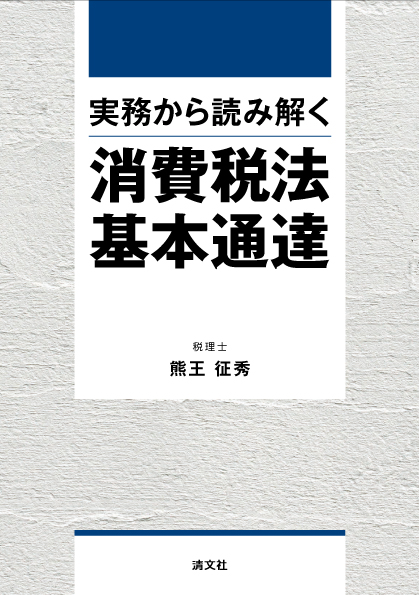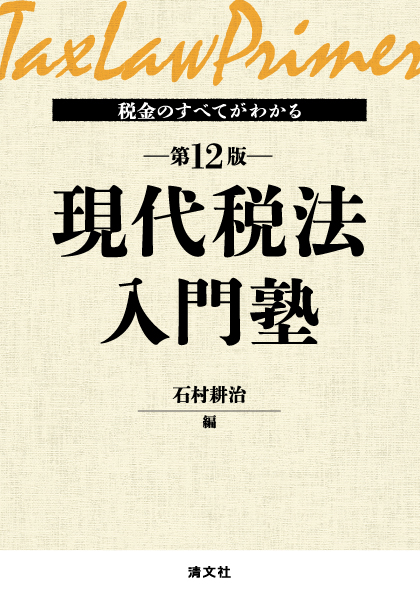酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第26回】
「消費税法上の「事業」と所得税法上の「事業」(その2)」
~租税法内部における同一概念の解釈~
中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦
Ⅳ 解説
1 消費税法上の「事業」の定義
本件事案においては、消費税法上の「事業」の意義が争点とされた。
Yは、消費税法上の「事業」とは、「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう」とする消費税法基本通達5-1-1の考え方を示した上で、この定義からすれば、その判断に当たって事業の規模を問うものではないと主張した。
ここで、消費税法基本通達5-1-1をみることとする。
法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。
(注)
1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。
2 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、その全てが、「事業として」に該当する。
そして、Yは、
消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別消費税と異なり、消費者に広く薄く負担を求めるという観点から、金融取引あるいは資本取引などのほか、医療、福祉及び教育の一部を除き、ほとんどすべての国内取引や外国貨物を課税の対象として、事業者の負担ではなく、事業者の販売する物品やサービスの価格に上乗せ・転嫁されて、最終的には消費者に負担を求める税である。このことからすれば、納税義務者である事業者か否かを判断するに際して、その行う事業の規模の大小を問わないことは当然である。
という。
これに対して、Xは、Yの主張によれば、消費活動以外の反復、継続、独立した収入を得る活動は事業活動に該当することになり、
国民のほとんどが消費税法上の事業者に該当し、事業を行う個人として納税義務があることになるが、このような結果を導く主張は、消費税法全体の構成、趣旨目的に反する。
というのである。その上で、消費税法は、Yの主張するような、少額な収入まで全てを事業として取り込む趣旨で小規模事業者の納税義務の免除制度(限界控除制度)を設けたものではないという。
さらに、Yが引用する消費税法基本通達5-1-1については、限界控除制度廃止前に出されたものであるから、廃止後もこれと同様に解すべきではないと主張したのである。
2 消費税法上の「事業」と所得税法上の「事業」
(1) 所得税法と消費税法の基礎とする「担税力」の相違
担税力に応じた適正公平な課税の実現など、所得税法と消費税法に共通の趣旨を掲げたとしても、次に乗り越えなければならない問題がある。それは、「担税力」に対する所得税法と消費税法の視角の相違という壁である。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。