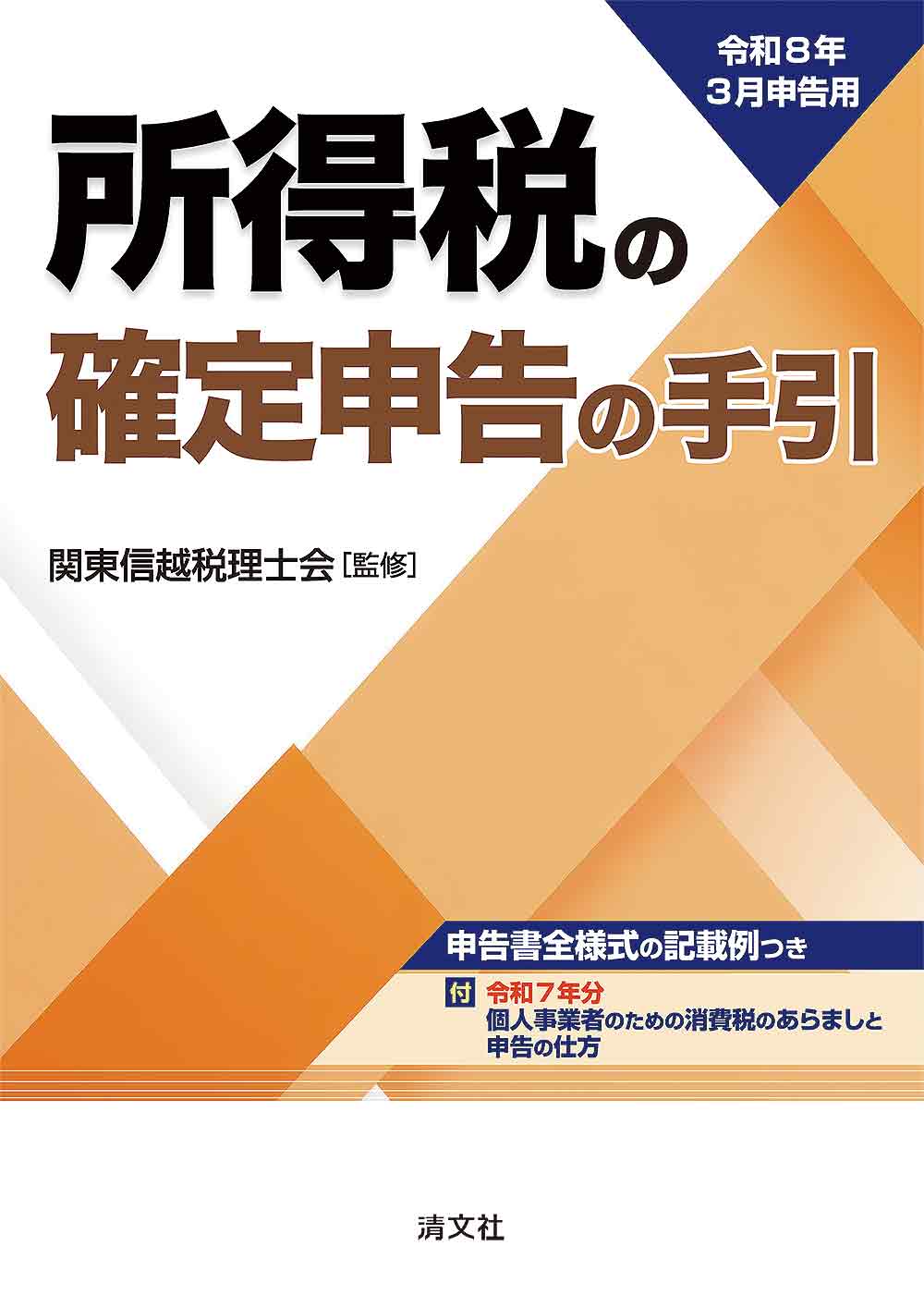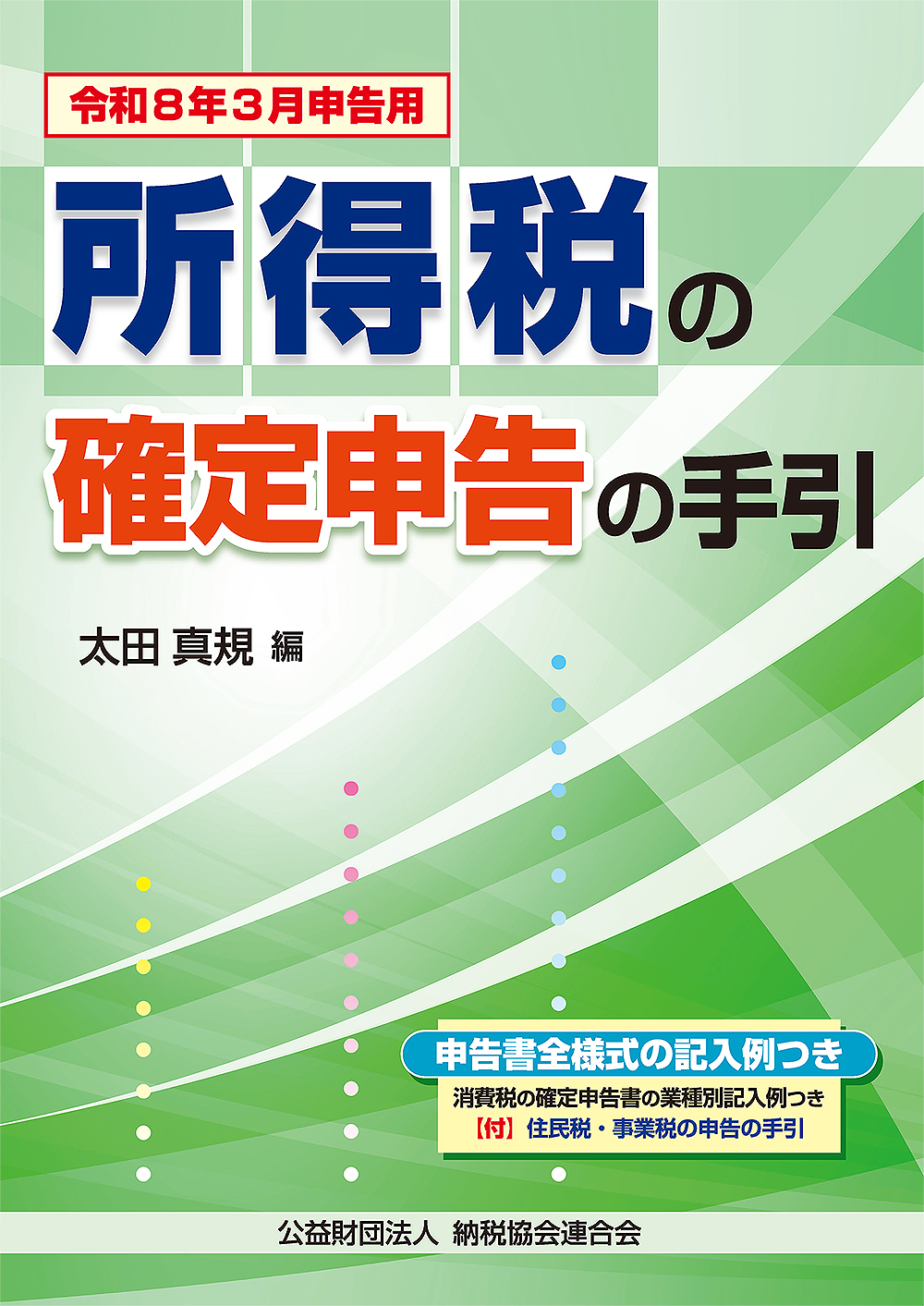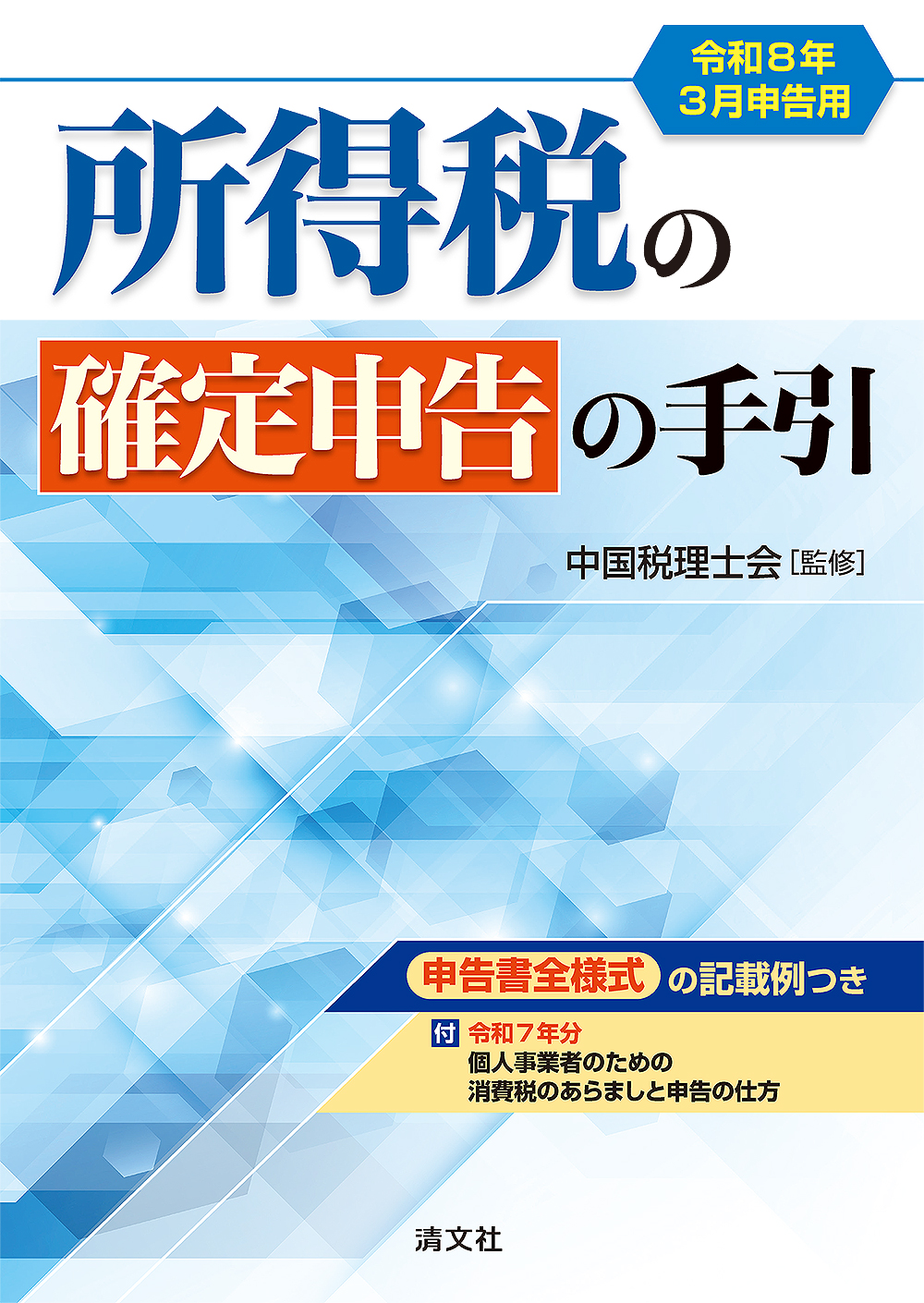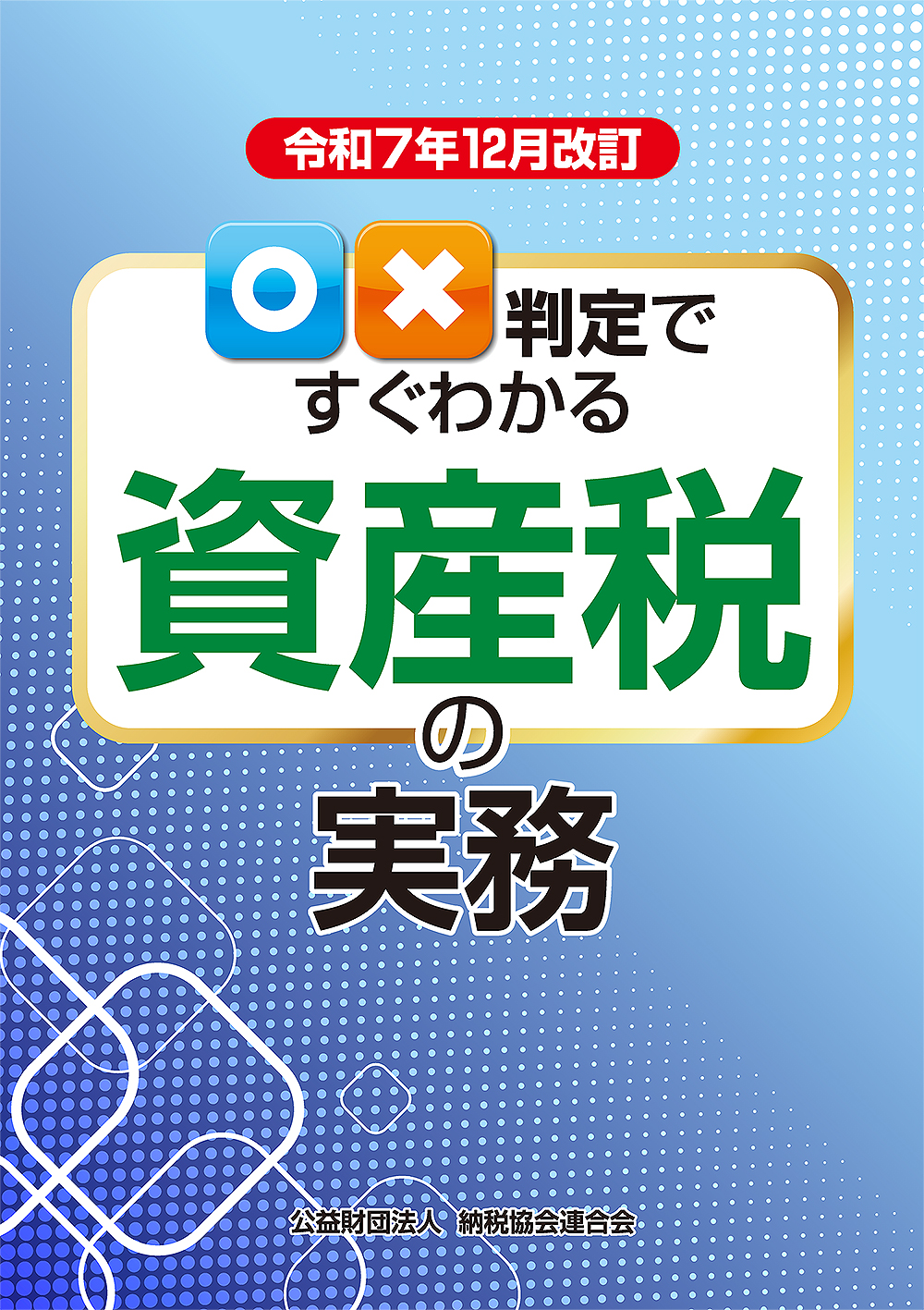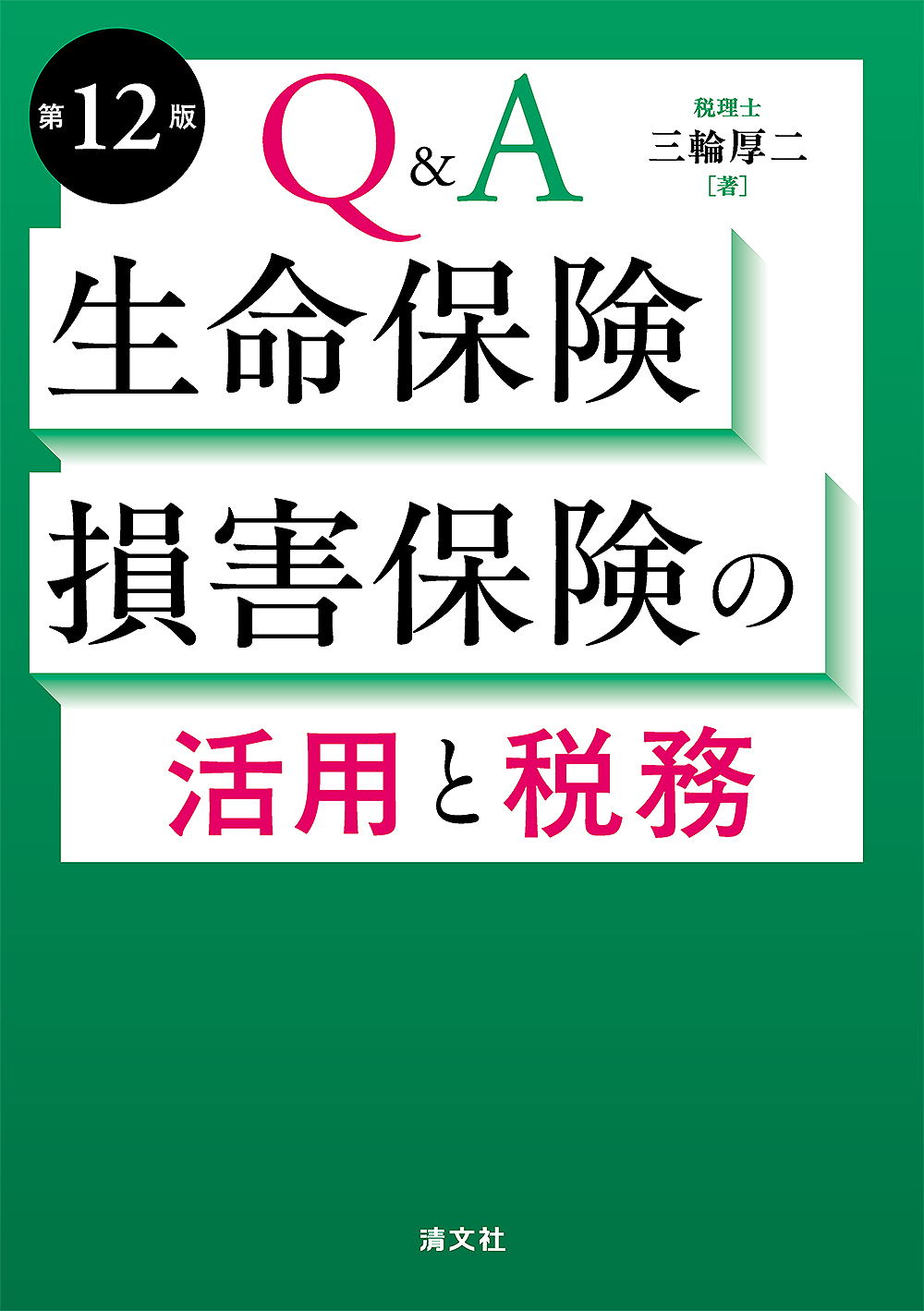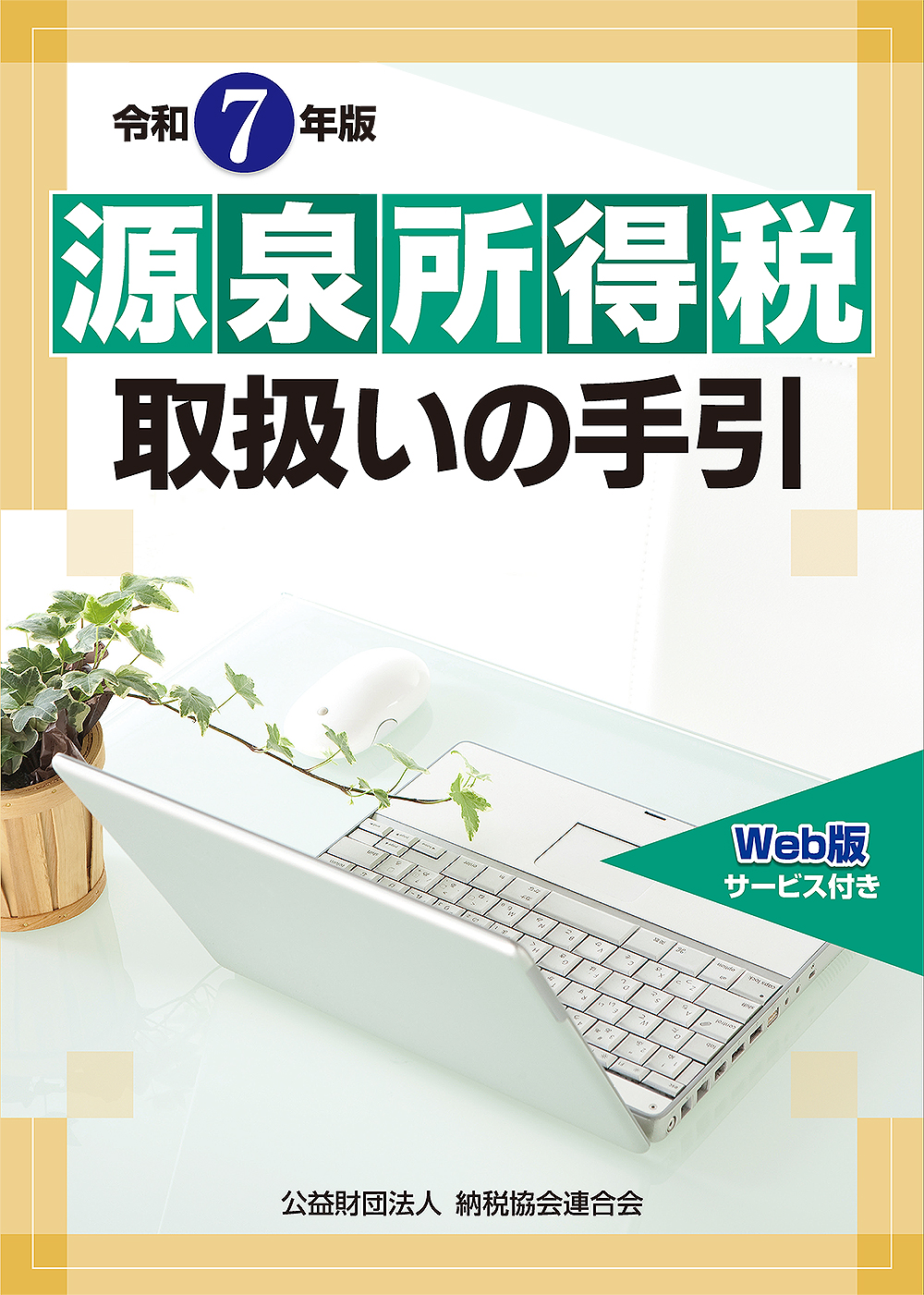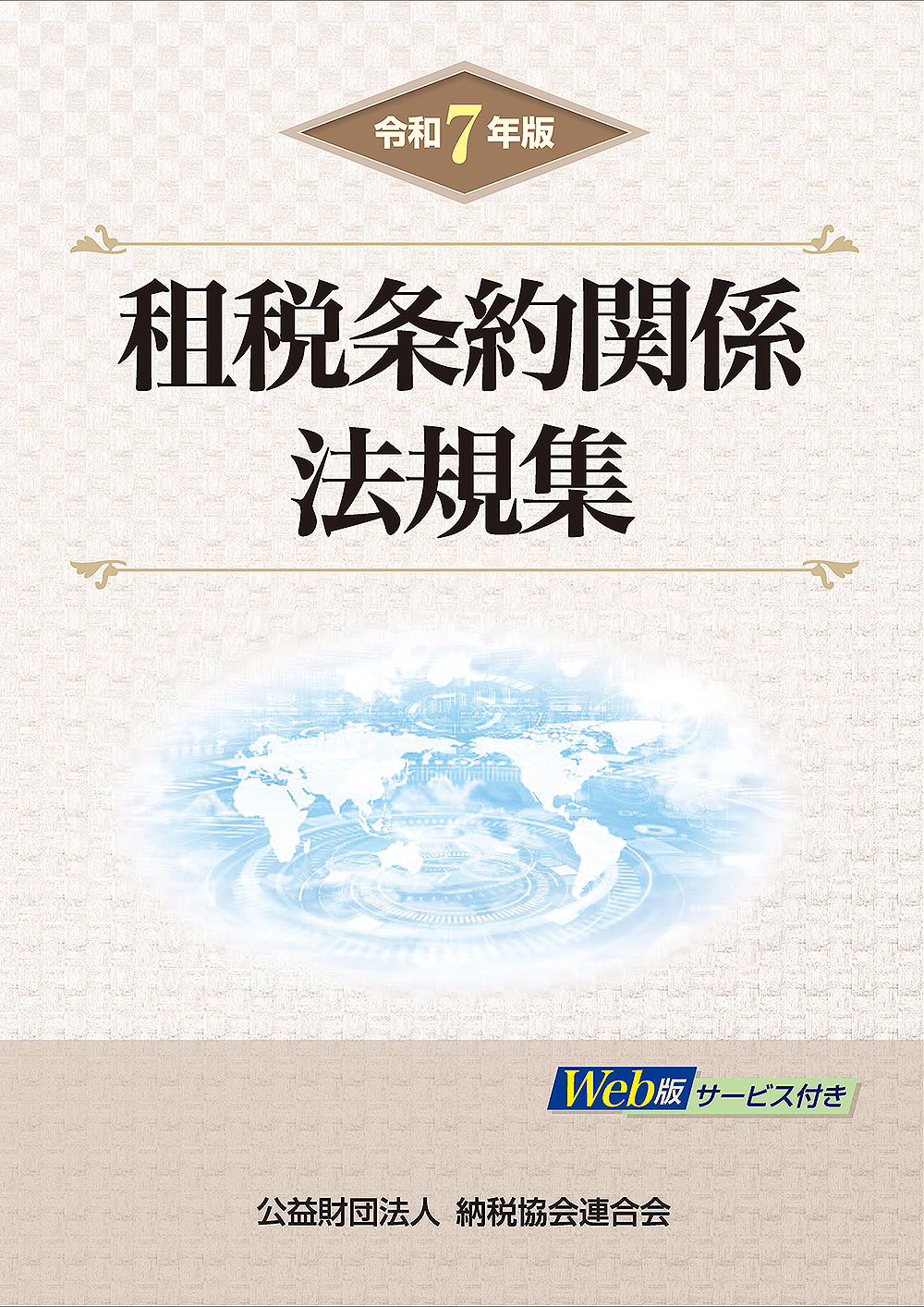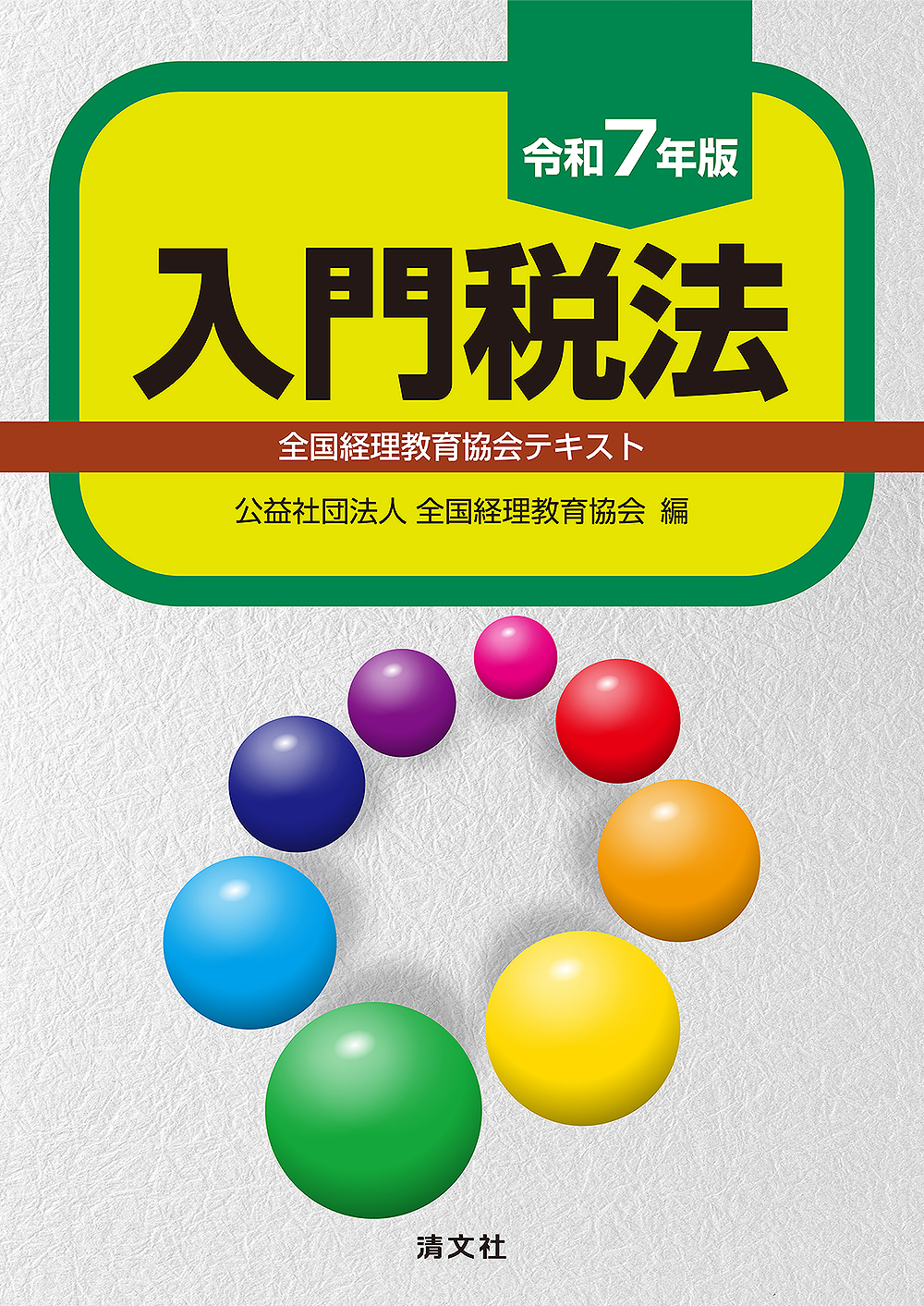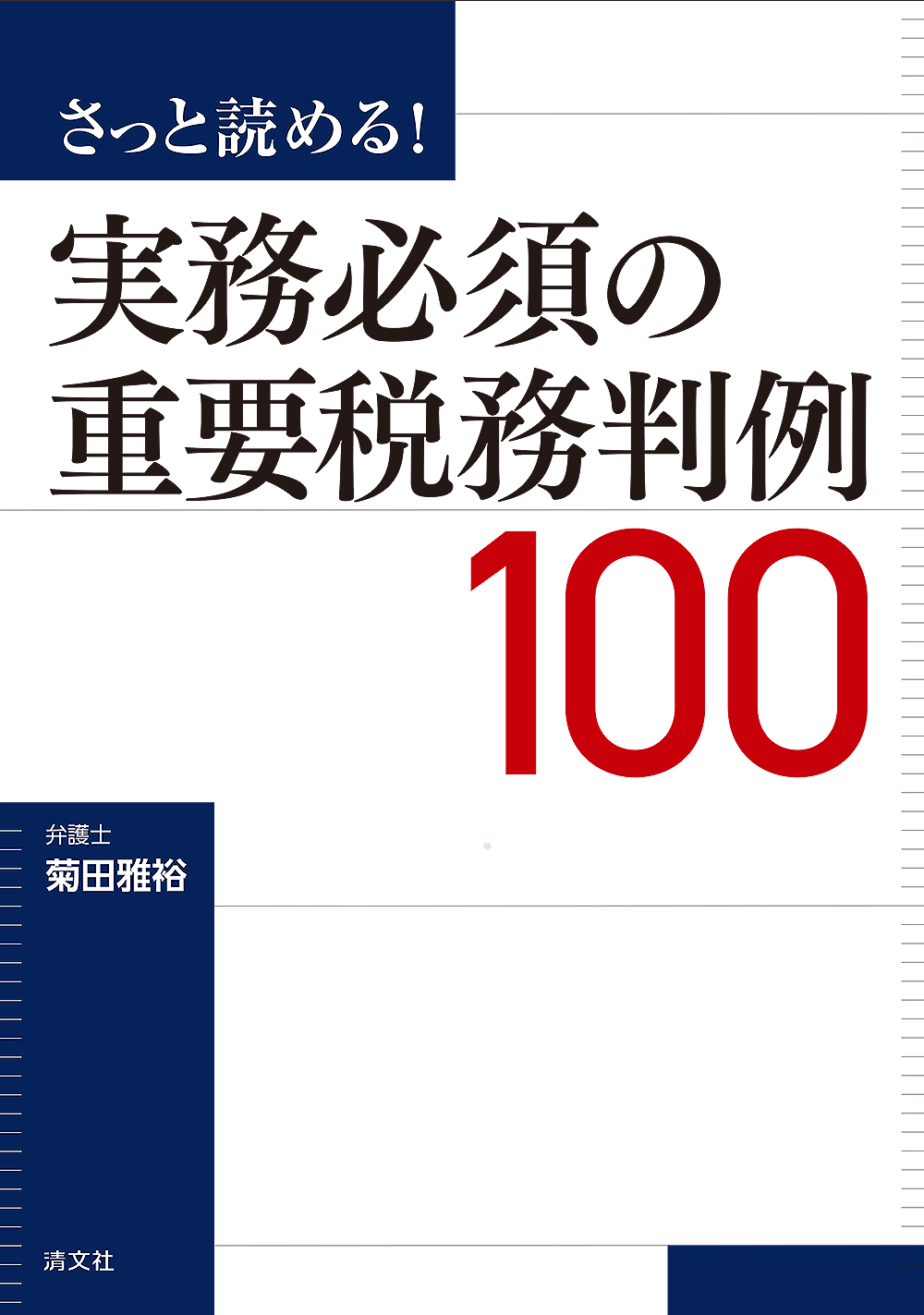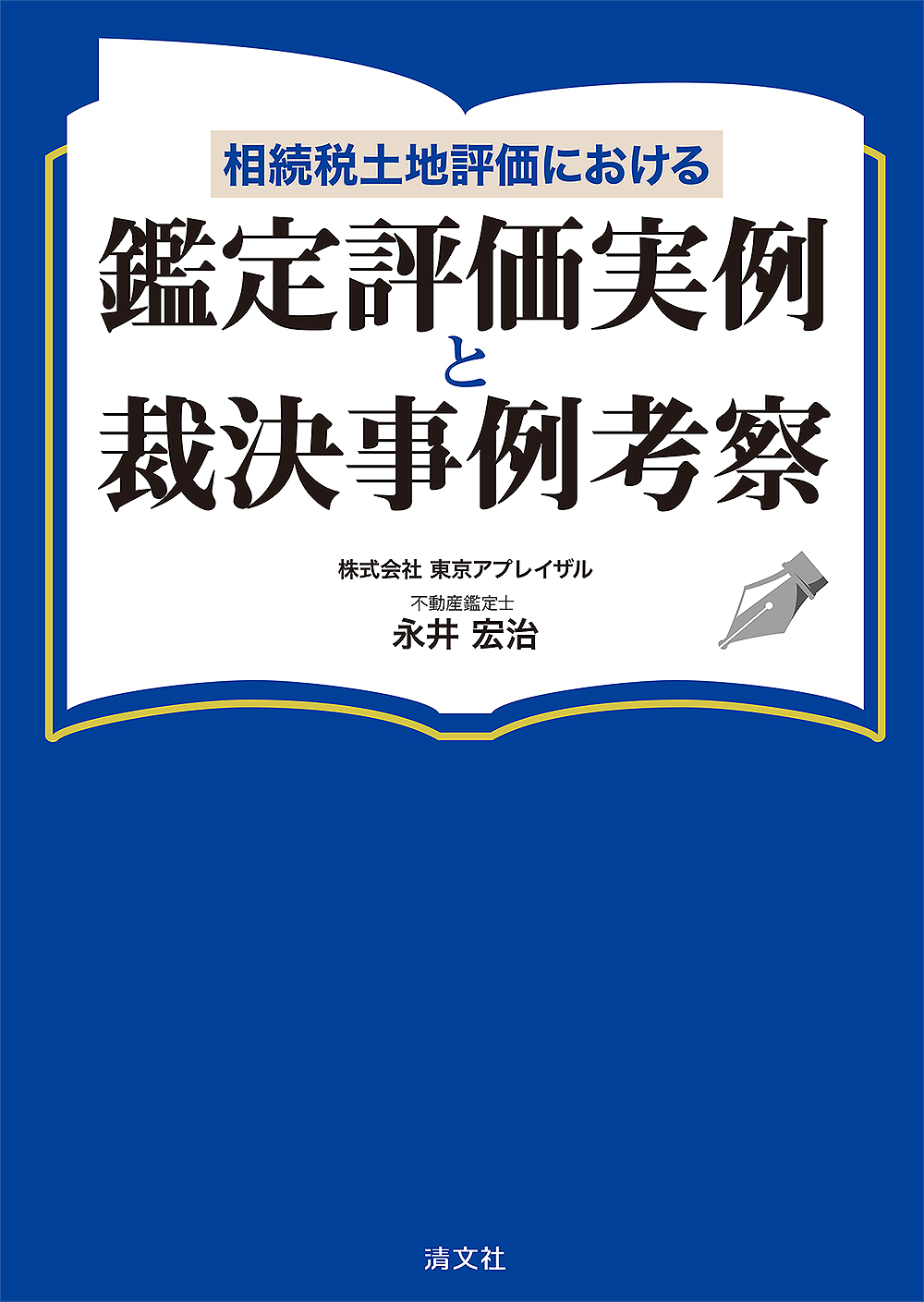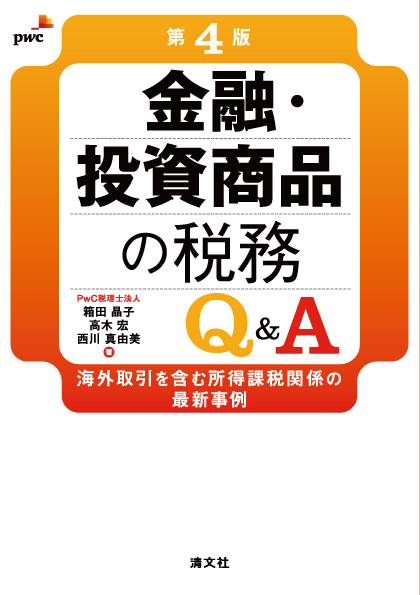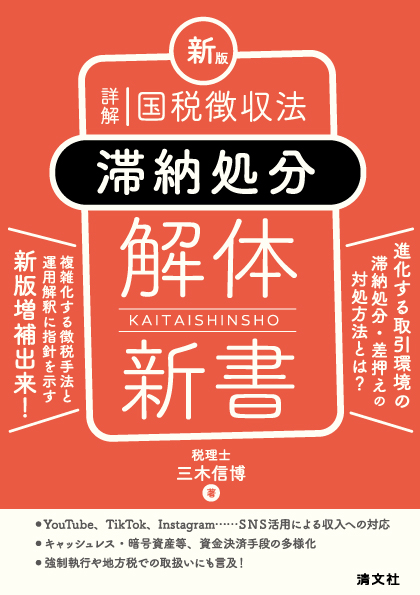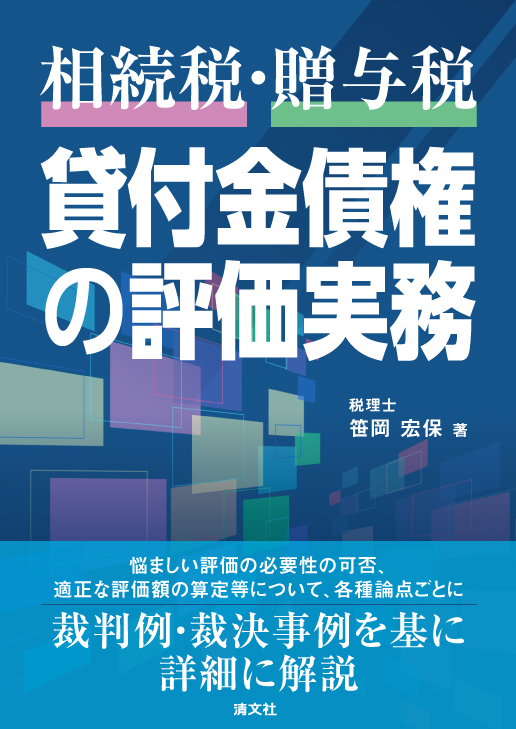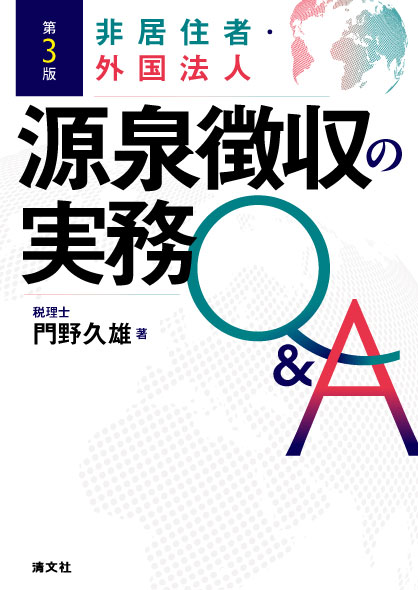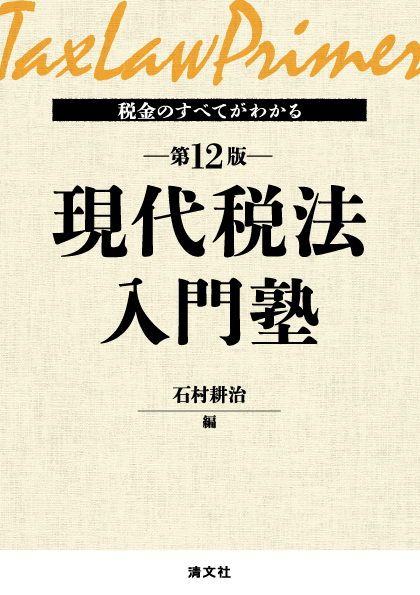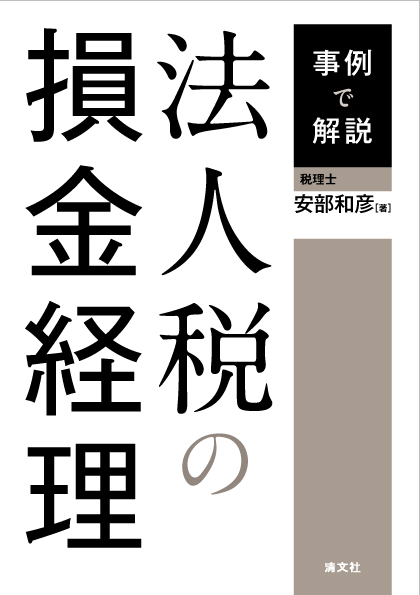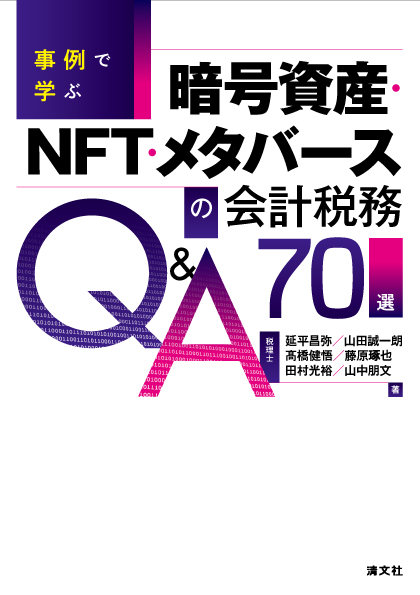酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第110回】
「節税商品取引を巡る法律問題(その4)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
《(その1)はこちら》
はじめに
Ⅰ 節税商品取引における「投資者保護」の必要性
1 一般的金融商品取引と投資者保護
2 節税商品取引と投資者保護
小括
《(その2)はこちら》
Ⅱ 節税商品取引を抽出する研究の試み
1 米国訴訟との比較による節税商品過誤訴訟の今後の趨勢
2 米国におけるタックスシェルター・マルプラクティス訴訟の状況
3 我が国の節税商品過誤訴訟の状況
4 節税商品取引を巡る環境の変化
5 タックスシェルター・マルプラクティス訴訟と節税商品過誤訴訟の相違点
《(その3)はこちら》
Ⅲ 節税商品の特殊構造と特有な説明義務の模索の必要性
1 節税商品の特殊構造
(1) 商品の二重構造性
(2) リスクの二重構造性
(3) 商品の新規性
2 説明内容の二重構造性
前回の1(1)のとおり、節税商品は二重構造性を有しており、融資契約を介在していることが多い。例えば、借入金を使って減価償却資産を購入し、支払利息の計上とキャッシュフローを伴わない減価償却費の計上を織り込むことで所得税や法人税を軽減する節税商品や、不動産が財産評価基本通達によって評価されることを前提として借入金を使って不動産を購入することで相続税を軽減させる節税商品などがそれである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。