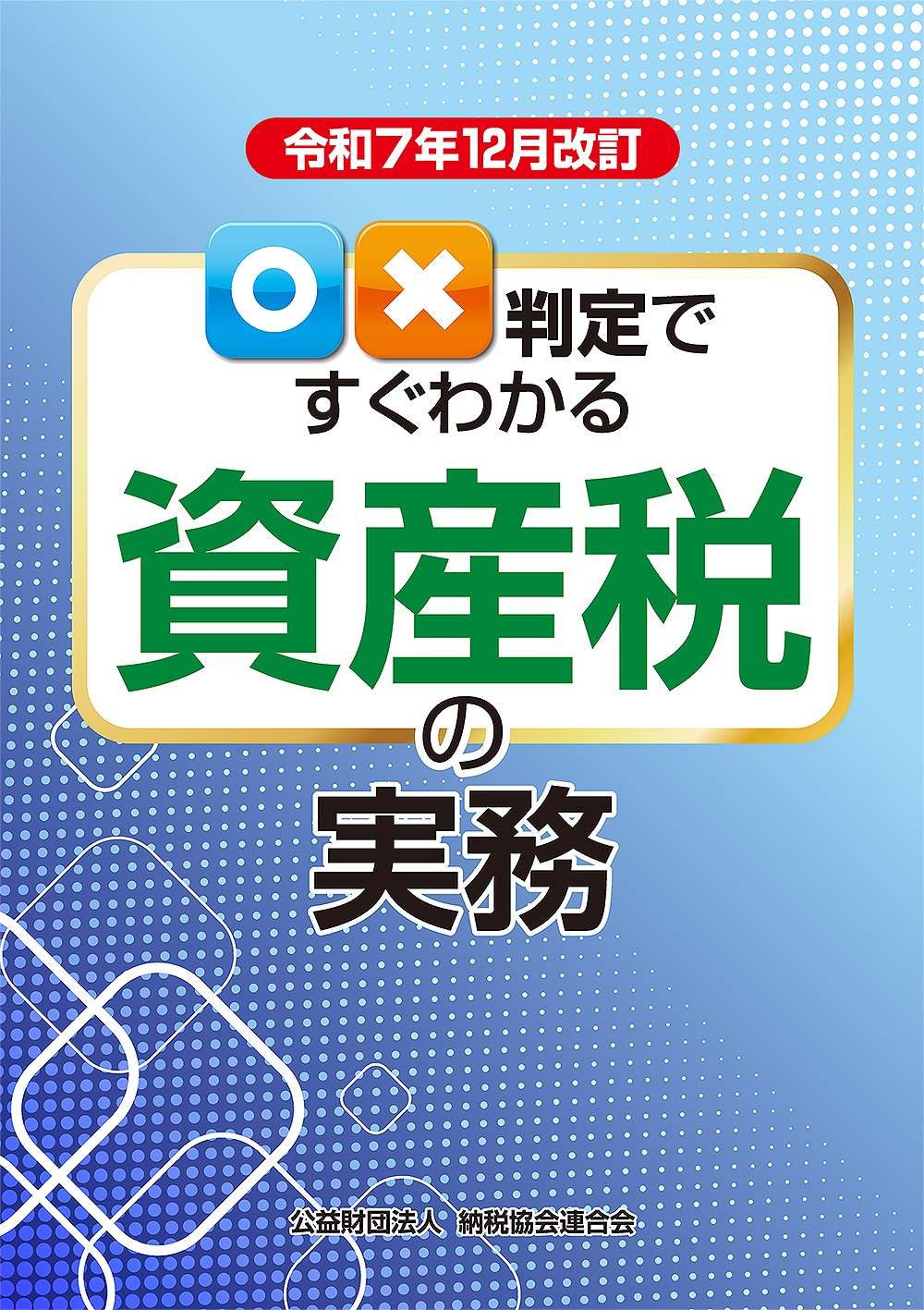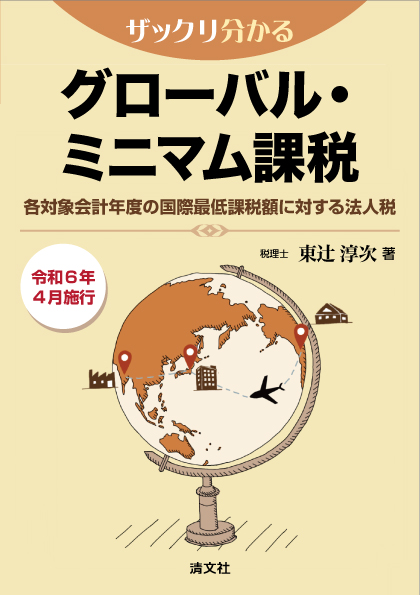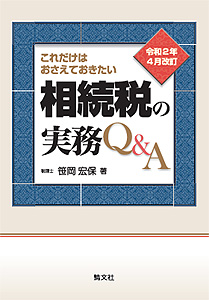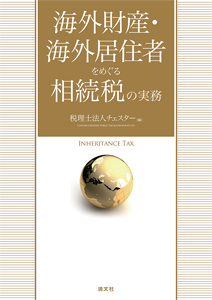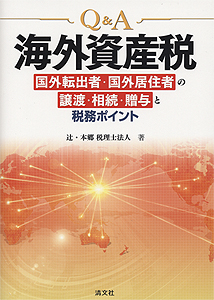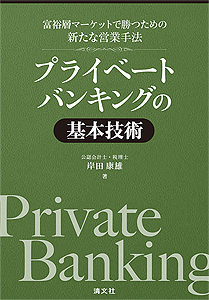酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第7回】
「武富士事件(その1)」
~「住所」の認定はいかにしてなされるべきか?~
国士舘大学法学部教授・法学博士
酒井 克彦
1 はじめに
租税法上で用いられている「ある用語」の意味がその文脈から明確ではない場合、それが私法から借りてきた概念(借用概念)であるとすれば、当該私法上の概念の意味内容に従って解釈をすることが、租税法律主義の要請する法的安定性や予測可能性に資すると考えられている。
このように、租税法の解釈では、多くの場面で、いわゆる「私法準拠」といって、私法の概念に依拠する態度をとっている。
ところで、租税法の解釈適用の場面では、しばしば「住所」の認定が問題となることがある。それは、例えば、「居住者」か「非居住者」かという納税義務者の属性を判断する際にも、また、課税対象の認定をする際にも重要な論点となる。
しかしながら、「住所」について、租税法では、その意味を明らかにする条文上の手当てをしていない。そこで、上記のとおり、「住所」という用語が民法からの借用概念であると考えられるのであれば、民法に従えばその意味は明らかになるし、事実認定も明快になるはずである(借用概念統一説)。
ところが、今回取り上げるいわゆる“武富士事件”においては、民法上の「住所」概念を用いて相続税法上の「住所」の意味をいかにして明らかにするかという点が議論されたのである。租税法上の「住所」の意味は民法と同じように解釈すればよいのであるから、何も裁判において争われるほどのことはないように思われるのにもかかわらず、である。
実は、民法においては、後に述べるとおり、「住所」を「生活の本拠」に規定するだけでそれ以上のことは何も述べていないのである(民22)。
すると、そこにいう「生活」や「本拠」の意味が明らかにされなければ住所の意味もまた明らかにならないのであるが、これらの意味は民法の条文からは判然としない。
そこで、学説をみてみると、民法上の学説は「住所」についてあまり強い関心を寄せているとはいえず、また、これを取り上げる学説においても、住所概念の理解について住所複数説と単数説に分かれているし、住所認定上の問題として客観説と主観説に分かれているなど、見解の一致をみていないのである。
では、民法上の判例はどうであろうか。
残念ながら、民法以外の「住所」概念を争う判例はあるものの、民法上の住所を巡る判例はないのである。
このように、租税法上に用語の定義がない場合であっても、これを民法と同じに理解すれば問題なく解釈できるなどということは到底いえないのである。
そこで、今回から武富士事件を素材として、この租税法上の概念の理解に係る問題につき、考えてみたい。
2 事案の概要
X(原告・被控訴人・上告人)は、亡B及びCから、平成11年12月27日付けの株式譲渡証書(以下「本件贈与契約書」という)により、D社(オランダ王国における有限責任非公開会社)の出資口数各560口、160口(合計720口、以下「本件出資」という)を取得したことについて、平成11年分贈与税の決定処分(以下「本件決定処分」という)及び無申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい、本件決定処分と併せて「本件決定処分等」という)を受けた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。