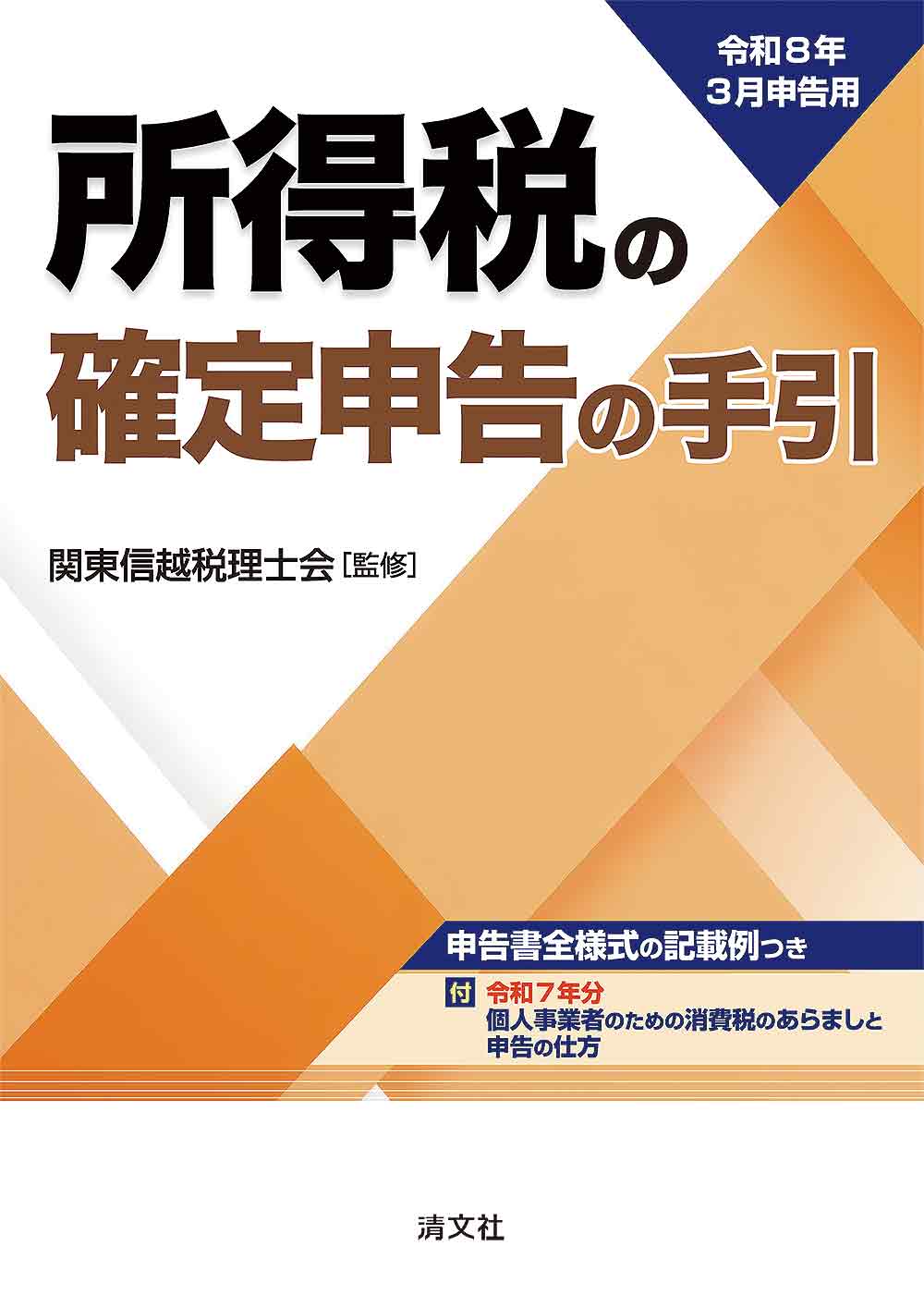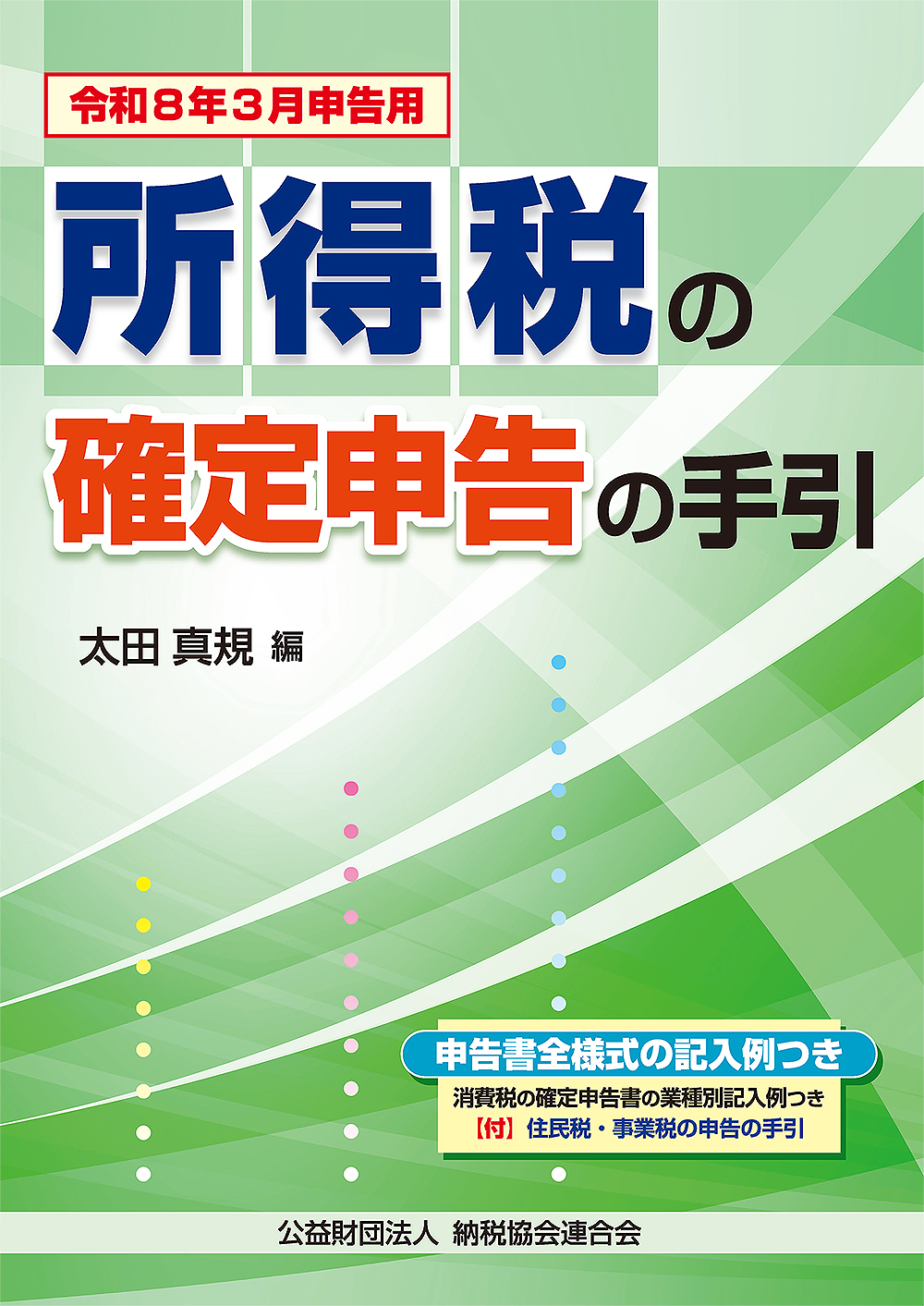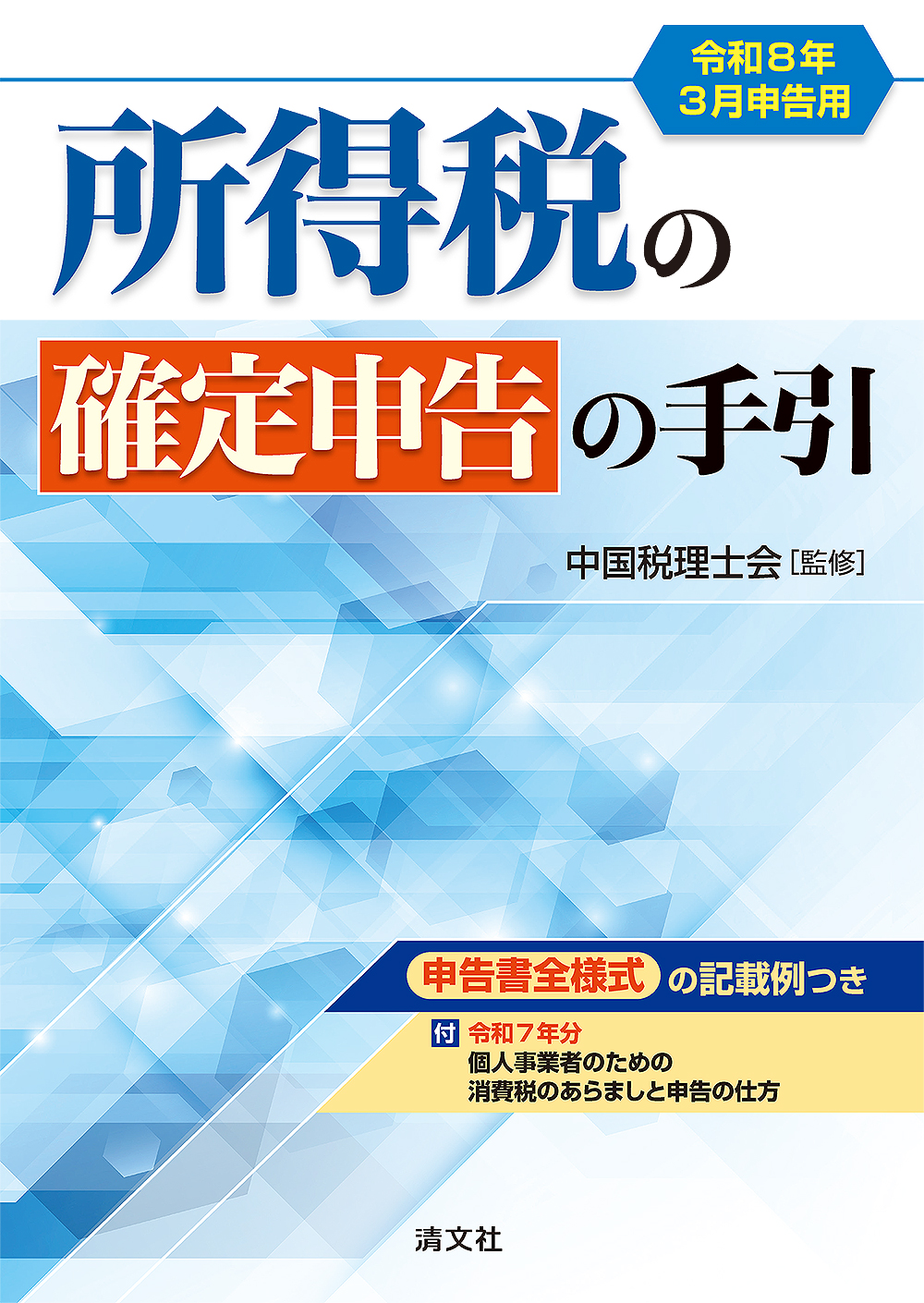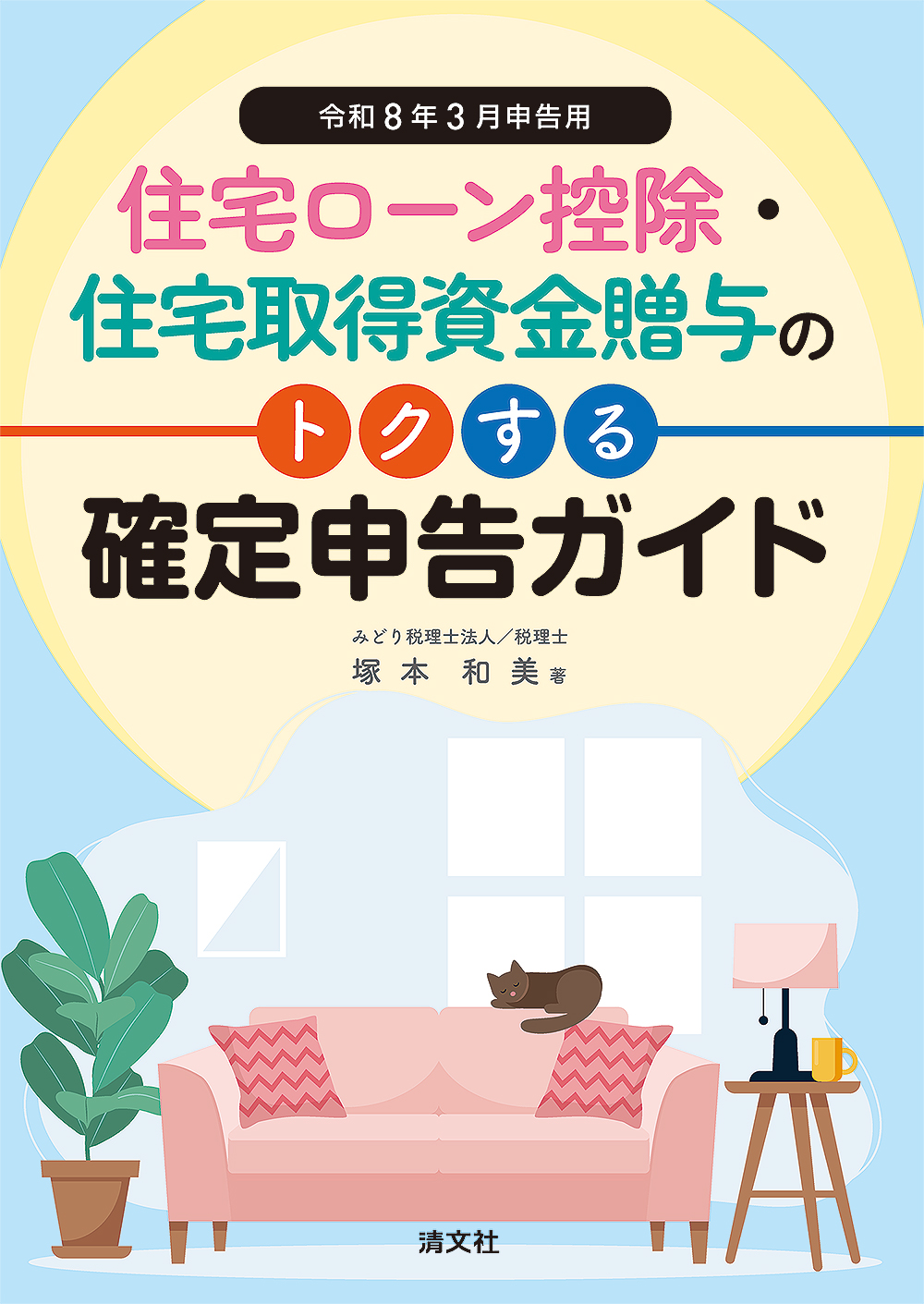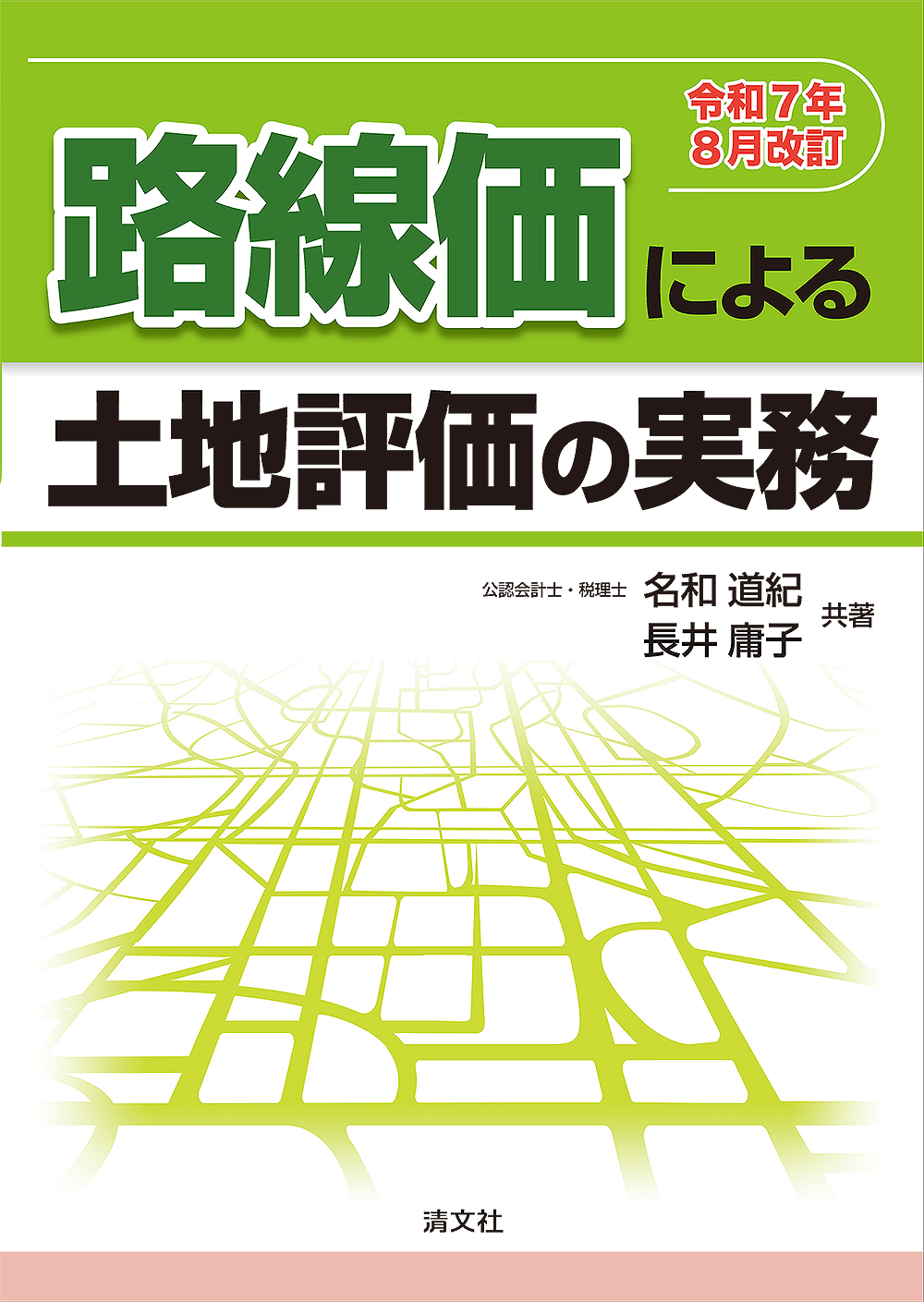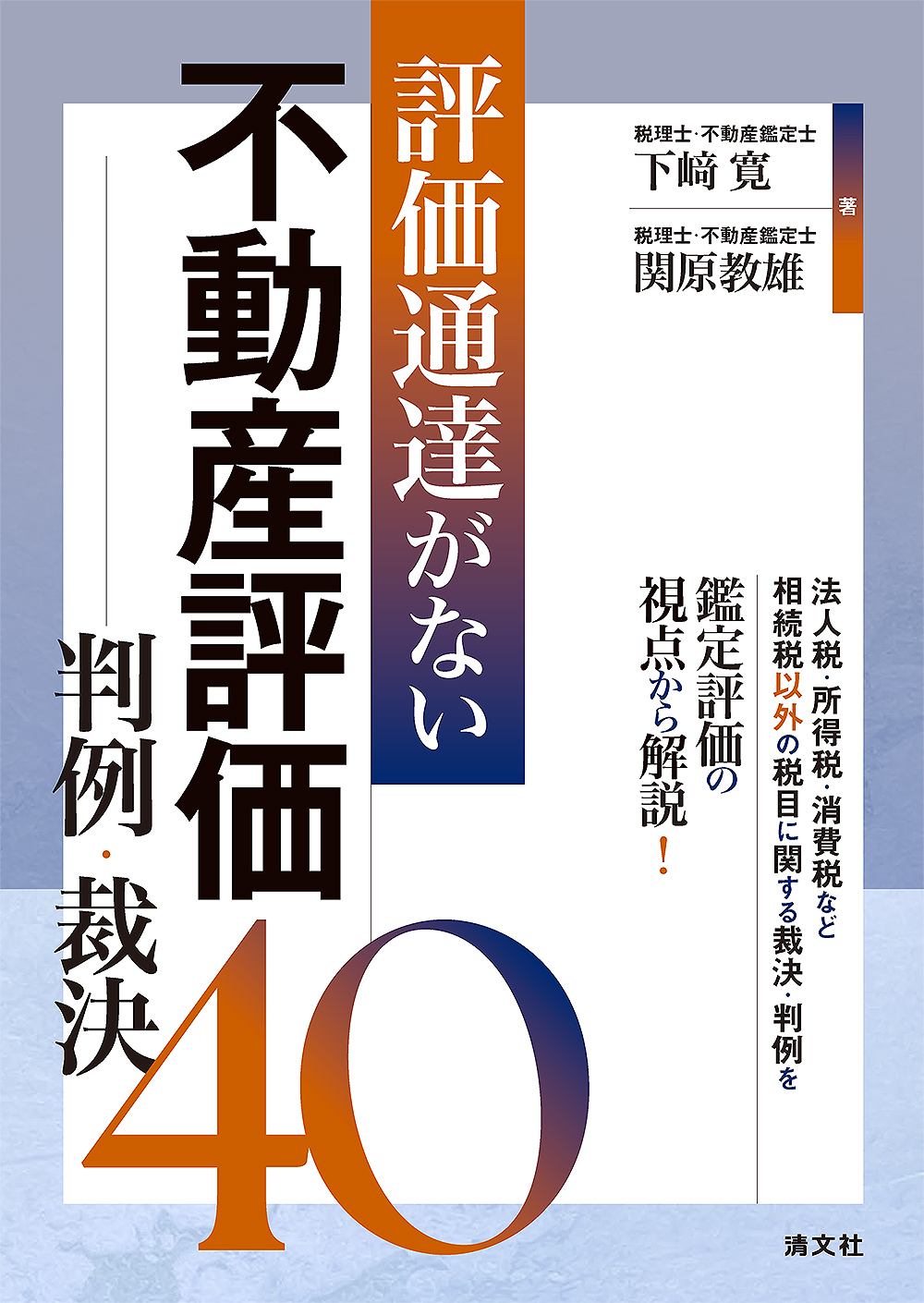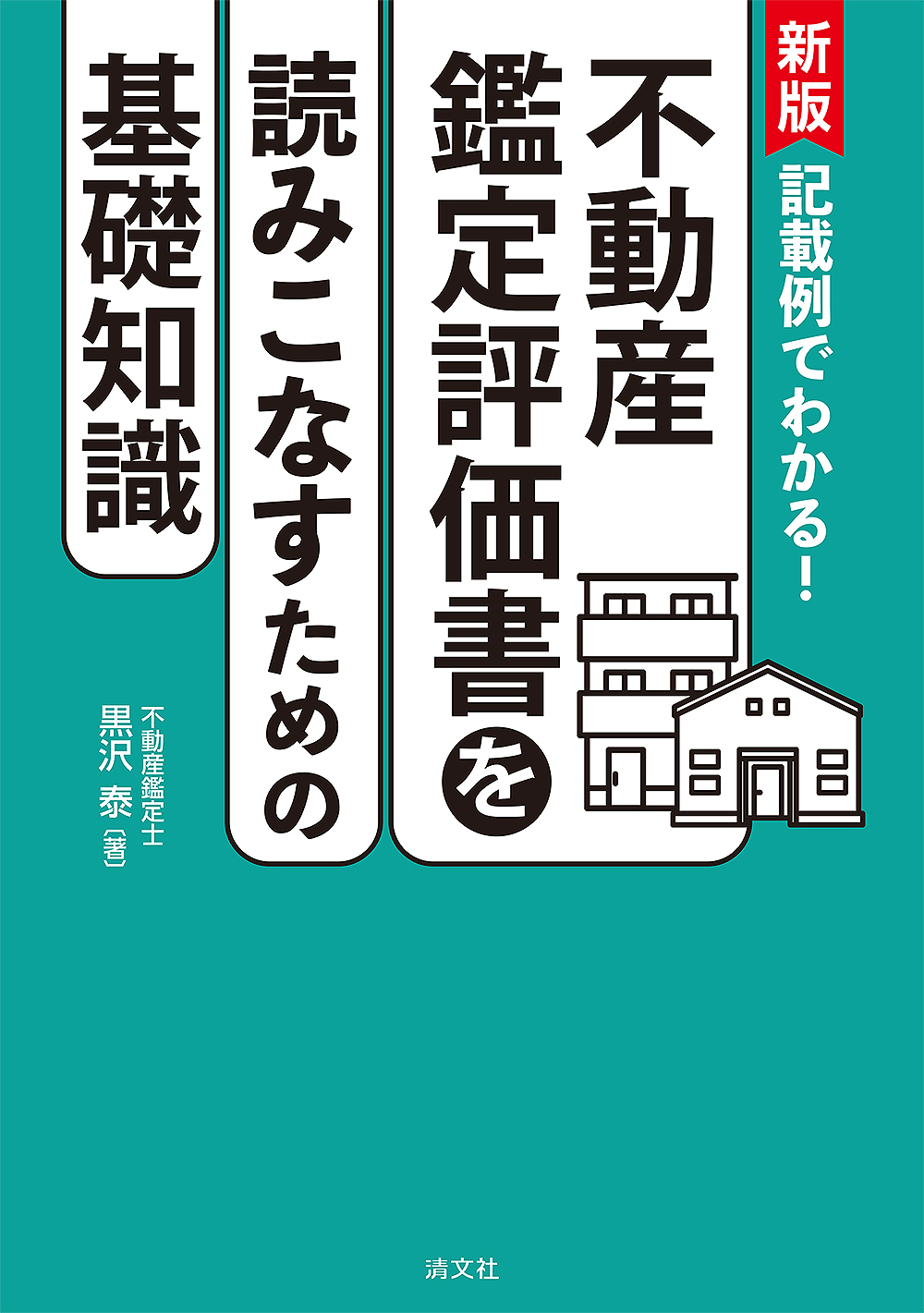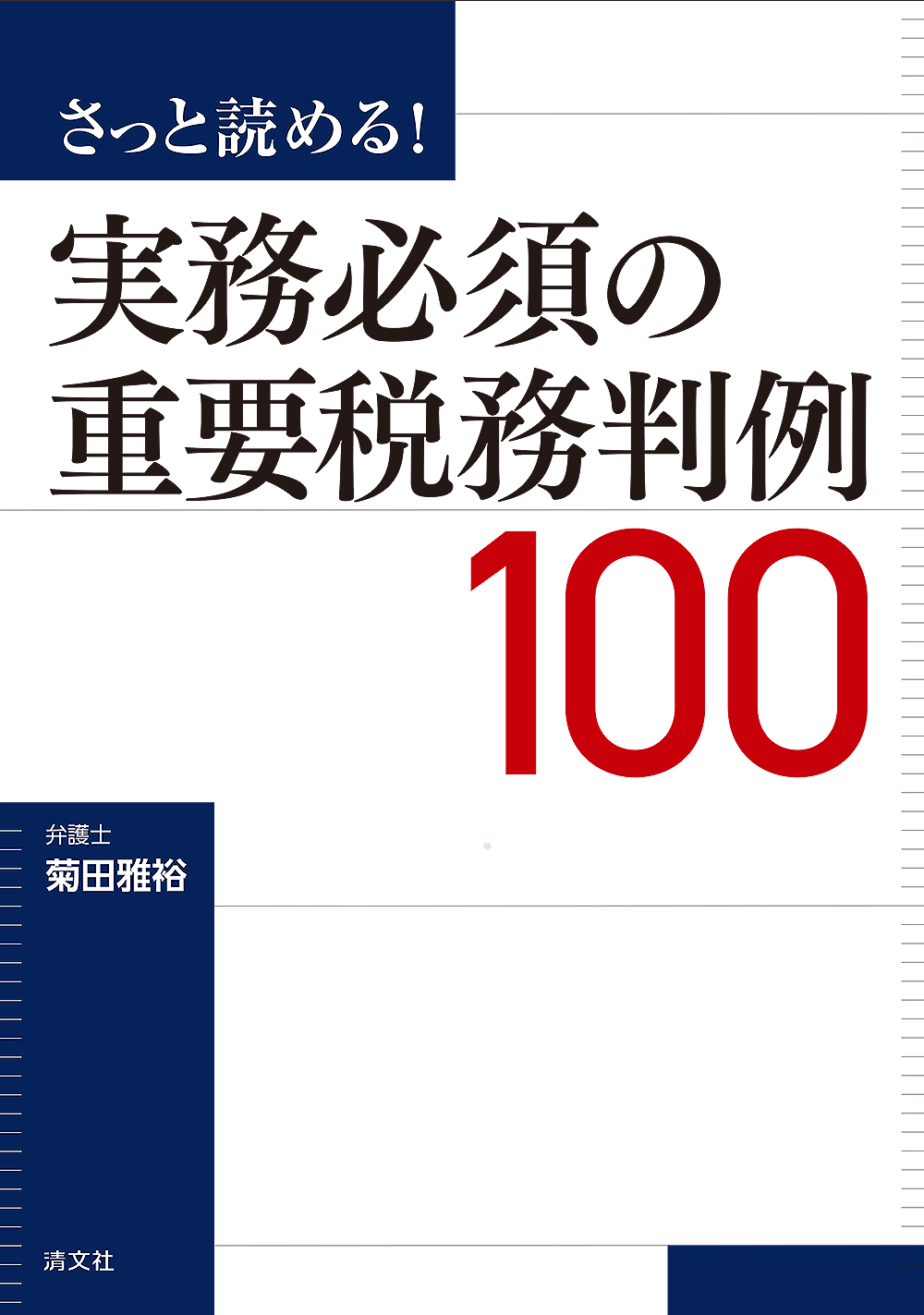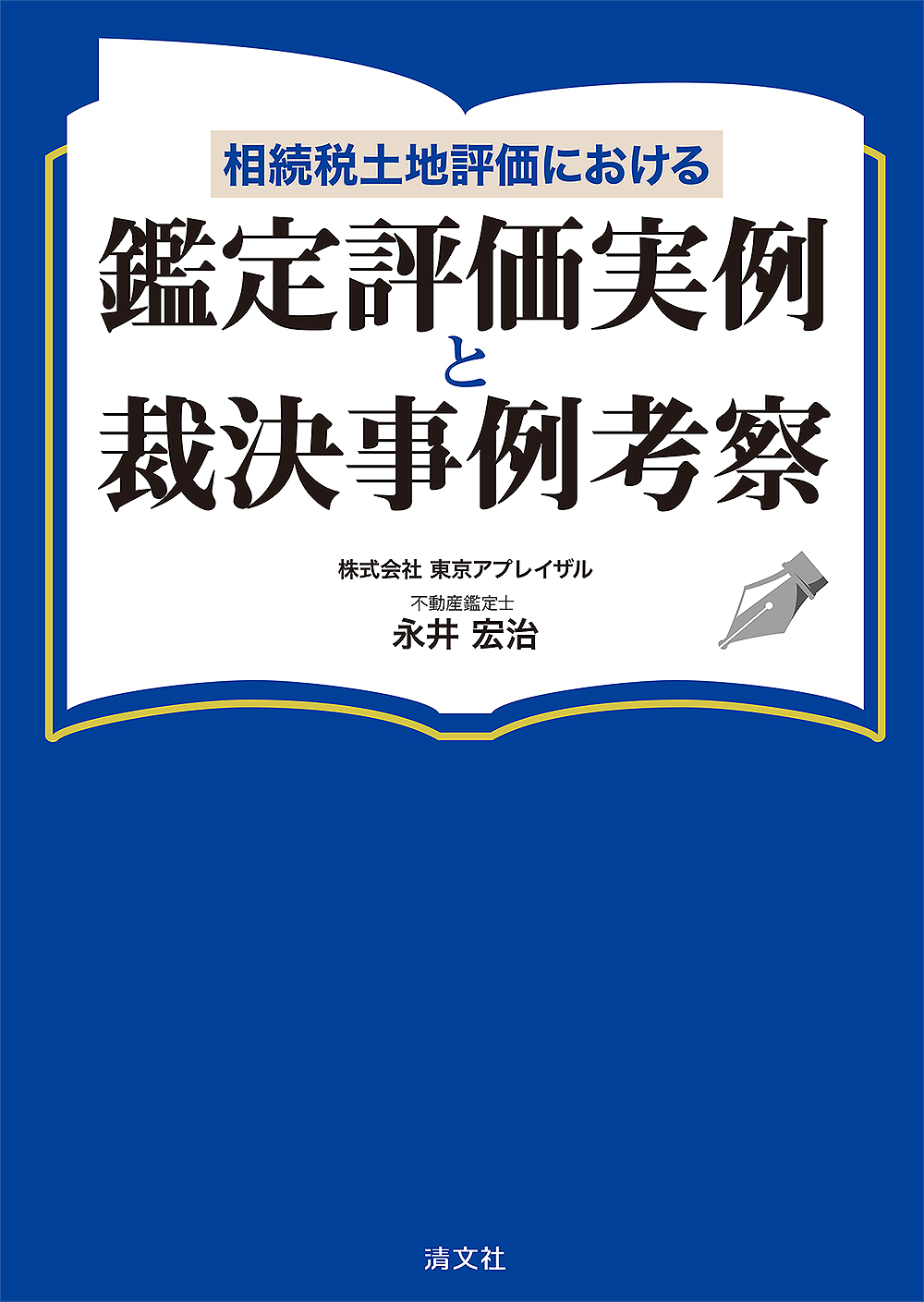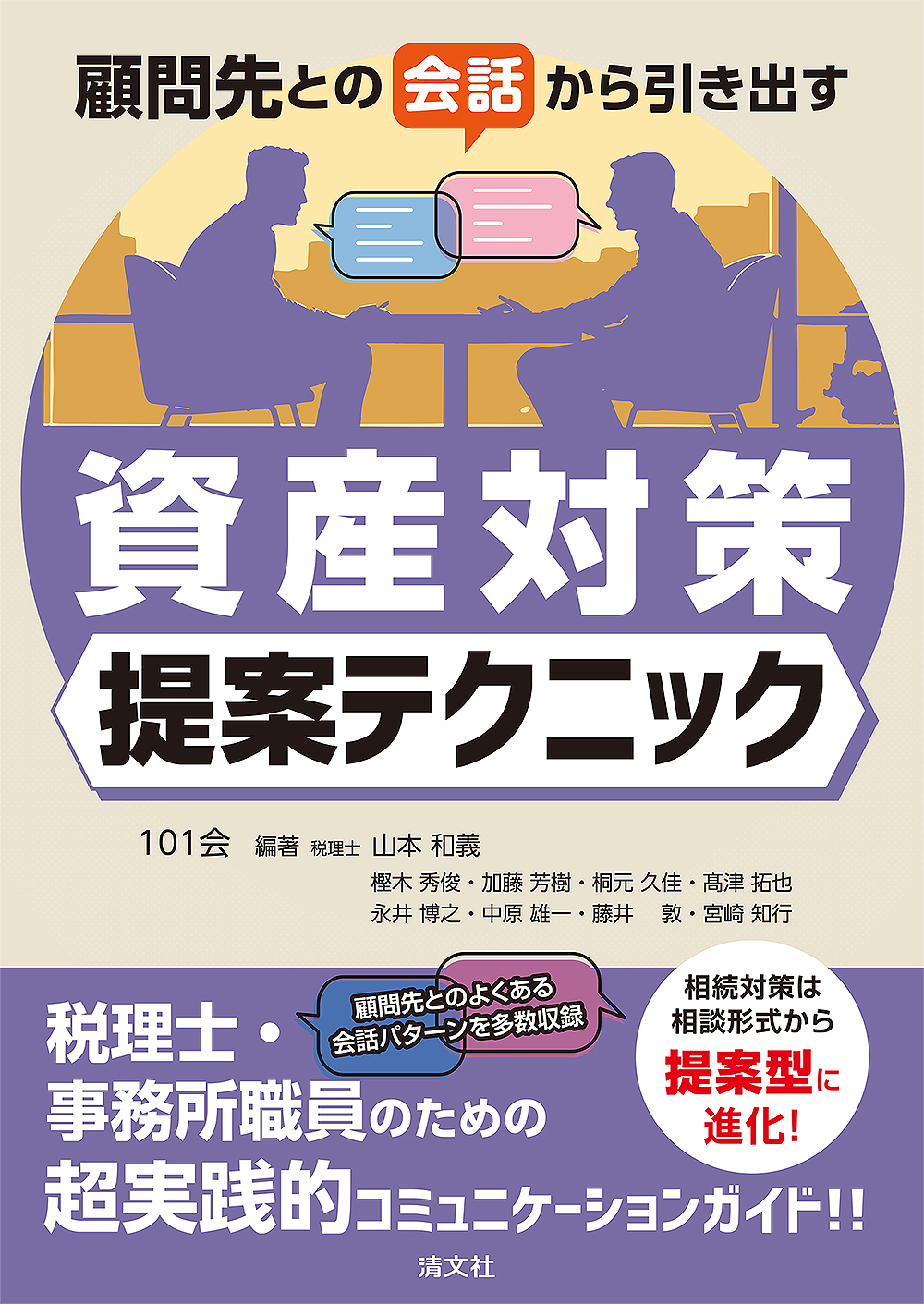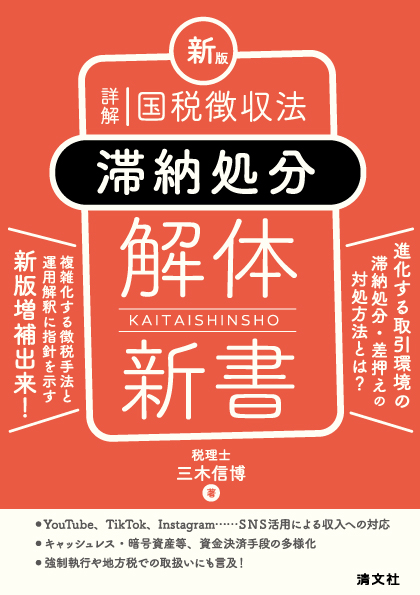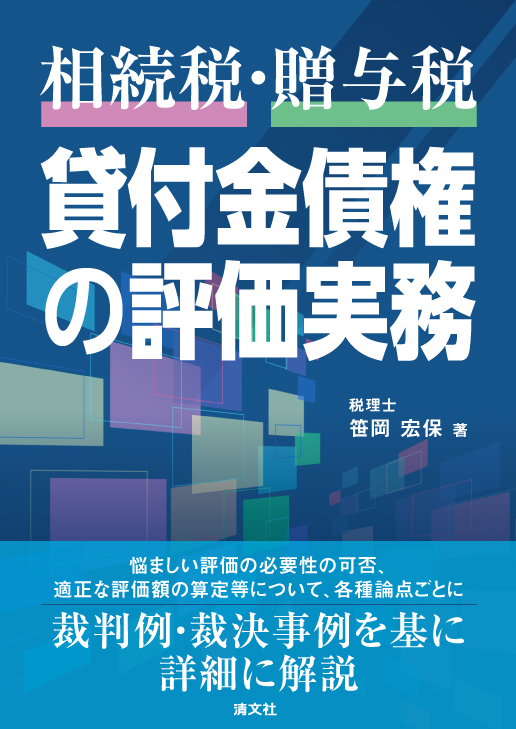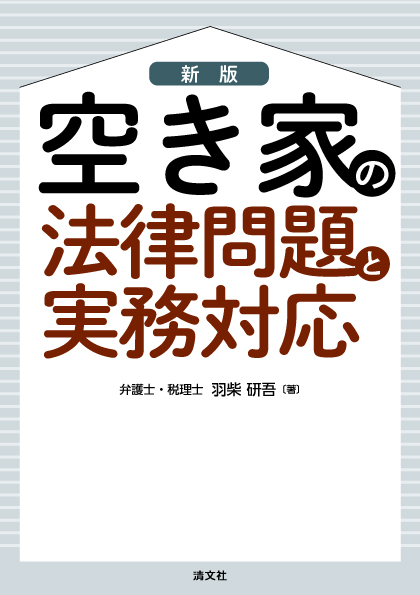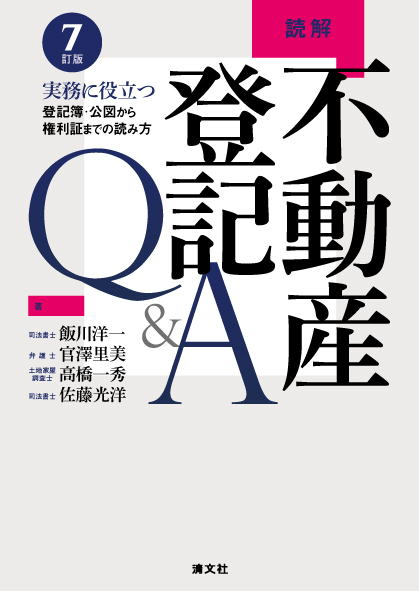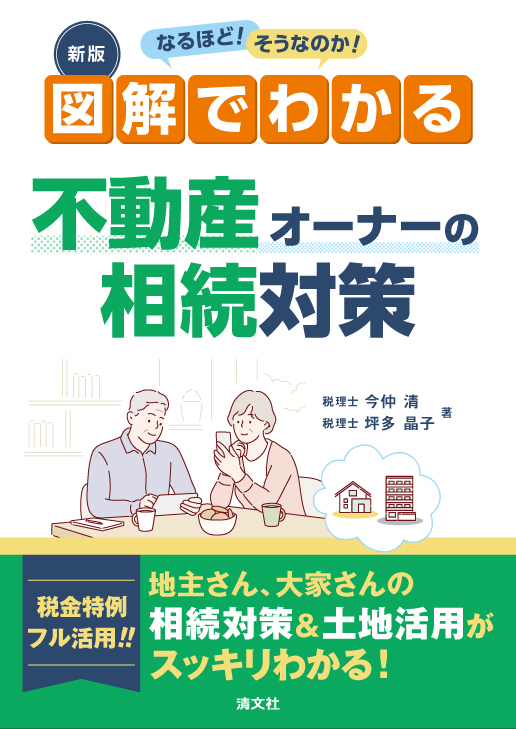酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第16回】
「建替え建築は『新築』か『改築』か?(その1)」
~住宅借入金等特別控除と借用概念~
中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦
はじめに
これまでこの連載でも取り上げてきた借用概念の解釈を巡っては、多くの訴訟が提起されている(本連載第7回~9回で取り上げた「住所」の概念、第10~12回で取り上げた「配偶者控除にいう『配偶者』」の概念なども参照)。
例えば、居住者が、現在の居住用建物を取り壊して、新たにその基礎(土台)に新しい家を建てた場合に、かかる家は「改築」された家というのであろうか。あるいは、「新築」された家というのであろうか。
このような話が単なるネーミングの問題であればそれほど深刻なことにはならないが、例えば、建築工事費用のための借入金について、その建築が「改築」に該当すれば、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用対象になり、「新築」に該当すれば、同控除の適用対象にならないという場合には、租税負担に大きな違いが生じるので、その違いを軽視することはできないであろう。
向こう10年以上にわたって、控除を受け続けることができるかどうかは、当初の要件次第であるから、ここで「改築」と解釈されないと納税者にとっては、タックスメリットが完全に否定されてしまうことになるのである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。