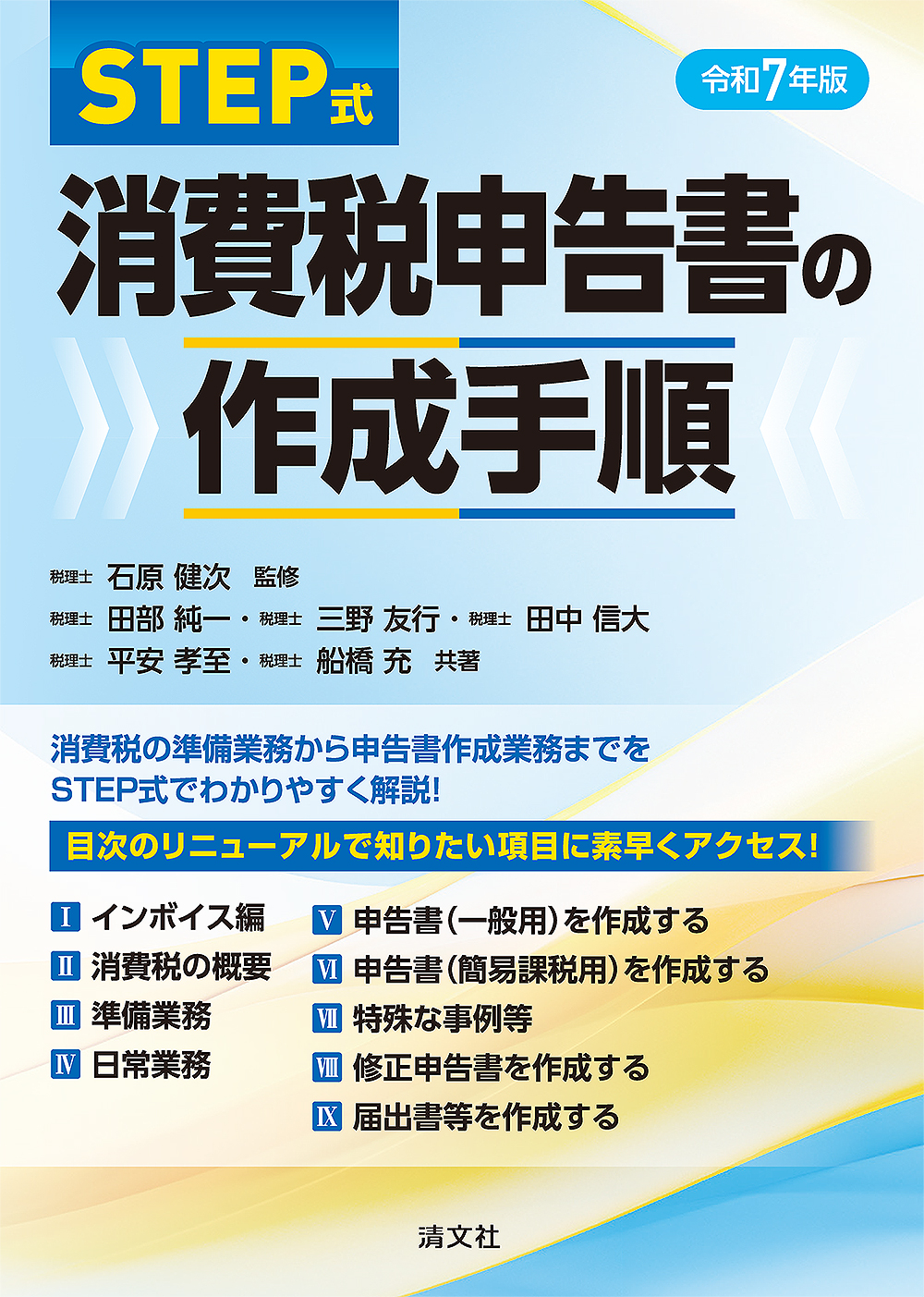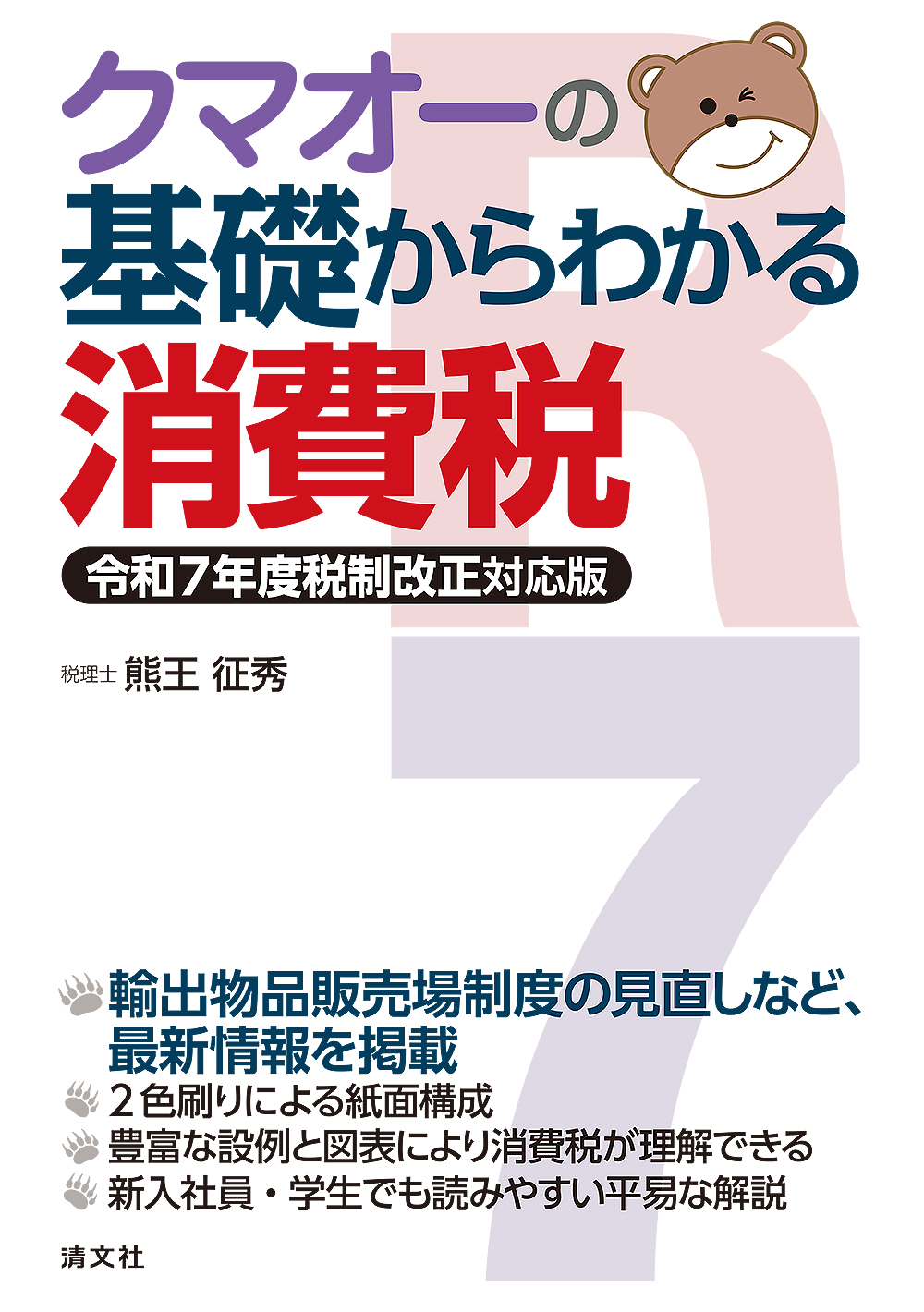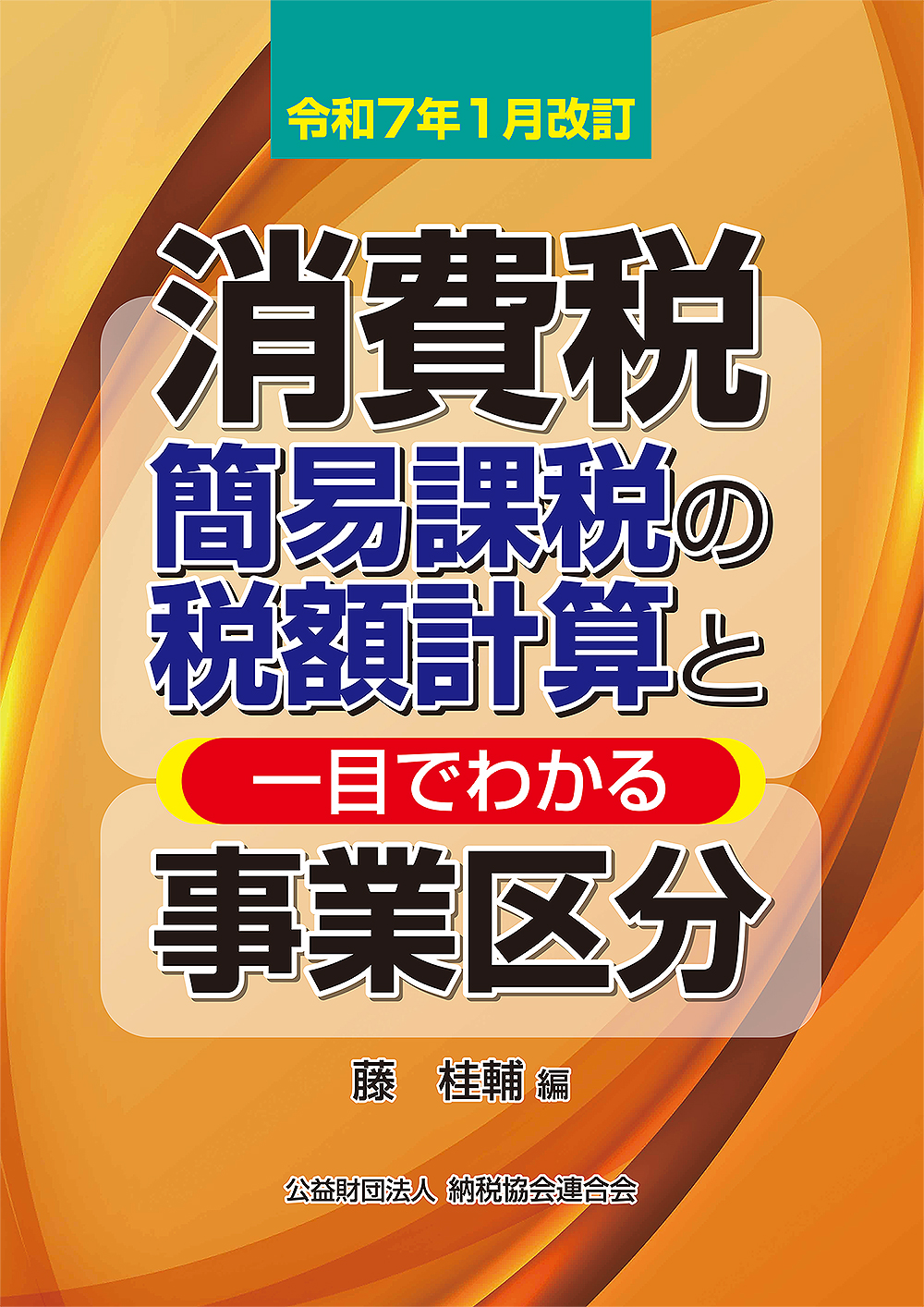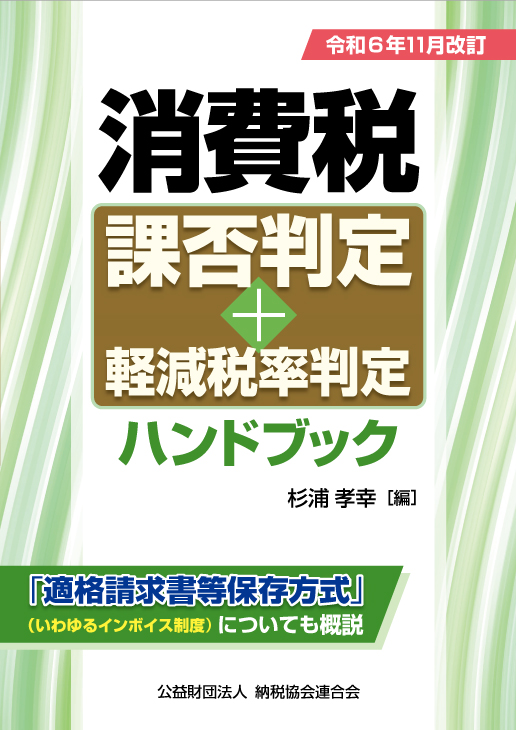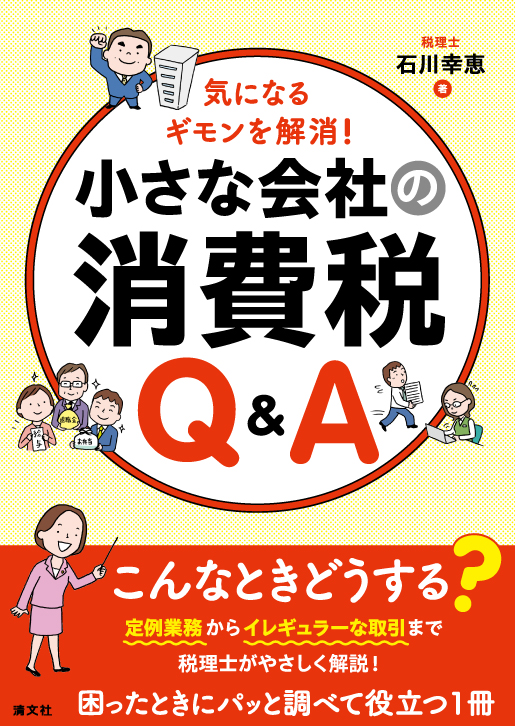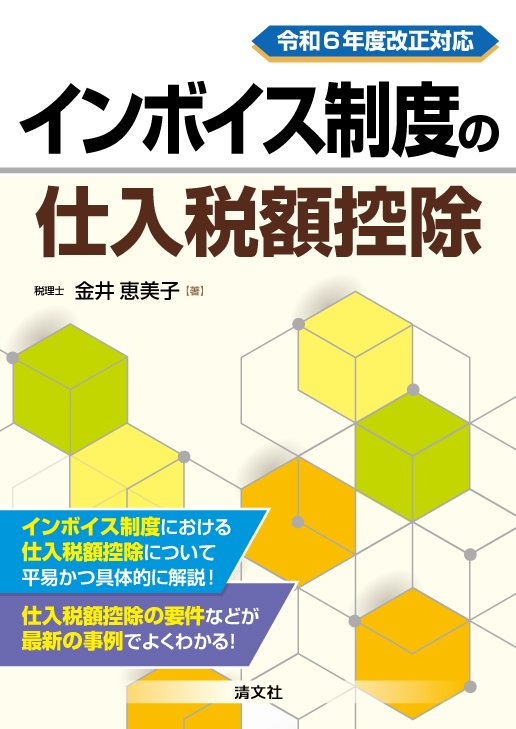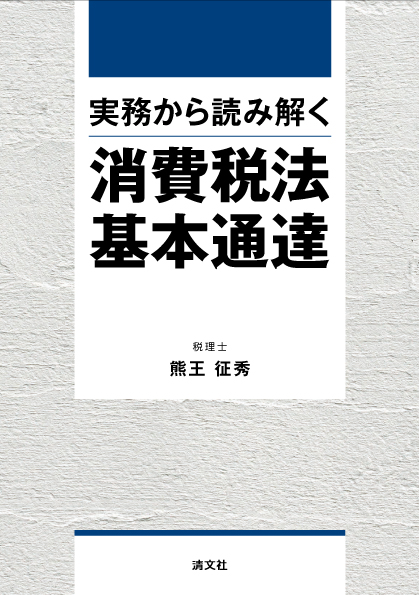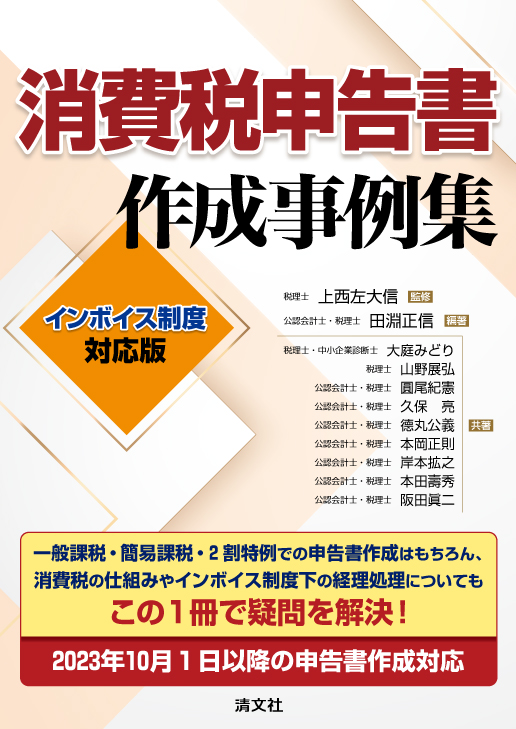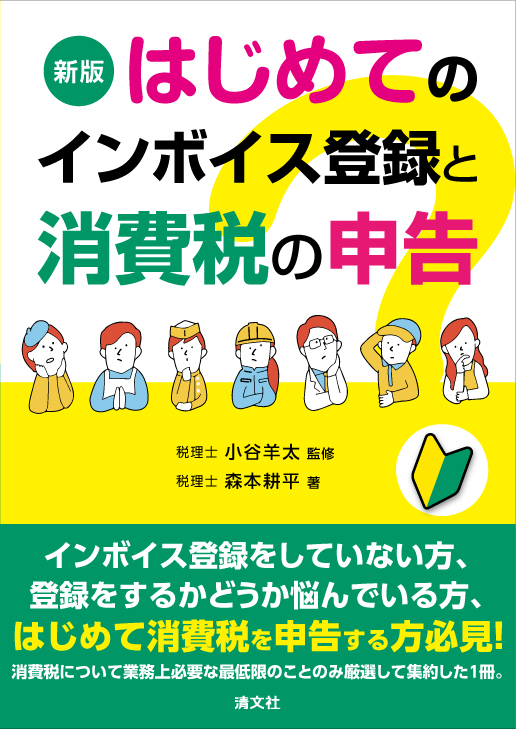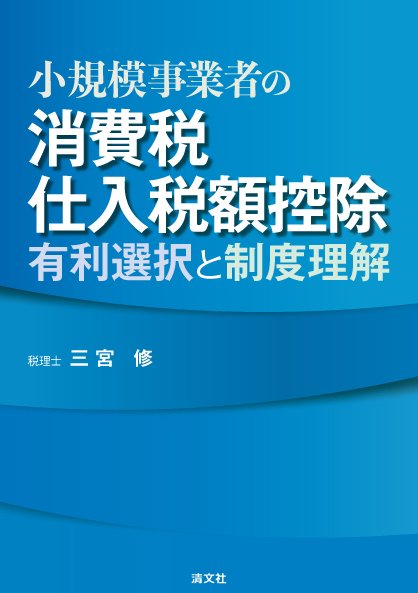酒井克彦の
〈深読み◆租税法〉
【第124回】
「消費税法判例解析講座(その1)」
中央大学法科大学院教授・法学博士
酒井 克彦
はじめに
令和5年10月から消費税法においてインボイス制度がスタートした。同制度を巡っては、喧々諤々の賛否両論が展開されているが、国民の中には誤解に基づくと思われる議論を展開しているように見受けられるものもある。また、租税専門家の中の議論においても、間接税というものが、担税者と納税義務者を分かちえていることの本質論を無視したような議論や、税制改革法を念頭に置いていないような議論も散見されるのである。
この新たな制度が我が国として経験のないものであることからすれば、導入に当たっての混乱や誤解も無理のない話であるように思われるものの、他方で、今こそ、国民の租税、なかんずく消費税法についての理解が広がるべきであるとも思われる。そもそも、揮発油税や酒税などの間接税についての理解もままならない中にあって、消費税の法的性質を論じるに遅すぎるということはないであろう。
そこで、本連載において、消費税法に特化した議論を展開することとした。差し当たりは、重要と思われる消費税法上の裁判例等の解析を通じて、同法の本質に迫るような議論を展開したいと考えている。
かかる新たな連載の第1回目として、最高裁平成16年12月16日第一小法廷判決(民集58巻9号245頁)を取り上げることから始めてみよう。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。