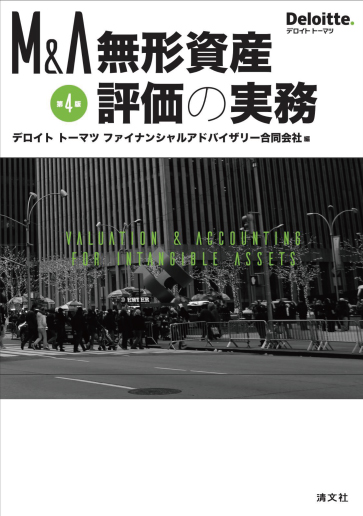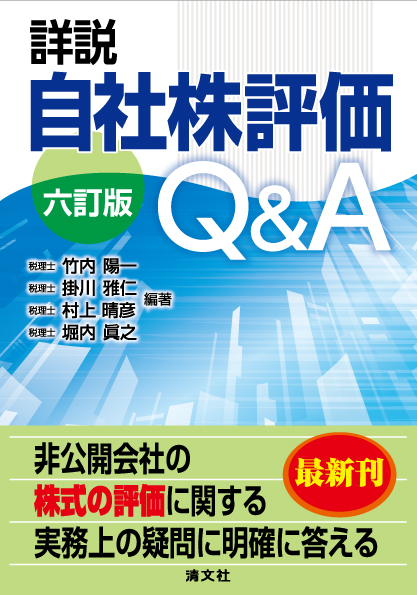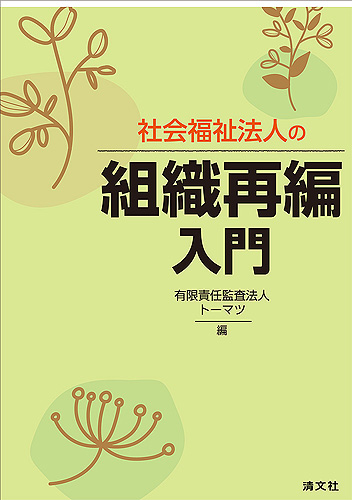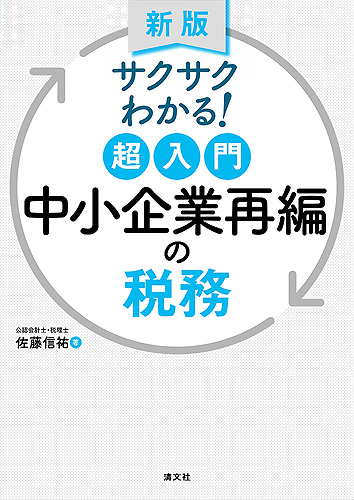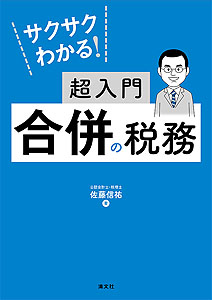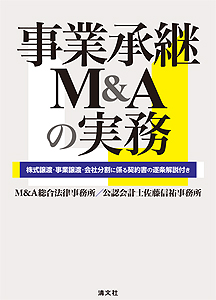企業結合会計を学ぶ
【第6回】
「取得原価の配分方法①」
-識別可能資産及び負債の範囲-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
【第3回】で示した次の吸収合併の〔例〕を用いて、「取得」の会計処理における取得原価の配分方法について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 吸収合併
〔例〕
次の条件による吸収合併を行った(会社法2条27号)。
① A社(存続会社、取得企業)はB社(消滅会社、被取得企業)を吸収合併した(結合分離適用指針5項(1)(2))。
② A社(存続会社)が取得企業であると決定した(企業結合会計基準10項、18~22項)。
③ A社がB社から受け入れた資産及び引き受けた負債(諸資産)の時価は900であった。
④ 合併直前のB社の資産及び負債(諸資産)の帳簿価額は700であった。
⑤ A社はB社の株主にA社の株式を交付した。交付されたA社の株式の時価は1,000であった。
A社(存続会社、取得企業)の吸収合併(取得)に関する会計処理は次のとおりである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。