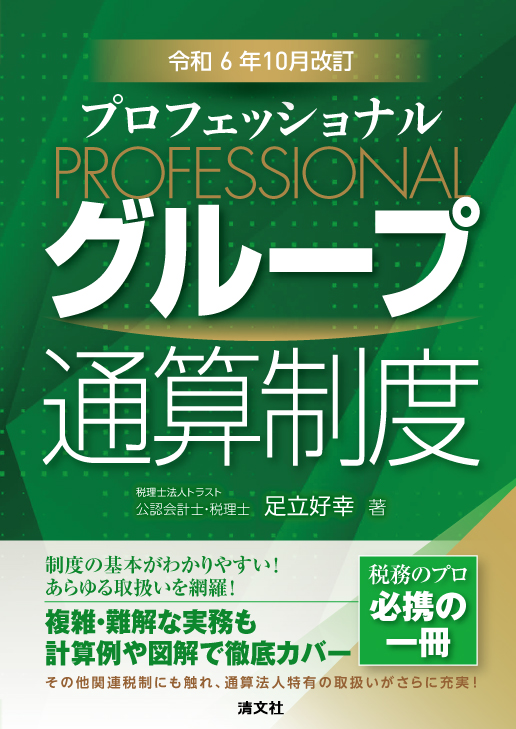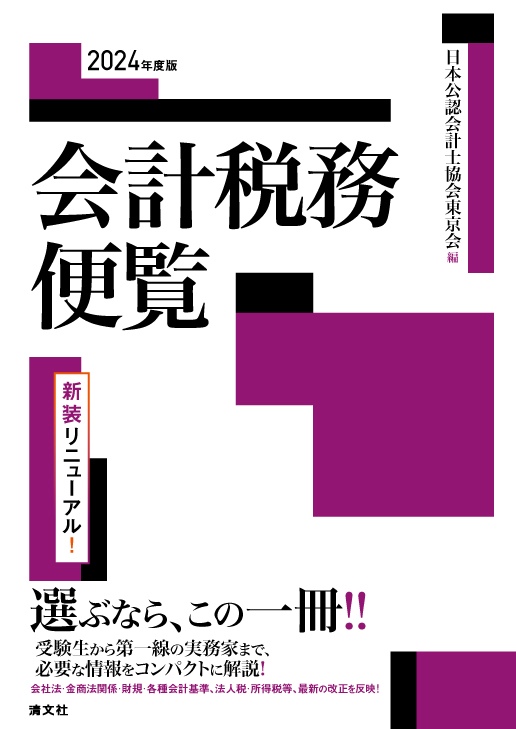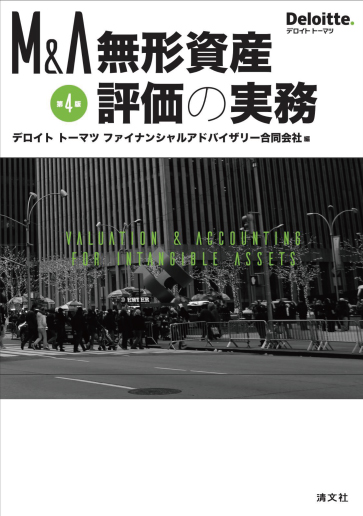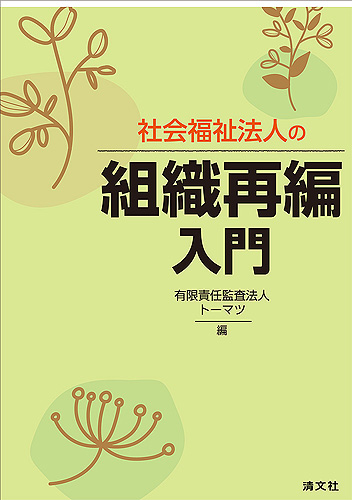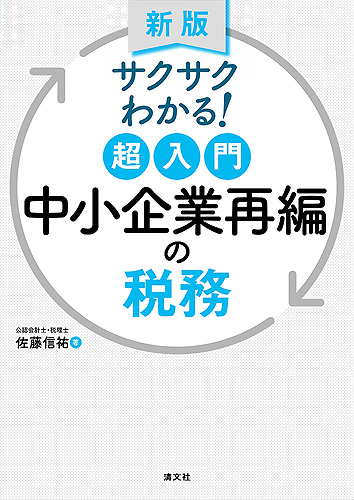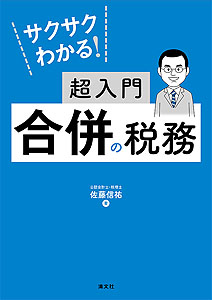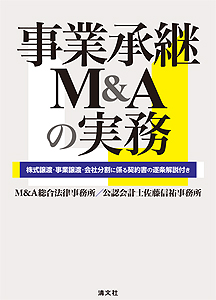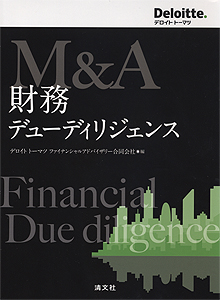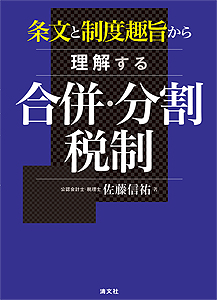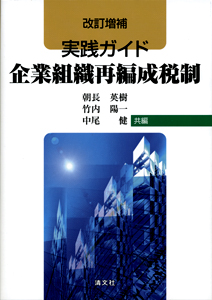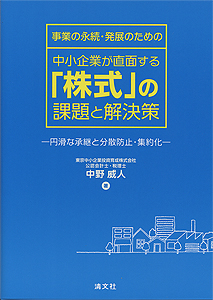企業結合会計を学ぶ
【第30回】
「①同一の株主(企業)により支配されている子会社同士の合併の会計処理
(合併対価が吸収合併存続会社の株式と現金等の財産である場合)と
②同一の株主(個人)により支配されている企業同士の吸収合併の会計処理」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
今回は、共通支配下の取引等の会計処理のうち、次の2つを解説する。
① 同一の株主(企業)により支配されている子会社同士の合併の会計処理(合併対価が吸収合併存続会社の株式と現金等の財産である場合)
② 同一の株主(個人)により支配されている企業同士の吸収合併の会計処理
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。