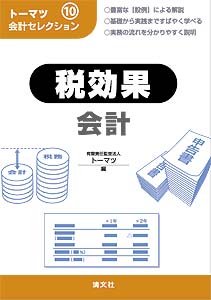法人税、住民税及び事業税等に関する
会計基準を学ぶ
【第1回】
「適用範囲と定義」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会から「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号。以下「法人税等会計基準」という)が公表されている。
これは、次のものを基本的に踏襲した会計基準である。
① 「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」(監査・保証実務委員会実務指針第63号)
② 「税効果会計に関するQ&A」(会計制度委員会)
③ 「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(実務対応報告第12号)
本シリ-ズは、上記の実務指針等の基本的な内容を踏まえて、法人税等会計基準について、解説を行うものである。
前述のように、法人税等会計基準は、基本的に日本公認会計士協会の実務指針等の内容を踏襲しており、実質的な内容の変更を意図したものではない(法人税等会計基準41項)ことから、実務指針等の趣旨や公表時の背景、従来の実務慣行も引き続き、重要な側面があると思われる。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 適用範囲
1 適用範囲の概要
法人税等会計基準は、主として法人税、地方法人税、住民税及び事業税に関する会計処理及び開示について規定している(法人税等会計基準1項)。
つまり、同会計基準の対象は、原則として、我が国の法令に従い納付する税金のうち法人税、住民税及び事業税等に関する会計処理及び開示ということである(法人税等会計基準2項(1))。
法人税等会計基準は、連結財務諸表及び個別財務諸表における次の事項に適用する(法人税等会計基準2項)。
(1) 我が国の法令に従い納付する税金のうち法人税、住民税及び事業税等に関する会計処理及び開示
(2) 我が国の法令に従い納付する税金のうち受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税に関する開示
(3) 外国の法令に従い納付する税金のうち外国法人税に関する開示
2 適用範囲に関する留意点
次の税については、法人税等会計基準の対象外とされている(法人税等会計基準26項、27項)。
① 事業所税及び特別土地保有税(一般的に金額的な重要性が高いとは言えず、営業費用等で会計処理を行っている実務が浸透しているため)
② 消費税(「消費税の会計処理について(中間報告)」が公表されているため)
③ 固定資産税(一部の業種を除いて、一般的に金額的な重要性が高いとは言えないため)
④ 在外子会社や在外支店等が所在地国の法令に従い納付する税金
3 適用時期等
法人税等会計基準は、2017年3月16日に公表されており、その後、2022年10月28日に改正されている。
2022年の改正は、税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関して行われており、原則的な方法として、当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益(又は評価・換算差額等)に区分して計上することが規定されている(法人税等会計基準5項、5-2項)。
同改正は、2024年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からの適用であり、ただし、2023年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することができるとされている。
本シリーズでは、改正後の法人税等会計基準について解説しているので、2022年の改正に関する規定の適用時期に注意していただきたい。
なお、当該改正の解説については、次の解説をご参照いただきたい。
Ⅲ 定義
法人税等会計基準では次の定義を規定している(法人税等会計基準4項)。
法人税
法人税法の規定に基づく税金をいう。
地方法人税
地方法人税法の規定に基づく税金をいう。
住民税
- 地方税法の規定に基づく税金のうち、道府県民税及び市町村民税をいう。
- 道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する(地方税法1条2項)。
事業税
- 地方税法の規定に基づく税金であり、法人の行う事業に対して都道府県が課すものをいう。
- 事業税には、付加価値額によって課すもの(付加価値割)、資本金等の額によって課すもの(資本割)、所得によって課すもの(所得割)がある。
受取利息及び受取配当金等に課される源泉所得税
所得税法174条各号に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場合に、同法の規定により課される所得税をいう。
外国法人税
- 外国の法令により課される法人税に相当する税金で政令に定めるもの(法人税法69条及び法人税法施行令141条)をいう。
- 外国法人税には、法人税法等に基づき税額控除の適用を受けるものと税額控除の適用を受けないものがある。
所得
法人税の関係法令又は事業税の関係法令の規定に基づき算定した各事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額をいう。
Ⅳ 貸借対照表
貸借対照表においては、法人税、住民税及び事業税等のうち納付されていない税額は、貸借対照表の流動負債の区分に、未払法人税等などその内容を示す科目をもって表示するとされている(法人税等会計基準11項)。
Ⅴ 損益計算書
法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)は、損益計算書の税引前当期純利益(又は損失)の次に、法人税、住民税及び事業税などその内容を示す科目をもって表示するとされている(法人税等会計基準9項)。
また、事業税(付加価値割及び資本割)は、原則として、損益計算書の販売費及び一般管理費として表示し、ただし、合理的な配分方法に基づきその一部を売上原価として表示することができるとされている(法人税等会計基準10項)。
(了)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準を学ぶ」は、隔週で掲載されます。