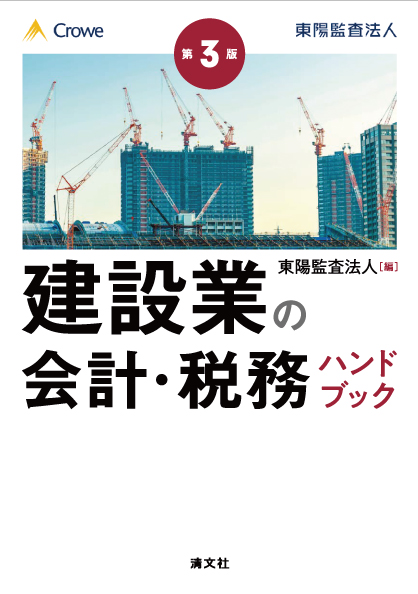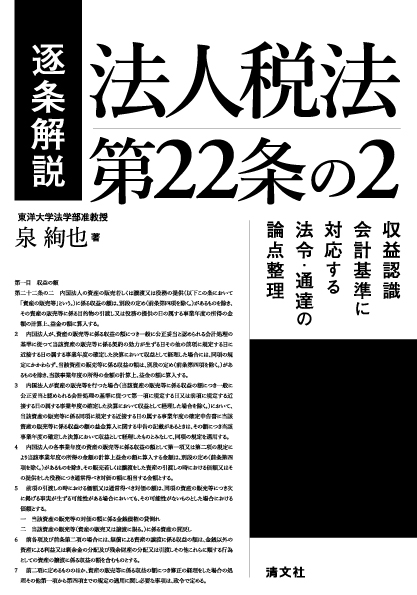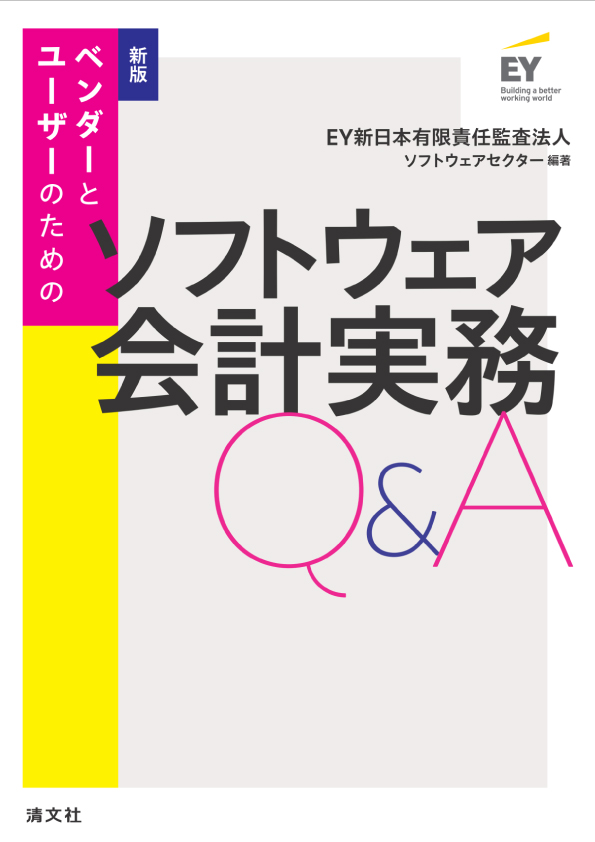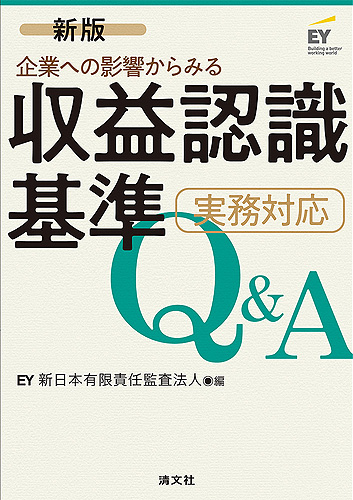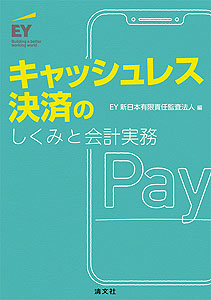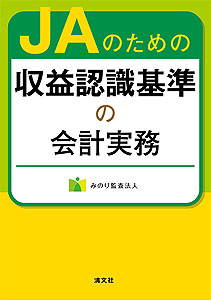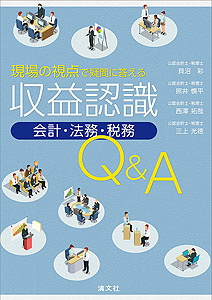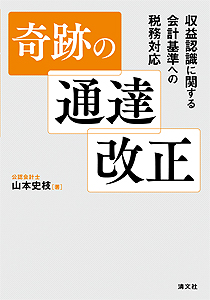収益認識会計基準を学ぶ
【第1回】
「収益認識会計基準の概要と適用範囲」
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号、以下「収益認識会計基準」という)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号、以下「収益認識適用指針」という)は、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用される。
収益認識会計基準は、収益認識に関する詳細な規定が設けられており、また、抽象的な表現も見られることから、実務への適用に際しては、十分な理解が必要となる。
本シリ-ズは、収益認識会計基準に関して、実務への適用を踏まえつつ、その理解に資するように解説を行うものである。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 概要
収益認識会計基準の主な構成は次のようになっており、収益認識適用指針には設例が付されている。
① 目的
② 範囲
③ 用語の定義
④ 会計処理
⑤ 開示(表示・注記事項)
通常、会計基準を読むときは、目次の順番にしたがって、各規定を読みつつ、その根拠となった「結論の背景」を読みながら理解を深めることが多いと思われる。
しかしながら、収益認識会計基準の規定には、抽象的な表現も見られ、実務に適用しようとする際に、理解しづらい部分があると思われる。
そこで、ただちに収益認識会計基準の本文を最初から読むのではなく、まず、収益認識適用指針の設例を読み、ある程度のイメージをもってから、次に、収益認識会計基準及び収益認識適用指針の本文を読むという方法が考えられる。
また、収益認識会計基準の「開発にあたっての基本的な方針」として、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の定めを基本的にすべて取り入れていることから(収益認識会計基準97項、98項)、収益認識会計基準を理解し実務に適用する際に、IFRS第15号の規定を参考にすることが考えられる。
Ⅲ 適用範囲
1 顧客との契約から生じる収益
収益認識会計基準は、次の①から⑦を除いて、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示に適用される(収益認識会計基準3項)。
① 「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)の範囲に含まれる金融商品に係る取引
② 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)の範囲に含まれるリース取引
③ 「保険法」(平成20年法律第56号)における定義を満たす保険契約
④ 顧客又は潜在的な顧客への販売を容易にするために行われる同業他社との商品又は製品の交換取引(例えば、2つの企業の間で、異なる場所における顧客からの需要を適時に満たすために商品又は製品を交換する契約)
⑤ 金融商品の組成又は取得に際して受け取る手数料
⑥ 「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第15号)の対象となる不動産(不動産信託受益権を含む)の譲渡
⑦ 「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号)における定義を満たす暗号資産及び「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)における定義を満たす電子記録移転権利に関連する取引
このため、顧客との契約の一部が上記の①から⑦に該当する場合には、①から⑦に適用される方法で処理する額を除いた取引価格について、収益認識会計基準を適用するので、顧客との取引を検討する際に注意が必要である。
また、関連する取引が「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(実務対応報告第38号)の範囲に含まれる場合には、これに従って会計処理することになり、そうでない場合には、関連する会計基準等の定めが明らかではない場合として、企業が会計方針を定めることになる(収益認識会計基準108項-2)。
「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号)は、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合とは、特定の会計事象等に対して適用し得る具体的な会計基準等の定めが存在しない場合をいうと定義している(4-3項)。
2 「顧客」と「契約」
収益認識会計基準で取り扱う範囲は、IFRS 第15号と同様に、顧客との契約から生じる収益である(収益認識会計基準102項)。
このため、顧客との契約から生じるものではない取引又は事象から生じる収益は、収益認識会計基準の対象とならない(収益認識会計基準102項)。
収益認識会計基準は、「顧客」と「契約」を次のように定義しており、当該定義を満たすかどうかの判断が重要になると考えられる(収益認識会計基準5項、6項)。
① 顧客
対価と交換に企業の通常の営業活動により生じたアウトプットである財又はサービスを得るために当該企業と契約した当事者をいう。
② 契約
法的な強制力のある権利及び義務を生じさせる複数の当事者間における取決めをいう。
3 同業他社との商品又は製品の交換取引
顧客又は潜在的な顧客への販売を容易にするために、同業他社との商品又は製品の交換取引が行われることがある。
当該取引において、商品又は製品を交換する同業他社は、企業の通常の営業活動により生じたアウトプットを獲得するために企業と契約しているため、顧客の定義に該当するが、IFRS 第15号と同様に、収益認識会計基準の適用範囲に含めないこととされた(収益認識会計基準3項(4)、106項)。
IFRS 第15号では、同業他社との棚卸資産の交換について収益を認識し、その後で再び最終顧客に対する棚卸資産の販売について収益を認識すると、収益及び費用を二重に計上することになり、財務諸表利用者が企業による履行及び粗利益を評価することが困難となるため適切ではないとされている(収益認識会計基準106項)。
わが国においては、棚卸資産の交換取引に関する会計処理の定めが明示されていないが、IFRS 第15号と同様に、同業他社との棚卸資産の交換について収益を認識することは適切ではないと考えられる(収益認識会計基準106項)。
4 固定資産の売却
IFRSでは、企業の通常の営業活動により生じたアウトプットではない固定資産の売却について、IFRS 第15号と同様の収益の認識を行うようIAS 第16号「有形固定資産」が改正されている。
一方、収益認識会計基準では、企業の通常の営業活動により生じたアウトプットではない固定資産の売却については、論点が異なり得るため改正の範囲に含めておらず、収益認識会計基準の適用範囲に含まれないとされた(収益認識会計基準108項)。
また、企業の通常の営業活動により生じたアウトプットとなる不動産の売却は、収益認識会計基準の適用範囲に含まれるが、当該不動産の売却のうち、不動産流動化実務指針の対象となる不動産(不動産信託受益権を含む)の譲渡に係る会計処理は、連結の範囲等の検討と関連するため、収益認識会計基準の適用範囲から除外している(収益認識会計基準3項(6))。
5 契約コスト
収益認識会計基準では、棚卸資産や固定資産等、コストの資産化等の定めがIFRSの体系とは異なるため、IFRS 第15号における契約コスト(契約獲得の増分コスト及び契約を履行するためのコスト)の定めを範囲に含めていない(収益認識会計基準109項)。
なお、IFRS又は米国会計基準を連結財務諸表に適用している企業の取扱いに注意する(収益認識会計基準109項)。
6 提携契約に基づく共同研究開発等
前述のとおり、収益認識会計基準は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示に適用される(収益認識会計基準3項)。
このため、例えば、企業の通常の営業活動により生じたアウトプットである財又はサービスを獲得するためではなく、リスクと便益を契約当事者で共有する活動又はプロセス(提携契約に基づく共同研究開発等)に参加するために企業と契約を締結する当該契約の相手方は、顧客ではなく、当該契約に収益認識会計基準は適用されないことになる(収益認識会計基準111項)。
なお、顧客の定義は前述のとおりである(収益認識会計基準6項)。
7 工事契約
収益認識会計基準は、工事契約について、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号)における定義を踏襲している(収益認識会計基準13項、112項)。
なお、請負契約ではあってももっぱらサービスの提供を目的とする契約や、外形上は工事契約に類似する契約であっても、工事に係る労働サービスの提供そのものを目的とするような契約は、「工事契約に関する会計基準」と同様に、工事契約に含まれない(収益認識会計基準112項)。
8 受注制作のソフトウェア
収益認識会計基準は、受注制作のソフトウェアの範囲について、「工事契約に関する会計基準」と同様に、「研究開発費等に係る会計基準」(企業会計審議会)及び「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第17号)を踏襲している(収益認識会計基準14項、113項)。
【参考】 ASBJホームページ
- 企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」
- 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
- 企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」
(了)
「収益認識会計基準を学ぶ」は、隔週で掲載されます。